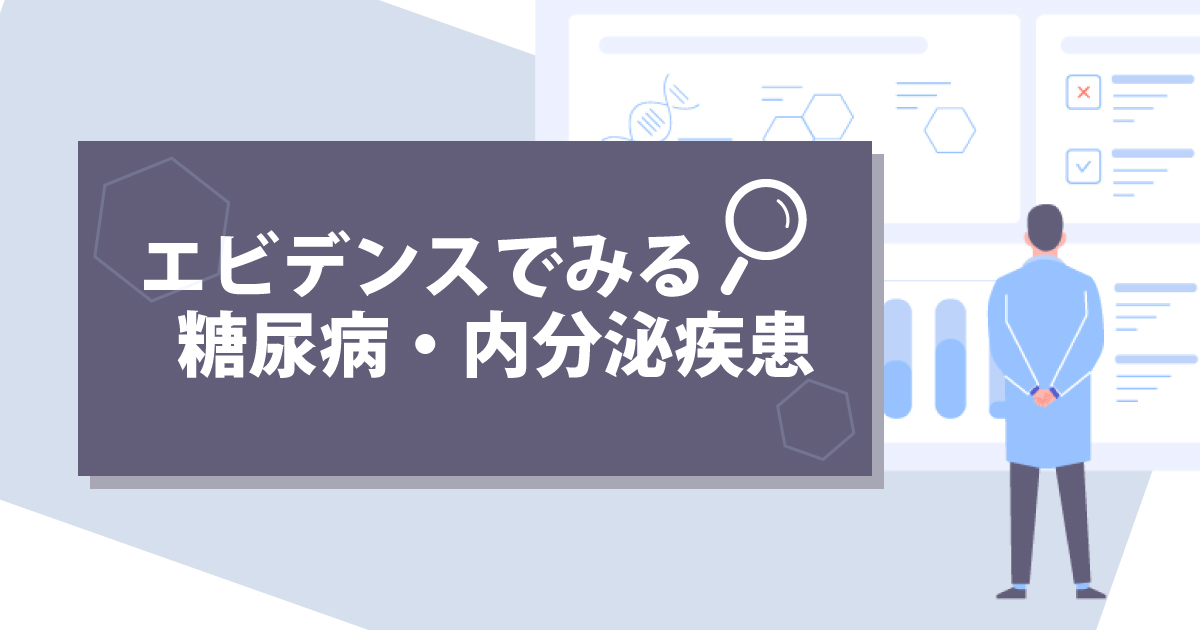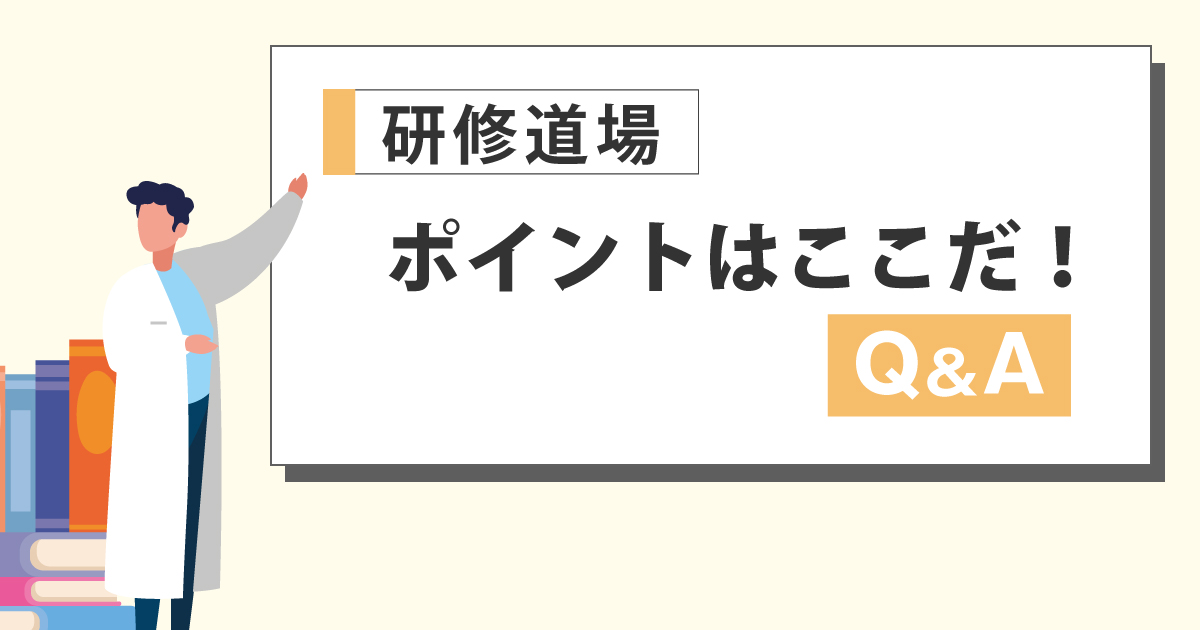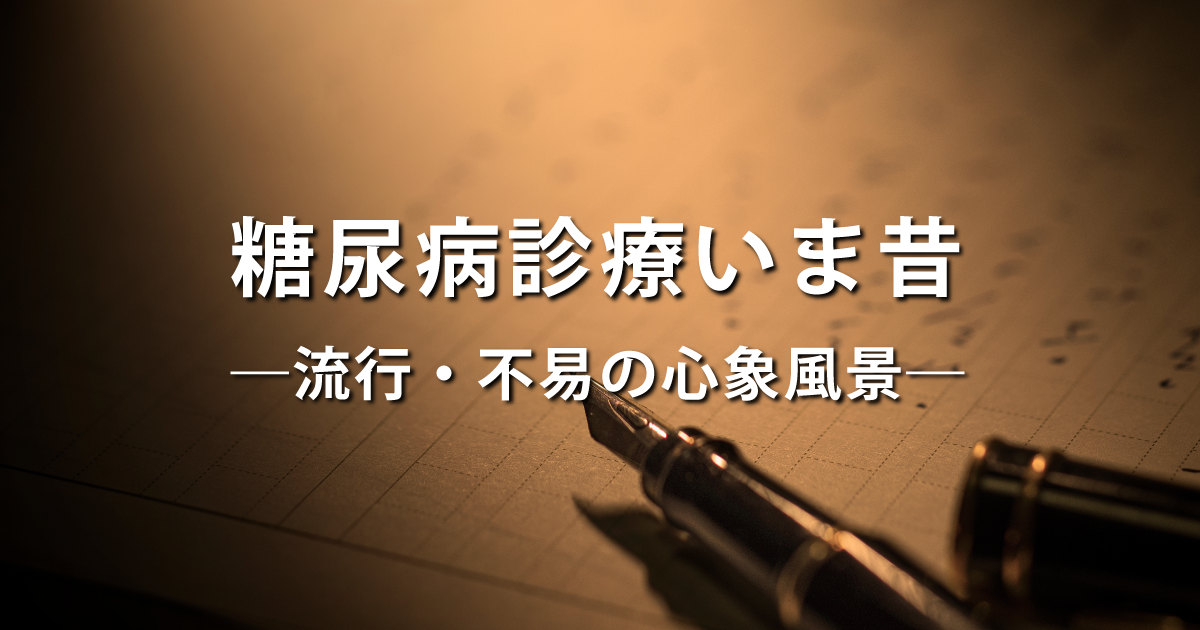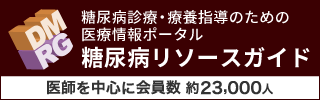今は昔の物語
https://doi.org/10.57554/2025-0097
はじめに
私が医学部を卒業したのは1983年、糖尿病を専門にすることを決めたのが1985年からです。その年から1年間自治医科大学の内分泌代謝科で、葛谷健先生、松田文子先生、岩本安彦先生にご指導いただきました。金澤康徳先生が主任をされていた東京大学第3内科糖尿病研究室に戻り外来にデビューしたのが1986年、赤沼安夫先生が所長をしておられた朝日生命成人病研究所にて臨床に研究に、糖尿病漬けの日々を送ったのが1988年からです。
相澤先生にならって、私のかけだし時代からの糖尿病外来診療を思い出してみます。
新しいインスリン療法の登場について
ペン型インスリン注入器が登場
1988年にインスリン製剤の入ったカートリッジをペン型の注入器に充填して使うペン型インスリン注入器が登場しました。これにより、患者さんは1回ごとにバイアルから注射器でインスリンを吸引する手間から解放されました。
ヒトインスリンが登場
遺伝子組み換えヒトインスリン製剤は1980年代に日本に導入され、1980~1990年代にかけて普及しました。それまで使われていたのは、ブタやウシの膵臓から抽出・精製されたインスリンでした。精製技術が進歩するにつれ、アレルギーなどの副反応は減ってはいたものの、インスリンに対する中和抗体ができ、治療に難渋することも経験しました。ヒトインスリン製剤の開発には、そのような臨床の要請が大きかったと思いますが、世界中で糖尿病患者が増加の一途を辿っており、そのうち世界中のブタとウシから得られるインスリンだけでは需要に応えきれなくなる、ということもヒトインスリン製剤の開発が急がれた理由のひとつと聞いた覚えがあります。
鳴物入りで登場したヒトインスリン製剤のおかげで、中和抗体ができて治療に難渋することは極めて少なくなりましたが、中間型ヒトインスリンの半減期はブタやウシの製剤に比べて短く、私が当時勤務していた朝日生命糖尿病研究所に、通院中の1型糖尿病の患者さんの7%は中間型を1日に3回注射されていました。ある患者さんは、毎日午前2時に目覚ましをかけて3回目の中間型インスリンを注射するよう指導され、厳格に守っていました。
生物由来でないインスリンアナログが登場
2001年に最初のインスリンアナログである超速効型インスリンの販売が開始され、これまでは食事の30分前に打つ必要があった食後の血糖上昇に対応するインスリンを食事の直前に打てばよくなり、患者さんの利便性が大きく向上しました。
続いて、2003年12月にインスリングラルギンの販売が開始されました。半減期が長く、中間型インスリンに比べて血中濃度のピークが緩やかなインスリングラルギンが使われるようになり、全ての1型糖尿病患者さんが1日3回の中間型インスリン注射から解放されました。1日2回の中間型インスリン注射が1回で済む方も多くおられ、このインスリンは1型糖尿病の方にとってインスリン注射の負担感を大いに軽減しました。ところが、2003年12月にインスリングラルギンと同時に販売が開始されたインスリングラルギンのディスポ型注入器が、大変残念なことに、簡単な誤操作で破損・故障することが報告されました。必要量よりも過量のインスリンが注射される事例(1例は6単位注射のつもりが160単位注入された)が10例報告されたため、わずか3カ月後に自主回収となりました。ペン型注入器も正しく使用しないと過量投与の可能性があると、2004年4月に国から緊急安全性情報が出されました。せっかくよいインスリン製剤が出たのに、リスクがある注入器と向き合わなくてはならなくなった患者さん方の失望は大変大きなものでした。当時、インターネット上の「掲示板」にペン型注入器回収のスレッドが立てられ、多くの1型糖尿病患者さんの嘆く書き込みを目にしたことを覚えています。中間型のカートリッジに、空のバイアルから吸ったインスリングラルギンを充填して使っている、との強者(?)の書き込みも目にしました。後に、インスリングラルギン用の新しい注入器が日本のメーカーの監修のもと制作・販売され、この騒動は終結したと聞いた覚えがあります。2005年に日本の工場の独創的なアイデアで登場したダブルテーパー構造のインスリン注射針もそうですが、ものづくりといえば日本、という時代を誇らしく思った記憶があります。