【最新号】3巻6号(2025年11・12月号)
特集
セミナー
連載
特集
-
3巻6号(2025年11・12月号)
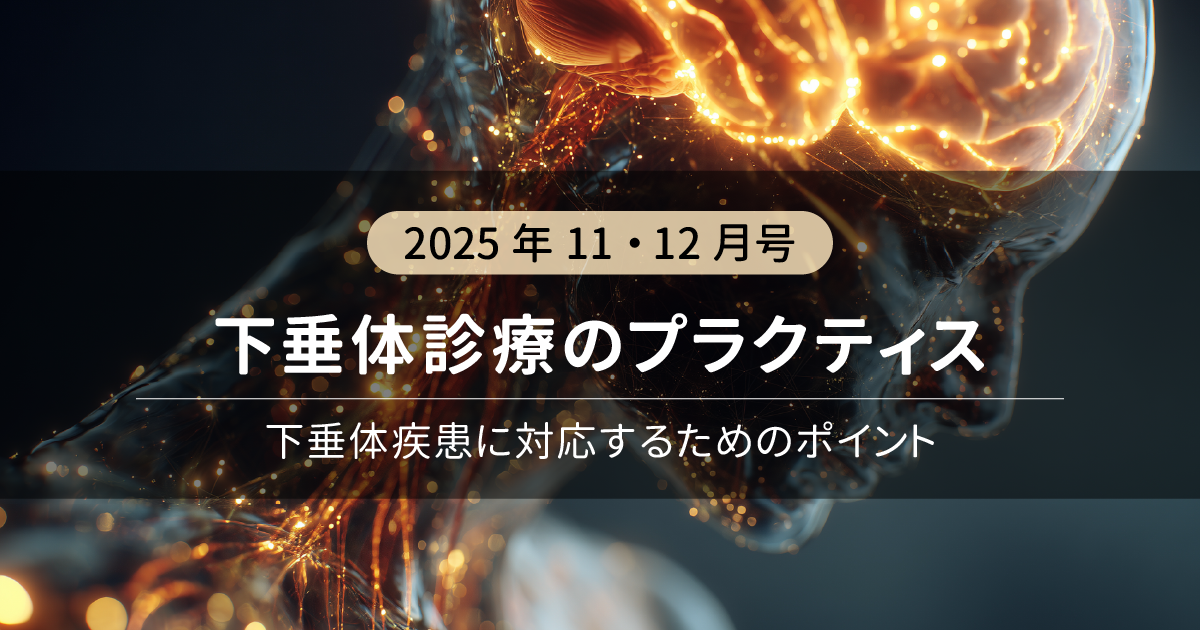
-
3巻5号(2025年9・10月号)
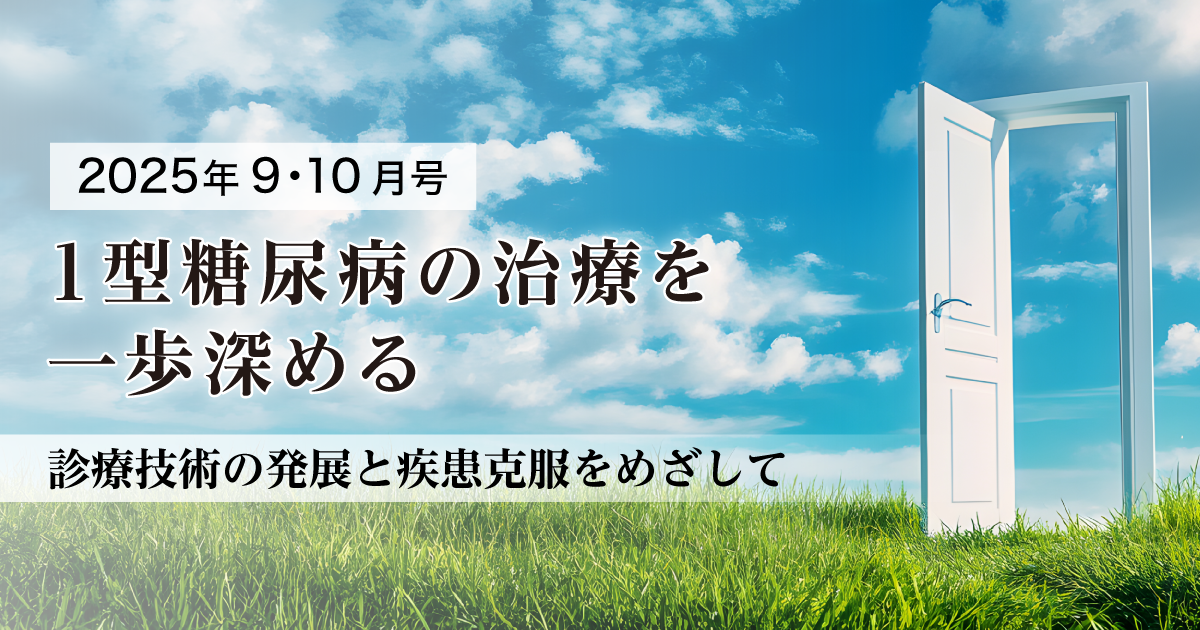
-
3巻4号(2025年7・8月号)
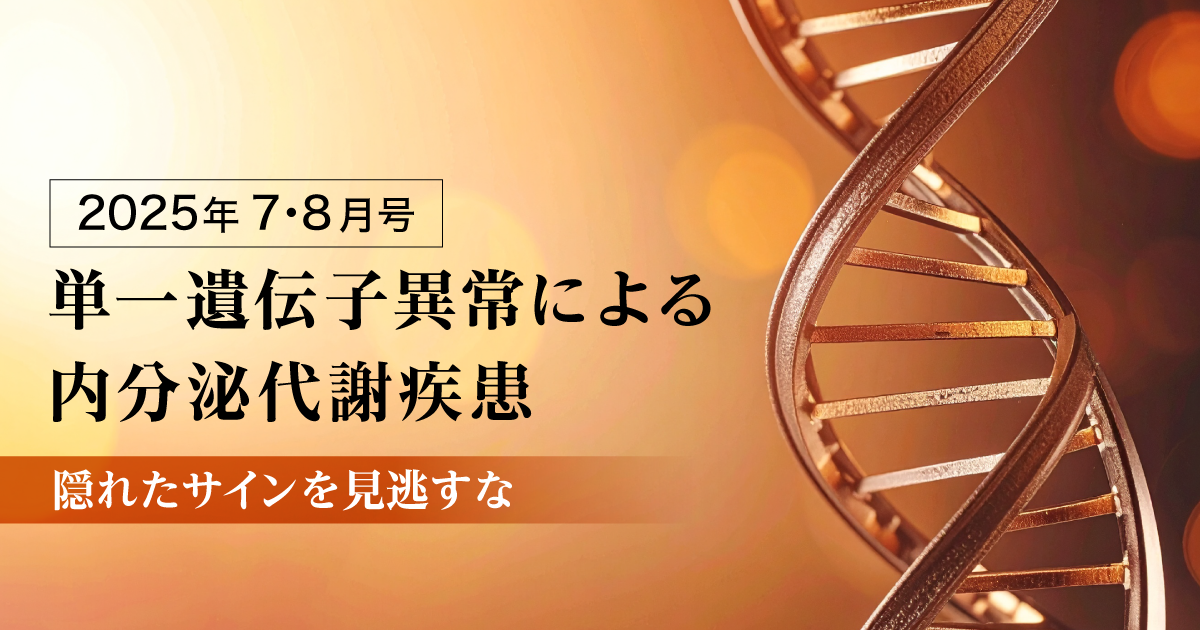
-
3巻3号(2025年5・6月号)
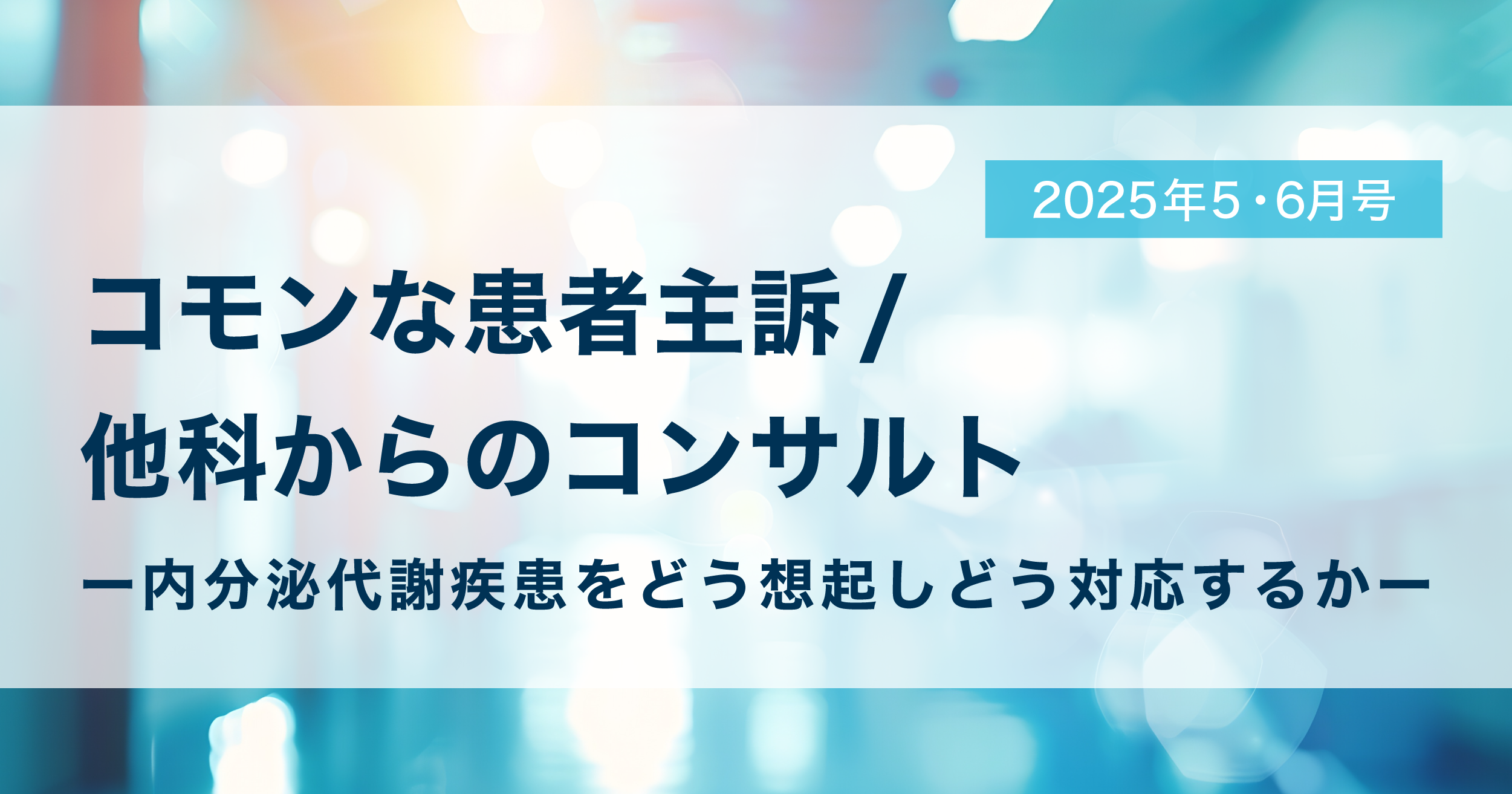
-
3巻2号(2025年3・4月号)
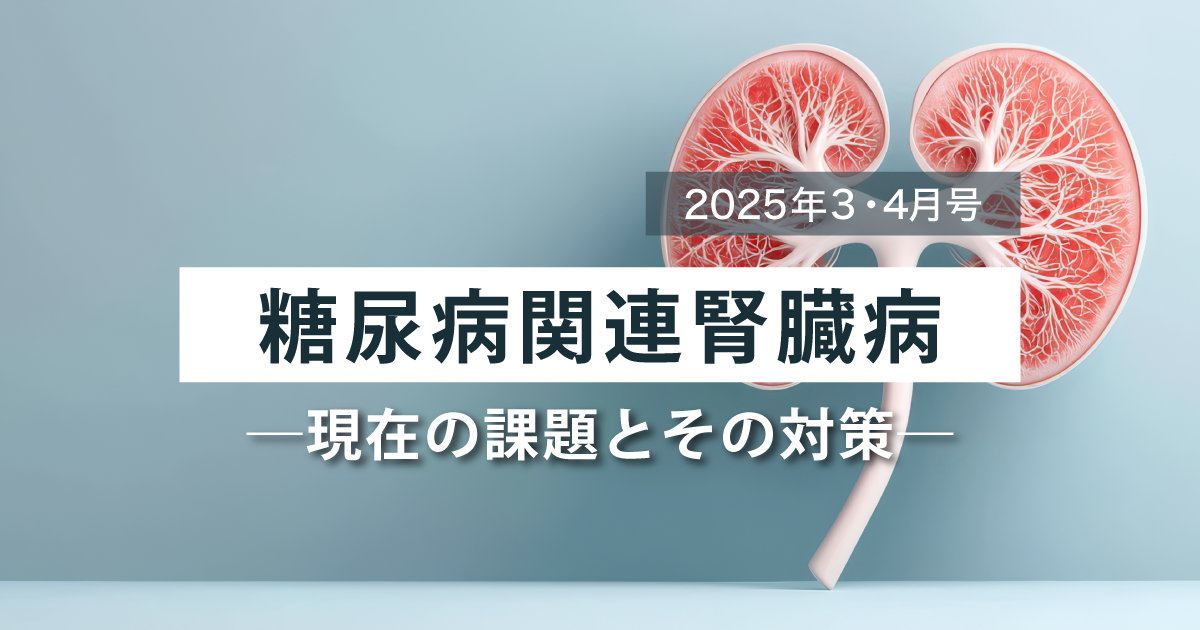
-
3巻1号(2025年1・2月号)
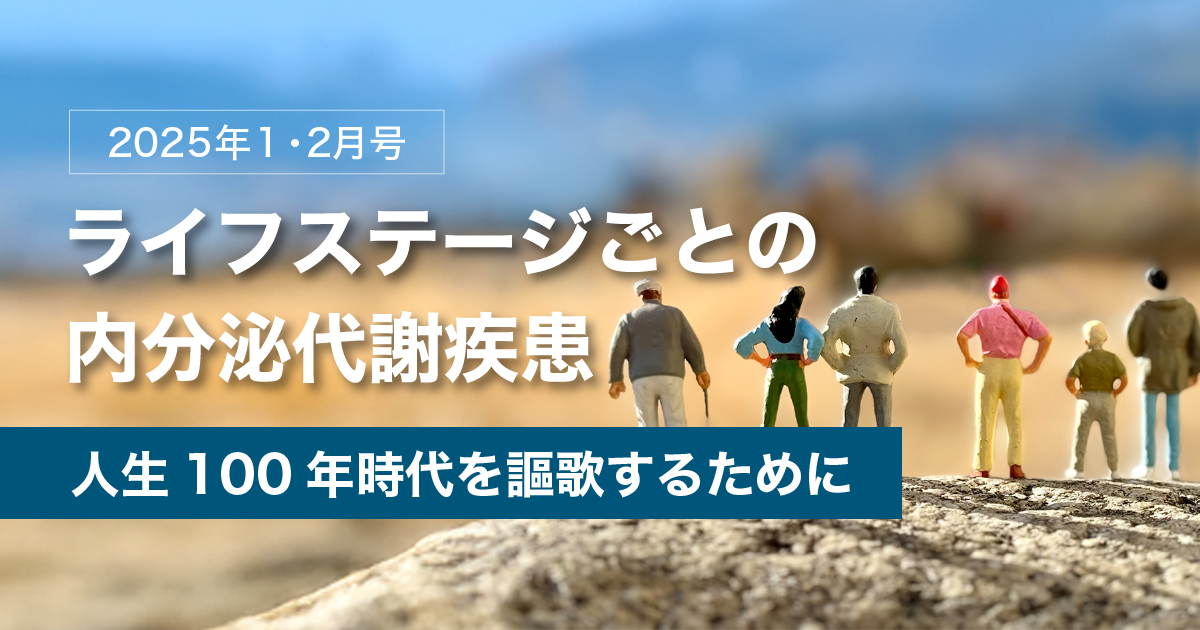
セミナー
連載
-

続 糖尿病と保険診療
-

糖尿病診療いま昔 ―流行・不易の心象風景―
-

糖尿病・内分泌疾患で用いる漢方
-

エビデンスの裏側 ―眼光紙背に徹す論文読解学―





