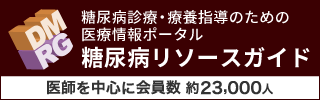- トップページ
- 新着論文一覧
新着論文一覧
-
連載

第4回 更年期障害への加味逍遙散
はじめに 更年期障害は卵巣機能の低下に伴う多彩な症状を呈し、インスリン抵抗性増大や血糖値上昇をきたすなど、糖尿病や内分泌疾患とともに生きる女性にとって大きな負担となることが少なくない 1)。漢方治療は、個々の患者の「証」に基づき心身一如の対応が可能なため、ホルモン療法の適応外・不耐例や併用療法としても期待される。加味かみ逍しょう遙散ようさんは婦人科三大処方として、現在最も多く処方されている漢方薬のひとつである 2)。 1.更年期障害への対応 更年期は、閉経前後5年の合計10年間とされ、この時期に現れる多種多様な症状のうち、器質的変化に起因しない症状を更年期症状と呼び、その中で日常生活に支障をきたす病態を更年期障害と定義する。更年期症状には、①顔のほてり・のぼせ(ホットフラッシュ)・発汗などの血管運動神経症状、②易疲労感・めまい・動悸・頭痛・肩こり・腰痛・関節痛・足腰の冷えなどの身体症状、③不眠・イライラ・不安感・抑うつ気分などの精神症状がみられる。 日本産科婦人科学会のガイドラインでは、更年期障害への対応として、①受容と共感による傾聴、②生活習慣の改善指導、③カウンセリングや認知行動療法などの心理療法、④ホットフラッシュ、発汗、不眠などが主な症状であればHRT(ホルモン療法)、⑤HRTでは、子宮摘出後はエストロゲン単独を、子宮がある場合はエストロゲンと黄体ホルモンを併用、⑥不定愁訴と呼ばれる多彩な症状を訴える場合には漢方療法などを用いる、と記載されている 3)。
2025年12月11日 -
特集

5.下垂体機能の評価:ホルモン基礎値の評価から内分泌負荷試験の実際と注意点
はじめに 内分泌系は、神経系、免疫系と共に生体の恒常性を維持する役割を担っている。下垂体は、その上位器官の視床下部と共に内分泌調節機構の中心である。下垂体は、副腎刺激ホルモン(ACTH)、甲状腺刺激ホルモン(TSH)、ゴナドトロピン(黄体形成ホルモン〔LH〕、卵胞刺激ホルモン〔FSH〕)、成長ホルモン(GH)、プロラクチン(PRL)を産生・分泌する前葉(腺下垂体)と視床下部で産生されたバソプレシン、オキシトシンを分泌する後葉(神経下垂体)に分けられる。下垂体疾患を疑った場合、診断、治療方針決定に下垂体機能評価は必須である。本稿では、下垂体疾患を疑った場合のホルモン基礎値およびホルモン分泌能検査の基本、施行上の注意点を概説する。 1.下垂体ホルモン分泌障害を疑った場合の検査の進め方 下垂体はホルモン産生、分泌臓器であり、注意深い問診、診察により下垂体ホルモン分泌低下症、下垂体ホルモン分泌過剰症による症状、症候をとらえることが重要である。これらの症状、症候より疑われる下垂体ホルモンおよびその標的臓器ホルモン、バソプレシンの場合には血漿浸透圧(または血清Na)、尿浸透圧を測定する(表1)。ホルモン基礎値の明らかな異常が認められなくても、症候などより下垂体ホルモン分泌低下症が疑われる場合、ホルモン分泌刺激試験により下垂体ホルモン分泌能を評価する。逆に下垂体ホルモン分泌過剰症が疑われる場合、生理的な調節機構を逸脱しているかを評価するため、ホルモン分泌抑制試験を行う。これらにより異常下垂体ホルモンの種類とその分泌状態(低下、亢進)を明らかにすることができる(図1)。
2025年12月11日 -
特集

4.自己免疫性下垂体疾患:新たな疾患概念とその臨床的意義
はじめに 視床下部下垂体炎は、ほかの自己免疫疾患を合併する例、種々の自己抗体の陽性例、さらに下垂体へのリンパ球浸潤がみられることから、自己免疫的機序の関与が示唆されている。中でもリンパ球性下垂体炎は、その代表的な病態である。下垂体炎は原発性、二次性に分類され、さまざまな疾患との鑑別を要する(表1)。下垂体機能低下症や中枢性尿崩症(アルギニンバソプレシン〔arginine vasopressin:AVP〕欠乏症)に対しては、適切な評価を踏まえたホルモン補充が基本的治療となる 1, 2)。自己免疫性下垂体炎の病態として、近年、本邦からの報告を中心に、リンパ球性下垂体炎、免疫チェックポイント阻害薬(immune checkpoint inhibitor:ICI)関連下垂体炎、傍腫瘍性自己免疫性下垂体炎に関する新たな知見が蓄積されつつある。 表1 下垂体炎の原因と鑑別 1.リンパ球性下垂体炎 リンパ球性下垂体炎は、下垂体や視床下部にリンパ球や形質細胞浸潤を認め、主たる炎症の病変部位により、リンパ球性下垂体前葉炎、リンパ球性漏斗下垂体後葉炎(lymphocytic infundibulo-neurohypophysitis:LINH)、リンパ球性汎下垂体炎に分類される。LINHの診断は、中枢性尿崩症の臨床・検査所見とMRI画像所見(下垂体茎の肥厚または下垂体後葉の腫大、病変部位の均一な強い造影増強効果)から総合的に診断する 1, 2)。下垂体腫瘍やその他の炎症性/肉芽腫性疾患などとの鑑別が困難なこともまれではなく、診断上の課題も多い。機能と画像所見の両面から、さらに経時的変化を踏まえた判断が必要となる。 近年、自己免疫性下垂体炎の中でも下垂体後葉や漏斗部を主病変とする中枢性尿崩症の症例において、血中に抗ラブフィリン3A抗体が高頻度に検出され、ラブフィリン3AがLINHの原因抗原であることが示された 3, 4)。 ラブフィリン3Aはエキソサイトーシスを含む小胞輸送の重要な制御因子であり、下垂体後葉と視床下部のAVPニューロンに発現する 3)。ラブフィリン3Aをマウスに免疫原として投与すると、下垂体後葉および視索上核にリンパ球浸潤が生じ、低張尿の増加などLINHに類似した病態を呈した。この結果から、ラブフィリン3Aが病原性抗原として機能し、特異的T細胞の免疫応答による炎症がLINHの発症に関与することが示唆された 5)。さらに、ラブフィリン3Aのユビキチン化を制御する分子(cullin-associated NEDD8-dissociated protein 1:CAND1)も関与する可能性が示され、病因・病態の解明が進みつつある 6)。
2025年12月04日 -
セミナー

歯科疾患を有する糖尿病患者への対応・支援
Q&A編はこちら はじめに 1990年代と比較すると、わが国の糖尿病人口は大幅に増加している。この事実は、歯科疾患を有した糖尿病人口の増加を示唆するものである。う蝕と歯周病は、2大歯科疾患ともいうべき存在であるが、いずれも進行すると咀嚼機能の低下をもたらす。咀嚼機能の低下は、食事摂取に大きな影響を与え、とりわけ栄養管理が重要な糖尿病患者における影響は、健常者よりも相当に大きい。従って、歯科疾患を有する糖尿病患者が適切な口腔ケアを受けられるように、医療従事者の対応や支援が重要である。本稿では、2大歯科疾患の説明を加えながら、糖尿病患者におけるこれらの疾患の進行による影響、そして糖尿病患者の口腔ケアを多職種連携の観点から解説する。 1.糖尿病患者における歯科疾患 国民健康・栄養調査から、2000年代以降の「糖尿病が強く疑われる者」および「糖尿病の疑いがある者」は、1990年代の約2倍となり大きく増加している 1)。糖尿病には、1型糖尿病や2型糖尿病、妊娠性糖尿病や薬剤・疾患に合併した糖尿病などさまざまな種類があるが、中でも2型糖尿病の割合が最も多い。2型糖尿病は、食事やライフスタイルの欧米化によって、肥満となりインスリン抵抗性が惹起されて発症すると理解されている。すなわち、2型糖尿病は生活習慣病・成人病としての側面を強く持ち、同疾患を発症する素地として、さまざまな生活習慣上の問題点が存在することが多いと考えられる。 う蝕と歯周病は、その罹患率の高さから2大歯科疾患として長らく認識されている。両疾患とも、ブラッシング不良による磨き残しに口腔内細菌が繁殖し、それぞれのプラークとなり、蓄積することによって発症するバイオフィルム感染症である(図1)。 図1 う蝕と歯周病 う蝕は、ミュータンス菌などのう蝕の原因菌が糖分などを栄養に酸を産生し、エナメル質や象牙質を破壊することで起こる。う蝕の好発部位は、磨き残しが発生しやすい歯冠(歯の頭)の裂溝(小さな溝)や隣接部(歯と歯が隣り合う場所)、そして根面(根元)である。う蝕が進行すると、冷温刺激や甘味などに応じて一過性の知覚過敏(しみる症状)や疼痛が強くなり、やがて刺激に応じて持続的な疼痛や、自発痛(いわゆる歯痛)が起こる。このように歯髄症状を呈した場合の多くは、歯髄の除去(抜髄)が必要となる。歯髄がなくなった歯は失活し、生活歯(歯髄が残っている歯)と比較して、長期的に破折するリスクが高まり、歯の保存に大きな影を落とす。2型糖尿病患者では、健常人と比較してう蝕発生率には有意な差はないが、根面う蝕の発症率は2倍以上との報告 2)や、小児1型糖尿病患者では活動性う蝕の増加がみられるとの報告 3)がある。 対して、歯周病菌はポルフィロモナス・ジンジバリス菌などのグラム陰性細菌が主体であり、歯肉よりも深部の歯周ポケット内のプラーク中で増殖し、歯周組織に感染して炎症を誘発する。歯周病は歯肉に炎症が起きることで発赤・腫脹や排膿・出血を呈し、歯を支える歯肉(歯ぐき)や歯槽骨が破壊され、やがて歯が動揺し最終的に脱落あるいは抜歯を余儀なくされる。かつては、う蝕が成人の抜歯の原因疾患として最多であったが、8020運動の推進などにより、う蝕有病率は大きく減少し、現在では歯周病が抜歯の原因疾患の第一位の座にある 4)。
2025年11月27日 -
セミナー
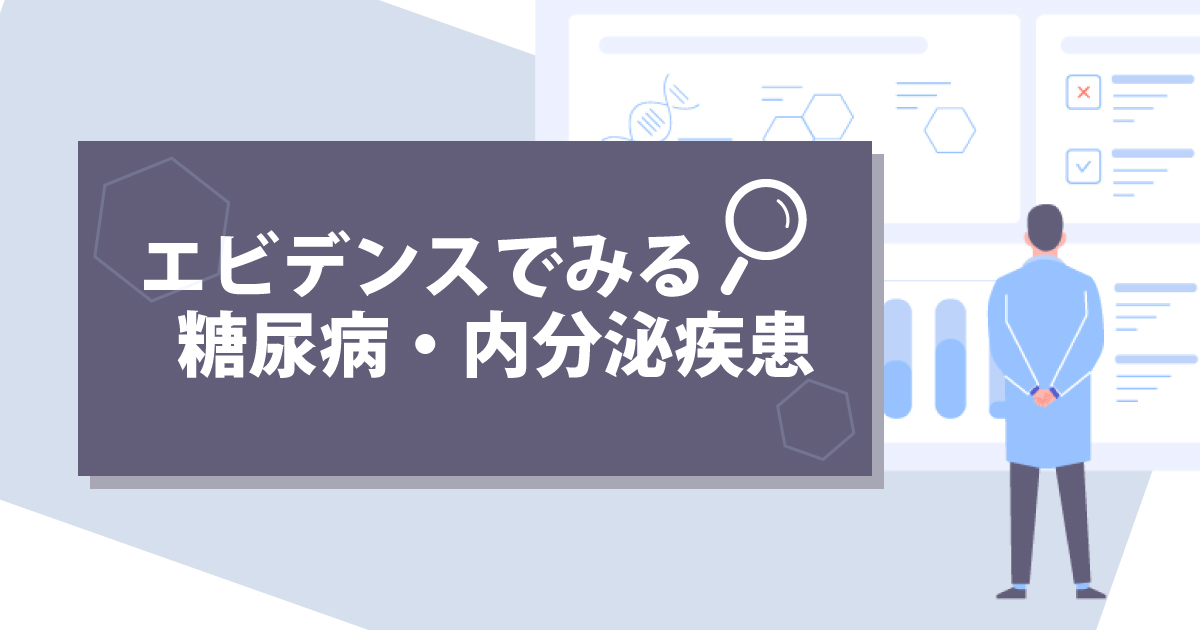
入院患者の血糖マネジメントに関する最新エビデンス
ポイント 適切な血糖マネジメント目標値は患者の状態(ICU/非ICU、周術期/非周術期)によって異なる。 basal-bolusインスリン療法(基礎-追加インスリン療法)は入院患者の血糖マネジメントにおいて従来のスライディングスケール(sliding scale〔SS〕)よりも効果的である。 専門的な糖尿病ケアチームの介入は入院期間短縮や再入院率低下に寄与する。 持続血糖モニタリング(Continuous Glucose Monitoring:CGM)や人工膵臓などの新技術が入院患者の血糖マネジメントに導入されつつある。 GLP-1受容体作動薬など新しい薬剤の入院での使用に関するエビデンスが蓄積中である。 1.総論 入院患者の血糖マネジメントは、糖尿病の有無にかかわらず入院アウトカムに大きく影響する。近年、米国糖尿病学会(ADA)など主要学会からガイドラインが発表され、具体的な血糖マネジメント目標値や管理方法が提示されている。入院時の高血糖は免疫機能低下、炎症反応増加、血管内皮機能障害などを引き起こし、さまざまな合併症リスク増加と関連する。一方で、過度な血糖降下による低血糖も有害事象と関連するため、患者状態に応じた適切な血糖マネジメント目標の設定が重要となる。
2025年11月27日 -
TRENDS

「先進医療機器により得られる新たな血糖関連指標に関するコンセンサスステートメント」について
1.日本におけるCGM導入と現状 日本では2010年に持続グルコース測定(Continuous Glucose Monitoring:CGM)が保険適用となった。その後、特にCOVID-19パンデミック以降、CGM機器の利用は急速に拡大し、日常診療においても広く用いられるようになった。この普及に際して、膨大なCGMデータをいかに標準化して評価し、臨床の場に還元するかという課題が表在化した。その解決策の一つとして、血糖コントロールの評価指標である「Time in Range(TIR)」という概念が提唱された 1)。 2.Time in Range(TIR)という概念の確立 2019年に開催された国際会議「Advanced Technologies and Treatments of Diabetes(ATTD)」において、TIRに関する国際コンセンサスステートメントが発表された。このステートメントでは、血糖値70~180mg/dLの範囲を「目標血糖範囲」と定義し、その範囲内にある時間の割合をTIR(%)とした。さらに、目標範囲を超える高血糖はTAR(Time Above Range)、下回る低血糖はTBR(Time Below Range)と定義された 1)。
2025年11月20日 -
TRENDS

甲状腺眼症の新しい治療薬(テプロツムマブ)
はじめに 甲状腺眼症は、バセドウ病に合併して発症する自己免疫性の眼窩疾患である。眼瞼腫脹、眼球突出、羞明、眼痛など多彩な症状を呈し、重症例では複視や視力低下など視機能の低下に至ることもある。慢性かつ再燃性の経過をとることが多く、患者のQOLに与える影響は極めて大きい。 1.甲状腺眼症の治療法 治療法の詳細は『バセドウ病悪性眼球突出症(甲状腺眼症)の診断基準と治療指針2023(第3次案)』(日本甲状腺学会・日本内分泌学会)1)を参照されたい。高度の眼球突出や複視を伴う中等症~重症例で、Clinical Activity Score(CAS)が高値を示す、あるいはMRIで明らかな炎症所見を認めるような活動性甲状腺眼症に対しては、従来ステロイドパルス療法が第一選択であった。しかし、3日間連続投与を3週繰り返す「Daily法」では入院が必要であり、週1回投与を12週継続する「Weekly法」では改善までに時間を要する。さらに、眼球突出の改善は得られにくく、副作用のリスクも高いなど、ステロイドパルス療法には課題があった。 このような背景のもと、病態メカニズムに基づく分子標的薬として登場したのが、IGF-1受容体に対するヒト型モノクローナル抗体「テプロツムマブ」である。甲状腺眼症では、眼窩線維芽細胞が病態の中心的役割を担っているが、その表面には甲状腺刺激ホルモン(TSH)受容体が発現しており、バセドウ病に伴うTSH受容体抗体による刺激を受け、炎症・浮腫や脂肪増生などの組織変化を誘導することが知られている。一方、テプロツムマブの標的であるIGF-1受容体はTSH受容体と共発現し、クロストークを介したシグナル伝達によって、これらの変化に寄与していると考えられている。
2025年11月20日 -
特集

3.クッシング病の診断と治療update
はじめに クッシング病は、下垂体の副腎皮質刺激ホルモン(ACTH)産生腫瘍からACTHが過剰分泌され、その結果として副腎皮質からコルチゾールが過剰産生される疾患である。過剰なコルチゾールにより、満月様顔貌、中心性肥満、野牛肩(肩部脂肪沈着)、皮膚の菲薄化と赤色皮膚線条、筋力低下などの特徴的な臨床症状を呈し、また高血圧、耐糖能異常・糖尿病、骨粗鬆症、抑うつ傾向、易感染性など全身の合併症を伴いやすい。早期に治療を開始しなければ、感染症や心血管イベントにより生命予後が悪化するため、早期診断と治療が重要である。 1.クッシング病の症候・徴候と診断 1)クッシング病の症候 クッシング病で見られる症候、および徴候とその頻度を図1 1~3)に示す。特異的症候を主訴として来院した症例では診断に至ることは比較的容易であるが、非特異的症候、特に高血圧や耐糖能異常、骨粗鬆症など一般に頻度が高い症候を呈する症例でも、特異的症候がないかを常に意識して診療することがクッシング病を見逃さないために重要である。特異的症候を示す場合でも、医原性に副腎皮質ステロイドが投与されている場合もあるため、問診の際には副腎皮質ステロイドの投与の有無について、経口投与に限らず点鼻薬、関節注射、吸入薬、外用薬などの投与経路についても確認する必要がある。 図1 症候・徴候の頻度表(文献1~3を参考に作図) クッシング病の診断フローチャートを図2 3, 4)に示す。クッシング病を疑う所見を得た場合、次に血液検査を行い、ACTHとコルチゾールを同時測定し、ともに正常〜高値を示すことを確認する。採血は早朝(午前8時から10時の間)、30分の臥床安静後に行うことが望ましい。また、蓄尿検査が可能である場合は尿中遊離コルチゾールが高値であることも確認する。外来で検査を進める場合は、次のスクリーニング検査も並行して行うこともある。 スクリーニング検査としては、一晩少量(0.5mg)デキサメタゾン抑制試験ならびに血中コルチゾール日内変動の確認を行う。少量デキサメタゾン抑制試験では、翌朝の血中コルチゾールが5μg/dL以上であればクッシング病を疑うが、3μg/dL以上の場合でもサブクリニカルクッシング病の可能性がある。コルチゾール日内変動では、深夜睡眠時のコルチゾールが5μg/dL以上であることを確認する。
2025年11月20日 -
セミナー

ミトコンドリアの機能とそれへの薬理
はじめに ミトコンドリアは赤血球を除く全ての真核細胞に存在し、好気的呼吸により効率よくアデノシン三リン酸(ATP)を産生し、全身の代謝を制御する。インスリンを産生し分泌する膵β細胞においては、ミトコンドリアで産生されたATPはKATPチャネルを閉鎖し、細胞の脱分極を誘導することによりグルコース応答性インスリン分泌を惹起する。また、小胞体などの細胞内小器官との相互作用や、ミトコンドリアオートファジー(マイトファジー)の異常が、膵β細胞の機能障害に関わることがわかっている。本稿では、糖代謝に関与する骨格筋、脂肪組織、肝臓、および膵β細胞におけるミトコンドリアの役割や糖尿病病態への関与、さらに既存の糖尿病治療薬がミトコンドリアに与える影響などに関して概説する。 1.骨格筋におけるミトコンドリアの役割 加齢による筋力低下(サルコペニア)は日常生活動作(ADL)や生活の質(QOL)の低下を招き、特に糖尿病患者においてはサルコペニアが進行しやすいため、骨格筋を標的とした治療戦略が求められている。骨格筋は全身の熱消費量の約30%を占め、生体内の組織の中で最もエネルギーを消費する。遅筋と速筋に大別され、遅筋においてはミトコンドリアが多く含まれ、主に好気的代謝を行い持久力運動などに関わる。速筋においては解糖系酵素の活性が高く、主に嫌気的代謝が行われ瞬発的な筋肉収縮に関わり、ミトコンドリア含量が少ない。高齢者や糖尿病患者の骨格筋では、ミトコンドリアの量や機能が低下していることがわかっている。骨格筋において、ミトコンドリアの機能低下はジアシルグリセロール(DAG)などの脂質の蓄積を誘導し、IRS-1(インスリン受容体基質-1)のセリンのリン酸化促進とチロシンのリン酸化阻害によりインスリン抵抗性を惹起する。また、DAGはトリアシルグリセロールとして骨格筋に蓄積し、サルコペニアの形成に関わる。ミトコンドリアの生合成や脂肪酸酸化に関与するPGC-1α(peroxisome proliferator-activated receptor gamma coactivator 1-alpha)は骨格筋、褐色脂肪細胞、肝臓などに発現し、2型糖尿病患者の骨格筋ではPGC-1αのプロモーター領域のメチル化の増加やmRNAの低下により、ミトコンドリアの機能や量の低下に関わる可能性が示されている 1)。PGC-1αは持続的な運動によって増加し、骨格筋特異的にPGC-1αを過剰発現したマウスでは、骨格筋のミトコンドリア量が増加し持久的運動能が上昇する。骨格筋においてPGC-1αにより増加し、血中に分泌されるマイオカインのIrisin(イリシン)は白色脂肪細胞のベージュ化を促進する 2)。また、ミトコンドリアの分裂に関わるDrp1(Dynamin-related protein 1)を骨格筋で欠損したマウスでは、ミトコンドリア病のバイオマーカーであるGDF15(Growth Differentiation Factor 15)が増加し、速筋の成長が阻害されることが示されている 3)。糖尿病治療薬のメトホルミンはミトコンドリアのComplex Ⅰを阻害し、アデノシン一リン酸(AMP)の増加およびAMP活性化プロテインキナーゼ(AMPK)の活性化を誘導するが、AMPKα2は骨格筋においてミトコンドリアの生合成やPGC-1αの発現増加に寄与することが明らかとなっている 4)。
2025年11月13日 -
特集

2.先端巨大症の診断と治療update
はじめに 先端巨大症は特徴的な身体所見を呈する疾患であるが、現在も診断までに時間を要していることが多く、早期診断には課題が残っている。一方、治療法は多様に発展しており、その適切な選択が求められている。また治療目的として、生化学的寛解に加え、生活の質(QOL)や合併症の改善の重要性が注目されている。本稿では、先端巨大症の概要を述べ、日常診療におけるポイントを解説する。 1.原因と病態 先端巨大症は、主に成長ホルモン(GH)の過剰分泌を原因とし、その結果、インスリン様成長因子(IGF)-Ⅰ作用も過剰となる。GHは主にIGF-Ⅰを介して骨格筋、骨、軟骨における成長に関わっていると同時に、肝臓や筋肉、脂肪組織などに作用し、代謝を調整するホルモンである。しかし、本症における過剰なGHとIGF-Ⅰは、心血管系、呼吸器系、腫瘍性疾患の高い罹患率と、これらに起因した死亡率上昇と関連している。 本疾患のほとんどが、GH産生下垂体腫瘍によって発症するが、まれな原因として、成長ホルモン放出ホルモン(GHRH)産生腫瘍などが知られている。骨端線閉鎖前に発症した場合には高身長を呈し、「下垂体性巨人症」として「先端巨大症」と区別される。
2025年11月13日 -
特集

1.画像所見と臨床所見に基づいた下垂体疾患の診断
はじめに 下垂体疾患の鑑別診断には画像診断、特にMRIが重要である。MRIは禁忌(喘息、高度の腎機能障害、造影剤アレルギーなど)がなければ可能な限り造影を行う。シーケンスはspin echo法のT1およびT2強調画像の冠状断と矢状断が基本であるが、疾患の診断に合わせて軸位断やspoiled gradient echo法、T2*強調画像などのシーケンスを追加する。また、磁場の高いMRIを用いるとS/N比が高くなり、画像が鮮明になる。石灰化の検出にはCTが有用である。しかしながら、画像のみで完全に診断をつけることは難しい場合があるため、ほかの臨床所見と組み合わせて診断を進めることが重要である。 1.下垂体神経内分泌腫瘍(PitNET) PitNETは下垂体前葉内部から発生する腫瘍であるため、腫瘍周囲を正常下垂体が覆っていることがほとんどである。腫瘍が大きくなると主に前葉は上方~後方へ圧排され、左右はいずれかに偏ることが多い。下垂体は強い造影効果を伴い造影T1強調画像で高信号となるが、PitNETは正常下垂体と比べると造影効果がやや弱いため前葉と区別できる(less enhancement)(図1)。また、造影を行うと前葉よりも遅れて造影効果が生じ、約90秒前後で最も正常下垂体とのコントラストが強くなる(golden time)。造影後、短時間での撮像を繰り返すことでこのコントラストが強い時間を用いてmicrotumor(微小腫瘍)の検出を行うダイナミックMRIがある。ただし、ダイナミックMRIは短時間の撮影を行うことで解像度が悪くなるため、近年はこのgolden time前後で解像度の高い撮影を行うことが多くなっている。 腫瘍はサイズによって10mm未満をmicrotumor、10mm以上をmacrotumorと呼ぶ。また、40mm以上をgiant tumorとする場合もある。PitNETは球形のみではなく、しばしば不整形に上方や外側へ進展し、トルコ鞍底の骨破壊を伴い蝶形骨洞や斜台に進展することもある。上部では鞍隔膜部分で腫瘍がくびれてダンベル型(または雪だるま型)と呼ばれる形態となるものがある。この場合、手術時に鞍上部部分が下降しにくく、全摘出が困難なことがあるため注意が必要である 1)。左右側方への伸展は、冠状断の内頸動脈膝部が見えるスライスで上下の内頸動脈(C3、4)を基準として、どの程度外側へ伸展しているかを分けるKnosp分類を用いることが一般的である。Knosp分類は腫瘍が内頸動脈内側にとどまる場合をgrade 0、内頸動脈の中心を越えない場合をgrade 1、中心を越えて外側を越えない場合をgrade 2、外側を越える場合をgrade 3、内頸動脈を取り囲む場合をgrade 4とする 2)。Gradeが上がると海綿静脈洞浸潤が増加し、先端巨大症では寛解率が異なることが報告されている 3)。また、grade 3は膝部より外側に進展する場合を3A、C4より下で内頸動を外側に越える場合を3Bと分けられ、BはAよりも寛解率が悪い 4)。 疾患別では、先端巨大症では病理亜型のdensely granulated somatotroph PitNETではT2強調画像で低信号となりやすく、薬物療法が有効であることを予測しやすい 5)。クッシング病は約半数がmicrotumorであり、中には腫瘍の描出が難しい場合がある。微小な腫瘍ではthin slice(薄層撮像)の3D撮影が有効で、特にspoiled gradient echo法は腫瘍と正常下垂体とのコントラストが強く診断に有用である 6)。非機能性PitNETのうち、TPITが陽性となるsilent corticotroph PitNETは一般に女性に多く、上方よりも側方の伸展が強く、T2強調画像でmicrocyst(小嚢胞)が多数認められることが特徴である 7, 8)(図2)。
2025年11月06日 -
特集

(扉)特集にあたって
下垂体は「ホルモンの司令塔」と称され、全身の恒常性維持に重要な役割を担う。その一方で、疾患の稀少性や症状の多彩さ、診断・治療に高度な専門性を要することから、臨床現場では常に課題が存在してきた。近年は画像診断技術や内分泌検査の精緻化、外科・内科治療の進歩、免疫学的研究や分子病態の解明などにより、下垂体疾患診療は大きな変革期を迎えている。こうした背景を踏まえ、本特集では「プラクティス」という視点から、日常診療に直結する最新知識と実践的対応を提示することを目的とした。 まず福原紀章先生(虎の門病院)による「画像所見と臨床所見に基づいた下垂体疾患の診断」では、傍鞍部に生じる多彩な病変をいかに鑑別するかという基本課題を取り上げた。MRI所見に加え、病態や臨床症状を統合して判断する姿勢は不可欠であり、豊富な臨床経験に基づいた解説と画像は日常診療の指針となろう。 続いて大町侑香先生・福岡秀規先生(神戸大学)による「先端巨大症の診断と治療update」、亀田啓先生(北海道大学)による「クッシング病の診断と治療update」では、代表的な機能性下垂体腫瘍の診断と治療戦略が整理されている。腫瘍の制御に加え、心血管疾患や骨代謝異常、感染症など全身合併症への対応が予後に直結するため、包括的視点の重要性が強調される。新規薬物療法や治療方針のアップデートは、日常診療に対して大きな示唆となるだろう。 さらに浦井伸先生・髙橋裕先生(奈良県立医科大学)による「自己免疫性下垂体疾患:新たな疾患概念とその臨床的意義」では、リンパ球性漏斗下垂体後葉炎の自己抗原として同定されたラブフィリン3A抗体、免疫チェックポイント阻害薬による下垂体炎や傍腫瘍性自己免疫性下垂体炎など、新たに明らかとなった疾患概念が紹介される。内分泌学と腫瘍免疫学が交差する領域であり、今後の研究進展が期待される。 また大月道夫先生(東京女子医科大学)による「下垂体機能の評価:ホルモン基礎値の評価から内分泌負荷試験の実際と注意点」では、基礎値評価と負荷試験の解釈に加え、下垂体卒中やブロモクリプチンによる悪心などのリスクが具体的に示され、医師のみならず看護師にとっても有用である。 最後に中野靖浩先生・大塚文雄先生(岡山大学)による「下垂体機能低下症におけるホルモン補充療法」では、一般的な補充療法に加え、年齢やライフステージに応じた工夫、さらにシックデイ対応や自己注射指導、服薬支援といった患者教育の実際が解説されている。医師のみならず看護師・薬剤師にとっても不可欠な知識である。 本特集で取り上げたテーマはいずれも日常診療に根ざし、かつ最新の学術的進歩を反映したものである。診断から長期フォローアップまでを支える実践的知識は、まさに「プラクティス」と呼ぶにふさわしい。下垂体疾患診療は今後さらに個別化医療・患者中心医療の観点からの発展が求められる領域であり、本特集がその一助となることを願う。 著者のCOI(conflicts of interest)開示:竹内靖博;講演料(協和キリン、アムジェン、アレクシオンファーマ) 本論文のPDFをダウンロードいただけます
2025年11月06日 -
連載

第80回 持続グルコースモニタリングデバイスと人工膵臓2025
はじめに 日本人工臓器学会では、人工膵臓は膵臓の機能、特にインスリンを適切なタイミングで適切な量を分泌して、血糖値を一定の幅でコントロールする機能の代替を自律的に行う装置と定義している。主な目的は、日常生活で血糖コントロールを行い糖尿病合併症の予防をすること、および手術や重症疾患など血糖値が上昇しやすい患者に人工膵臓を用いて治療成績を改善すること、と示している 1)。 人工膵臓は実際の血糖値とその変動状態を確認しながら、連続的に投与量を微調整していくことが可能であり、低血糖などのリスクが低減できる。そして、目的に応じた人工膵臓が開発されており、日本ではベッドサイド型人工膵臓と携帯型インスリン注入ポンプを使用することができる。 よって今回は、持続グルコースモニタリングデバイスおよび人工膵臓の診療報酬上の算定要件について、医科点数表および特掲診療料の施設基準の告示・通知について概説する。 1.ベッドサイド型人工膵臓と携帯型人工膵臓について 1, 2)(図1) ベッドサイド型人工膵臓は、図1に示すように、持続的な静脈血採血でリアルタイムに血糖値を測定し、設定した血糖値よりも上昇/低下すると、内蔵されている計算式により必要なインスリン量/グルコース量を演算し、それぞれのポンプで自動的にインスリン/グルコースを静脈に注入して設定内に自律的に血糖値を是正する。そしてベッドサイド型人工膵臓は、現状では日機装社製のSTG-55に限られ、「J043-6 人工膵臓療法」で算定する。ベッドサイド型人工膵臓は、血管内に留置した二重腔カテーテルから吸引した血中のグルコース値を連続して測定するが、携帯型人工膵臓は、皮膚下の「間質液」からグルコース濃度を測定して血糖値を予測する。 図1 ベッドサイド型人工膵臓である人工膵臓STG-55の血糖管理メカニズム(文献1, 2より) 携帯型人工膵臓は、日常生活の中で携帯して血糖コントロールを補助・代替してくれる装置で、大きく3種類に分けられる。 ①インスリンポンプ療法 インスリンポンプと注入回路を腹部などに装着することでインスリンを注入できる治療法であり、持続皮下インスリン注入療法(Continuous Subcutaneous Insulin Infusion:CSII療法)ともいう。基礎インスリンの投与のほかに、必要に応じて投与量の変更や注入のタイミングも簡単に調整することが可能である。 ②持続血糖測定 持続血糖測定(Continuous Glucose Monitoring:CGM)とは、腹部などにグルコース濃度測定センサを装着し、持続的に間質液のグルコース濃度を測定する。そして、インスリンポンプと持続血糖測定を組み合わせ、血糖値の変化を確認しながらインスリン投与を行うことが可能である。ただし、機器がそれぞれ独立しているため、投与量の増減には、必ず血糖の変化を確認して手動で設定を変更する操作が必要である。 ③SAP療法/HCL療法 SAP療法(Sensor Augmented Pump:SAP)は、インスリンポンプ療法と持続血糖測定の治療を連動して行う。センサにて測定したグルコース濃度を用い、血糖の変化を予測して低血糖が予想される場合は基礎インスリンを一時的に停止し、低血糖を回避すると再開するなどの機能を持っている。 ボーラスはボタン操作での投与が必要となる。また、HCL療法(Hybrid Closed Loop:HCL)は持続血糖測定と連動し、インスリンポンプがこれまでのインスリン投与情報と直近のグルコース濃度情報を用い、基礎インスリンを目標値に近づけるよう自動調整する機能を用いる。加えて、高血糖を予測し自動で補正インスリンを投与するインスリンポンプもある。ボーラスはカーボカウントの自動計算機能を用い、糖質量をボタン操作にてインスリンポンプに入力し投与する。
2025年10月30日 -
連載

第3回 こむら返りへの芍薬甘草湯
はじめに 有痛性筋痙攣、いわゆるこむら返りは、日常診療でもしばしば認められるが、糖尿病のある人では糖尿病のない人に比べて高頻度にみられ、生活の質(QOL)を低下させる症状のひとつである。特に、夜間に生じるこむら返りは睡眠障害の原因となり、日中の活動性低下や血糖コントロール増悪の悪循環を招くことが知られている。西洋医学的治療では、従来、筋痙攣に対して筋弛緩薬や抗痙攣薬(抗てんかん薬)が用いられてきたが、眠気などの副作用により使用が制限される場合も多い。一方、芍薬甘しゃくやくかん草ぞう湯とうは、その速効性と安全性から期待される薬剤である。 1.こむら返りの病態生理 こむら返りは、疼痛を伴う突発する骨格筋の不随意な強直性収縮であり、通常数秒から数分続く。発生メカニズムは、神経軸索の不安定な脱分極による筋肉の異常収縮により起こるとされている 1)。健康な人でも運動の後や、発汗過多による脱水時や塩分喪失時など、また高齢者では就寝中にしばしばみられる。基礎疾患として、パーキンソン病および筋萎縮性側索硬化症などの神経疾患や末梢神経障害、脊柱管狭窄症や椎間板ヘルニアなどの腰椎疾患、糖尿病、甲状腺機能低下症、副腎機能低下症などの内分泌疾患、さらに血液透析、肝硬変、電解質異常、熱痙攣などが挙げられる。 糖尿病では、糖尿病性末梢神経障害による末梢神経の脱随や軸索変性により、筋収縮の調整機能障害が生じるだけでなく、低カルシウム血症や低マグネシウム血症などの電解質異常、脱水、虚血なども複合的に関与する 2)。
2025年10月30日 -
特集
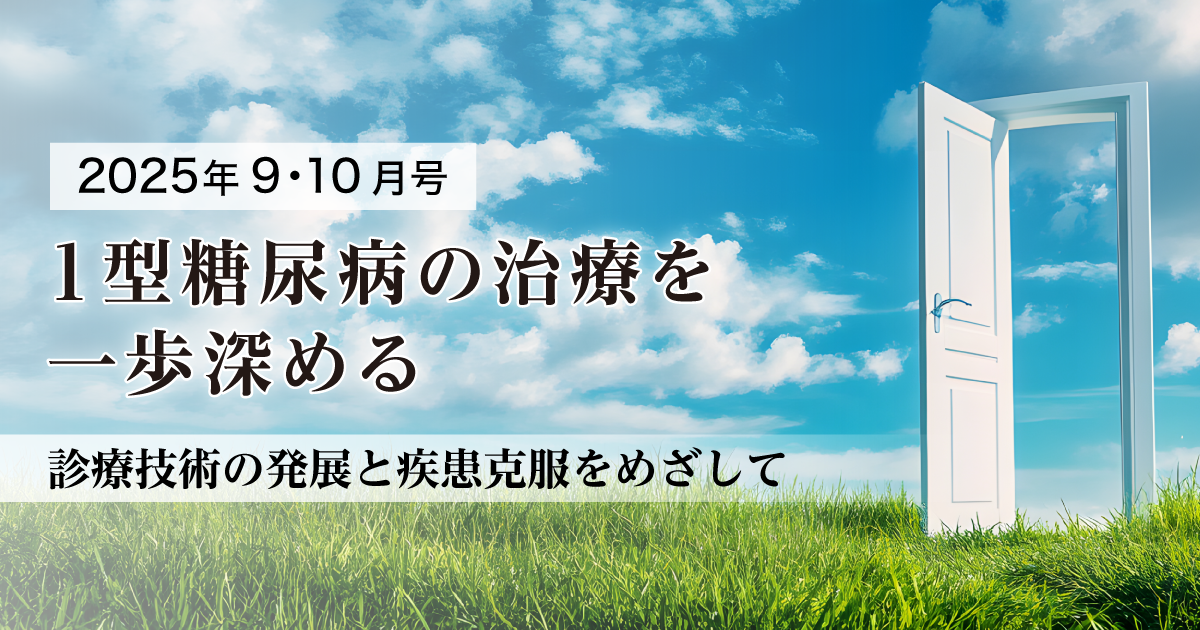
5.カーボカウント実践のコツ ―取っ掛かりを工夫する―
はじめに 血糖管理目標は従来HbA1cが指標とされており、日本糖尿病学会では合併症予防のための目標値はHbA1c 7.0%未満と定められており、65歳以上の高齢者糖尿病では認知機能や日常生活自立度、使用薬剤などによって個別に設定することが推奨されている 1)。また、強化インスリン療法における血糖マネジメントでは、低血糖を回避しつつ血糖マネジメントを行う必要があるため、HbA1cだけでなく、持続血糖測定(continuous glucose monitoring:CGM)を活用した血糖値の推移にも着目することが推奨されている 2)。血糖推移に着目した管理目標は、血糖値70~180mg/dLを治療域(Target Range)としてその範囲内である時間をTime in Range(TIR)と定義し、TIR 70%以上を目指すことが推奨されている 2)。近年、CGMやリアルタイムCGM機能付きインスリンポンプ(sensor-augmented insulin pump:SAP)の普及に伴い、カーボカウントの理解が血糖マネジメントに直結するようになった。本稿では、カーボカウントについて概説した上で、調理習慣のない患者や中食・外食中心の患者にカーボカウントを実践してもらうコツについて解説する。 1.カーボカウントとは タンパク質、脂質、糖質の中で食後の血糖上昇に最も強く作用する栄養素は糖質である。カーボカウント(carbohydrate counting)とは、食後の血糖上昇に影響を及ぼす主な栄養素である糖質が食事中にどれだけ含まれているかを把握し、糖質量や追加インスリン量を調整することにより血糖マネジメントを行う食事療法である 3)。カーボカウントの実践は、HbA1cのみならずTIRの改善にも有用であるため、強化インスリン療法を実施している患者、とりわけ1型糖尿病患者に有用である。
2025年10月23日 -
セミナー
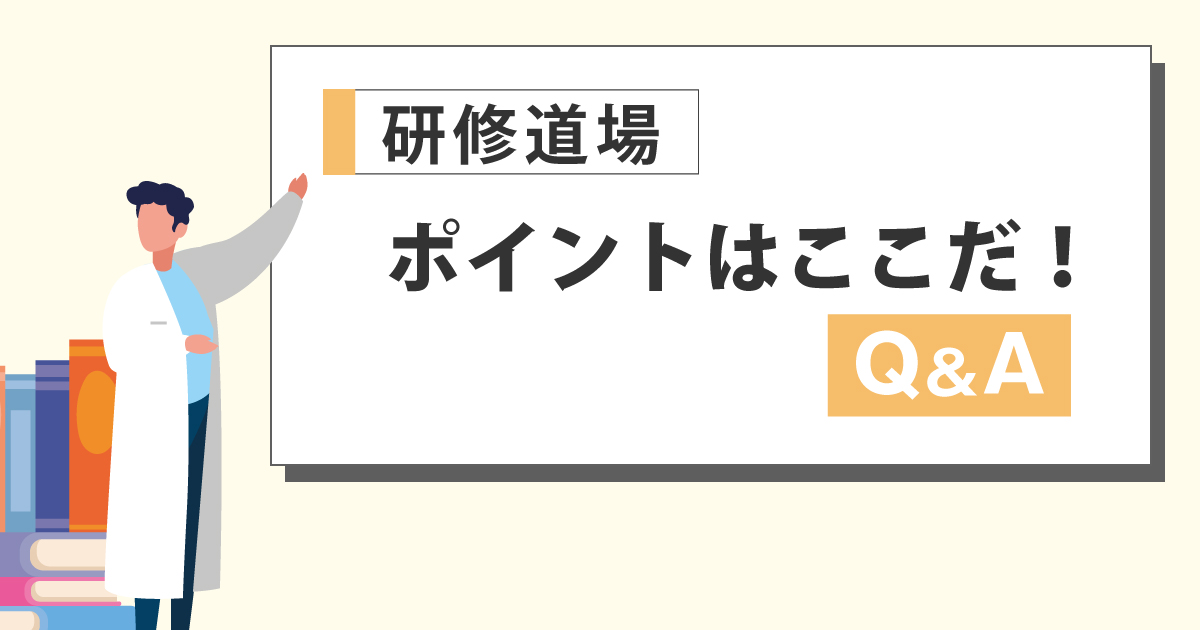
膵性糖尿病
Q&A編はこちら はじめに 膵臓は、血糖降下作用を有するインスリンと血糖上昇作用を有するグルカゴンを分泌する内分泌機能を持つとともに、消化酵素を含む膵液を分泌する外分泌機能を持つため、血糖値の維持に重要な役割を果たす臓器である。膵切除後、慢性膵炎、膵癌などの疾患が原因で主にインスリン分泌の低下により二次性糖尿病を発症することがあり、これらは「膵性糖尿病」とも呼ばれる 1)。本稿では、特に膵切除後の膵性糖尿病の診断、治療について述べる。 1.症例 70代女性。健診の腹部エコーで偶発的に膵嚢胞性病変を指摘され、精査の結果膵体部の膵管内乳頭粘液性腫瘍(IPMN)と診断された。主膵管拡張を伴う主膵管型IPMNであったため、膵体尾部切除術を行う方針となった。術前検査ではHbA1c 5.5%、空腹時血糖値103mg/dLであった。 1)膵切除と糖尿病の発症 膵切除には膵部分切除と膵全摘があり、さらに膵部分切除の術式として膵頭部を切除する膵頭十二指腸切除術と、膵体尾部を切除する膵体尾部切除術がある。膵体尾部切除術を施行された患者のほうが、膵頭十二指腸切除術を施行された患者よりも術後の糖尿病を発症する割合が高かったという報告があり 2)、日本膵臓学会の『膵癌登録報告2007』によると膵体尾部癌切除術後の12.1%、膵頭部癌切除術後の8.5%に糖尿病の発症を認めたとの報告もある 3)。これは膵島が膵尾部に多く存在することも要因のひとつと考えられる。元々耐糖能正常であった症例が、膵部分切除後に耐糖能異常を発症するかどうかは術前の膵線維化の程度によるとされるが、術後にどの程度の血糖上昇をきたすのかを事前に予測することは難しい。症例によって大きく異なり、術後も耐糖能正常のままで推移する症例も少なくない。また、膵全摘を行った場合は内因性インスリン分泌が消失するため、インスリン依存型の糖尿病が必発である。内因性インスリン分泌の著明な低下もしくは消失という点では1型糖尿病に類似するが、膵全摘後は膵α細胞からのグルカゴン分泌も消失する。また、膵外分泌機能低下による消化吸収障害も加わることで血糖値の変動が大きくなり、血糖管理が困難となることが多い 4)。
2025年10月16日 -
特集
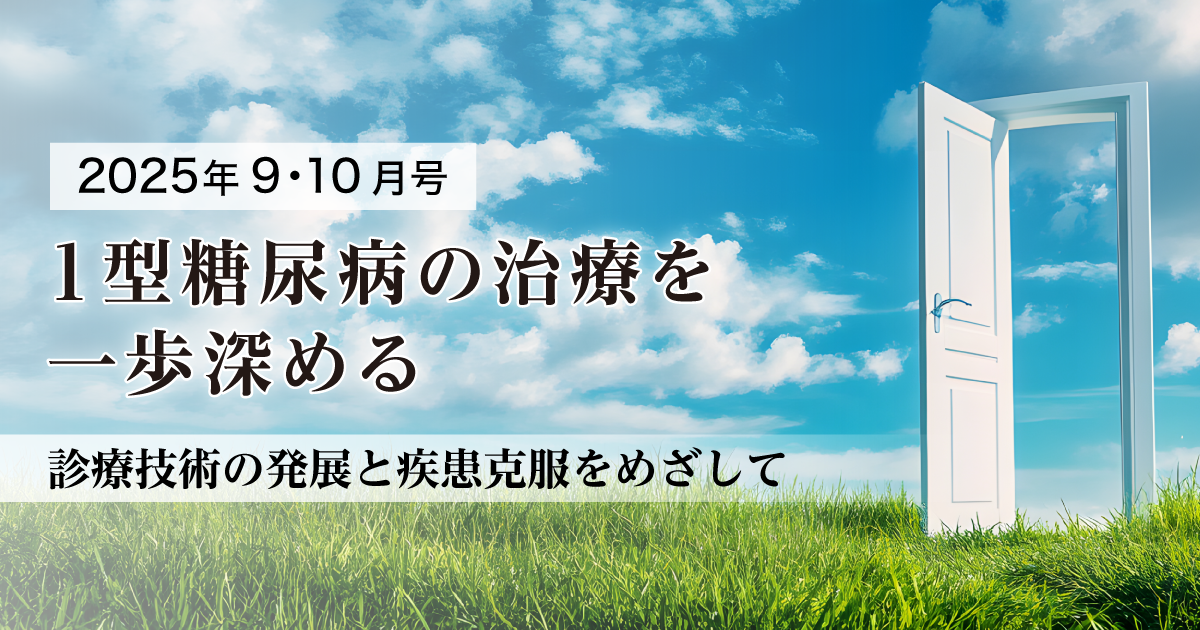
4.移植医療のリアル ―治療選択のための具体的アドバイス―
はじめに 1型糖尿病は若年で発症し、生涯にわたりインスリン治療が必要な慢性疾患である。インスリン療法の進展により多くの患者が日常生活を維持できるようになったが、長期間の高血糖は合併症を引き起こしやすく、とりわけ糖尿病性腎症は末期腎不全に進展するリスクが高くなる。糖尿病性腎症は透析導入の原因疾患として最多であり、2023年には新規透析導入者の38.3%を占めた 1)。 透析治療は生活の質(QOL)や生命予後への影響が大きく、特に1型糖尿病患者ではその傾向が顕著である。一方、腎移植は透析と比べ、生命予後の改善、QOLの向上、社会復帰率の改善が期待され、透析開始前の先行的腎移植(preemptive kidney transplantation:PEKT)も注目されている 2, 3)。 さらに、重症低血糖や血糖コントロール不良に悩む1型糖尿病患者にとって、膵腎同時移植(simultaneous pancreas kidney transplantation:SPK)は、腎機能だけでなく血糖自律性まで同時に回復できる画期的治療で、長期的な代謝改善や合併症進展抑制が報告されている 4)。 本稿では、日本における1型糖尿病患者への腎移植とSPKの現状、制度・登録方法・アクセス手段、患者・家族への説明ポイント、医療者としての具体的アプローチを概説する。 1.腎移植 1)意義と種類 日本では腎移植が慢性腎不全に対する標準的治療のひとつとして位置づけられている。移植方法は以下の2種類である。 献腎移植:脳死または心停止ドナーからの臓器提供。2023年は248件(脳死219件、心停止29件)実施された 5)。 生体腎移植:健康な親族からの腎臓提供。2023年には1,753件が実施された 5)。 献腎移植を希望する登録者数は約1万4,000人であるのに対し、年間ドナーは120名程度と著しく不足しており、登録者の約0.9%しか移植を受けられていない 6)。そのため、多くの患者が生体腎移植に頼らざるを得ず、献腎移植の選択肢は限られている。 2)PEKTの有用性 PEKTは透析開始前に移植を行う方針で、心血管合併症や透析関連合併症を回避し、生命予後を改善する利点が報告されている。メタ解析では死亡率が22%減少(HR=0.78)、移植腎喪失率も19%減少(HR=0.81)とされる 7)。 3)腎移植適応と課題 慢性腎不全で推算糸球体濾過量(eGFR)が20mL/min/1.73m2を下回るCKD stage 4では、移植を見据えた早期の移植施設への紹介が推奨される。なお、eGFRが15mL/min未満になると、PEKTの登録が可能である。
2025年10月09日 -
セミナー

糖尿病患者のやる気を高めるアプローチ
Q&A編はこちら はじめに 糖尿病は別名「自己管理の病気」と言われる。しかし、「持続血糖モニター(CGM)」など先進糖尿病デバイスを用いて血糖値を見える化し、ガイドラインや教科書通りの薬物治療を行っても、血糖管理がうまくいかず、患者のやる気は低下する 1)。この問題に対し、各職種がそれぞれの専門領域で対応する従来のアプローチだけでは限界があることが知られている。そこで、「糖尿病患者のやる気を高めるアプローチ」と題して、患者のやる気を引き出す多職種連携による分野融合的なアプローチ法について解説する。 1.「医学的なおどし」の限界 従来の糖尿病療養指導では、「このままの高血糖を放っておくと大変なことになりますよ」といういわゆる「医学的なおどし」で危機感を強め、行動変容に向かわせるという指導がよく行われてきた。「保健信念モデル(Health Belief Model)」では、「今の血糖値では糖尿病が進行すると失明や末期腎不全のリスクがある」と感じる罹患性や「糖尿病が悪化すると、足の切断が必要となり、仕事に支障をきたす」とする重大度が高まると危機感が強まると、行動の利益と障害を天秤にかけ、利益のほうが上回れば行動変容の見込みが高まると考える(図1)。しかし、こういった危機感は長くは続かない 2)。その要因として、糖尿病の初期段階では目立った自覚症状がないこと、正常性バイアス(「自分は大丈夫」と思い込み、リスクを過小評価する心理)が働くこと、「合併症は他人事」と考える意識、さらに「慣れ」による感覚の鈍化(高血糖状態が続いても悪化していないと感じる)、心理的防衛機制(不安が強すぎると現実逃避する)、対処を後回しにする心理が挙げられる。ただ単に危機感を煽るより、ほかのアプローチ方法が今日、求められている。
2025年10月02日