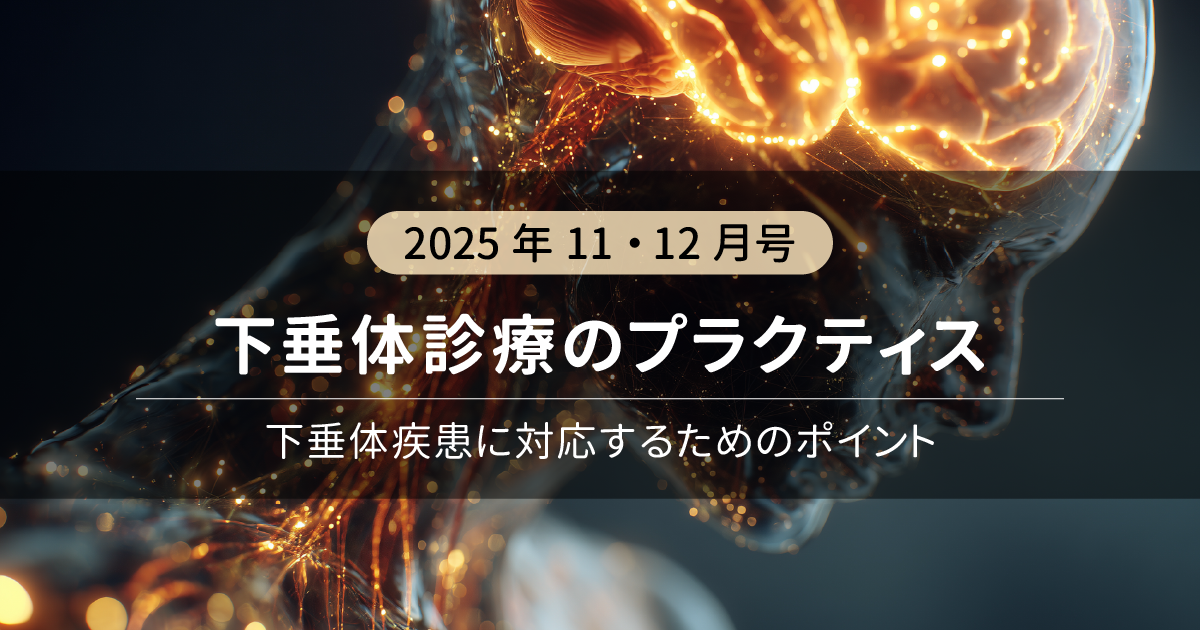- トップページ
- 新着論文一覧
新着論文一覧
-
特集
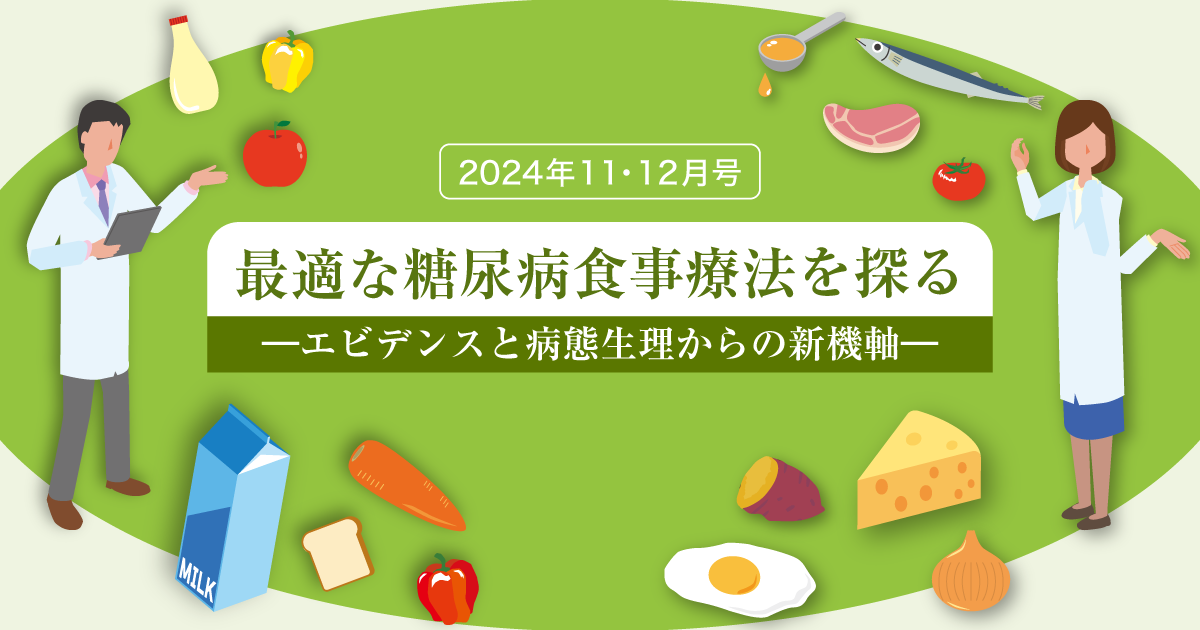
3.食欲に対するアプローチ
はじめに われわれ人間が生きるために必要なエネルギーは全て食物から得ている。従って、摂食行動は生命活動の根源である。摂食行動は、体内貯蔵エネルギーが不足することによって作り出される空腹感(hunger)によって引き起こされる。そして、食物摂取によって得られる飽満感(satiation)によりその空腹感が満たされ、結果として摂食行動が終了する。食物摂取によって食物への欲求が満たされると満腹感(satiety)が生じる。満腹感の持続は、空腹感の抑制に働き、次の摂食行動開始までの間隔を作り出す 1)(図1)。食物への欲求→摂食行動は、空腹感だけでなく、食欲(appetite)によっても調節される。食欲は、内部環境因子(快楽的因子、病的要因、特定栄養素に対する欲求など)と外部環境因子(学習による嗜好/嫌悪、心理的因子、社会的因子、生活環境因子など)によって調節され、特定の食物への欲求に作用する。従って、空腹感と食欲は摂食行動を刺激する異なる因子であり、脳の高次機能が発達した人間においては摂食調節における食欲の関与は大きい。 図1 空腹感・飽満感・満腹感と摂食行動の概念図(文献1より改変) 世界肥満連合の報告によると、世界的に肥満人口は増加の一途を辿っており、このまま対策を講じなければ、2035年には4~5人に1人が肥満になると推測されている。肥満は、摂取エネルギー量が消費エネルギー量を長期的に上回ることで生じる。従って、過食は肥満の主な原因の一つであり、その予防・改善の重要性は言うまでもない。近年は、美味しいものに囲まれた豊かな食環境で、かつ、ストレスの多い社会環境が食欲を刺激するため、過食を予防・改善することは容易ではない。本稿では、過食の原因となる摂食調節機構を概説し、過食および肥満の改善に向けたアプローチについての知見を紹介する。 1.2つの摂食調節機構:恒常性摂食調節と報酬性摂食調節 摂食行動には恒常性摂食と報酬性摂食の2種類の調節があると考えられている 2)。恒常性摂食とは生命活動に必要なエネルギーを得るための摂食行動で、これは飢餓・空腹感に対応したものであり、主に視床下部の機能によって調節されている。一方、報酬性摂食とは、生体のエネルギー状態とは独立した摂食行動で、匂いや美味しさによる快楽的因子や気分やストレスなどの心理的因子などによって調節される摂食行動である。この報酬性摂食は主に、中脳の腹側被蓋野のA10と呼ばれるドーパミン産生神経が大脳辺縁系の側坐核に投射する経路(中脳辺縁系経路)と、腹側被蓋野から前頭前野に投射する経路(中脳皮質経路)によって調節される(図2)。 恒常性摂食中枢の視床下部は、複数の神経核から構成され、各神経核に存在する特有の神経がネットワークを形成して摂食行動を調節している(表1) 3~5)。中でも、弓状核(arcuate nucleus)は摂食行動を制御する重要な役割を担っており、ここに存在する一次ニューロン(first-order neurons)と呼ばれる神経細胞がその機能を果たしている。一次ニューロンには摂食亢進系のNPY(ニューロペプチドY)/AgRP(アグーチ関連ペプチド)神経と、摂食抑制系のPOMC(プロオピオメラノコルチン)神経が存在する。成体マウスの弓状核NPY/AgRP神経を特異的に破壊すると餓死し 6)、反対に、光遺伝学的に活性化すると摂食行動が促進される 7)。POMC遺伝子、または、その産物であるα-MSH(メラノサイト刺激ホルモン)の受容体:メラノコルチン4受容体の欠損・異常は、マウスやヒトにおいて過食と肥満になる 8~10)。近年の報告では、化学遺伝学的手法にてNPY/AgRP神経の活性化とPOMC神経の抑制を同時に起こすと相加的に摂食亢進が誘導され、これら2種の神経の相反的な作用が摂食行動調節に重要であることが示された 11)。 摂食の調節には、短・中・長期的な調節機構がある。短期的な調節機構としては、食物刺激によって分泌変動する胃腸膵ホルモンの視床下部への作用がある。例えば、空腹時に分泌亢進される胃ホルモンのグレリンは、NPY/AgRP神経を直接もしくは間接的に(求心性迷走神経を介して)活性化する 12, 13)。反対に、食後に分泌される膵ホルモンのインスリンは、NPY/AgRP神経活動を抑制し 14)、POMC神経を活性化する 15)。中・長期的な調節機構としては、白色脂肪組織由来のレプチンは体脂肪量に応じて血中に分泌されるが、レプチンはPOMC神経の強力な活性化因子である 15)。また、摂食と体内の三大栄養素との関連は、糖平衡説、アミノ酸平衡説、脂質平衡説などが提唱されているが、低血糖刺激がNPY/AgRP神経を活性化する 12)。
2024年12月06日 -
セミナー

SGLT2阻害薬の最新エビデンス
ポイント SGLT2阻害薬は、血糖改善作用に加えた、additional benefitを期待し得る薬剤である。 心血管疾患・心不全・CKDのイベント発症リスクを低減させることが知られる。 適応拡大される中で、使用する個々人の特性に配慮した適正使用が求められる。 はじめに SGLT2(sodium-glucose cotransporter 2)阻害薬は、リンゴの樹皮に含まれるフロリジンから開発された薬剤で、腎臓の近位尿細管における糖の再吸収を阻害することで尿糖排泄を増加させ、インスリンに依存しない血糖改善作用をもたらす。さまざまな大規模研究の結果、SGLT2阻害薬が単なる血糖改善作用のみならず、心血管疾患、慢性腎臓病(chronic kidney disease:CKD)や心不全のリスクを低減することが明らかとなり、現在、適応が拡大された薬剤によっては糖尿病の有無にかかわらず使用されるようになり、その使用割合は年々増加している。additional benefitが期待できる一方、開始初期の脱水や性器・尿路感染症などの有害事象を考慮する必要があり、さらに尿糖排泄亢進に伴う体重減少は高齢者においてサルコペニア・フレイルを悪化させる可能性があり、使用する個々人の特性に基づいた適正使用が求められる 1, 2)。 本稿では、本邦において広く使用されている、SGLT2阻害薬の心血管疾患・心不全・CKDにおける有効性に関するエビデンスを概説し、次に使用の際に留意すべき点、特に併存症の多い高齢者への使用において注意すべき点について論じたい。
2024年12月03日 -
セミナー

骨粗鬆症治療薬の使い分け
Q&A編はこちら はじめに 骨粗鬆症治療の目的は骨折を予防することである。骨折は健康寿命のみならず、生命予後を短縮させる。閉経後の原発性骨粗鬆症に加え、原発性副甲状腺機能亢進症などの内分泌疾患、2型糖尿病や慢性腎臓病などの生活習慣に関連する疾患が骨粗鬆症の原因となるため、内分泌代謝内科は骨折予防の第一線を担うべき診療科といえる。骨粗鬆症治療薬として、従来から用いられてきた骨吸収抑制薬に加え、骨形成促進薬が使用可能となっている。骨折の危険性が高い骨粗鬆症患者に対しては骨形成促進薬を先行して投与する「アナボリックファースト」により、大幅な骨量増加を目指せる。骨粗鬆症治療を安全に行うために薬剤ごとの注意点を理解する必要がある。本稿では、これから骨粗鬆症治療に関わる方を対象に、治療のエッセンスをまとめた。 1.骨粗鬆症の疫学 骨粗鬆症はcommon diseaseの1つである。地域住民を追跡した国内のコホート研究結果を基に、国勢調査データより算出された骨粗鬆症有病者数は1,590万人とされる 1)。加齢により骨折リスクは上昇し、閉経後から椎体骨折が、70歳代からは大腿骨骨折の頻度が増加する。国内でも概念が整理されつつある多疾患併存(multimorbidity)状態においては、骨折リスクに関連する疾患や病態を複数有する。骨関節疾患や脳卒中後の転倒リスク増加、グルココルチコイドや抗凝固薬などによる骨脆弱化など、骨折リスクを意識しながらmultimorbidityに対応するための全身管理は、内科医にとって不可欠な技量といえる。 骨折予防は、心血管疾患や脳卒中の予防と同様に、健康寿命の確保ならびに生命予後の延伸につながる。75歳以上の後期高齢者がひとたび大腿骨近位部骨折をきたせば、1年以内に20%が死亡するとされている 2)。さらに、国内における要介護となる原因の上位を骨折が占めていることは周知の事実であり、女性では脳血管疾患を上回る。
2024年11月29日 -
セミナー

神経障害を有する糖尿病患者への療養支援
Q&A編はこちら はじめに 糖尿病性神経障害は、糖尿病を有する患者に最も高頻度にみられる合併症である。糖尿病性神経障害の自覚症状は多岐にわたり、QOLを損なうだけでなく、足潰瘍および下肢切断、心血管死のリスクを上昇させる。糖尿病を有する患者の増加に伴い、糖尿病性神経障害を有し、足病変や心血管死のリスクが高い患者が増加していくことが考えられる。ほかの合併症と同様、定期的に神経障害の有無や症状を評価し、必要に応じて対症療法やフットケアを行う必要がある。 1.糖尿病性神経障害の分類 糖尿病性神経障害は、全身性で遠位対称性の多発神経障害と、局所性の単神経障害・神経根症に分けられる 1)。主に前者を糖尿病性多発神経障害(diabetic polyneuropathy:DPN)と呼び、糖尿病性神経障害の大半を占める。DPNはさらに感覚・運動神経障害と自律神経障害に分類される。 局所性の神経障害のうち頻度が高いのは単神経障害で、脳神経障害と四肢絞扼性・圧迫性神経障害が含まれる(表1)。 表1 糖尿病性神経障害の分類(日本糖尿病学会編・著: 糖尿病診療ガイドライン2024. 南江堂, 東京, 2024, p.209より)
2024年11月22日 -
特集
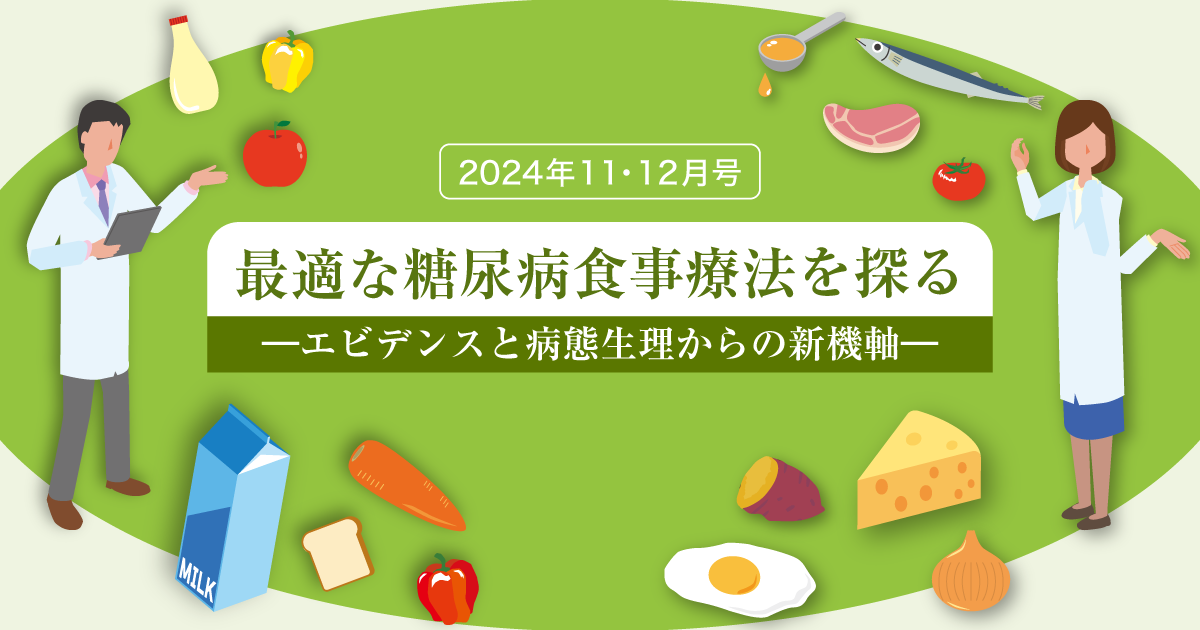
2.3大栄養素の量と質を考慮した食事療法
はじめに 糖尿病患者における最適な食事療法とは、適正なエネルギー量で、栄養バランスがよく、規則正しく食事を摂取することにより、合併症の発症または進展の抑制を図る糖尿病治療である。栄養バランスとしてのエネルギー産生栄養素(3大栄養素)の量(比率)、また量だけではなく質も、血糖管理や合併症の抑制において重要である。本稿では、3大栄養素の量と質を考慮した食事療法について解説する。 1.糖尿病食事療法における最近の基本的な考え方 糖尿病食事療法は、運動療法や薬物療法と並んで糖尿病治療の三本柱の一つであり、薬物の使用の有無にかかわらず、全ての糖尿病患者にとって生涯にわたり重要な治療法である。特に2型糖尿病では、まず十分な食事療法と運動療法を実践し、それでも効果が不十分な場合に薬物療法を検討することが治療の基本となる。 2型糖尿病における食事療法の重要性は、全身の代謝状態を良好に保つことで合併症の発症を予防し、その進行を抑制することにある。インスリンは糖代謝だけでなく、脂質やタンパク質の代謝にも関与しており、これらの代謝は互いに密接に関連している。そのため、食事療法を行う際には、個々の病態に応じて高血糖だけでなく、さまざまな側面からその妥当性を検証する必要がある。 2型糖尿病の病態は人種差による影響が大きく、わが国を含む東アジア人患者は欧米人患者より肥満度が低いことが以前から知られている 1)。また、日本人のインスリン分泌能は北欧白人よりも低下しやすいことを示唆する報告もある 2)。さらに食事内容や食習慣においては民族差が影響する。従って、糖尿病食事療法は、各国の臨床エビデンスに基づき、国ごとに確立することが求められる。 糖尿病診療における新ガイドラインである『糖尿病診療ガイドライン2024』では、エネルギー摂取量の制限は「過体重・肥満を伴う2型糖尿病患者の血糖コントロールにおいて推奨」と明記されているが、過体重・肥満を伴わない2型糖尿病患者や1型糖尿病の血糖コントロールに対するエネルギー摂取量の制限の効果については文献が乏しく、今後のさらなる科学的根拠の集積が必要とされている。このように、わが国においても、糖尿病食事療法に関して個々の病態に応じた治療方針の変化がみられている。最近の糖尿病食事療法は、従来までの「エネルギー摂取量の制限」に重きを置いた食事療法から「患者背景や病態を考慮し栄養バランスを重視する」食事療法へ変化しつつある。糖尿病の病態が多様化している現在、患者一人ひとりの状況に応じて、食事療法は量的にも質的にも個別化する必要がある。
2024年11月15日 -
セミナー
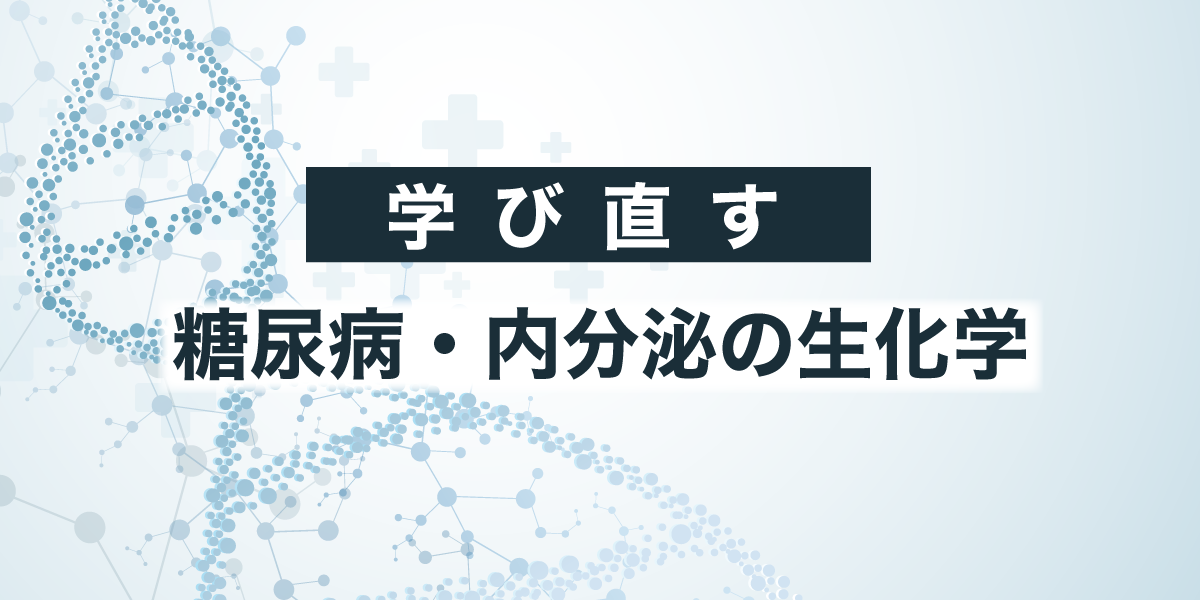
低酸素ストレスによるインスリン分泌不全
はじめに インスリンは血糖恒常性の維持に必須のホルモンであるが、持続する高血糖は膵β細胞からのインスリン分泌不全を惹起する(糖毒性)。糖毒性によるインスリン分泌不全はさらなる高血糖を引き起こすことで一種の悪循環が形成される。高血糖はβ細胞に酸化ストレスやERストレスなどを惹起することでインスリン分泌不全を引き起こすことが知られていたが、近年の研究の結果、糖毒性の背景に膵β細胞の低酸素化という現象が存在していることが明らかになってきた。本稿では、高血糖が膵β細胞に低酸素を惹起するメカニズムおよび低酸素によるインスリン分泌不全機構について概説する。 1.膵β細胞と低酸素ストレス グルコースは生体内における最も基本的な栄養素であり、血中グルコース濃度(血糖)は膵臓のβ細胞から分泌されるインスリンにより制御される。膵β細胞に取り込まれたグルコースは解糖系でピルビン酸に代謝された後、ミトコンドリアに運ばれTCA回路・電子伝達系を介してATPが合成される。細胞内ATP量の上昇によるATP依存性カリウムチャネルの閉鎖、細胞膜の脱分極に引き続き電位依存性カルシウムチャネルの活性化が起こり、β細胞内にカルシウムが流入することで血糖レベルに応じたインスリン分泌が惹起される。 電子伝達系でATPが合成されるためには酸素分子が必要であり、インスリン分泌時にはATPの合成に伴い酸素が消費される。細胞内酸素量は、細胞外から細胞内への酸素供給とミトコンドリアで使われる酸素消費のバランスで規定されているため、「供給」より「消費」が高くなる場合に細胞内が低酸素に陥ると考えられる。高血糖状態ではインスリン分泌を増加させる必要があるため、膵β細胞内でより多くの酸素が消費され、β細胞が低酸素状態に陥る可能性が考えられた。そこで糖尿病のモデル動物であるob/obマウスやKK-Ayマウスの膵島を用いて検討を行ったところ、これらモデルマウスの膵島は高血糖により著明に低酸素化が起きていることが判明した 1)。その後、別の糖尿病モデルであるdb/dbマウスの膵島も低酸素化されていることが報告され 2, 3)、糖尿病モデルマウスの膵島細胞は酸素消費の亢進により低酸素状態に陥っていることが明らかになった。低酸素はβ細胞からのインスリン分泌を低下させることで 4)、高血糖のさらなる増悪を惹起する(図1)。低酸素はβ細胞糖毒性の一因であると考えられる(低酸素ストレス)。 図1 高血糖(糖毒性)は膵β細胞低酸素を惹起する 低酸素はインスリン分泌を障害し、高血糖を増悪させる(低酸素ストレス)。
2024年11月12日 -
特集
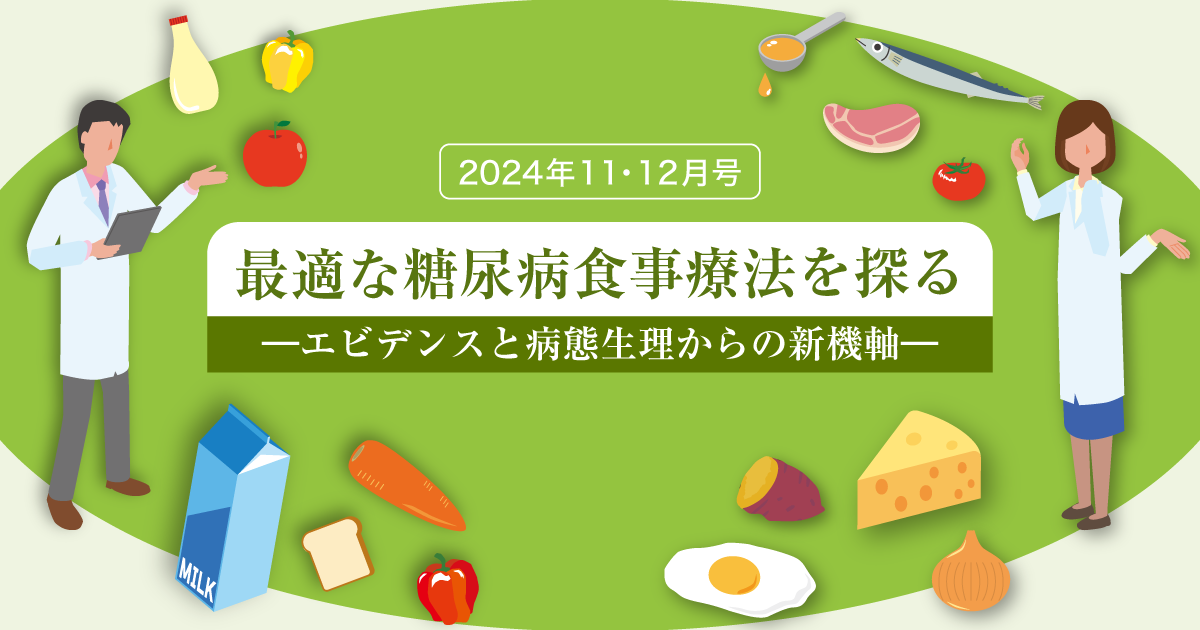
1.エネルギー設定の仕方
はじめに 食事療法・運動療法は、糖尿病診療と合併症予防を考える上で、根源的な治療法である。しかしながら、糖尿病患者に対してどの程度のエネルギー設定をすればよいのか、実は明確なエビデンスが乏しい。本稿では、日本糖尿病学会刊行の『糖尿病治療ガイド2022-2023』および『糖尿病診療ガイドライン2024』を補完する形で、エネルギー設定について解説する。また、二重標識水法を用いた糖尿病患者のエネルギー代謝の実態調査に基づいて、エネルギー設定に関して考察する。 1.糖尿病と食習慣・運動習慣そして体重の関係 現体重は、長期間のエネルギー摂取量とエネルギー消費量の出納の総和を表している。糖尿病に限らず、健常者あるいは多くの疾患にとって、理想の体重が存在するはずである。患者を個人としてとらえると、糖尿病以外にも複数の併存疾患を有していたり、高齢であったり、個人によってさまざまな条件が異なることから、「個人にとって理想の体重」を設定する必要がある。一般に肥満糖尿病患者にとっては、体重減少にメリットが多いであろうし 1)、逆にやせの高齢糖尿病患者では体重を増やすべきであろう。しかしながら、現在の体重に落ち着いている理由は、生活習慣、遺伝、併存疾患、薬剤などさまざまであり、食事量を習慣的に変化させることは容易ではないのも事実である。特にやせている患者の体重を増加させるのは容易ではない。
2024年11月08日 -
特集
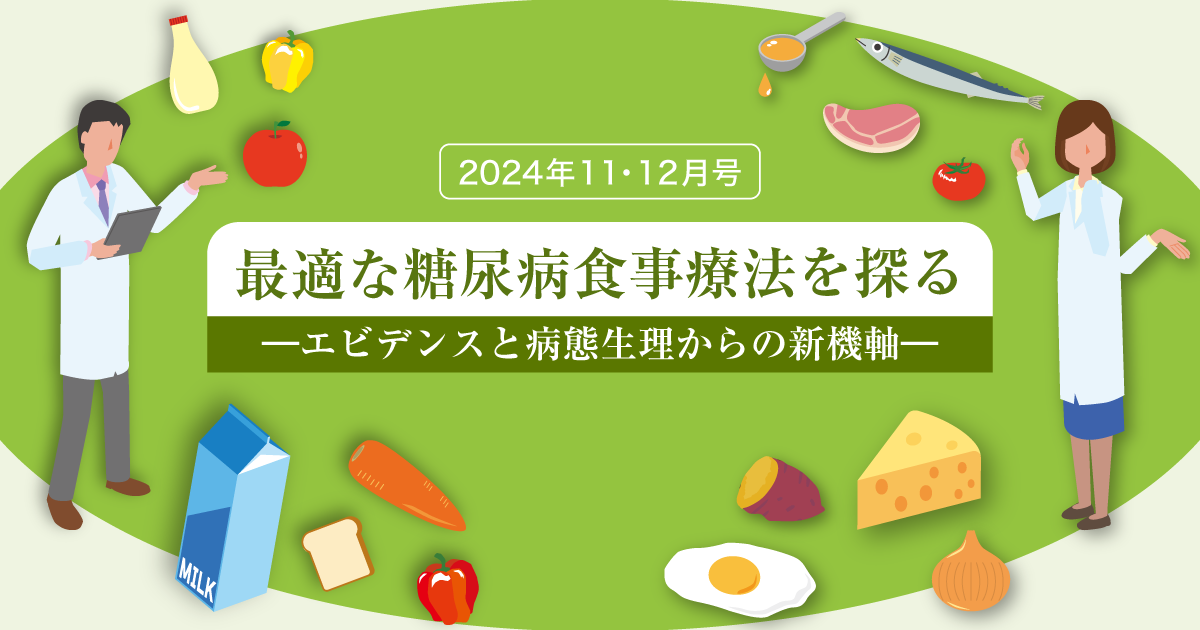
(扉)特集にあたって
糖尿病をもつ人における最適な食事療法とは、適正なエネルギー量で、栄養バランスがよく、規則正しい食事を実践し、合併症の発症または進展の抑制をはかることができる食事療法を実践することである。非肥満の糖尿病、特に高齢者では食事の制限ではなく適切な量のエネルギーを摂取する必要がある。一方、肥満症例ではエネルギー管理が必要となる。食欲のマネジメントは大変重要であり、食後の高血糖、血糖スパイクが血管障害、臓器障害のリスクになるということを考えると食習慣の調整が重要となる。すなわち、よく噛んでゆっくり食べる、野菜・主菜(たんぱく質食品)を先に摂取する、食物繊維を多く含んだグリセミックインデックスの低い食物を摂取することなどに加えて、夜遅い時刻に食べると肥満や高血糖を助長するので、分割食にすることも有効である。また、食事は朝型(朝食を充実)にすることが肥満抑制、血糖値の改善、筋肉を増やすなどメリットが大きく、時間栄養学も考慮した食事療法が推奨されている。 一方、わが国では世界に類を見ない糖尿病患者の高齢化が進んでおり、どのような食事療法を実施していくかは重要な課題である。すなわち、筋肉量を維持することが転倒防止、ADLを維持するために重要であるが、高齢者はanabolic resistanceの状態で筋肉が増えにくい、また糖尿病患者では筋肉が減りやすいため十分な量の良質なたんぱく質、またエネルギーの摂取が必要である。一方で腎機能障害を合併した高齢者におけるたんぱく質の摂取量には議論があるところではあるが、高齢者糖尿病においてはサルコペニアの発症・進展抑制も目指した治療を行うことが重要であり、そのために適切な食事療法を実施することが望まれている。 本特集では、この分野でのエキスパートの方々から最新の食事療法についてのエビデンスに基づく新機軸の話題提供をいただいた。今後、読者の皆様の日常診療において本誌が一助となる内容となっているものと自信を持っており、糖尿病治療の目標である、糖尿病のない人と変わらない寿命とQOLを実現するためには、医学的に最適な食事療法と、食事のおいしさや楽しさ、豊かさなどを両立することを考え、是非に、ご活用いただけるようにと切に願っている。 著者のCOI(conflicts of interest)開示:本論文発表内容に関連して特に申告なし 本論文のPDFをダウンロードいただけます
2024年11月08日 -
特集
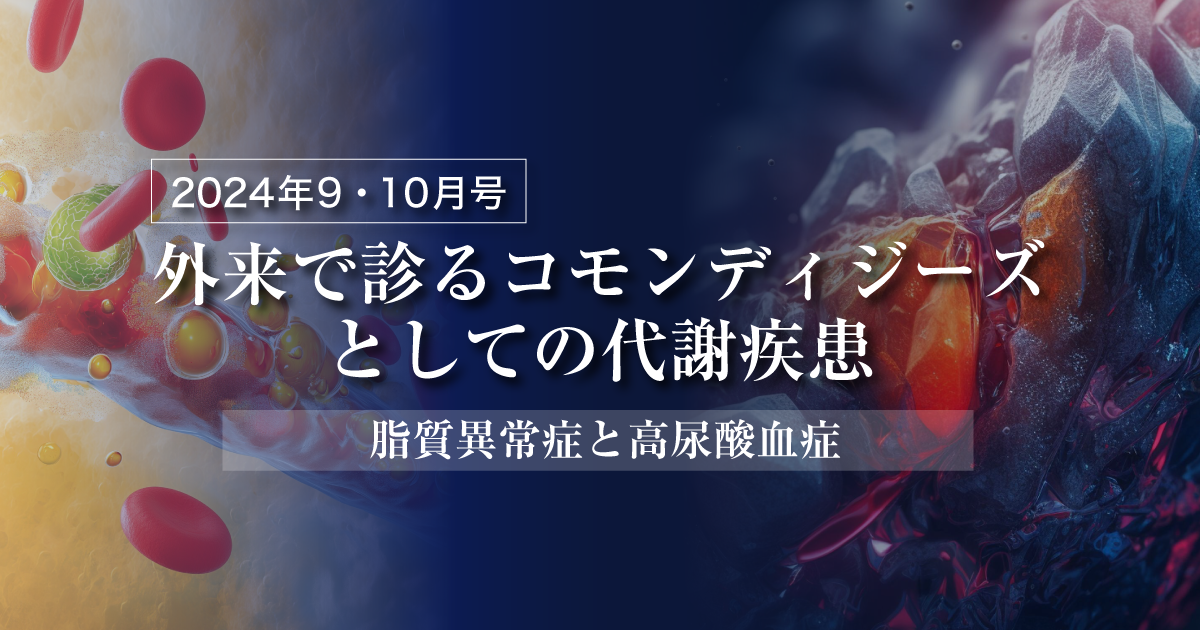
5.臨床医のためになる尿酸異常症治療薬:生体内での作用点から実臨床での注意点まで
はじめに 尿酸は、生体におけるエネルギーの通貨と呼ばれるATPをはじめとしたプリン体の代謝によって生じる。多くの哺乳類は尿酸代謝酵素を有しており、尿酸はさらに代謝されてアラントインに変換された後に体外へと排泄されるが、ヒトを含む多くの高等霊長類では遺伝的に尿酸代謝酵素を欠いているため、尿酸がプリン体の最終代謝産物となる。尿酸は体内に蓄積することで痛風の原因となるほか、心血管疾患や慢性腎臓病との関連も指摘されていることから、「悪玉」と見なされることが多い。しかしながら、尿酸は強い抗酸化作用を有することも知られており、パーキンソン病をはじめとする神経変性疾患に対して尿酸が保護的に働く可能性も示唆されている。これらを踏まえ、近年では、血清尿酸値が至適濃度よりも高値となる高尿酸血症と、低値となる低尿酸血症を併せた疾患概念である尿酸異常症(dysuricemia)が提唱されるようになった 1)。本稿では、尿酸の体内動態制御機構を踏まえ、尿酸異常症に用いられる治療薬について概説する。 1.尿酸の体内動態制御 尿酸は、主に肝臓や小腸などにおいて、キサンチン酸化還元酵素(xanthine oxidoreductase:XOR)がヒポキサンチンそしてキサンチンを順次酸化することで合成される。合成臓器から血中へと移行した尿酸は、腎臓や小腸を介して体外へと排泄される。腎臓は尿酸の排泄に最も大きく寄与する臓器であり、体外へと排泄される尿酸のおよそ2/3が腎臓を介して尿中へと排泄される。糸球体に到達した尿酸は、そのほぼ全てが濾過され原尿中へと移行するものの、集合管に至る過程で約90%が再吸収され、最終的に尿中へと排泄される尿酸の割合は、糸球体濾過量の10%程度となる。この過程には、urate transporter 1(URAT1)をはじめとする多くの尿酸トランスポーターが関わる 2)。小腸は腎外の尿酸排泄経路として最も重要な臓器であり、体外へと排泄される尿酸の約1/3は、小腸から糞中へと分泌されている。小腸からの尿酸分泌においても尿酸トランスポーターは重要であり、この過程では、薬物の排泄トランスポーターとしても知られるATP-binding cassette transporter G2(ABCG2)が中心的な役割を担っている 3)。血清尿酸値は、尿酸の合成と排泄のバランスが保たれることで、一定の範囲に維持される。尿酸異常症は、こうした尿酸の合成と排泄のバランスが崩れた状態であり、血清尿酸値が2mg/dL以下となった場合が低尿酸血症、7mg/dLを超える場合が高尿酸血症と定義される。尿酸異常症では、発症要因に基づく病型分類と合併症のリスクを踏まえ、薬物治療が考慮される(表1)。 表1 尿酸異常症の分類
2024年10月31日 -
連載

第74回 診療報酬改定2024 ―内分泌疾患を中心に―
はじめに 2024年度診療報酬改定において、診療報酬は+0.88%(医科 +0.52%、歯科 +0.57%、 調剤 +0.16%)、薬価は-0.97%の改定率となり、改定に当たっては以下に示す4点が基本的視点として示された 1)。 現下の雇用情勢も踏まえた人材確保・働き方改革等の推進 ポスト2025を見据えた地域包括ケアシステムの深化・推進や 医療DXを含めた医療機能の分化・強化、連携の推進 安心・安全で質の高い医療の推進 効率化・適正化を通じた医療保険制度の安定性・持続可能性の向上 そして、これらの視点ごとに具体的方向性が示され、個別項目の改定がなされた。 内分泌疾患に係る改定は、主に医科診療報酬点数表の第1章基本診療料第2部入院料等、第2章特掲診療料第1部医学管理等および第3部検査であり、今回は改定された項目の告示、通知および施設基準について概説する。なお、本連載では内分泌疾患を対象にするのは初めてであるため、診療報酬の改定箇所のほかに、医科点数表の内分泌疾患に係る主な算定項目についても概説する。また、DPC(Diagnosis Procedure Combination:包括評価)制度については別途概説する。 1.主な内分泌疾患と指定難病(表1, 2) 診療報酬の算定に当たり、対象となる主な内分泌疾患については、表1には小児慢性特定疾病情報センターに示された内分泌疾患41分類92疾患の一覧 2)を、表2には指定難病の内分泌21疾患 3)を示す。このように内分泌疾患には多くの疾患が含まれ、診療報酬の算定項目・算定要件も多岐にわたる。 表1 内分泌疾患の疾患一覧(文献1より) 画像をクリックすると拡大します 表1 内分泌疾患の疾患一覧(文献1より) $(".vol5_r14_h1").modaal();
2024年10月30日 -
連載

低血糖時のブドウ糖摂取は推奨しない
今年の夏休みは、一人旅に出かけた。6月下旬の土曜日、札幌に用事があったので、その後ひたすら西へ東へと乗り物を乗り継ぐことにしたのだ。今回、銀輪は持参しなかった。 旅の始まりは函館だ。金曜日の夜、北海道新幹線で東京駅を出発し、深夜の到着。その日はホテル併設の温泉に浸かるだけで、主たる目的は朝食のバイキングである。北海道産いくらの醤油漬け食べ放題が有名な宿なのだ(写真1)。満腹になったところで、さっさと特急列車に乗り込み札幌へと向かう(写真2)。 写真1 いくら写真2 特急北斗 札幌へ行った時に必ず立ち寄るのが、雪印パーラーである(写真3)。この店の看板メニューであるアイスクリーム「スノーロイヤル」は、昭和43年(1968年)の8月、北海道百年記念式典に際しご臨場された天皇・皇后両陛下のために作られた。現在でも、北海道・雪印パーラーのみの限定販売である(写真4)。乳脂肪分はなんと15.6% 。ハーゲンダッツのバニラでも15.0%であるから、それよりも多く乳脂肪分を含んでいる。ちなみに、乳固形分15.0%以上(乳脂肪分8.0%以上)のものを「アイスクリーム」といい、乳固形分10.0%以上(乳脂肪分3.0%以上)のものは「アイスミルク」、乳固形分3.0%以上のものは「ラクトアイス」と分類されている。
2024年10月25日 -
セミナー

チームで実践する妊娠糖尿病診療
Q&A編はこちら はじめに 妊娠糖尿病は、日本において妊婦の12.1%で合併する妊娠中の比較的頻度の高い合併症であり 1)、母体の高血糖によって、母体の妊娠高血圧症候群・早産・帝王切開のリスク、胎児の巨大児・肩甲難産・高ビリルビン血症・低血糖・呼吸障害・NICU入室などのリスクが増大する 2)。一方で、妊娠中に血糖を良好に管理することでそれらの合併症を抑制できる 3)ことが知られているが、妊娠糖尿病と診断された妊婦は、その病気の受容や治療管理に関わる負担は大きいことが臨床の場面では多く経験される。妊娠中は精神的にも不安定な状態になりやすいこともあり、適切なサポートには多職種で取り組む心理的配慮が大変重要であろう。 多職種医療従事者の各知見をもとに、妊娠糖尿病に対するチーム医療と心理的配慮に注目した新たな取り組みとして、近年関心を集めているモバイル・アプリケーションやオンライン診療について先進的な取り組みも含めて紹介する。 1.多職種で考える妊娠糖尿病 1)医師の視点から 妊娠糖尿病と診断された患者は、病気の受け入れから始まる。“糖尿病”という言葉が持つ“スティグマ(負の烙印)”の影響もあり、診断にショックを受ける人が少なくない。しっかりと病気を理解してもらい、適切な治療管理につなげることが大切である。日本を含む東南アジアの妊娠糖尿病の有病率は12.7%、標準化有病率(年齢を25~30歳に標準化した場合)は20.8%と、北米(有病率6.0%、標準化有病率7.1%)や欧州(有病率7.0%、標準化有病率7.8%)と比較しても高いことが知られている 4)。晩婚化や高齢出産の影響もあり、日本での妊娠糖尿病の有病率はさらに上昇することが予想されている。妊娠糖尿病は、体質や年齢、妊娠という特殊な状況が組み合わさって起きていること、妊娠糖尿病の合併症や経過、治療目標や方法も糖尿病とは異なることをしっかりと理解してもらうことが良好な医師との関係構築において重要である。将来の子どもに対する希望と責任を強く感じる時期であるからこそ、適切な医学的知識の提供と多職種と連携した心理的配慮が適切な医学的管理に導く上でとても大切である。 【妊娠糖尿病症例】 年齢23歳、妊娠前BMI 19kg/m2で妊娠中期の75gOGTTで2点陽性となり、妊娠糖尿病と診断された。母体の体重増加がほとんどない(『産婦人科診療ガイドライン産科編 2023』では妊娠前に普通体重の方で10~13kg増加が指導の目安 5))ことから、食事量の聞き取りを行ったところ明らかに食事量、特に炭水化物の摂取を制限されており、400~600kcal/日の摂取量と推定された。本人はやはり炭水化物の摂取に伴う血糖上昇に対して自責とインスリン導入への過剰な忌避から、必要以上の炭水化物、食事摂取を制限していた。 日本は世界的にも低出生体重児が多く、その割合が上昇していることが問題となっている。最近の研究では、低出生体重児は将来の2型糖尿病や肥満、心血管疾患、精神疾患の発症に関連することが示されている 6)。低出生体重児の原因は、高齢出産や胎盤機能不全など母体や胎児のさまざまな要因が関連しているが、母体のBMIや栄養不良は低出生体重児の出産リスクが高い 7)ことが報告されている。日本は妊娠適齢期の女性において12.4%でやせ(BMI<18.5kg/m2)が多く、間違った食事療法をとってしまう方は少なくない。もちろん、妊娠中の食欲増進の影響で必要以上の食事摂取になっている症例もあるが、学会などの推奨摂取カロリーを参考に患者の解釈モデルを理解することで、適切な医学的管理につなげられるであろう。 本症例でも、在宅療養指導を導入しインスリン治療に関わる本人の心理的不安の軽減を心がけ、栄養指導を導入し適切なカロリー摂取を行ってもらうように指導し無事出産となった。
2024年10月23日 -
特集
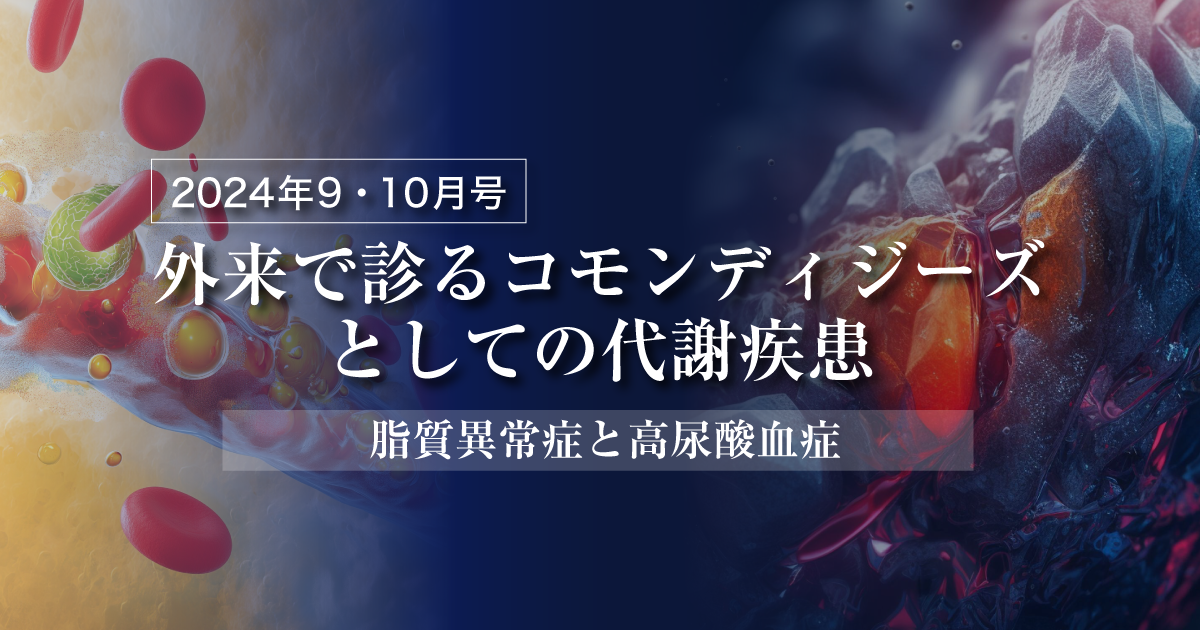
4.代謝疾患としての尿酸異常症(Dysuricemia):予後や臓器障害との関連を含めて
はじめに 高尿酸血症(>7.0mg/dL)は結晶沈着による痛風性関節炎を引き起こすのみならず、メタボリックシンドローム発症や心血管疾患・死亡との関連も多数報告されている。一方で、低尿酸血症(≦2.0mg/dL)も腎障害リスクがあり、注意が必要な場合がある。本稿では、尿酸異常症が患者や一般住民に及ぼす問題について解説し、日常臨床や健康診断における尿酸値測定の意義を述べる。 1.高尿酸血症の定義と疫学 性別や年齢を問わず、高尿酸血症は血清尿酸値が7.0mg/dLを超えた場合と定義される。これは、高尿酸血症が尿酸塩沈着症(痛風性関節炎や痛風腎)の病因という観点において、通常の体温(37℃)やpHの範囲において7.0mg/dL以下の濃度で尿酸塩が溶解する(結晶として沈着しない)ことに基づく。 本邦における高尿酸血症の割合は、食生活の欧米化に伴い1960年代以降の数十年間に急激に増加した。2000年代の大規模な疫学調査に基づくと、成人男性における高尿酸血症の割合は男性で約20~25%とされ、1,000万人を超える 1, 2)。これは、主な生活習慣病である高血圧や糖尿病患者数に近い数値であり、日本人成人男性において重要な生活習慣病の一つである。 女性においては、女性ホルモンによる尿酸排泄促進作用や高尿酸血症と関連があるとされる「体重・ヘマトクリット値・飲酒量」のそれぞれに差があることなどにより、血清尿酸値は男性よりも1.5mg/dL程度低く、男性に比較し高尿酸血症の有病率は2%前後と低い 2~4)。 年代別にみると、男性では、健診での血清尿酸値が>7mg/dLを呈する高尿酸血症の割合は30~40代が最も多く加齢に伴い低下するが 2)、痛風の発症やその他の併発疾患(慢性腎臓病など)により尿酸降下薬治療を受ける患者は加齢に伴い増加する。よって、治療・未治療を合わせた高尿酸血症全体の割合は加齢とともに低下していない。女性では、尿酸値に対して保護的に働いていたエストロゲン作用が加齢により減少するため、血清尿酸値は加齢とともに上昇する 3)。 ヒトの体内尿酸プールは成人男性で約1,200mg、成人女性で約600mgである。食事由来のプリン体摂取、生体内のプリン体合成や細胞崩壊により、1日当たり約700mgのプリン体が尿酸プールに入るが、腎臓から約500mg、腎外(腸管)から約200mgの尿酸が体外に排泄され、尿酸プールは一定に維持される。尿酸の産生量が増加したり排泄量が低下すると、尿酸プールが増大し高尿酸血症をきたす。『高尿酸血症・痛風の治療ガイドライン第3版』によると、高尿酸血症は、これまで尿中尿酸排泄に基づいて、産生過剰型、排泄低下型、両者の特徴をもつ混合型に分類されてきた。しかし、腎外(腸管)排泄低下による高尿酸血症の場合は、尿中尿酸排泄が亢進するために、見かけ上は尿酸産生過剰型を呈する。さらに腸管排泄低下となる尿酸トランスポーターABCG2の一塩基多型の頻度が比較的高いことが明らかとなり、尿酸排泄低下型を(腎)排泄低下型と腎外排泄低下型に分類することになった。現在は、新たな考え方に基づいて、高尿酸血症は産生過剰型、(腎)排泄低下型、腎外排泄低下型、混合型に分類される 1)(図1)。
2024年10月15日 -
セミナー
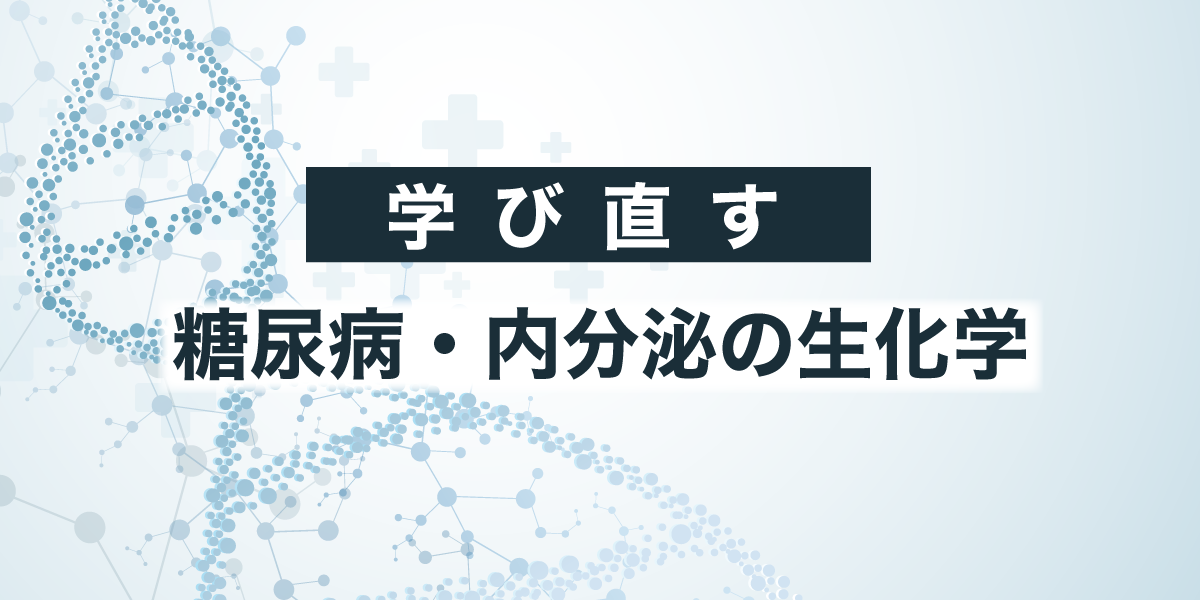
Gタンパク質共役受容体
はじめに Gタンパク質共役受容体(G protein-coupled receptor:GPCR)は細胞膜タンパク質における最大のファミリーで、ヒトでは800種を超えるメンバーから構成される。ホルモン、神経伝達物質、感覚刺激などさまざまな細胞外シグナル分子(リガンド)に対する細胞応答を仲介する。多様な生理反応に関わり、数多くの疾患に関わることも報告されていることから、創薬の標的としても注目度が高く、実際にGPCRを標的とした治療薬が臨床で用いられている。昨今、糖尿病および肥満症の治療薬として使用され、適応外使用でも問題となっているGLP-1(glucagon-like peptide-1)受容体作動薬も、その分子標的であるGLP-1受容体はGPCRである。 1.GPCRの構造と分類 ヒトでは800種以上のGPCRが存在し、そのリガンドも多岐にわたるが、全てのGPCRは共通の基本構造を有する。7本のαヘリックスが細胞膜を貫通しており、N末端領域は細胞外に、C末端領域は細胞内に存在する。αヘリックス同士は、それぞれ3つの細胞外ループと細胞内ループによってつながっている。細胞内領域のリン酸化修飾は、受容体の脱感作につながる。その他、C末端領域においてパルミトイル化修飾、細胞外領域において糖鎖修飾などを受ける。 アミノ酸配列の相同性や機能的な役割などから、5つあるいは6つのサブファミリーに分類されるが、800種の多くは下記3つ(A、B、C)のサブファミリーに属する 1)。ファミリーAは最大のサブファミリーで、細胞外にあるN末端領域が短く、膜貫通領域においてリガンドを受容する。受容するリガンドは、ロドプシン、アセチルコリン、アドレナリン、エンドセリンなど、脂溶性低分子からペプチドまで多岐にわたる。GPCRのおよそ半数を占め、揮発性低分子(匂い物質)を受容する嗅覚受容体も、ファミリーAに属する。本稿の後半で取り上げるファミリーBは、100~300アミノ酸からなるやや長いN末端領域において、セクレチン、グルカゴン、GLP-1などのペプチドホルモンをリガンドとして受容する。ファミリーCは、300~600アミノ酸からなる特徴的なドメイン構造を有するN末端領域において、グルタミン酸やγ-アミノ酪酸などを受容する。
2024年10月08日 -
特集
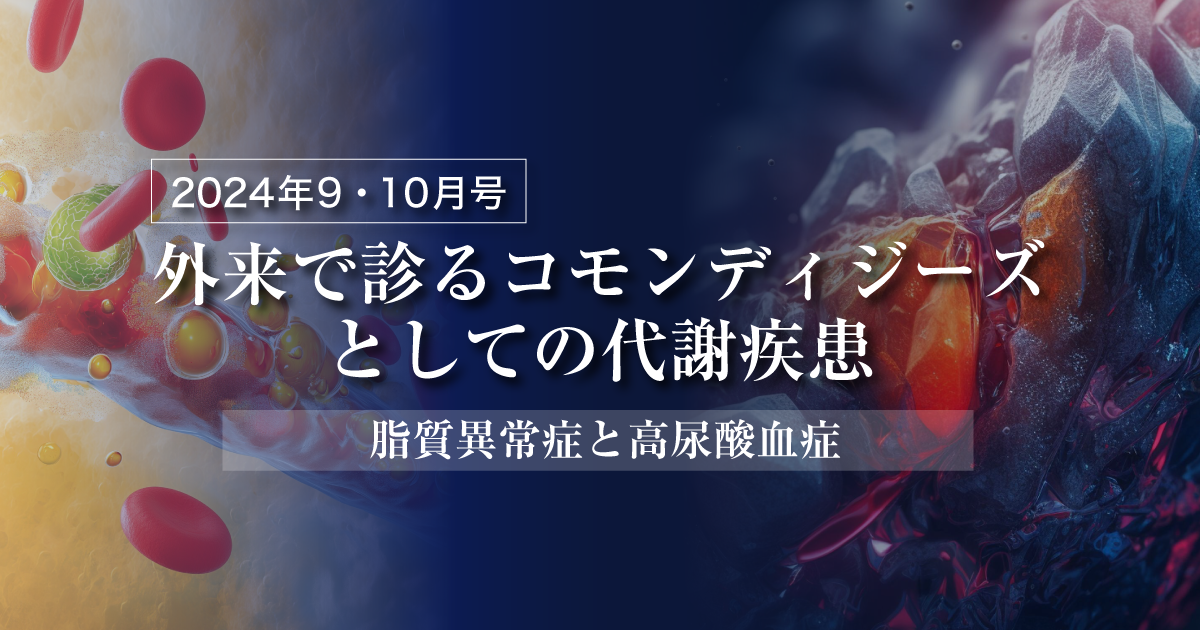
3.脂質異常症に対する食事療法のエビデンスと指導のポイント
はじめに 脂質異常症は冠動脈疾患を中心とする動脈硬化性疾患(atherosclerotic cardiovascular disease:ASCVD)の予後を決定する重要な危険因子であり、遺伝的な脂質異常症においてでさえ食生活の是正が予防や治療の基本である 1)。そのため、食事に関する脂質(エネルギー源である脂肪とエネルギー源でないコレステロールを合わせたもの)の生化学的な代謝と臨床的なエビデンスを正しく知ることが重要になる。またダイエットパターンとしての日本食や地中海食、dietary approach to stop hypertension diet(DASH食)が注目されている。本稿では、『動脈硬化性疾患予防ガイドライン2022年版』 1)と『動脈硬化性疾患予防のための脂質異常症診療ガイド2023年版』 2)を中心にASCVD予防のための食事療法を解説する。なお、内容の詳細や引用文献、また食物繊維(穀物、野菜、果物)、果糖を含む加工品、海藻、ナッツ類などは誌面の都合上割愛するが上記ガイドラインを参照されたい。 1.総エネルギー摂取量と脂肪エネルギー比率 肥満者においては、総エネルギー摂取量を制限して減量することによる総死亡リスクの減少と脂質異常や血圧の改善がメタ解析で示され、ASCVD予防の可能性があると考えられる。よって、まず適正な総エネルギー摂取量と適正な体重を維持することが大切である。エネルギー比率でみると、炭水化物の摂取エネルギー比率50〜55%で総死亡リスクが最低であり、低炭水化物あるいは高炭水化物食は総死亡リスクを上昇させる 1)。血清脂質については、高脂肪食と比較したところ低脂肪食で総コレステロール(TC)とLDLコレステロール(LDL-C)の低下、トリグリセライド(TG)の上昇およびHDLコレステロール(HDL-C)の低下(通常、わずかな低下にとどまる)が認められる 1)。したがって適正な総エネルギー摂取量のもとで脂肪エネルギー比率20〜25%、炭水化物エネルギー比率50〜60%に設定することが勧められる(表1)。 目標とする体重の目安は、総死亡リスクが最も低いBMIが年齢によって幅があることを考慮し、かつ肥満症の定義 3)を踏まえて表1および欄外の式から算出する。ただし高齢者では現体重に基づき、フレイル、摂食状況や代謝状態の評価を踏まえ適宜判断する。
2024年10月02日 -
投稿論文
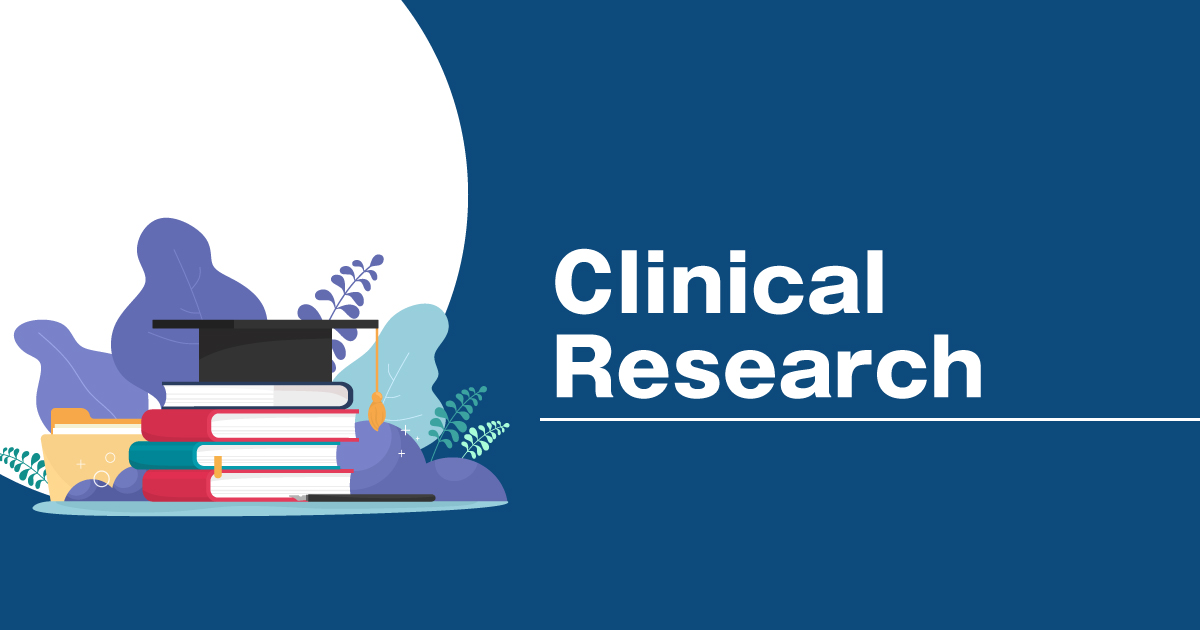
長期間血糖コントロール良好(HbA1c 7.0%未満)2型糖尿病患者の臨床像
要約 2006~2019年に川井クリニックを初診した20歳以上65歳未満、初診時HbA1c 7.0%以上の2型糖尿病患者データをCoDiC-MSより抽出、初診1年以内にHbA1c 7.0%未満達成者(973名)と非達成者(557名)の比較と達成者で7.0%未満を初診3年後まで維持できた165名とできなかった540名の比較を行った。 達成群は非達成群より初診時罹病期間が短く、他院通院歴ありが少なく、薬剤なし・経口薬1剤治療者が多く、初診時HbA1cは各々9.5/10.1%、1年後のHbA1cは6.8/8.2%であった。初診時BMIに差はなかったが、1年後は非達成群で増加していた。 維持群は非維持群と比べ達成群の特色をより強く備え、経口薬1剤以下の治療が維持され、3年後のHbA1cは各々6.3/7.3%であった。以上より、2型糖尿病治療では早期の治療開始と生活習慣改善への啓発および改善意欲の継続が重要であることを再認識した。
2024年09月27日 -
セミナー

GLP-1受容体作動薬の種類と使い分け
Q&A編はこちら はじめに Glucagon-like peptide-1(GLP-1)は小腸の消化管内分泌細胞であるL細胞から分泌されるペプチドである。食事による血糖上昇に応答する形で膵β細胞のGLP-1受容体に結合し、β細胞からのインスリン分泌を促進するため、血糖上昇時のみにインスリン分泌をもたらすことが特徴である。GLP-1はdipeptidyl peptidase-4(DPP-4)により分解され活性を失うため、GLP-1受容体作動薬はDPP-4による分解を受けにくい構造を持ち、GLP-1受容体を刺激することで血中GLP-1を薬理学的濃度まで上昇させ血糖降下作用が得られるように開発された。GLP-1の膵外作用として、胃内容物排泄遅延、食欲中枢における食欲抑制も認めることから、GLP-1受容体作動薬には体重減少効果も期待される。加えて、近年では心血管イベントや腎イベント進行抑制のエビデンスも明らかとなってきていることから、実臨床で使用されるケースが年々増加しており、本稿では各製剤の特徴および実際に使用した症例に関して解説する。 1.GLP-1受容体作動薬の分類と特徴 構造からはヒトGLP-1に由来する製剤とアメリカドクトカゲの唾液腺から抽出されたexendin-4に由来する製剤に分類、作用時間からは短時間作用と長時間作用型に分類される。現在本邦で使用できる各製剤の特徴を表1に示し、概説する。 表1 本邦で使用可能なGLP-1受容体作動薬一覧(商品名:ウゴービ〔セマグルチド〕を除く) 画像をクリックすると拡大します 表1 本邦で使用可能なGLP-1受容体作動薬一覧(セマグルチド〔商品名:ウゴービ〕を除く) $(".vol5_r11_h1").modaal();
2024年09月26日 -
特集
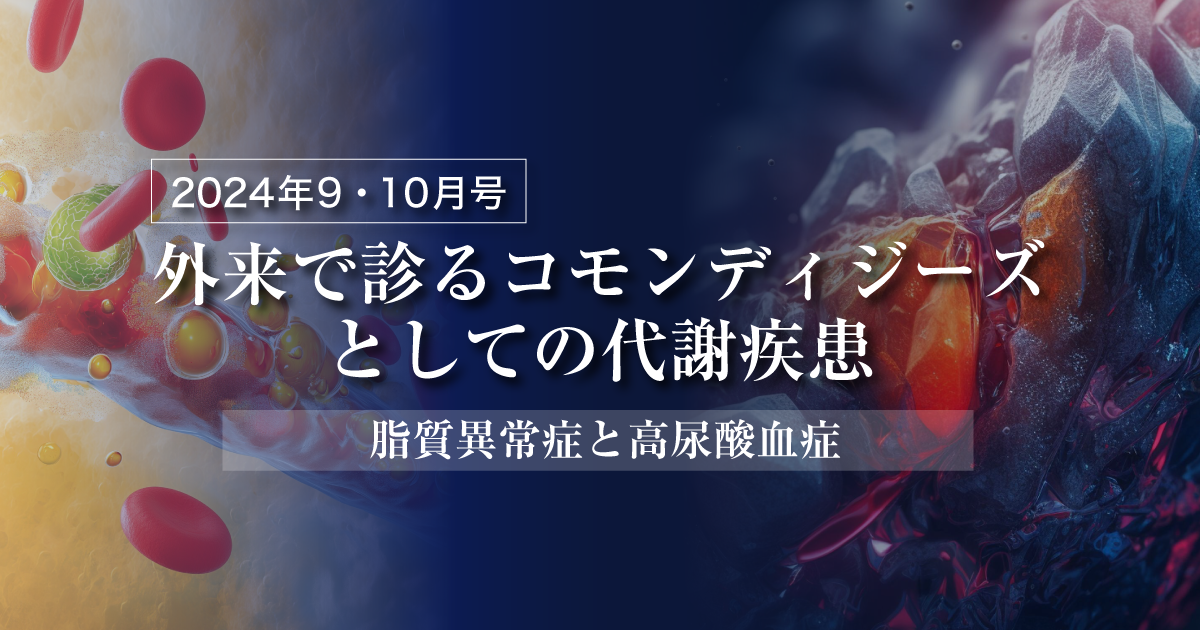
2.高TG血症に対する治療介入をどう考え実践するか
はじめに 高トリグリセライド血症(高TG血症:hypertriglyceridemia)は、血中トリグリセライド濃度(TG値)が異常高値となる状態であり、高コレステロール血症とともに脂質異常症の代表的な疾患である 1)。TG値が空腹時採血で150mg/dL以上、または随時採血で175mg/dL以上であれば高TG血症となる(表1)。高TG血症は動脈硬化性疾患の重要な危険因子の一つであるほか、TG値が著明高値の状態は急性膵炎の発症要因である 2)。一般外来で日常的に遭遇する高TG血症は、そのほとんどがいわゆる生活習慣病として生活習慣の改善を含めた治療介入を必要とする。本稿では高TG血症の病態とともに、治療介入のポイントについて、特に動脈硬化性疾患発症予防の観点でどのようにすべきかを中心に解説する。 表1 脂質異常症診断基準(日本動脈硬化学会編: 動脈硬化性疾患予防ガイドライン2022年版. 日本動脈硬化学会, 東京, 2022; p.22.より) 1. 高TG血症の病態と疾患リスク 1)TGの役割と体内での移動 TGは生体にとって主にエネルギーの輸送媒体として重要である。また、皮下脂肪や内臓脂肪などの脂肪組織で貯蔵される脂質は主にTGである。肥満はこれら脂肪組織などに過剰にTGが蓄積した状況である。 食事で摂取した脂肪は消化管でいったん分解され小腸で吸収された上でTGに生合成されるほか、肝臓では糖や脂肪酸などを材料として合成される。合成されたTGは血中で脂質を輸送するタンパク、すなわちリポ蛋白に含まれる形でコレステロールなどとともに血中を輸送される。このリポ蛋白は比重によって主に4つの分画に分けられ、比重の低い方からカイロミクロン(chylomicron:CM)、超低比重リポ蛋白(very low-density lipoprotein:VLDL)、低比重リポ蛋白(low-density lipoprotein:LDL)、高比重リポ蛋白(high-density lipoprotein:HDL)と呼ばれる。また、リポ蛋白は比重が小さいほど粒子が大きい。すなわちCMが最も大きく、HDLが最も小さい。CMは外因性リポ蛋白で主に小腸で合成され血中に放出される。VLDLとLDLはいずれも構造タンパクとしてアポリポ蛋白B100(apolipoprotein B100:apoB100)を含む一連の内因性リポ蛋白で、VLDLが肝臓で合成され血中に放出される。CMやVLDL中のTGは血中でリパーゼによる代謝を受け、TGが減少したリポ蛋白は、粒子サイズが小さくなると同時に比重が高くなり、VLDLはLDLとなる。HDLはコレステロール逆転送を担うとともに血中で他のリポ蛋白からTGを受け取り拡散させている。 TG値は基本的に血中へのTGの供給と血中からの代謝により決まり、供給過剰と代謝遅延の片方あるいは両方が生じると高TG血症となる。供給過剰は主に食餌摂取量が過多の状況で生じ、代謝遅延については後述するがさまざまな要因によって生じ、その要因によって重症度もさまざまである。
2024年09月18日