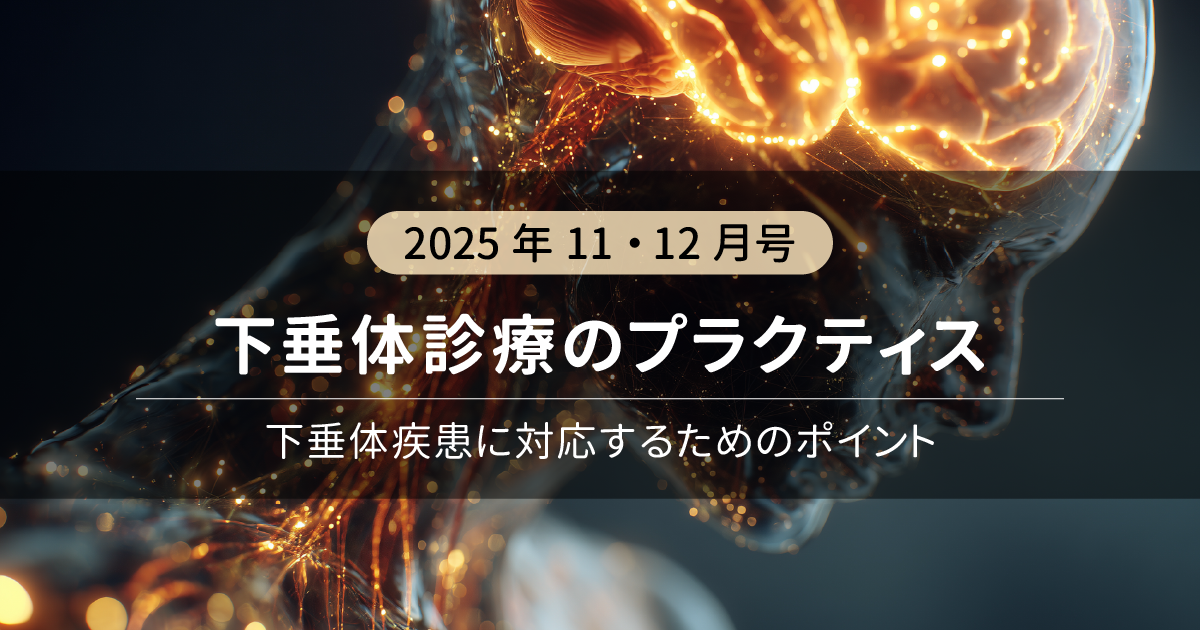- トップページ
- 新着論文一覧
新着論文一覧
-
セミナー
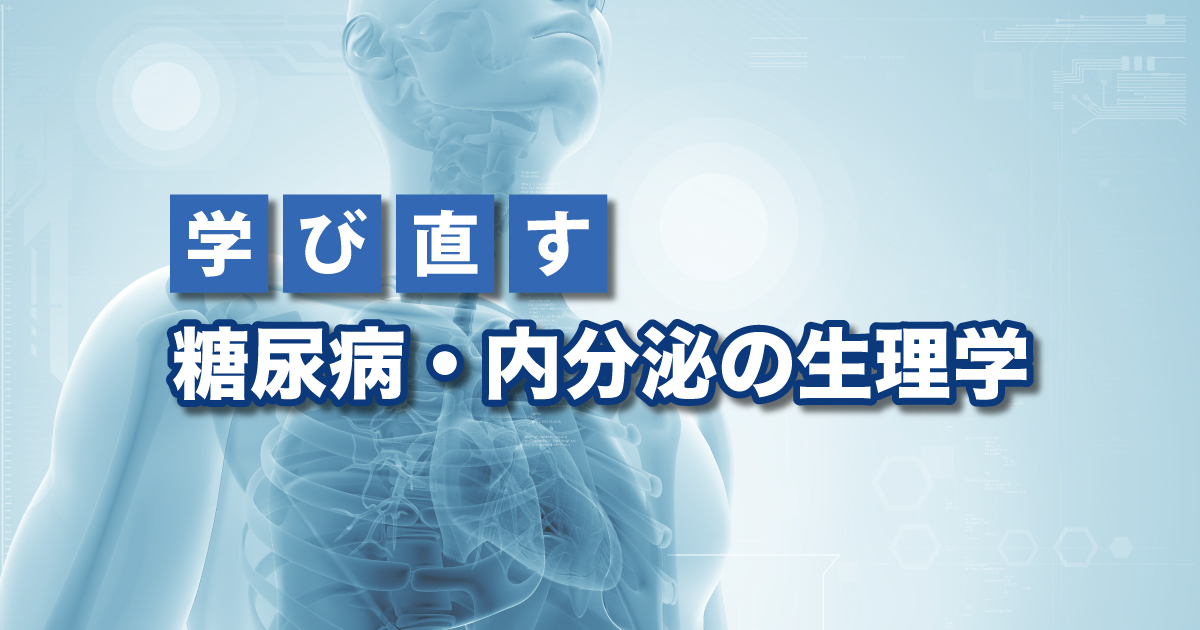
神経系による腎機能の保護
はじめに 近年、腎臓領域において、腸内細菌との関連(腸腎連関)や心血管疾患との関連(心腎連関)が数多く報告されており、腎臓と多臓器との連関が注目されている。そのため、日常臨床においても専門分野だけでなく、臓器連関を意識した治療が肝要である。特に糖尿病・内分泌領域と腎臓領域との関わりといえば、sodium-glucose cotransporter 2(SGLT2)阻害薬の腎保護効果が想起され、すでに日常診療に浸透し始めている。慢性腎臓病におけるダパグリフロジンの効果を検討したDAPA-CKD試験では、CKD 患者において、糖尿病の有無にかかわらず、推算糸球体濾過量(eGFR)低下、末期腎不全、腎疾患死・心血管死の複合リスクがダパグリフロジン投与群で有意に低いという結果であった 1)。SGLT2阻害薬による腎保護効果の機序としては緻密斑を介した尿細管糸球体フィードバック、Na利尿作用による体液再分配、尿細管仕事量の減少による糖毒性や低酸素の改善、後続の尿細管への仕事量増加に起因した酸素需要の亢進によるエリスロポエチン産生促進などが挙げられる 2)。また、その他にもSGLT2阻害薬により心拍数増加を伴わない血圧低下がみられることから、交感神経への直接作用なども示唆されている。 交感神経・副交感神経からなる自律神経系は大部分の内臓機能を制御する神経系であり、動脈圧、胃腸管分泌、膀胱排泄、発汗などを介して、数秒から数十秒の単位で迅速かつ強力に内臓機能を変化させることができる。近年になって自律神経系が免疫系を介して、腎臓をはじめとした多臓器へ作用を及ぼすことが分かってきたが、依然として不明な点も多い。本稿では腎臓と自律神経系に関する生理学的な内容を確認し、神経系との関連(脳腎連関)におけるこれまでの知見や臨床応用への展望について概説していく。 1.自律神経支配と腎臓 自律神経系は中枢神経を出た後、神経節を経由して節前線維から節後線維へ乗り換え、標的臓器を支配する。交感神経・副交感神経のいずれも節前線維は共通してコリン作動性神経であり、神経伝達物質のアセチルコリンを放出し、節後線維へ興奮を伝える。節後線維は標的臓器において、神経終末よりノルアドレナリン(交感神経)、アセチルコリン(副交感神経)を放出し、臓器にさまざまな影響を及ぼす(図1、2)。また、腎臓は腹腔内臓器の中でも神経支配が豊富な臓器であり、特に交感神経と感覚神経線維が主である 3)。腎神経叢は腹腔神経節、上部・下部腎臓神経節、上腸間膜神経節、胸部内臓神経線維から構成され、主にノルアドレナリンを神経伝達物質とするアドレナリン作動性ニューロンからなる。腎動脈などの血管平滑筋細胞ではα1Aアドレナリン作動性受容体を介して血管収縮や腎血流を調整し、糸球体傍装置ではβ1アドレナリン作動性受容体を介してレニン分泌を調節し、尿細管ではα1Bアドレナリン作動性を介してナトリウム再吸収などに関与する。また、副交感神経が腎臓へ直接入る経路も一部で報告されているが、その機能は明らかになっていない。
2023年11月10日 -
特集
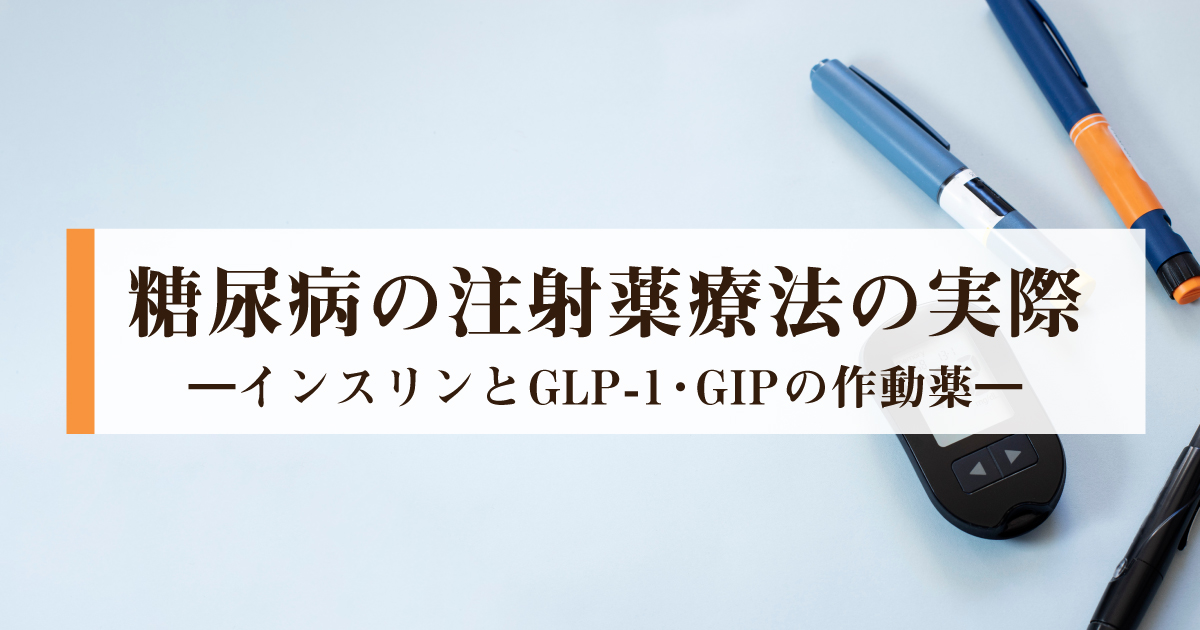
1.1型糖尿病のインスリン治療
はじめに 1型糖尿病の治療はインスリン療法が必須である。1993年に発表されたDiabetes Control Complication Trial 1)より、1型糖尿病患者には「強化インスリン療法」を行うことが普及した。「強化インスリン療法」は「頻回注射療法」と同義ではなく、例えば、米国糖尿病学会(ADA)から出版されたKaufmanらの書 2)には、「生活スタイルに合わせて患者自身がインスリンを調節し良好な血糖コントロールを求める方法」と定義されている。一方、本邦の丸山らの書 3)ではもっと具体的な治療方針を含む記述が示され、「頻回注射療法(MDI)あるいはインスリン持続皮下注入療法(CSII)に血糖自己測定(SMBG)を併用し、インスリン注射量を患者自らが調節しながら可能な限り良好な血糖コントロールを目指す方法」と定義している。「患者自らが生活や血糖に応じてインスリンを調整する」ことこそが強化インスリン療法である。 1型糖尿病患者は、非糖尿病患者と同じように、食事や運動のほか、仕事や趣味の活動、家族や友人との会食や結婚式などのイベントへの参加、学校生活や修学旅行、海外旅行、進学や就職、結婚、出産、そして高齢期へ、といった人生を送る上でのありとあらゆる場面において、血糖を調節するためにどのようにインスリン療法を合わせるか、という工夫と共に生きなければならない。その工夫を行うために、医療従事者は1型糖尿病のインスリン治療や製剤について正しく理解し指導できること、また患者がそれらを日常生活の中で実践できるような指導を行うことが求められる。 現在の1型糖尿病のインスリン治療の選択肢を表1に示す。インスリン療法は、ペン型注入器を用いたMDIとインスリンポンプを用いた治療(CSIIとSAP〔Sensor Augmented Pump〕)の2種類から選択可能である。本稿で扱うMDIは、1型糖尿病治療では最も基本的なインスリン治療方法であり、CSIIやSAPを選択した患者も、ポンプトラブルの際にはMDIに直ちに切り替える対応を要することから、全ての1型糖尿病患者でMDIの考え方や実践方法を習得することが望ましい(CSIIやSAPについては本特集の他稿を参照されたい)。 また、すべての1型糖尿病患者においては血糖推移の把握のためSMBGや持続血糖モニター(CGM)で自身の血糖を把握し、その値や血糖変動を踏まえてインスリン調整を行う。また近年では、経口糖尿病薬であるSGLT2阻害薬の中で1型糖尿病に保険適用がある薬剤(イプラグリフロジンあるいはダパグリフロジン)も使用可能となった。 表1 1型糖尿病の治療選択肢 1.MDIの原理 MDIで重要なポイントは、基礎インスリンと追加インスリンの役割を分けて考え、両者の特徴を意識して単位数調整を試みる。ヒトのインスリン分泌には、食事による血糖上昇に対応して分泌される『追加分泌』と、カテコラミンなどのホルモンによる血糖上昇を抑制し血糖値を常に一定レベルに制御し、また脂肪の分解により脂肪酸が肝に流入しケトン体が産生されるのを抑制するために、絶え間なく分泌される『基礎分泌』の2種類の分泌様式から構成されている。1型糖尿病の治療では基礎・追加分泌補充を適切に行うことが不可欠である。
2023年11月06日 -
特集
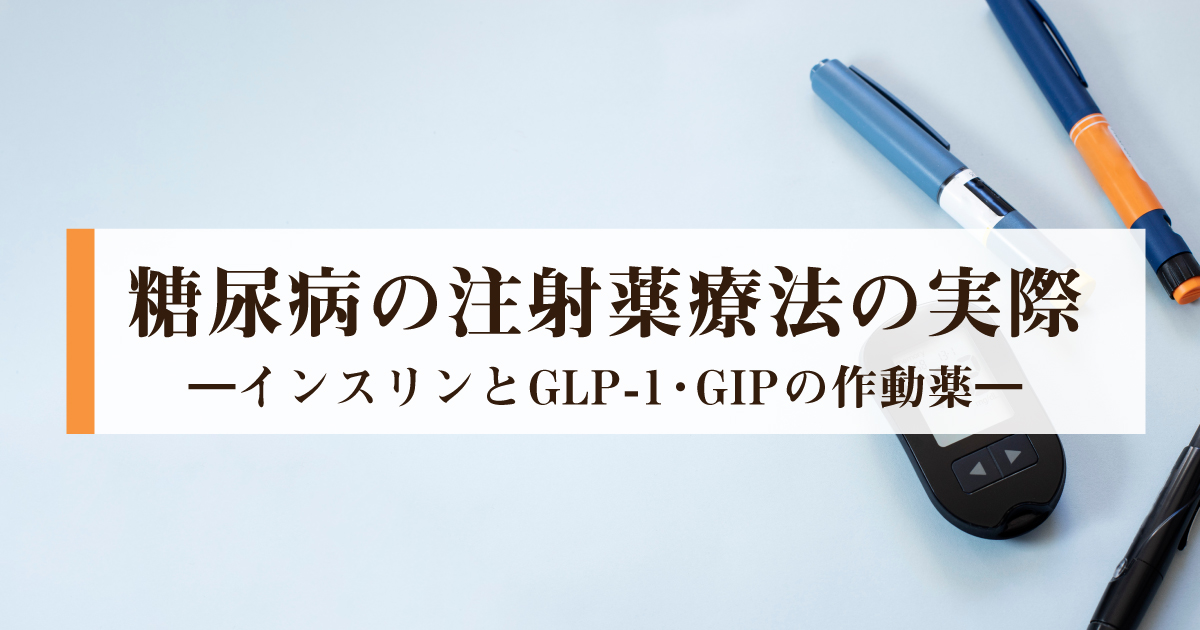
(扉)特集にあたって
インスリンが1922年に発見されて高血糖状態であったレオナルド・トンプソン少年に注射されてから今年で101年目となる。自分(黒田)が1型糖尿病となりブタあるいはウシのインスリン製剤を打ち始めて約40年となった。当時のインスリンは現在のようにペン型のようなものはなく、使い捨ての注射器こそあったものの針は27Gと現在の34Gの注射針と比べると大変太い針であった。その後ヒトインスリン、ペン型注射器、インスリンポンプ、CGMが次々と開発利用されて糖尿病治療は飛躍的な進化を遂げた。しかしながら、これら最新の治療のUpdateについていくのが糖尿病専門医でも大変困難となってきているように感じる。 本特集では「糖尿病の注射薬療法の実際 ―インスリンとGLP-1・GIPの作動薬―」と題して7名のエキスパートの先生方にそれぞれのテーマの詳細と最新情報をご執筆いただいた。伊藤 新先生からは「1型糖尿病のインスリン治療」として強化インスリン療法の基本を中心にご執筆いただいた。岩田葉子先生、弘世貴久先生からは「2型糖尿病のインスリン治療」としてインスリンの導入についてのコツをご執筆いただいた。前田泰孝先生からは「最新インスリン注入デバイスを活用した糖尿病治療(ポンプを中心として)」として最新のHCLの治療についてご執筆いただいた。石黒瑞稀先生、西村理明先生からは「CGMデータを活用したインスリン治療の最適化」としてisCGM(FreeStyleリブレ)を用いてどのように治療に活かすのかについてご執筆いただいた。利根淳仁先生からは「GLP-1受容体作動薬による2型糖尿病治療」として注射のみならず内服製剤についてもご執筆いただいた。大西由希子先生からは「GIP/GLP-1受容体作動薬(チルゼパチド)の特徴」としてチルゼパチドの治験を中心にご執筆いただいた。大門 眞先生からは「インスリン・GLP-1受容体作動薬配合注」としてインスリンとGLP-1受容体作動薬の併用のメリットをご執筆いただいた。 全体に非常に読みやすく、その道のビギナーからプロといわれる先生方にとっても充実した内容に満足されることと期待する。 著者のCOI (conflicts of interest)開示:黒田暁生;講演料(ノボ ノルディスク ファーマ、日本イーライリリー、サノフィ)、鈴木 亮;講演料(ノボ ノルディスク ファーマ、日本イーライリリー、サノフィ) 本論文のPDFをダウンロードいただけます
2023年11月06日 -
連載

第68回 糖尿病の検査2022(後編)
はじめに 厚生労働省によると、わが国の糖尿病患者数は、生活習慣と社会環境の変化に伴って急速に増加している。糖尿病は、糖尿病網膜症、糖尿病腎症、糖尿病神経障害、糖尿病足病変、糖尿病大血管症などの慢性合併症を引き起こし、さらに糖尿病は脳卒中、虚血性心疾患などの心血管疾患の発症・進展を促進することも知られている。そしてこれらの合併症の把握と治療目的でさまざまな検査が行われている。よって本連載では諸検査の算定要件について、前回は検査の通則、検体検査判断料と検体検査管理加算および糖尿病が適応である各検体検査について概説した。そして今回は後編として、医科点数表の区分が「呼吸循環機能検査等」、「監視装置による諸検査」、「脳波検査等」、「神経・筋検査」、「眼科学的検査」、「負荷試験等」および「画像診断」について概説し、適応となる糖尿病と関連疾患を表に示した。各生体検査の医学的意義については、本誌の各特集などを参考にされたい。 1.「呼吸循環機能検査等」である基礎代謝測定、体液量等測定、脈波図・心機図・ポリグラフ検査および「監視装置による諸検査」であるノンストレステストについて(表1) 1~4) 「D204 基礎代謝測定」は、空腹安静時の二酸化炭素排出量/酸素摂取量に相当する酸素の燃焼カロリーから単位時間当たりのエネルギー量を算出する検査であり、糖尿病が適応となる。 「D207 体液量等測定」は、脱水や溢水状態を診断するために全体液量や細胞外液量を測定する検査であり、糖尿病性ケトアシドーシスや糖尿病性昏睡が適応となる。 「D214 脈波図、心機図、ポリグラフ検査」の「6 血管伸展性検査」は、記録した脈波図により脈波伝達速度を求めて動脈硬化の程度を調べる検査であり、糖尿病が適応となるが、脈波図検査とは併せて算定できない(表2)。 「D219 ノンストレステスト(一連につき)」は、妊娠中に、分娩監視装置により子宮収縮などのストレスがない状態で、胎児の状態を胎動と心拍数により評価する。通知に示された適応患者には、「ス 糖尿病(治療中のものに限る)または妊娠糖尿病(治療中のものに限る)の患者」が含まれる。そして入院中は週3回、外来では週1回算定できる。 表1 「呼吸循環機能検査等」と「監視装置による諸検査」の告示および通知の要点と推定される適応疾患(文献1~4より) 画像をクリックすると拡大します 表1 「呼吸循環機能検査等」と「監視装置による諸検査」の告示および通知の要点と推定される適応疾患(文献1~4より) $(".vol5_r13_h1").modaal();
2023年10月30日 -
特集

5.肥満症患者の心理・性格特性とオベシティスティグマ
はじめに 肥満症治療の対象となる患者は種々の心理特性や性格特性を持ち、その理解は肥満症治療において不可欠である。また肥満者に対する社会的偏見・差別(オベシティスティグマ)の存在は治療の妨げとなるばかりでなく、医療政策上も看過できない問題となっている。本稿では、肥満者や高度肥満症患者の心理特性、性格特性について述べ、オベシティスティグマについて概説する。 1.肥満者の心理特性 肥満者の心理特性として、よく研究されているのは“抑うつ”である 1)。肥満と抑うつは双方向性に影響を与える関係にあることが確認されている。肥満者は抑うつ時に体重が増え活動が減少する傾向が見られる。その場合は、悲哀や苦痛など“典型的うつ病”の症状に収まらない“非定型うつ病”の可能性がある。気分障害の約3分の1がこれに当てはまるといわれ、食欲の亢進または著しい体重の増加がその診断基準の一つとなっている。非定型うつ病では、抑うつや不安状態に反応してむちゃ食いが見られ、特に炭水化物や甘い菓子類が多いといわれる 2)。他に、肥満症患者の心理特性には、自尊感情や自己効力感の低下、認知の歪み、ボディイメージの障害などが見られるが、高度肥満になるほど、その傾向が強くなる。 肥満者の食行動も心理特性と関連している。肥満者ではむちゃ食い(制御できない過食:binge eating)、だらだら食い(grazing)、夜間摂食症候群などがしばしば見られる 3)。これらの異常な摂食行動は、“抑制的摂食”の反動としての心理的“脱抑制による摂食”や、ストレスや不快な感情が誘因となる“情動的摂食”に基づく場合が多い。
2023年10月25日 -
特集

4.肥満症治療における内視鏡的治療の進歩―内視鏡的スリーブ状胃形成術
はじめに 近年、糖尿病合併肥満症に対するGLP-1受容体作動薬など、肥満症例に対する内科的治療の進歩は著しいが、生活指導や内科治療法のみで減量を長期に維持することは未だ容易ではない。高度肥満症例に対しては、腹腔鏡下スリーブ状胃切除術(laparoscopic sleeve gastrectomy:LSG)が保険収載され、標準治療として実施されているようになり良好な長期成績が報告されている 1, 2)。その結果、外科的治療の実施数は着実に増加傾向にあるが、海外に比べ高度肥満症例の割合が低く、外科的治療の社会的周知・理解も十分とはいえない状況で、多くの適応症例が治療機会を逃していると予想される。 治療抵抗性の高度肥満例の多い欧米では、内科的治療と外科手術の橋渡し的役割として、さまざまな内視鏡的インターベンションが開発されてきた。特に、本稿で紹介する、Mayo Clinicのグループにより考案された内視鏡的スリーブ状胃形成術(endoscopic sleeve gastroplasty:ESG)は、2013年に初の臨床例が報告されて以来、すでに2万5千例以上の実施例が報告されている 3, 4)。 1.ESG手技の実際 1)ESGの手順 ESGは、内視鏡用縫合器(OverStitch Sx, Apollo Endosurgery社)を用いて胃を内腔から縫縮し、食後の満腹感を早期に達成させるとともに、胃内容の排出時間を遅延させることで長時間にわたる食欲の抑制を目指す治療法である 3)。治療に用いられるOverStitch Sxは、内視鏡先端に取り付けた曲針を用いて組織を縫工する器具で、小型の糸付き針を、曲針を組織に穿通させた後、鉗子孔を通して挿入した持針器とでやり取りすること縫合を行う。ESGでは、胃壁全層をコークスクリュー状の組織アンカーデバイスによって曲針内に引き込み、全層縫合による強固かつ耐久性の高い縫縮を目指す。縫縮は、胃角レベルから始め、前壁→大彎→後壁→後壁→大彎→前壁の順で口側へと縫い進め、「U字型」に連続縫合をした後、糸どめ用デバイスで固定する。約5~10針を胃体下部から体上部にかけて行うと、胃体部はスリーブ手術後同様に円筒状に変形する(図1)。 糸の縫縮力が不十分な場合、術後早期に縫合が緩むことで満腹感が減少し、体重が再増加する可能性がある。小規模な前向き研究では、従来の「U字型」縫縮に対して、胃の長軸方向の縫縮を追加した手法により体重減少効果に有意差が見られた 5)。当院でも、縫合回数を増やすことや、「U字型」にさらに大彎横方向のステッチを加える「ボックス型」縫合を導入するなどの縫縮力を強化するための改善策を試みている。
2023年10月18日 -
セミナー

糖尿病の各薬剤を処方する時に最低限注意するポイント(経口薬)
Q&A編はこちら はじめに 糖尿病治療の目標は「糖尿病のない人と変わらない寿命とQOL」である 1)。いずれの糖尿病治療薬にしても、血糖コントロールを改善することが第一の目的であることが多いが、最近はadditional benefitsとして合併症の抑制なども考慮して薬剤を選択することもある 2)。しかし血糖コントロールや合併症の指標が改善しても、副作用や社会・経済的な負担が大きければQOLが低下し、糖尿病治療の目標と逆行することにもなり得る。 近年、新しいクラスの糖尿病治療薬が次々と登場し、それらの選択の幅が大きく広がったことにより、一人一人の患者に適した治療がますます求められるようになっている。そのためには薬剤のメリットだけでなくデメリットも十分に考慮して、目の前の患者にとって最適な治療薬の選択をすることが望ましい。本稿では経口糖尿病薬を選択する際(投与前)、あるいは経過のフォローアップ中(投与後)に最低限注意するポイントについて解説する。 1.総論 2023年6月現在、わが国では9クラスの経口糖尿病治療薬が使用可能である(表1)。それぞれの薬剤を初めて投与する際は、薬剤の特徴や内服方法についての説明のほか、事前に予想される副作用についても患者に十分説明しておくことが望ましい。以下にすべての経口糖尿病治療薬に共通して注意するポイントを挙げる。 表1 わが国で使用可能な経口糖尿病治療薬(日本糖尿病学会編・著: 糖尿病治療ガイド2022-2023. 文光堂, 東京, 2022, p.40-41.より) 画像をクリックすると拡大します 表1 わが国で使用可能な経口糖尿病治療薬(日本糖尿病学会編・著: 糖尿病治療ガイド2022-2023. 文光堂, 東京, 2022, p.40-41.より) $(".vol5_k10_h1").modaal();
2023年10月12日 -
特集

3.肥満2型糖尿病を含めた代謝性疾患への減量・代謝改善手術の臨床応用
はじめに 新型コロナ感染症の世界的大流行(パンデミック)はやっと落ち着きを見せているが、肥満も世界的に大流行の状態にあり、2017年のOECDのデータでは日本では肥満と定義されるBMI 25以上人口がメキシコ・米国では70%、ハンガリー・イギリス・カナダなどでも50%を超え、大きな社会・医学的問題となっている。 肥満をもたらす病態は複雑であり、基本治療である栄養・運動療法だけでは減量は困難なことも多い。近年、薬物治療とともに、肥満外科治療(減量・代謝改善手術)の進歩と普及は目を見張るものがあり、これらの最新の医療・医学を統合的に組み合わせた肥満症治療が推奨される。特に、肥満外科手術は肥満関連がんの予防、非アルコール性脂肪性肝炎(NASH)関連疾患の改善などが次々と明らかにされ、注目を集めている。本稿では減量・代謝改善手術の進歩、現状と課題に焦点を当てて解説する。 1.肥満の現状とその複雑な病態 日本国内における肥満人口の割合は厚生労働省「令和元年 国民健康・栄養調査結果の概要」から過去10年間では横ばいないし、微増の傾向にあるが、1980年と比較すると男性ではほぼ倍増し、中高年の増加が目立つ。また、治療に難渋するBMI≧35の高度肥満については「平成29年 国民健康・栄養調査報告」から0.6%存在している。 肥満とは医学的には摂取エネルギーが消費エネルギーを超えて余剰エネルギーが体内で脂肪として過剰にたまる状態であり、その中でも内臓脂肪型肥満は糖尿病・脂質異常症(高脂血症)・高血圧・冠動脈硬化など生活習慣病の原因となり、肥満の改善や予防は医学的観点からだけでなく、医療費の抑制という医療経済学的観点からも重要である。肥満の原因は単純には過食と運動不足となるが、その背景は運動をしないでも済む社会の実現、商業主義にあおられた美食・大食のもたらす食物の過剰摂取の存在に加えて、孤食の機会の増加、小児での食育の課題、高ストレス社会におけるストレス対応としての過食の問題など要因は複雑であり、運動療法と食事療法だけではうまくいかないことも多く、個別の病因・病態を把握した上での、食事療法、運動療法、認知行動療法に加えて、難治例には薬物療法、最近では肥満外科療法を含めた統合的肥満症治療が必要である 1)。
2023年10月05日 -
セミナー

FGF23関連低リン血症性くる病・骨軟化症―X連鎖性低リン血症(XLH)と腫瘍性骨軟化症(TIO)の最新エビデンス―
1.ポイント 線維芽細胞増殖因子(fibroblast growth factor:FGF)23関連低リン血症は、FGF23作用過剰により慢性低リン血症をきたし、小児ではくる病、成人では骨軟化症をきたす。低リン血症性くる病・骨軟化症を疑った場合、慢性低リン血症であることを骨型アルカリフォスファターゼ(bone alkaline phosphatase:BAP)高値で確認し、その後に血清カルシウム値と血清1α,25水酸化ビタミンD(1,25 dihydroxy vitamin D:1,25OH2D)が基準内中央よりも低値であることから原発性副甲状腺機能亢進症を除外した上で、低リン血症存在下でのFGF23相対的高値(≧30pg/mL)の有無を確認する。 完全ヒト型抗FGF23モノクローナル抗体であるブロスマブは、血清リン、1,25OH2Dを従来療法(経口リン製剤、活性型ビタミンD製剤)より効率的に改善し、偽骨折、骨折の高い治癒や予防効果が期待できるため、X連鎖性低リン血症(X-linked hypophosphatemia:XLH)および原因腫瘍が同定できないまたは手術が困難な腫瘍性骨軟化症(tumor-induced osteomalacia:TIO)症例(関節置換が必要となる例や美容的な問題が生じる例なども含む)に対して有用である。また経口リン製剤や活性型ビタミンDによる従来療法で問題となる腎機能障害進展のリスクを回避できる。 XLHではくる病・骨軟化症のほかに、脊柱靱帯骨化症、関節周囲の骨棘、アキレス腱の腱付着部症といった異所性骨化症を30~40歳以降に合併し、QOL低下の原因となるが、病因は明らかでなく血中リン濃度の補正や抗FGF23抗体による改善は見込めない。 後天性FGF23関連低リン血症性骨軟化症で最も高頻度なのは、骨や軟部組織に発生するphosphaturic mesenchymal tumor(PMT)によって惹起されるTIOであり、局在診断がなされれば、拡大切除により治癒が期待できる。 PMTの局在診断には、fluorodeoxyglucose-positron emission tomography/computed tomography(FDG-PET/CT)、本邦で保険未収載だがFGF23全身静脈サンプリング(FGF23 venous sampling:FGF23VS)、68Ga-DOTATOC PET/CTが有用である。 TIO以外の後天性FGF23関連低リン血症の鑑別疾患として、静注鉄剤、アルコール、神経線維腫症1型、悪性腫瘍に伴う異所性FGF23症候群がある。 2. 総論 1)病態 FGF23は成熟骨細胞から産生されるホルモンで、成熟骨細胞は局所のFGF受容体(FGF receptor:FGFR)を介して血中リン濃度を感知し、血中FGF23濃度を調整している。FGF23は腎近位尿細管におけるリン再吸収を抑制すると同時に、1α水酸化酵素を抑制し、24水酸化酵素の発現を促進させ、25水酸化ビタミンD(25 hydroxy vitamin D:25OHD)1,25OH2Dを低下させることで血中リン濃度を負に制御している 1, 2)。 FGF23の慢性的な過剰産生などによる慢性低リン血症では骨石灰化障害が惹起され、骨端線閉鎖前ではくる病、骨端線閉鎖後は骨軟化症を呈する。FGF23関連低リン血症性くる病・骨軟化症のうち頻度が高いのは、先天性のXLHと、後天性のTIOである。XLHはX染色体上のphosphate-regulating endopeptidase homolog, X-linked(PHEX)遺伝子の機能喪失型変異が原因となる。TIOは、骨や軟部組織に発生するPMTによって引き起こされ、原因となるドライバー変異としてfibronectin1(FN1)とFGFR1との相互転座などが報告されている 3)。
2023年10月02日 -
連載

つくば霞ヶ浦りんりんロードは、るんるんとはいかなかった
お誘いを受けて、梅雨の晴れ間のとある日曜日に、久しぶりの輪行そしてグループライドに参加した。cTDJ(cycling Team Diabetes Japan)による、およそ3年振りの企画である。cTDJとは、一見TDJ(Team Diabetes Japan)のサイクリング部門であるかのように思えるが、TDJの下部組織というわけではなく勝手に仲間内で名乗っているだけであり、したがって当然であるが公益社団法人日本糖尿病協会(日糖協)から公認を受けているわけではない。もちろん、日糖協へのチャリティーも行っていない。 本家(というべきではないのだろうが)TDJの方は、マラソンやウォークを通じて、糖尿病患者間の交流、治療継続意欲の向上、および糖尿病でない多くの国民に生活習慣病予防の啓発を目指すことを主旨・目的とした、日糖協の行う事業に基づくチームである(https://www.nittokyo.or.jp/modules/patient/index.php?content_id=7)。患者さんだけではなく、家族、医療関係者、企業、ボランティアなど、あらゆる方々が一緒に参加することによって連帯感を持つことを訴えかけている。cTDJの方はというと、1型糖尿病を持つ自転車好きが中心メンバーであるが、これまで糖尿病診療に関わる医療スタッフや、2型糖尿病を持つ自転車愛好家にも参加してもらってきた。言うなれば、患者会や診察室、SNS等で知り合った、自転車好き仲間のサークルである。主旨・目的は、TDJと同様と言えなくもない。日糖協を介するか介さないか、ホノルルまで行くか土浦まで行くかの違いであろう。 今回の趣旨としては、横浜市鶴見区で地域の糖尿病診療に多大なご尽力をいただいている「松澤内科・糖尿病クリニック」院長の松澤陽子先生が、最近ロードバイクを購入されたと聞きつけたので、是非ともcTDJにお迎えして一緒に走りましょうということになったのである。松澤先生は登山を趣味とされているような、元々アクティブな方なのだが、なにせロードバイクは初心者とのことで、車道の左端を走行することに慣れておらず、周囲の自動車や歩行者を気にすることなくロードバイクでの走行に集中できるようなサイクリングがしたいとのご希望であった。 そういうことならばと、cTDJの中心メンバーであるKさんが目をつけたのが、「つくば霞ヶ浦りんりんロード」である。つくば霞ヶ浦りんりんロードの全貌は、土浦駅を起点として東側の霞ヶ浦方面コース、西側の旧筑波鉄道廃線敷を活用したコースからなる、全長約 180 km のサイクリングコースである。土浦駅には、駅直結のサイクリング拠点施設である「りんりんスクエア土浦」が設けられ、シャワー、コインロッカー、更衣室だけではなくサイクルショップやレンタサイクルまで完備されている。cTDJではかつて東側のコースに取り組み、霞ヶ浦一周(通称カスイチ)を果たしたので、西側のコースを走破すればコンプリートできる。しかも、大部分が廃線跡を整地して造られたサイクリング専用の道路であり、鉄道路線だった頃の駅施設などが多数残されているという。まさに鉄・輪人のための、夢のような環境である。 余力のある若者は土浦まで自走したが、橫浜から参加する松澤先生とKさん、Nさんは常磐線直通列車で輪行するというので、品川駅から合流した。輪行のための自転車解体袋詰め作業も4年振りなので心配したが、意外に手順を覚えているもので、高輪ゲートウェイ駅前に人気がないのも幸いし、なんとか間に合った。早朝の車内は空いているので、大荷物を抱える我々にとっては都合がよい(写真1)。土浦駅の通路には、自転車の分解・組み立て専用スペースが用意されており、専用ラックも設置されているのがありがたい(写真2)。
2023年09月28日 -
特集

2. 肥満症治療薬の今後の展開
はじめに 世界の多くの国において肥満者の割合は増加し続けており、本邦における20歳以上のBMI 25kg/m2 以上の肥満者の割合は、男性33.0%、女性22.3% 1)に達している。肥満は糖尿病や脂質異常症、高尿酸血症などの代謝性疾患のみならず、閉塞性睡眠時無呼吸症候群、運動器疾患、月経異常といったさまざまな健康障害を引き起こす。日本肥満学会は、「肥満症」を「肥満に起因ないし関連する健康障害を合併するか、その合併が予測され、医学的に減量を必要とする疾患」と定義し、「肥満症治療指針」では、食事、運動、行動療法を行ったうえで減量目標が未達成の場合、肥満症治療食の強化や薬物療法、外科療法の導入を考慮することを示している 2)。肥満症治療薬として、持続性GLP-1(glucagon-like peptide-1)受容体作動薬セマグルチド(商品名:ウゴービ皮下注)が、本邦において承認を得たが、2023年現在、複数の薬剤が開発中である(図1)。本稿では、開発中の肥満症治療薬の現状とその展望について解説する。 図1 肥満症治療薬の体重減少率 それぞれの薬剤の臨床試験において示された最大の体重減少率を元に作図
2023年09月26日 -
セミナー

進化する1型糖尿病診療
Q&A編はこちら はじめに 1型糖尿病ではインスリンを分泌する膵β細胞が壊されてしまうことによりインスリンが分泌されなくなる。したがって、インスリンを補いさえすれば、1型糖尿病のない人と変わらない生活を送ることができるといわれている。しかし、適切にインスリンを補うことが簡単ではない。一人一人の生活、活動、食事の好み、体調、ライフイベント、また経済的状況などに合わせて、十人十色の血糖管理の方法がある。一人一人にベストな方法を見つけて、1型糖尿病のない人と変わらない人生を目指して、患者さんと共に取り組みたいと考える。 1.1型糖尿病の診断 1型糖尿病は発症様式別に、膵島関連自己抗体が関与する急性発症1型糖尿病 1)と緩徐進行1型糖尿病 2)、そして、特発性の劇症1型糖尿病 3)に分類される。急性発症1型糖尿病は高血糖症状の出現後、おおむね3カ月以内にケトーシスあるいはケトアシドーシスに陥り、直ちにインスリン療法を必要とする。緩徐進行1型糖尿病は、膵島関連自己抗体陽性を確認しても、ケトーシスあるいはケトアシドーシスに至らず、直ちにインスリン療法を必要としないことが多い。2023年、緩徐進行1型糖尿病の診断基準が改定された。最終観察時点でCペプチド<0.6ng/mLと内因性インスリン分泌の低下が確認されれば「緩徐進行1型糖尿病definite」と診断は確定する。インスリン分泌の低下を認めない場合は「緩徐進行1型糖尿病probable」としてCペプチドの推移を追う。この新しい診断基準により経年的に内因性インスリン分泌の低下を認めない症例においては、インスリン治療以外の治療法を検討する選択肢を考慮できるようになった。劇症1型糖尿病では高血糖症状出現後1週間前後でケトーシスやケトアシドーシスに陥り、直ちにインスリン注射の開始が必要となる。
2023年09月21日 -
セミナー
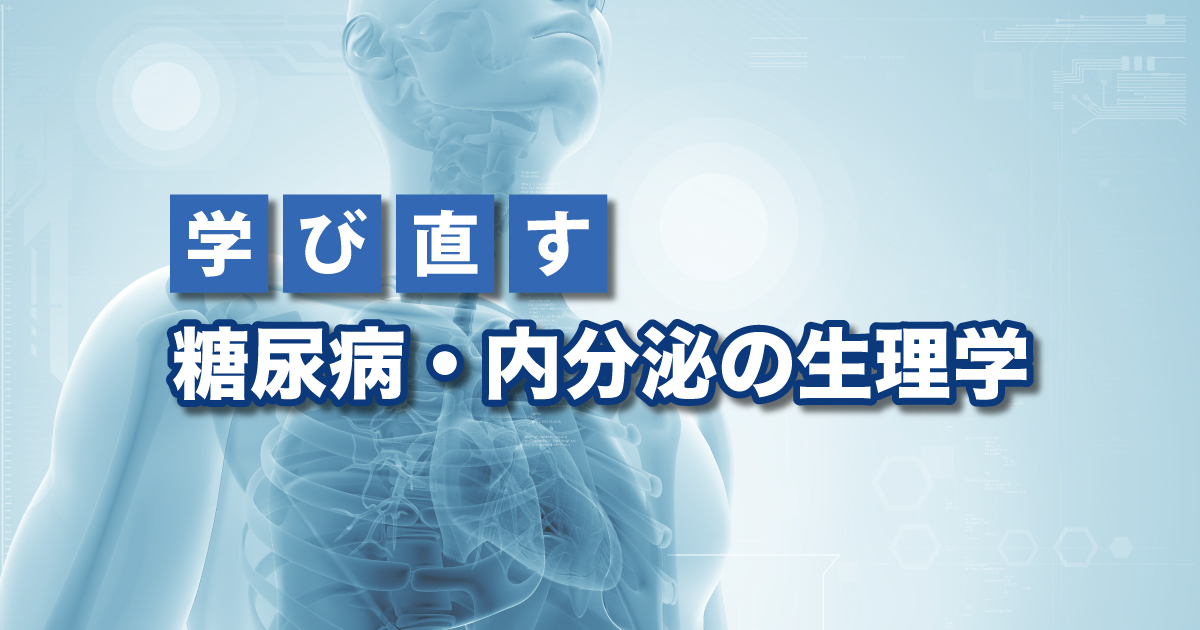
インクレチン
はじめに インクレチンは、栄養素の経口摂取に伴い消化管の腸内分泌細胞から血中に分泌され、膵β細胞に作用し、インスリン分泌を増強するホルモンの総称である。グルコース依存性インスリン分泌刺激ポリペプチド(glucose-dependent insulinotropic polypeptide:GIP)とグルカゴン様ペプチド-1(glucagon-like peptide-1:GLP-1)は生体で主要なインクレチンであることが示され、GIPとGLP-1は血糖値が一定以上の際にのみインスリン分泌増強作用を示すことから、2型糖尿病の治療標的として注目され、2009年からGLP-1シグナルを増強する薬剤が2型糖尿病の治療薬として世界中で広く用いられている。本稿ではGIPとGLP-1の膵β細胞への作用、生理的作用、そして分泌の分子機構について触れ、代謝内分泌疾患との関連も述べたい。 1.インクレチン効果 1932年にベルギーの生理学者Jean La Barreは、十二指腸の組織抽出物質が膵島のホルモン分泌を刺激する作用を持つことを実験的に示し、これらの生理作用を持つ腸管由来の因子を「インクレチン(incretin〔incrétine, une hormone intestine stimulait la sécrétion d’insuline、インスリンの分泌を刺激する腸管ホルモン〕)」と名付けた 1)。その後、1964年には、英国および米国の異なる研究グループが、経静脈グルコース投与と経口グルコース投与により同程度に血糖値を上昇させた際に、経口投与の方がインスリン分泌がはるかに多いことを報告し「インクレチン効果(incretin effect)」を量的に示した 2, 3)。摂食後に血糖値が上昇すると膵β細胞はインスリン分泌が誘導され、インスリン標的臓器が糖を取り込むことで血糖が低下する。栄養素の消化管への到達により分泌されるインクレチンは、膵β細胞のインスリン分泌を増強することで食後高血糖を是正し、血糖恒常性を維持する働きを持つ 4)(図1)。 図1 インクレチン効果(文献4より一部改変) 経口および経静脈グルコース投与では、経口投与の方が経静脈投与をはるかに上回るインスリン分泌を示す。「isoglycemic」経静脈投与とは、経口グルコース投与と同程度に血糖値を上昇させる経静脈的グルコース投与を行うことを意味する。
2023年09月13日 -
特集

1.肥満症治療薬としてのGLP-1受容体作動薬関連ペプチド
はじめに “肥満症”とは、BMI≧25の“肥満”のうち、肥満に起因ないし関連する健康障害を合併するか、その合併が予測される場合(内臓脂肪型肥満)で、医学的に減量を必要とする病態をいい、疾患単位として取り扱う(表1) 1)。また肥満症のうち、BMI≧35を高度肥満症とし明確に区別する。疾病側からみればその成因はさまざまであるが、肥満・内臓脂肪蓄積がその基盤にある病態とそうでないものを区別し合併症検索を行っていくとともに、肥満症では減量指導を第一に治療介入する意義を明確にすることが重要である。肥満症においては、食事・運動・行動療法を基本とした減量・内臓脂肪減少による健康障害の包括的な改善を目指すことを第一とするが、それらに抵抗性を示す主に高度肥満症例に対し、薬物治療や外科治療が考慮される。25≦BMI<35の肥満症の場合は、3~6カ月で現体重の3%以上の、BMI≧35の高度肥満症では現体重の5%以上の減量を目指す(図1) 1)。 表1 肥満症の診断(日本肥満学会編: 肥満症診療ガイドライン2022. ライフサイエンス出版, 東京, p.1, 9より改変) 図1 肥満症治療指針(日本肥満学会編: 肥満症診療ガイドライン2022. ライフサイエンス出版, 東京, p.3より)
2023年09月06日 -
特集

(扉)特集にあたって
三年以上にわたる新型コロナウイルス感染症との戦いも2023年5月に分類の5類移行に伴って、一つの区切りを迎え、今後、われわれは新型コロナ感染症と共存するニューノーマル時代を迎え、新たな医療の創造が求められている。このコロナのパンデミックの中でその重症化リスクとして肥満の危険性が明らかになり、コロナ以前からすでにパンデミックであった肥満の防止・治療の重要性が再認識された。 日本は世界に先駆けて肥満を病気として扱う肥満症という概念を提唱し、その治療に積極的に取り組んできたが、肥満をもたらす病態は複雑であり、基本治療である栄養・運動療法だけでは減量が困難な例も多い現状であったが、このような中、新たな肥満症治療薬の登場により、肥満症治療は急展開をしており、加えて、減量手術として始まった肥満外科治療(減量・代謝改善手術)は広く糖代謝を含めた代謝改善作用を認め、睡眠時無呼吸症候群、肥満関連がんの予防、NASH関連疾患などへの有用性も次々と明らかになっている。加えて、肥満症の治療に弊害となる肥満スティグマの問題や肥満患者に寄り添うための心理状態の理解も注目を集めており、これらの英知を集めた統合的な肥満症診療が今求められている。 本特集ではこれらの肥満症診療の進歩に焦点を当てて、薬物治療については臨床応用が進んでいるGLP-1受容体作動薬関連ペプチドについて、西澤 均先生・下村伊一郎先生に、さらに今後の肥満症治療薬の進歩・展開について廣田勇士先生に解説いただいた。また、肥満外科治療について最新の臨床応用を龍野が解説し、加えて、肥満外科治療として進歩の著しい内視鏡治療について伊藤 守先生・炭山和毅先生に解説いただいた。そして、最後に肥満症患者の心理状態と肥満スティグマについて野崎剛弘先生・澤本良子先生・小牧 元先生に解説いただいている。 本特集の執筆陣はこの分野に広範な経験と知識を有する専門家の方々であり、ご執筆の先生方のご尽力を多とするとともに、今回の特集によって読者諸賢の理解が深まり、それによって得られたものを臨床の現場にフィードバックしていただければ、企画者としてこのうえない喜びである。 著者のCOI (conflicts of interest)開示:小川 渉;講演料(住友ファーマ、アボットジャパン、日本ベーリンガーインゲルハイム、ノボ ノルディスク ファーマ)、研究費・助成金(住友ファーマ、帝人ファーマ、日本イーライリリー)、奨学(奨励)寄附(住友ファーマ、武田薬品工業、帝人ファーマ) 本論文のPDFをダウンロードいただけます
2023年09月06日 -
連載

第67回 糖尿病の検査2022(前編)
はじめに 糖尿病とその関連疾患に係る検査については、2年ごとの診療報酬改定の際に改定内容を概説してきた。今回は、2022年度の診療報酬改定に従い、「診療報酬の算定方法の一部を改正する件(告示)」 1)、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)」 2)、および「特掲診療料の施設基準等およびその届出に関する手続きの取扱いについて(通知)」 3)、これらをもとに、糖尿病とその関連疾患が適応となる検査 4, 5)を、前編・後編に分けて概説する。前編では、検査の通則、検体検査判断料と検体検査管理加算、および検体検査の各項目について、後編では、呼吸循環機能検査、脳波検査、監視装置による諸検査、神経・筋検査、眼科学的検査、負荷試験および画像診断について概説する。各検査の医学的意義については、本誌の各特集などを参考にされたい。 1.医科診療報酬点数表「検査」の通則について(表1) 医科診療報酬点数表告示の第3部「検査」では、第1節に検体検査料(検体検査実施料と検体検査判断料)、第3節に生体検査料、第4節に診断穿刺・検体採取料、第5節に薬剤料、第6節に特定保険医療材料料が示されている(※第2節は病理学的検査であったが、2008年に削除され、第13部「病理診断」として、「検査」とは別扱いになった)。 第3部「検査」の通則によると、その費用は、検体検査実施料、検体検査判断料および生体検査料の各区分の所定点数により算定するが、検体を穿刺・採取した場合は、診断穿刺・検体採取料の各区分の所定点数を合算して算定する。検査に当たって患者に対し薬剤を施用した場合は、特に規定する場合を除き、各区分の所定点数および薬剤料の所定点数を合算した点数により算定する。保険医療材料を使用した場合は、各区分、薬剤料および特定保険医療材料料の所定点数を合算した点数により算定する。医科診療報酬点数表に掲げられていない特殊な検査の場合は、医科診療報酬点数表に掲げられている検査のうちで最も近似する検査の各区分の所定点数により算定する。また、対称器官に係る検査の所定点数は、特に規定する場合を除き、両側の器官の検査料に係る点数とする。 第1節検体検査料第1款検体検査実施料の通則では、入院外の患者について、緊急のために、診療時間外、休日または深夜において、保険医療機関内において検体検査を行った場合は、時間外緊急院内検査加算として、第1款の各区分の所定点数に1日につき200点を所定点数に加算できるが、外来迅速検体検査加算は別に算定できない。この外来迅速検体検査加算は、入院外の患者に実施した検体検査の結果について、検査実施日に説明し文書により情報を提供し、検査結果に基づく診療が行われた場合に、5項目を限度として、外来迅速検体検査加算として、検体検査実施料の各項目の所定点数にそれぞれ10点を加算する。
2023年08月29日 -
特集
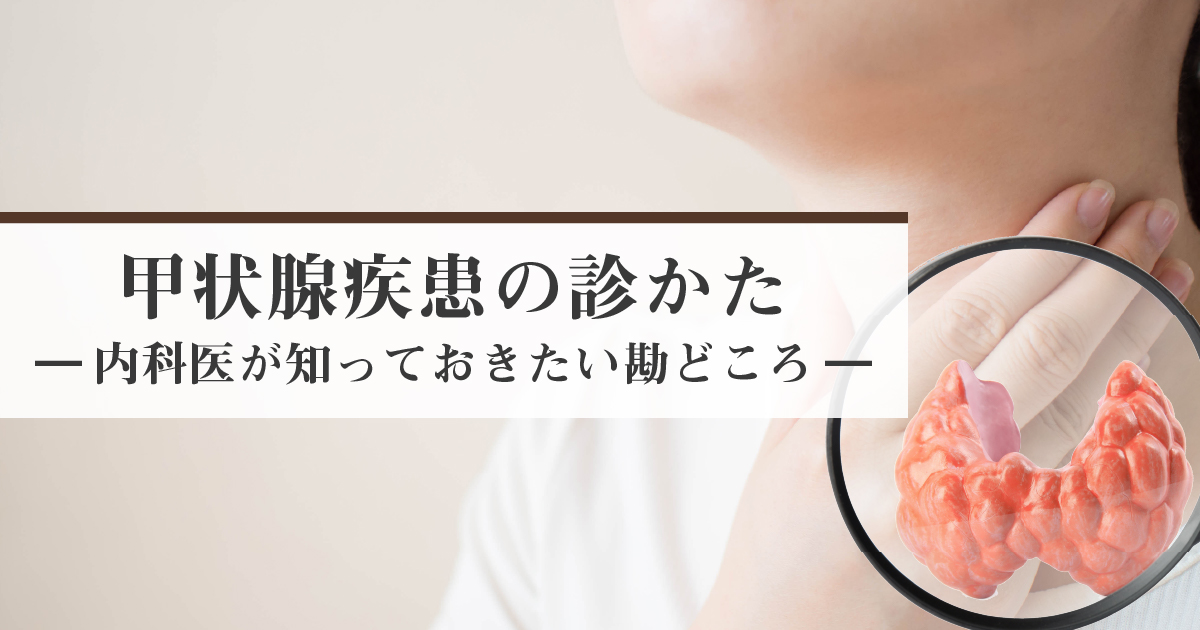
6.甲状腺疾患と妊娠・出産
はじめに 甲状腺ホルモンは妊娠の成立、胎児の発達や成長、妊娠維持に必須となるホルモンのため、母体甲状腺機能を妊娠早期から管理することは非常に重要な意味を持つ。未治療やコントロールの困難なバセドウ病の甲状腺機能亢進症の場合には、流早産、死産、妊娠高血圧症候群、心不全や甲状腺クリーゼの発症や低出生体重児出産や新生児甲状腺機能異常発症のリスクが一般妊婦に比較して高く、未治療の甲状腺機能低下症も流早産、妊娠高血圧症候群、胎盤早期剥離、低出生体重児、分娩後出血などの原因となる。これらのリスクは、妊娠前から妊娠中に適切な治療を行うことで軽減することが可能となる。また、潜在性甲状腺機能低下症であっても、妊孕性、流産や早産、妊娠糖尿病・妊娠高血圧症候群の発症、さらには児の精神発達への影響の可能性も報告されているが、レボチロキシン治療によってそれらが改善するかどうかは明らかではない。 1.生理的な妊娠中の甲状腺機能の変化(図1) 妊婦においても、遊離T4(FT4)、TSHを測定するが、非妊婦と同様にTSH低値でFT4が高値なら甲状腺機能亢進症と考えられ、逆にTSH高値でFT4が低値なら甲状腺機能低下症と考えられる。妊娠時にはエストロゲンの増加によってサイロキシン結合蛋白(TBG)が増加し、血中総サイロキシン(TT4)は増加するが、生理作用を発揮するFT4はTBGの増加の影響を受けないので、妊娠中の甲状腺系の評価にはFT4を用いる。着床後に絨毛組織から産生される性腺刺激ホルモンであるヒト絨毛性ゴナドトロピン(hCG)は妊娠8~10週をピークに分泌され、わずかな甲状腺刺激作用を有するため、妊娠初期にはFT4の軽度上昇とTSHの軽度低下をしばしば認める 1)。妊娠の中・後期には、FT4値は非妊娠時に比べて低値を示すことが多い(キットによりその程度はさまざまである)。妊娠中のFT4、TSH基準値は適切なヨウ素摂取対象者で決定されたその施設における各妊娠三半期の基準値が使用されるべきであるが、実際には施設ごとの基準値の決定は困難であることから、TSHの上限値はおよそ4.0μIU/mLもしくは基準値上限値−0.5μIU/mLと考えて管理を行う 2)。 妊娠12週くらいから児の甲状腺は機能をし始め20週以降には下垂体ー甲状腺系も完成することから、妊娠中のバセドウ病の病態は母児ともに考える必要がある。 図1 生理的な妊娠中の甲状腺機能の変化(Mandel SJ, Spencer CA, et al. : Are detection and treatment of thyroid insufficiency in pregnancy feasible? Thyroid. 2005; 15(1): 44-53. より作図)
2023年08月25日 -
特集
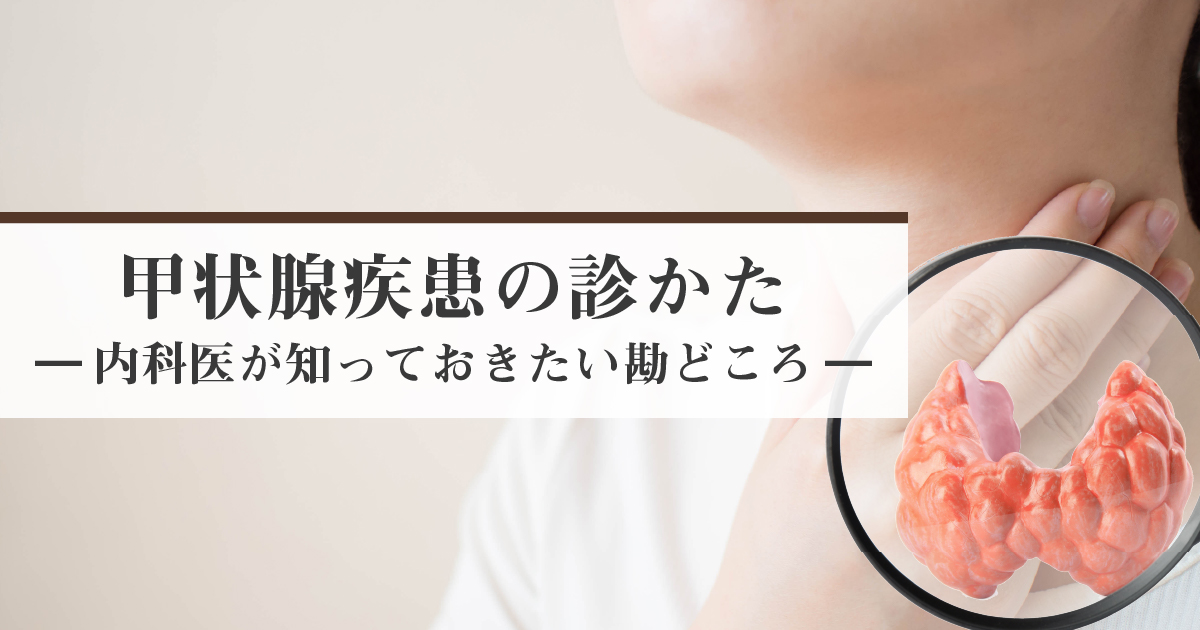
5.内科での甲状腺腫瘍の診かた
はじめに 臨床的に遭遇する甲状腺腫瘍の大部分は良性腫瘍であり、圧迫症状や甲状腺機能亢進症を呈さない限り、治療の必要はほとんどない。外来診療でのポイントは治療を要する甲状腺癌を見落とさないことである。これには超音波検査と穿刺吸引超音波検査が極めて有用である。甲状腺癌の約90%を占める乳頭癌はほぼ診断可能であるが、濾胞癌を診断することは難しい。 1.超音波検査 超音波検査は非侵襲で、外来で容易に施行できる。超音波機器の進歩で空間分解能も高くなり、Bモード以外カラードプラやエラストグラフィなどのモダリティもあり、甲状腺腫瘍の診断に極めて有用である。 超音波検査の観察ポイントは甲状腺を含めた頸部領域を9区分して観察し、甲状腺病変の見落としを防ぐことが重要である(図1) 1)。見落としやすいポイントとして甲状腺上極と下極、錐体葉と甲状腺峡部、甲状腺の背面、気管の近傍、腫瘍の近傍である(図2) 1)。日本超音波医学会の甲状腺結節(腫瘤)超音波診断基準を表1に示す 2)。良性腫瘍と悪性腫瘍の鑑別に有用性が高い、①形状、②境界の明瞭性・性状、③内部エコー(エコーレベル・均質性)を中心に観察する。また、④微細高エコーの有無、⑤境界部低エコー帯も観察する。 乳頭癌の典型例では形状不整、境界部不明瞭で粗雑、内部エコーは低で不均質、微細高エコーが多発し、境界部低エコー帯は不整ないしは欠如している(図3)。 図1 甲状腺超音波検査のスクリーニング甲状腺を含め、頸部を9領域に分けて観察する
2023年08月23日