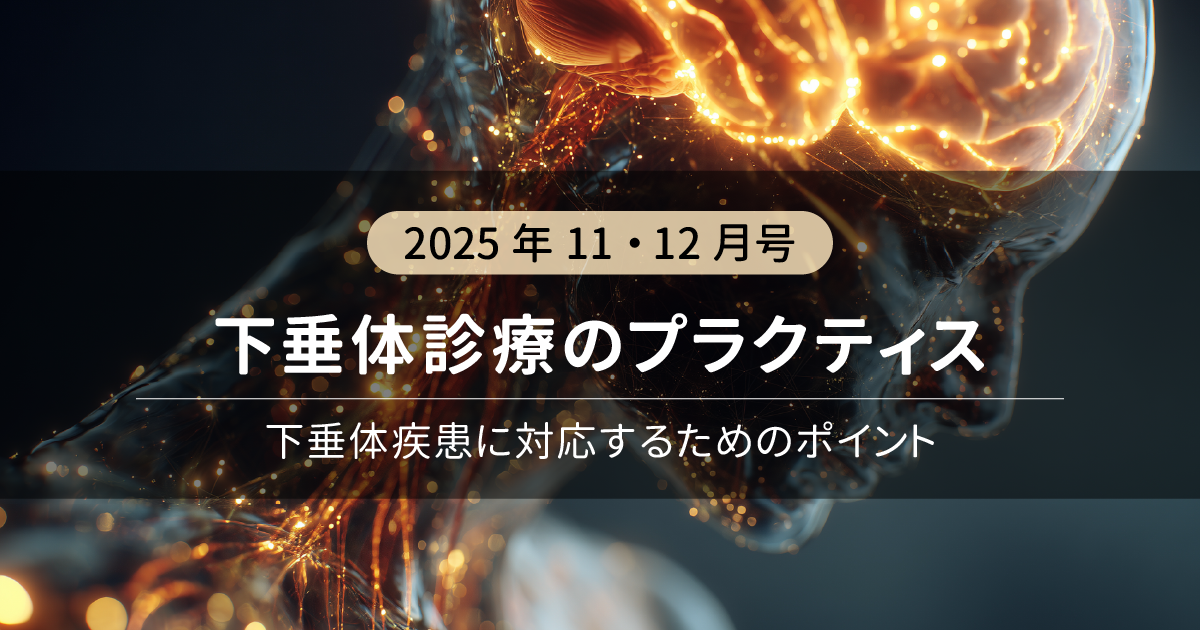- トップページ
- 新着論文一覧
新着論文一覧
-
特集
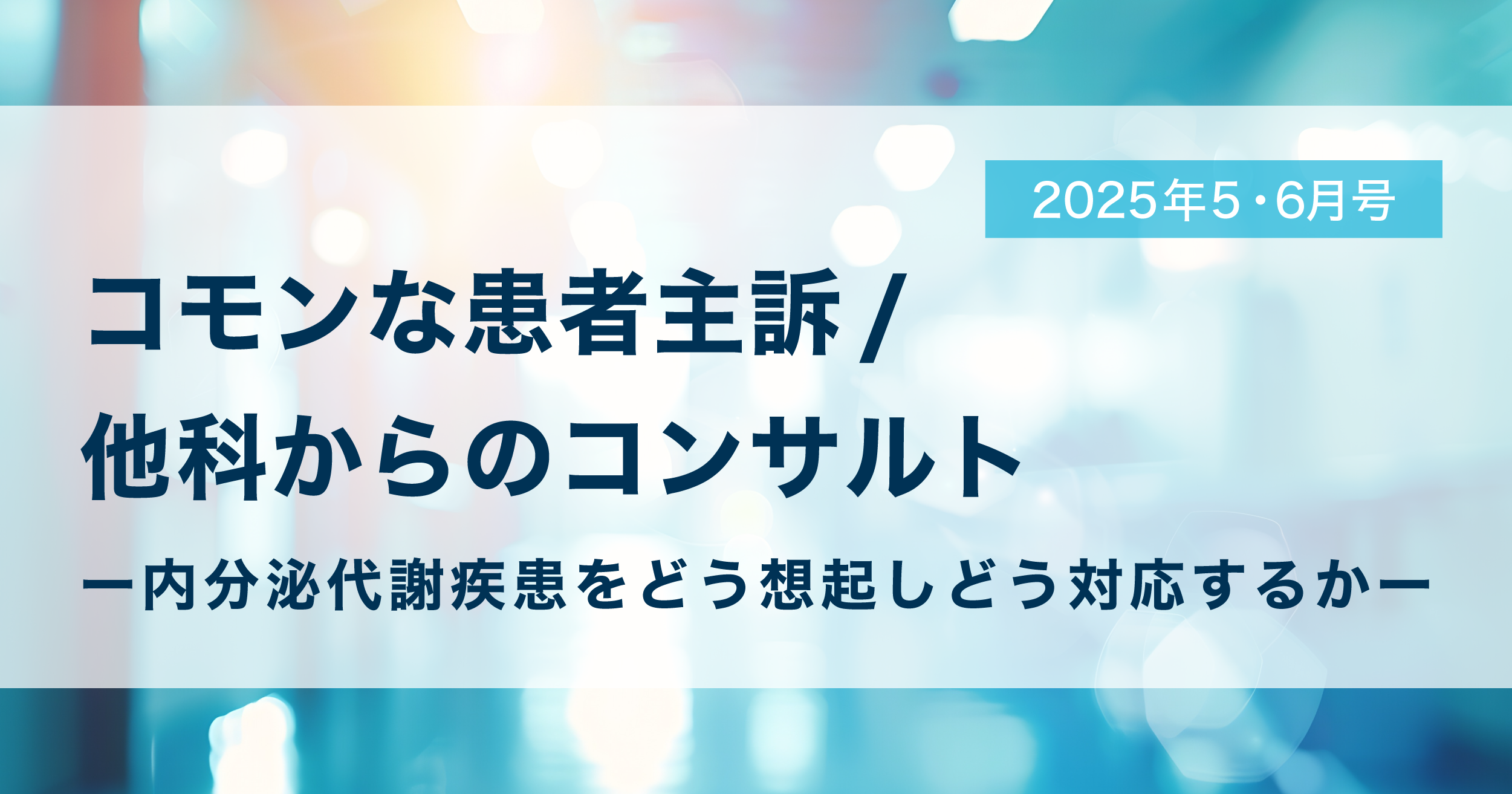
3.こむら返り・筋肉痛・筋力低下
はじめに こむら返り(筋肉のけいれん)、筋肉痛、筋力低下といった運動器症状は、日常診療において頻繁にみられる主訴であり、多くは神経内科や整形外科、総合内科を初診する。しかし、その背後に内分泌代謝異常が潜在することは少なくなく、糖尿病・内分泌代謝内科医の的確な病態把握と診断介入が求められる場面は多い。 特に、低カルシウム血症、低マグネシウム血症、低リン血症、低カリウム血症といった電解質異常は、症候の多様性ゆえに鑑別が難しいこともあり、見逃されやすい。本稿では、これらの疾患に共通する症候の発現機序と、それぞれの病態に応じた診断・治療のポイントについて、他科からのコンサルト対応を念頭に置きながら解説する。 1.症状から内分泌代謝疾患へのアプローチ こむら返り、筋肉痛、筋力低下といった症状は、初期診療では整形外科あるいは神経疾患として評価されることが多い。また、救急外来や総合内科においては、症状の性質が非特異的であるため、病歴聴取と身体所見のみで診断に至ることは困難である。これらの主訴から内分泌代謝疾患を見逃さないためには、症状と内分泌異常との関連を想起した問診、ならびに電解質やホルモンを含む初期検査が重要となる 1~7)。 糖尿病・内分泌代謝内科医が他科からのコンサルトを受けた時点では、すでに神経学的検査や整形外科的検査が行われていることも多く、スクリーニング検査で評価されていない項目を補完する役割が期待される。非特異的な運動器症状の中に内分泌的異常が潜んでいることを想定しておくことが診断遅延を防ぎ、予後を改善する第一歩となる。優先的に鑑別すべきは代謝性ミオパチーや急性電解質異常であり、特に低カリウム血症や低リン血症は早期に補正すべき救急疾患である。一方、慢性的に進行する筋力低下や筋肉痛では、甲状腺機能低下症、糖尿病性神経障害、ビタミンD欠乏症などが背景にある可能性を鑑別すべきである(表1, 2)。
2025年05月26日 -
連載

第2回 UKPDS91
今回の論文 Adler AI, Coleman RL, et al. : Post-trial monitoring of a randomised controlled trial of intensive glycaemic control in type 2 diabetes extended from 10 years to 24 years (UKPDS 91). Lancet. 2024; 404(10448): 145-155. [PubMed] はじめに 2型糖尿病治療のエビデンスはUKPDS(United Kingdom Prospective Diabetes Study)を抜きにしては語れません。1977年から英国で開始されたUKPDSは、2型糖尿病治療における血糖管理の重要性を初めて明らかにしました。新たに診断された2型糖尿病患者を対象としたランダム化比較試験(RCT)であるUKPDS33 1)とUKPDS34 2)の2つの論文は、読者の方々にも是非一読していただきたいと思います。 UKPDS33では、10年間にわたり従来療法群(食事療法)とスルホニル尿素(SU)薬またはインスリン投与による厳格な血糖管理を目指した強化療法群とが比較されました。その結果、強化療法群では網膜症をはじめとした細小血管障害は有意に減少しましたが、心筋梗塞および総死亡の有意な減少は認められませんでした。一方で、過体重患者(標準体重の120%以上)を対象としたUKPDS34では、従来療法群とSU薬/インスリン投与による強化療法群に加えて、メトホルミン投与による強化療法群とが比較されました。その結果、メトホルミン投与群において細小血管障害の有意な減少は認めませんでしたが、心筋梗塞および総死亡の有意な減少を認めました。 1977~1997年の20年間の介入試験の結果はUKPDS33および34として報告されましたが、試験終了時に生存していた患者は全て10年間のpost-trial monitoring studyに移行しました。その解析結果が2008年にUKPDS80 3)として報告されました。介入試験終了1年後には従来療法群および強化療法群のHbA1cはほぼ同一になりましたが、メトホルミン群における心筋梗塞および総死亡抑制効果はそのまま持続していました。さらにSU薬/インスリン投与群でも、心筋梗塞および総死亡の有意な減少が認められました。これが今ではよく知られている遺産効果(legacy effect)になります。そしてpost-trial monitoring study終了時に生存していた全ての患者がさらなる延長試験に移行し、UKPDS80報告14年後のフォローアップの解析結果が本論文として報告されました。
2025年05月23日 -
セミナー

持続血糖測定(CGM)システムの最新エビデンス
ポイント 持続血糖測定(CGM)を使用することで、24時間の血糖推移を可視化することができるようになった。 CGM指標としてTIR(time in range)、TAR(time above range)、TBR(time below range) という概念が広まり、HbA1cだけでなくこれらCGM指標の目標値が定められている。 CGMには大別して、プロフェッショナルCGM、間歇スキャン式CGM、リアルタイムCGMと3つの種類がある。 スマートウォッチ型CGMは米国食品医薬品局(FDA)や独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)に承認された製品はなく、用いるべきではない。 1.総論 1)CGMとは 糖尿病診療において、日々の血糖推移を把握することは、低血糖の予防、患者本人の治療意識の向上などの点から非常に有用である。血糖マネジメントの指標として、長年HbA1cが用いられてきたが、長期にわたる血糖管理状況を反映する指標であるため、日々の血糖値の変動を必ずしも反映しない。また、日々の血糖管理状況の把握のため血糖自己測定(SMBG)が広く用いられてきたが、いわゆる“点”の評価となるため、得られる情報は限られたものとなる。CGMの登場により、“線”での血糖推移の把握が可能になったことで、見逃されていた低血糖など多くの情報が得られるようになり、糖尿病診療は大きく飛躍したといえる。米国糖尿病学会(ADA)の『Standards of care in Diabetes-2025』においても「Diabetes devices should be offered to people with diabetes.(糖尿病デバイスは糖尿病を持つ人に勧めるべきである。)」 1)とデバイスの使用が推奨されており、糖尿病診療に携わるものとして、CGMの仕組みや機能について把握しておく必要がある。 CGMは皮下組織に留置したセンサーを用いて間質液中のグルコース濃度を連続して測定している。従って、血糖推移のトレンドを把握することが可能となるが、血糖を直接測定しているものではないことには留意が必要である。そのため、急激な血糖変動がある場合などは、CGMの測定値であるセンサグルコース値とSMBGでの測定値が乖離することがあり、必要に応じてSMBGで血糖値を確認する必要があることをあらかじめ伝えておくことも重要である。
2025年05月20日 -
セミナー

臨床における薬物動態
はじめに 臨床現場で用いられる薬物について“どのような薬(what)を” “どのように(how)”使うかと考えながら診療に従事するが、薬物動態(pharmacokinetics)を理解することで、年齢や合併症などで患者に薬物療法を最適化させる際に役立つと考えられる。本稿では臨床現場に役立つ薬物動態のポイントを解説する。 1.薬物の体内動態 投与された薬物が薬効を示し、体内から消失するまでの間に吸収(absorption)、分布(distribution)、代謝(metabolism)、排泄(excretion)の過程を経る。経口投与された薬物の場合、消化管から吸収され、血流に乗り、静脈内投与ではそのまま血流に乗って全身へ運ばれ作用点に到達し薬物はその効果を発揮するが、同時に代謝を受けており、最終的に尿中や胆汁中へ排泄されることとなる。 2.吸収 吸収とは、薬物が投与部位から主に循環血液へ取り込まれることをいう。経口投与の場合、多くの薬物は胃内で崩壊し、放出された薬物が消化管液に溶解されて主に小腸から吸収されるが、一部は胃、大腸などで吸収されるものもある。投与経路が異なれば鼻粘膜(点鼻薬)、口腔粘膜(舌下錠、バッカル錠)、直腸(坐薬)、皮膚(貼付薬)、皮下や筋肉(皮下注、筋注)から吸収される(図1) 1, 2)。 静脈内投与の場合、薬物は直接血管内に投与されるため投与した薬物は全量が循環血液へ移行する。しかし、先ほど示したその他の投与経路では、静脈注射と比較して循環血液へ移行する薬物の割合は低くなる。経口投与の場合、主に小腸で吸収され毛細血管に移行した薬物は、全身循環血に移行する前に消化管上皮細胞や肝臓で代謝(初回通過効果)を受ける。これにより、全身循環血へ移行する薬物の量は、消化管に投与される量よりも少なくなる。薬物の投与量に対する全身循環血へ移行した薬物量の割合を生物学的利用率(バイオアベイラビリティ)というが、インドメタシンのように98%と高いものもあれば、骨粗鬆症治療薬のアレンドロン酸のように2~3%と低いものと大きな差がある。
2025年05月16日 -
特集
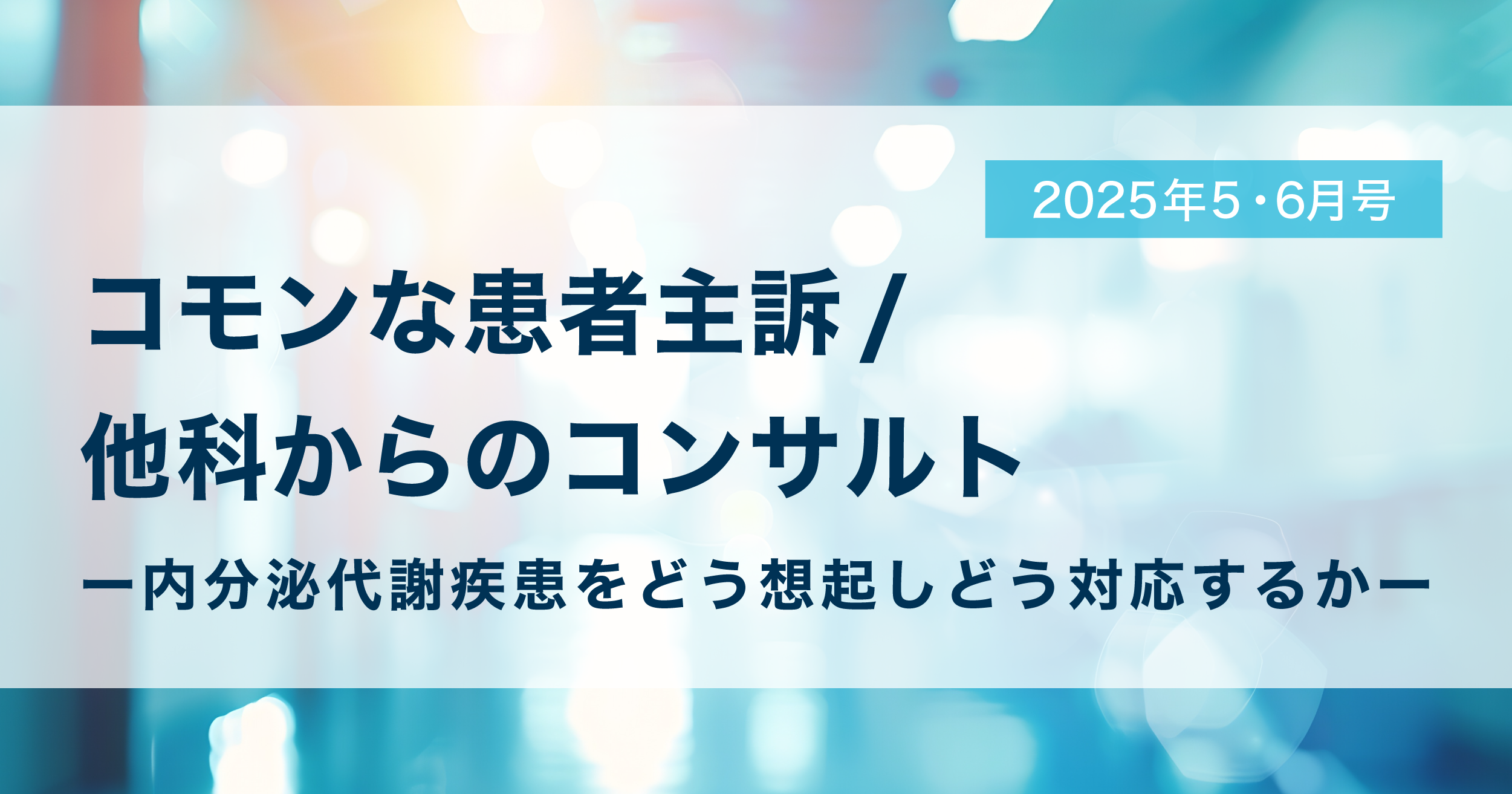
2.動悸・息切れ
はじめに 動悸や息切れは、日常診療で頻繁に遭遇する症状であり、心血管疾患や呼吸器疾患、貧血、神経・筋疾患、精神疾患など多岐にわたる原因が考えられる。しかし、これらの症状は内分泌代謝疾患によっても引き起こされることがあり、適切な鑑別診断が重要である。本稿では、動悸・息切れの鑑別診断について概説し、内分泌代謝疾患による動悸・息切れの原因(表1, 2)として代表的な甲状腺中毒症(甲状腺機能亢進症)と褐色細胞腫、パラガングリオーマを中心に、その随伴症状や診断のポイント、病態、診断、そして治療について解説する。 表1 動悸を呈する内分泌代謝疾患とその原因 表2 息切れを呈する内分泌代謝疾患とその原因 1.動悸の定義と種類 動悸は「心拍を自覚する症候」と定義される。患者の「動悸がする」や「胸がドキドキする」の訴えには、身体活動に相応する心拍数を超えている状態、すなわち「頻脈」である場合と、生理的には正常の心拍数もしくは若干の徐脈であっても「脈を強く感じる」場合があり、その際は脈1回あたりの心拍出量の増加が考えられる。これらの違いは鑑別診断につながるため、「動悸」の性状を詳しく聞き出すことは極めて重要である。さらに心電図上、不整脈による動悸と不整脈によらない非不整脈性の動悸に分類される(図1)。
2025年05月13日 -
特集
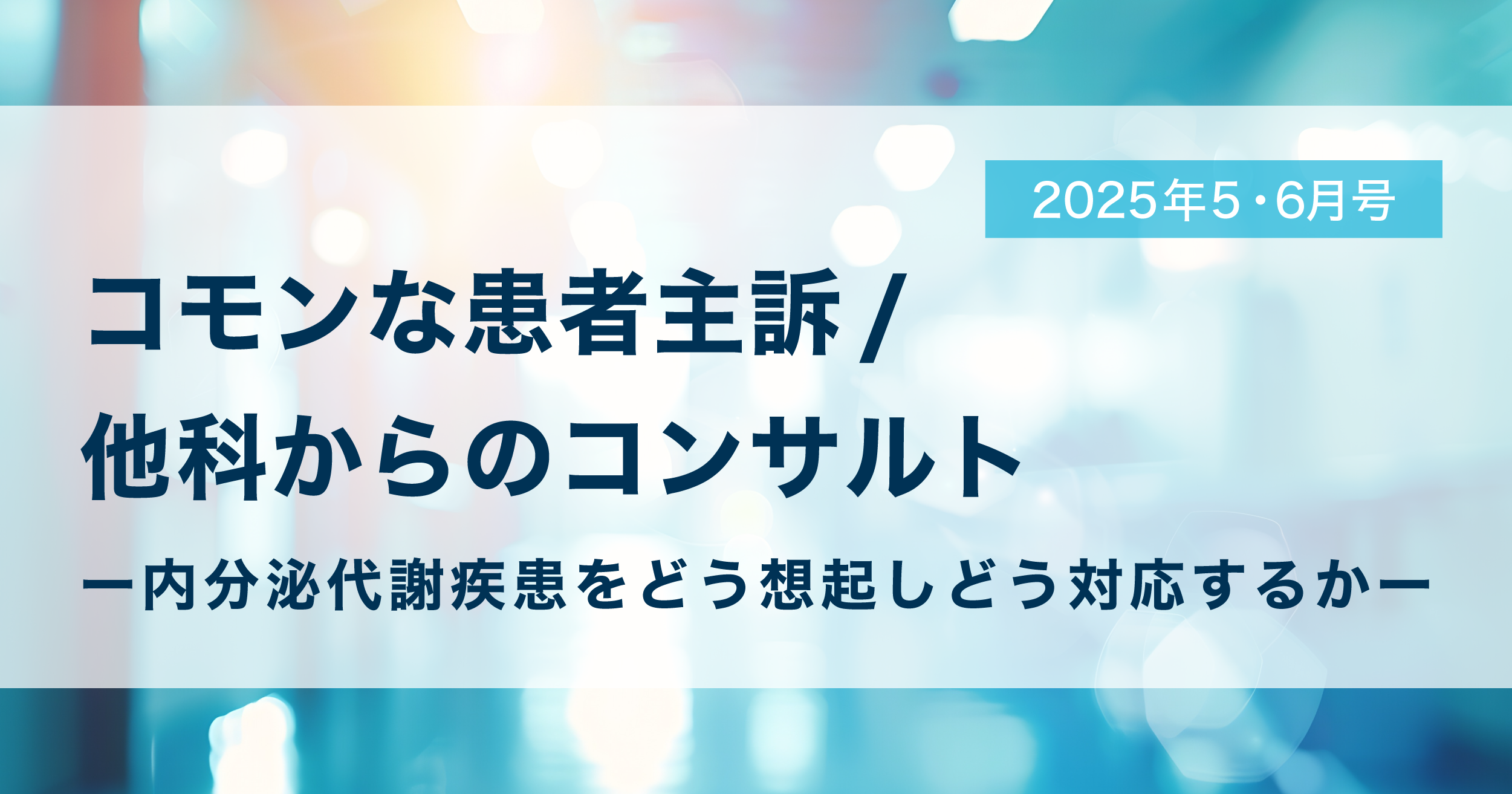
1.全身倦怠感・易疲労感
はじめに 日常診療において、倦怠感を訴える患者に遭遇することは少なくない。特にコロナ禍の特異的な状況を経て、倦怠感を訴えるケースは増加したと感じる。倦怠感を惹起し得る疾患は多岐にわたる。倦怠感の病因を内分泌疾患に見出すためには、患者の意味する倦怠感を紐解く問診を工夫すること、得られた病歴・理学所見からさまざまな内分泌疾患を鑑別するための随伴症状・身体所見を知り、一般検査での検査値異常にも留意しておく必要がある。 1.倦怠感の背景にある多様な病態 倦怠感は周囲から捉えにくい自覚症状であり、いわゆる不定愁訴として過小評価されやすい。そのため、倦怠感以外の随伴症状を探りながら、倦怠感の程度とその変化に着目して診察する。図1に示すように、倦怠感をきたし得る病態には、内分泌疾患を含めて30種以上の病態・疾患が含まれる。内科疾患では、種々の慢性感染症や悪性腫瘍、膠原病などの自己免疫性疾患、線維筋痛症などの慢性疼痛、各種の神経疾患や睡眠障害が挙げられる 1)。 この倦怠感をきたす病態の鑑別において、特に困難な部分は、身体的Physicalな疲労と、精神的Mentalな疲労の両者が混在しやすい点である。倦怠感を鑑別する場合は、内科・総合診療的視点が基軸となって対応するが、精神科・心療内科的視点も鑑別診断において必要となる。重要なファーストステップは、患者に寄り添う姿勢である。次に大事なことは、倦怠感に伴う随伴症候をキャッチすること、そして症状の変化を定期的診察においてフォローアップすることである 2)。
2025年05月09日 -
特集
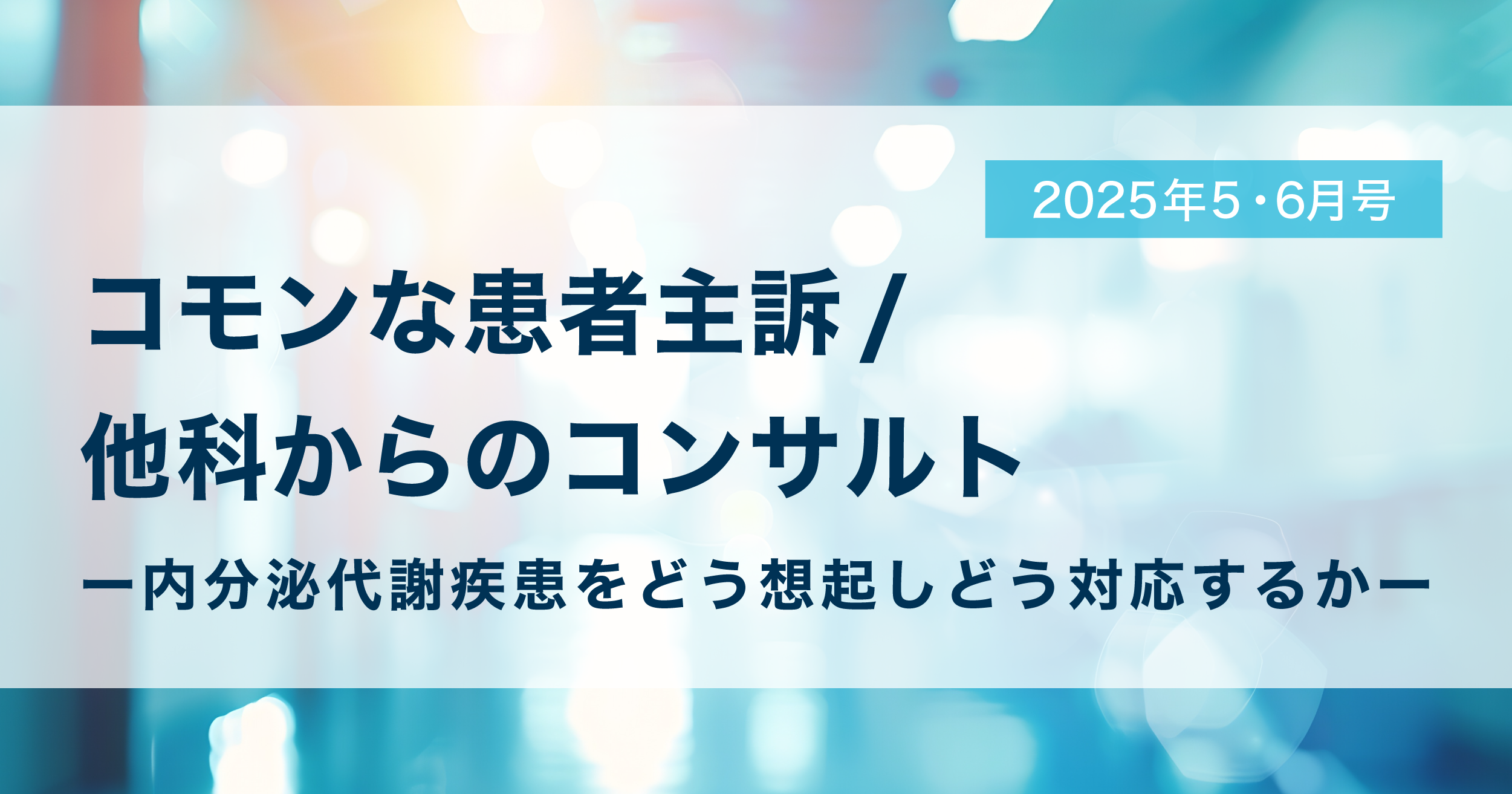
(扉)特集にあたって
内分泌代謝・糖尿病内科専門医の存在は、医療機関の診療の質の向上に大きく貢献する。周術期の血糖管理はいうまでもなく、何らかの内分泌代謝領域の問題を抱えている患者はまれではない。これらの患者の病態を見逃してしまうか、それとも正しく診断して適切な治療を提供するかによって、治療効果や患者の満足度は大きく変わってくる。ひいてはその医療施設の評価にも大きな影響をもたらすであろう。日常的に出くわすありふれた症状や検査値異常に内分泌代謝疾患が潜む可能性は必ずしも低くなく、それを相談する受け皿があることにより、診療の質全体の向上にも寄与し得ることが期待される。内分泌代謝科を志す医師には、自らの適切な評価と判断が、医療の質を左右していることを肝に銘じていただけるよう、切に願っている。 一方で、内分泌代謝領域の専門医を目指さない医師にとっても、日々遭遇する訴えに多くの内分泌代謝疾患が潜んでいることを理解しておくことは、自らの診療の質の向上に大きく貢献するであろう。臓器別診療科による診療が一般的となり、各領域の専門医は自らの定めた範囲から外れる症状や主訴に無関心となる傾向があることは必ずしも否めない。特に高齢患者の抱える医療的なプロブレムは単純ではなく、そこには多様な病態がオーバーラップしていることがある。全身倦怠感・易疲労感は極めてコモンな愁訴であるが、問診によってその具体的な問題のありかを整理することで、潜在する内分泌代謝疾患の可能性が見えてくることがある。あまりにもありふれた訴えであるがゆえに、つい聞き流してしまったり、自らの専門領域の視点からの評価に止まったりしていることはまれでないと想像される。 本特集は、以上のような背景から、本誌が対象とする内分泌代謝領域の専門医および専門医を目指す医師にとってはいうまでもなく、それ以外の領域の医師にも有意義な情報を提供するものとして企画された。この特集を目にする全ての人々にとって、明日からの診療に役立つものであることを編者一同確信している。 著者のCOI (conflicts of interest)開示:竹内靖博;講演料(協和キリン、アレクシオンファーマ) 本論文のPDFをダウンロードいただけます
2025年05月09日 -
連載

第77回 糖尿病と救急医療2025
はじめに 高血糖の急性合併症には、糖尿病ケトアシドーシスや高浸透圧高血糖症候群などがあり、このような合併症の場合は救命救急の治療が必要となる 1)。そして診療報酬医科点数表においては、「重症糖尿病」が算定対象になる救命救急入院料、特定集中治療室管理料、ハイケアユニット入院医療管理料、小児特定集中治療室管理料、新生児特定集中治療室管理料、新生児治療回復室入院医療管理料、救急医療管理加算、また「治療中の糖尿病患者」が算定対象になるハイリスク妊娠管理加算、ハイリスク分娩等管理加算、および「難治性低血糖症」や「糖尿病性昏睡などにおける救急的治療」などが対象となる人工膵臓検査・療法と皮下連続式グルコース測定について、算定要件や施設基準が示されている。よって今回は、これら特定入院料、入院基本料加算、検査および処置について医科点数表告示・通知(以下、告示、通知)より概説する。 1.A300 救命救急入院料について 2~5)(表1) 救命救急入院料の算定対象となる患者は、表1の通知(1)「ア」~「コ」に掲げる状態であり、「カ」に「重篤な代謝障害(肝不全、腎不全、重症糖尿病等)」が含まれる。そして救命救急入院料は、「基本診療料の施設基準等の一部を改正する告示 4)」(以下、施設基準告示)および「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) 5)」(以下、施設基準通知)により、以下の評価基準で「救命救急入院料1」〜「救命救急入院料4」に分けられる。 専任の医師・看護師数、専用施設、装置および器具など 「ハイケアユニット用の重症度、医療・看護必要度に係る評価票(施設基準通知の別紙18)」の基準を満たす患者割合 広範囲熱傷特定集中治療を行う十分な体制 そして、重篤な患者に対し救命救急医療が行われた場合に、以下を限度として、それぞれ所定点数を算定する。 当該基準に係る区分および患者の状態(通知)について別に施設基準の告示・通知に定める区分(救命救急入院料3・4に限る)では14日 別に定める状態の患者(施設基準通知)(救命救急入院料3・4に限る)では60日 別に定める施設基準の告示・通知に適合し届け出た保険医療機関に入院している急性血液浄化(腹膜透析を除く)または体外式心肺補助(ECMO)を必要とする患者は25日 臓器移植の患者では30日 自殺企図などによる重篤な精神疾患を有する患者またはその家族からの情報に基づいて、精神保健指定医または精神科の医師が精神疾患にかかわる診断治療を行った場合は、精神疾患診断治療初回加算として、精神保健指定医などによる最初の診療時に限り、届け出た保険医療機関において行った場合7,000点、それ以外は3,000点をそれぞれ所定点数に加算する。 別に定める施設基準告示・通知に適合し届け出た保険医療機関において救命救急医療が行われた場合は、「救命救急センターの新しい充実段階評価について」に基づく評価により、以下を1日につき所定点数に加算する。 充実段階Sは「救急体制充実加算1」1,500点 充実段階Aは「救急体制充実加算2」1,000点 充実段階Bは「救急体制充実加算3」500点 「救急医療対策事業実施要綱」に規定する高度救命救急センターで救命救急医療が行われた場合には、1日につき100点を所定点数に加算する。 急性薬毒物中毒の患者に対して救命救急医療が行われた場合には、入院初日に限り、「イ 急性薬毒物中毒加算1(機器分析)5,000点」、「ロ 急性薬毒物中毒加算2(その他のもの)350点」をそれぞれ所定点数に加算する。 15歳未満の重篤な患者に対して救命救急医療が行われた場合には、小児加算として、入院初日に限り5,000点を所定点数に加算する。 入室後早期から離床などに必要な治療を行った場合に、早期離床・リハビリテーション加算として、入室日から14日を限度として500点を所定点数に加算する。 入室後早期から必要な栄養管理を行った場合に、早期栄養介入管理加算として、入室日から7日を限度として250点、入室後早期から経腸栄養を開始した場合は、開始日以降は400点を所定点数に加算する。 精神疾患診断治療初回加算を算定する診断・治療を、「注2」の「イ 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行った場合」で、当該患者に対し、生活上の課題または精神疾患の治療継続上の課題を確認し、助言・指導を行った場合は、退院時に1回に限り、2,500点を更に所定点数に加算する。 重症患者の対応に係る施設基準の告示・通知に適合し届け出た病室の入院患者(救命救急入院料2・4に限る)については、重症患者対応体制強化加算として入院期間に応じ、「イ 3日以内の期間750点」、「ロ 4日以上7日以内の期間500点」、「ハ 8日以上14日以内の期間300点」をそれぞれ所定点数に加算する。
2025年04月30日 -
連載

私が糖尿病を始めたころ
はじめに 私が大学を卒業したのは1985年。今からちょうど40年前です。読者の多くの方は想像が難しいでしょうが、当時はヒトのインスリンが出たばかりで、まだブタやウシのインスリンが出回っており、SMBGも始まったばかりでした。1年先輩の野田光彦先生は「糖尿病は国民病、これからは糖尿病が重要な疾患になる」という言葉を繰り返し話されていました。1970年代から1980年代は、今に繋がる糖尿病学の基礎や臨床の実践の流れが形作られた時期でした。当時のことについて書いてみたいと思います。 1970~1980年代の糖尿病研究の進歩 1980年代以前は、日本では1970年に日本糖尿病学会から糖尿病の診断基準に関する最初の委員会報告が発表されましたが、国際的に統一された糖尿病の分類や診断基準はありませんでした。1979年に米国のNational Diabetes Data Group(NDDG)がそれまでの研究成果をもとに、世界のその後の基準作りのもとになる75g経口糖負荷試験(OGTT)に基づく診断基準や糖尿病の分類を発表しました 1)。1980年にWHO専門委員会はNDDG案に近い基準案を作成し、日本糖尿病学会はこれを参考に1982年に新たな糖尿病の診断基準を発表しました。その後WHOは糖尿病の分類や血糖判定基準に若干の変更を加え、1985年に改訂案を発表しました。1980年代には日本人の糖尿病有病率や発症率について数多くの報告が出ました。1992年に出された日本糖尿病学会疫学データ委員会の報告書によると、地域での成人調査、病院での調査や職場調査、政府刊行物などの公的資料だけでなく、18歳未満の小児糖尿病、原爆被爆者、アメリカに移住した日本人のデータについての報告もありました 2)。久山町研究や舟形町研究といった日本を代表する地域住民を対象としたコホート研究が始まったのもこの時期でした。久山町研究では、1988年の健診の結果、40~79歳の受診者の有病率は男性15.3%、女性10.1%を示し、多くの研究から1980年代後半になると40歳以上では5%以上、60歳以上では8~10%に達し、過去20年間に糖尿病人口が実に3~4倍になっていることが明らかになりました 3)。日本人は欧米人よりもインスリン分泌能の低い人が多く、肥満や運動不足などによりインスリン抵抗性が増大するとインスリン分泌が追いつかず、糖尿病を発病しやすいことも明らかになりました。まさに「国民病」です。
2025年04月24日 -
特集
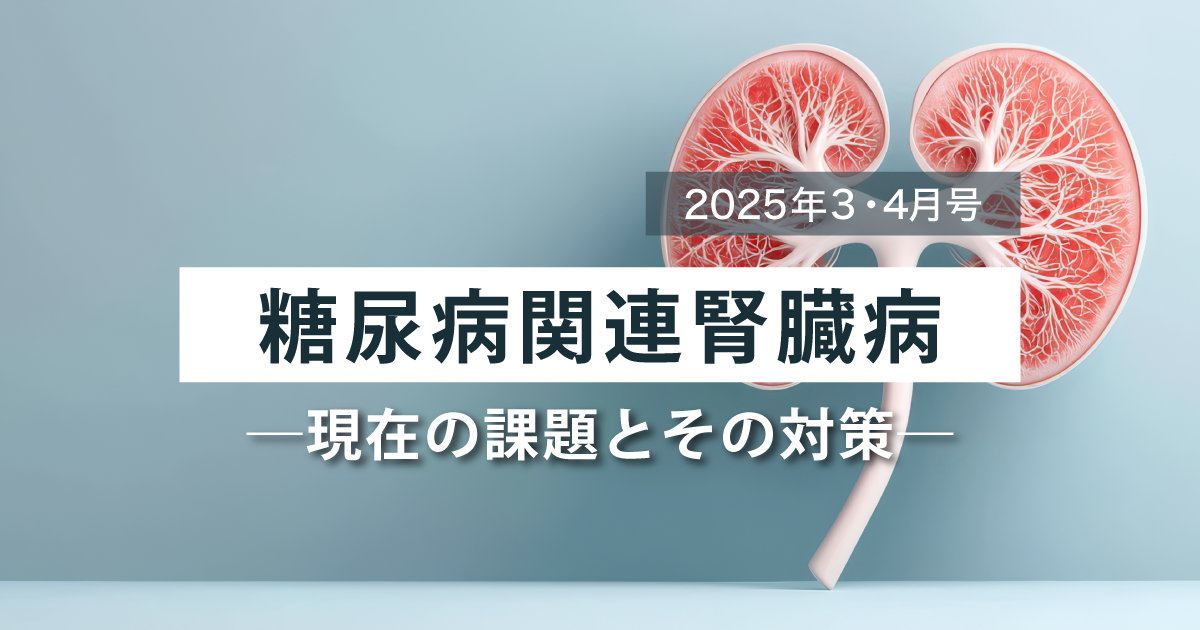
6.岡山県における糖尿病性腎症/糖尿病性腎臓病重症化予防に向けた取り組み ―腎症重症化予防に対する2つの医療ネットワーク―
はじめに 岡山県は県内に医学部のある大学が2つ(岡山大学、川崎医科大学)あり、医師数は320.1人(人口10万人対)と多いとされているが、地域によって偏在がある。県北には中国山地があり、広域にもかかわらず人口も医師も少ない医療圏である。一方、岡山市や倉敷市がある県南は交通の便もよく、人口や医師も多い医療圏であるが、県民の半数が岡山市に、残りのさらに半数が倉敷市に在住しており、人口あたりの専門医数は県北よりも少ない状況にある。県北、県南いずれの地域事情においても、年々増加している糖尿病や慢性腎臓病(CKD)に罹患した全ての県民を専門医だけでカバーすることは物理的に困難である。そこで岡山県では、2012年から第2次地域医療再生計画において、「糖尿病等生活習慣病医療連携推進事業」が開始された(2016年より「糖尿病医療連携推進事業」に改称)。その体制の下で、糖尿病対策専門会議およびCKD・CVD対策専門会議の独立した2つの会議体が設置されている 1)(図1)。この2つの会議体は、それぞれ行政や医師会、看護協会、薬剤師会や栄養士会などさまざまな団体とともに連携し、糖尿病やCKDの医療連携や普及・啓発活動に取り組んできた。今回は、岡山県における糖尿病やCKDに対する医療連携について紹介したい。 図1 岡山県の糖尿病等生活習慣病医療連携体制(岡山県ホームページ(健康推進課): 糖尿病対策について. 糖尿病性腎症重症化予防プログラム(令和7年3月改訂)より) 1.糖尿病ケアを支える総合管理医療機関とおかやま糖尿病サポーター 糖尿病に関しては、2012年に糖尿病等生活習慣病医療連携推進事業において糖尿病対策に取り組んでいる。事業目的として①岡山県の糖尿病医療水準の向上と均てん化、②岡山県の糖尿病医療連携の推進、③県民への普及啓発活動と受療率の向上、の3つを掲げている 2)。医療水準の向上、均てん化および医療連携において鍵となるのが、 “総合管理医療機関”と“おかやま糖尿病サポーター”である。“総合管理医療機関”とは、かかりつけ医療機関として総合管理を行う役割を担っており、認定された医療機関が県内各地にあることは岡山県の特徴の1つと言える。また、“おかやま糖尿病サポーター”は地域糖尿病療養指導士に相当し、糖尿病ケアを支援するメディカルスタッフに対する、岡山県認定の資格である。糖尿病ケアに賛同を得た職種を随時加えており、令和(2019年)以降に加えた職種に、歯科衛生士、公認心理士、臨床心理士、健康運動指導士がある。また、おかやま糖尿病サポーターには保健師も含まれており、医療機関に限らず、保健所や自治体など県内さまざまな機関や部署に糖尿病ケアに関わる人材がいることも特徴である 2, 3)(図2)。
2025年04月21日 -
セミナー

高中性脂肪血症の診断と治療
Q&A編はこちら はじめに 脂質異常症は生活習慣病の代表的な疾患である。日常診療で扱う高中性脂肪(triglyceride:TG)血症は糖尿病や生活習慣に起因する続発性のものが多いが、本稿では高TG血症をみた時の鑑別や必要な検査・治療について考えていきたい。 1.中性脂肪とは 中性脂肪とは、グリセロールに脂肪酸が3個エステル結合したトリアシルグリセロールを指す。そもそも脂質は種々のアポ蛋白とともにリポ蛋白という複合体を形成している。疎水性の強いコレステロールやTGが中心部に存在し、親水性の遊離コレステロールやリン脂質が表面を取り囲むことでリポ蛋白は血液中に存在できる。リポ蛋白は比重により以下に分類される。 カイロミクロン(chylomicron:CM) 超低比重リポ蛋白(very low-density lipoprotein:VLDL) 中間比重リポ蛋白(intermediate-density lipoprotein:IDL) 低比重リポ蛋白(low-density lipoprotein:LDL) 高比重リポ蛋白(high-density lipoprotein:HDL) CMから順に粒子サイズが小さく、比重は大きくなる。またTGの含有量は少なくなる。特にTG含有量が多いのがCMとVLDL、またそれらの代謝産物であるレムナント(CMレムナント、VLDLレムナント)である。血液検査のTGはこれらのリポ蛋白やその代謝産物に含まれるTGの総和を測定しており、高TG血症ではこれらが増加していることを意味している。 TGを含むリポ蛋白の代謝経路には大きく分けて2つある。代謝経路について図1に示す 1)。
2025年04月15日 -
特集
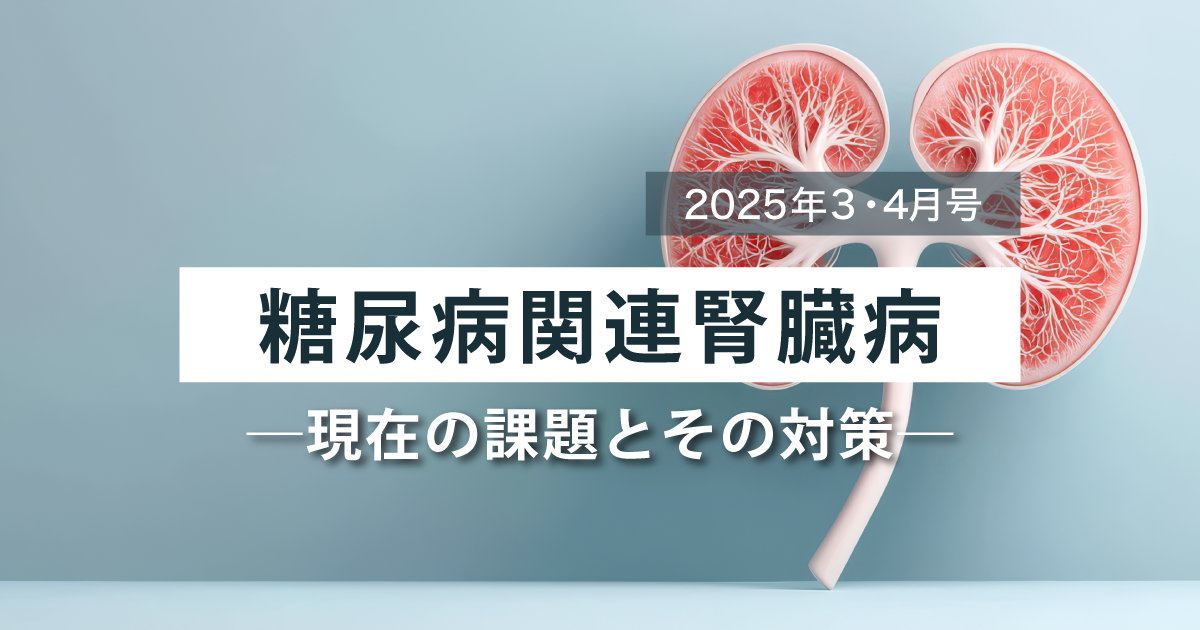
5.糖尿病関連腎臓病に対する多職種連携の実践とその課題
はじめに 慢性腎臓病(chronic kidney disease:CKD)の中でも、糖尿病関連腎臓病(diabetic kidney disease:DKD)は糖尿病の主要な合併症の一つであり、進行すると末期腎不全から透析療法を必要とする。また、DKD患者では心血管疾患のリスクも著しく増加するため、腎臓病の進行抑制だけでなく、全身的なリスク管理が求められる。そのため、早期からの包括的な管理が重要であり、医師を中心とした多職種連携のチーム医療の実践が不可欠となる。具体的には、医師による診断と治療方針の決定、看護師による日常生活支援、管理栄養士による食事療法の支援、薬剤師による薬剤管理、さらに理学療法士による運動支援やソーシャルワーカーによる社会的支援の提供などが挙げられる。実臨床でのDKD患者に対する多職種連携チーム医療は、腎機能低下速度を抑制し、透析導入回避期間を延長するだけでなく、患者満足度や生活の質(QOL)の向上にも役立つことが報告されている 1, 2)。しかし、多職種連携にはいくつかの課題も存在する。すなわち慢性的な人手不足や時間的制約、患者の心理的・社会的背景なども多職種連携の実践例にはハードルとなる。本稿では、多職種連携の具体的な実践例を紹介するとともに、それを阻む課題についてさらに詳しく考察し、今後の改善策も考えてみたい。 1.多職種連携の重要性とそれぞれの役割 DKD患者の治療目標は、腎機能の維持と合併症の予防である。血糖コントロール、血圧管理、脂質管理、食事療法などがその柱とされてきたが、最近では腎臓に保護的に作用する薬剤のエビデンスが次々に報告され、適切な薬剤選択も重要なチーム医療の一翼を担っている。しかしながら、薬剤投与だけでは限界もあり、これら全てを一貫して実施するためには、多職種の専門知識とスキルが求められる。具体的には以下の役割が挙げられる。 1)医師:診断、治療方針の立案、薬物療法の調整 医師は、DKD治療において中心的な役割を担うことは言うまでもない。まず、正確な診断を行い、患者の病態を総合的に評価した上で治療方針を立案する。この際、血糖コントロール、血圧管理、脂質管理などの基本的な管理に加え、近年のエビデンスに基づいた腎保護効果のある薬剤の適切な選択が重要となる。特に、アンジオテンシンⅡ受容体拮抗薬などのレニン・アンジオテンシン系(RAS)阻害薬 3, 4)に加えてSGLT2阻害薬 5~7)やGLP-1受容体作動薬 8, 9)、さらには非ステロイド型ミネラルコルチコイド受容体(MR)拮抗薬 10, 11)においては、腎機能の維持や心血管イベントのリスク低減に有効であることが示されており、これらの薬剤を患者の個別の病態に応じて適切に使用することが求められる。
2025年04月09日 -
セミナー

認知症のある方への糖尿病療養支援
Q&A編はこちら はじめに 近年、人口の高齢化に伴い、高齢の糖尿病患者は増えている。高齢の糖尿病患者は軽度認知障害や認知症が約1.5倍起こりやすくなる 1)。従って、認知症を伴った高齢者の糖尿病患者も増加している。認知症に至っていなくても認知機能障害があると、糖尿病のセルフケアの食事、運動、内服、注射などのアドヒアランスは低下し、セルフケアを肩代わりする介護者の負担は増加する。 本稿では認知症のある糖尿病患者の療養支援について解説する。 1.認知機能障害を疑う まず、目の前の糖尿病患者の認知機能がどの程度か知る必要がある。認知機能の検査をする前に、可能ならば介護者の協力のもとに、認知機能障害を疑う手がかり(行動)があるかどうかをみる。 記憶障害は、約束を忘れたり、外来の受診日を間違えたりするかどうかである。次に手段的日常生活動作(ADL)である買い物、交通機関を使っての外出、金銭管理、服薬などの障害があるかを確認する。手段的ADL低下は記憶障害とともに、認知症の早期発見に重要な所見である。さらに、糖尿病の内服薬が余ったり、インスリン注射の打ち忘れのために血糖が上がったりする場合も注意する必要がある。心理状態の変化も重要で、意欲低下、うつ傾向があり、家に閉じこもっていることも手がかりとなる。また、フレイルやサルコペニアなどの身体機能が障害されている場合も軽度認知障害を合併しやすいので、認知機能をチェックしたほうがいい。
2025年04月04日 -
特集
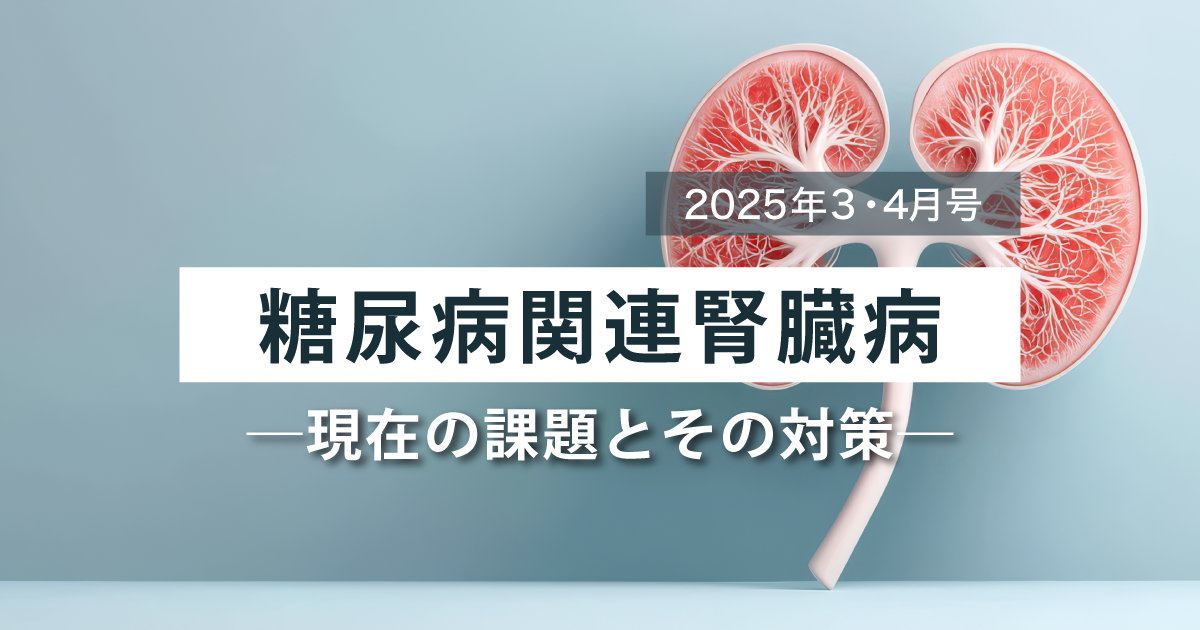
4.糖尿病関連腎臓病の薬物療法の進歩
はじめに 糖尿病関連腎臓病(DKD)はわが国の末期腎不全の主たる原因疾患である。近年、腎保護効果を持つ薬剤の登場により、DKDからの末期腎不全への進展抑制が大きく期待できるようになった。これらの背景から『エビデンスに基づくCKD診療ガイドライン2023』そして『糖尿病診療ガイドライン2024』においても、DKDの薬物療法に関して大幅なアップデートがなされている。共通しているのはSGLT2阻害薬を中心に、非ステロイド型ミネラルコルチコイド受容体(MR)拮抗薬、GLP-1受容体作動薬を併用していくという考え方である。従来から用いられているレニン・アンジオテンシン系(RAS)阻害薬を加えた、これら4つの薬剤がDKD治療の重要な柱になると考えられる。本稿では、これらの薬剤のクリニカルエビデンスとガイドラインでのポジショニング、今後の展望について述べる。 1.SGLT2阻害薬のエビデンス 腎アウトカム試験を完了したSGLT2阻害薬はカナグリフロジン(CREDENCE試験)、ダパグリフロジン(DAPA-CKD試験)、エンパグリフロジン(EMPA-KIDNEY試験)の3つの試験において、2型糖尿病合併あるいは非糖尿病CKD患者に対し、腎保護作用を示している 1~3)。『CKD診療ガイド2024』においてもクリニカルエビデンスのあるSGLT2阻害薬としてこの3剤が挙げられ、積極的な使用が推奨されている 4)。 1)CREDENCE試験(カナグリフロジン) CREDENCE試験(Evaluation of the Effects of Canagliflozin on Renal and Cardiovascular Outcomes in Participants With Diabetic Nephropathy)は、30歳以上の慢性腎臓病(Chronic Kidney Disease:CKD)合併2型糖尿病患者を対象に、カナグリフロジン100mg1日1回投与の効果をプラセボと比較検討した試験である 1)。主要評価項目は末期腎不全(透析、腎移植、またはeGFR 15mL/min/1.73m2未満の持続)、血清クレアチニン値の倍化、腎または心血管死である。計4,401例をカナグリフロジン群またはプラセボ群に1:1の割合で無作為に割り付け、中央値2.62年間にわたって追跡した。ベースラインにおける平均HbA1cは8.3%、eGFRは56.2mL/min/1.73m2であった。主要評価項目のイベントは、プラセボ群に比べてカナグリフロジン群で有意に低く30%低下していた(ハザード比〔HR〕0.70〔95%信頼区間(CI)0.59~0.82〕、p=0.00001)(図1)。
2025年03月31日 -
セミナー

テストステロン補充療法の最新のエビデンス
ポイント 男性性腺機能低下症は原発性(高ゴナドトロピン性)と続発性(低ゴナドトロピン性)がある。 器質的な異常のないLOH症候群が男性更年期障害として徐々に認知されつつある。 男性性腺機能低下症は臨床症状と血中総テストステロン低値から診断されることが多い。 テストステロン補充療法は男性性腺機能低下症に関連した性機能低下などの改善に有効である。 テストステロン補充療法に伴う前立腺癌や心血管疾患のリスク増加に関しては否定的な研究が多い。 日本ではテストステロン製剤は筋注製剤が中心であり、塗布製剤や貼付製剤などより安定した血中濃度が得られる薬剤の承認が求められている。 1.総論:男性性腺機能低下症について 性腺は生殖や性ステロイドに関与する組織であり、男性は精巣、女性は卵巣が該当する。性腺から分泌される性ステロイドは、視床下部や下垂体からのホルモンの調節を受け、ネガティブフィードバック機構が存在する。男性性腺機能低下症は、男性の精巣にある内分泌機能や精子形成能のなどが障害された状態である。精巣そのものが障害された原発性と、精巣より上位が障害された続発性に分類される(表1)。続発性では精巣に作用する黄体形成ホルモン(LH)、卵胞刺激ホルモン(FSH)の分泌が低下した低ゴナドトロピンであり、原発性では精巣からのテストステロンの産生や分泌低下が起き、ネガティブフィードバックが作用しないためにLH、FSHが増加した高ゴナドトロピンである。また、器質的異常のない加齢による血中テストステロンの低下とそれに伴う種々の症候を呈するものはlate-onset hypogonadism(LOH症候群)と呼ばれ、男性更年期障害として徐々に認知されつつある。 表1 男性性腺機能低下症の分類
2025年03月26日 -
特集
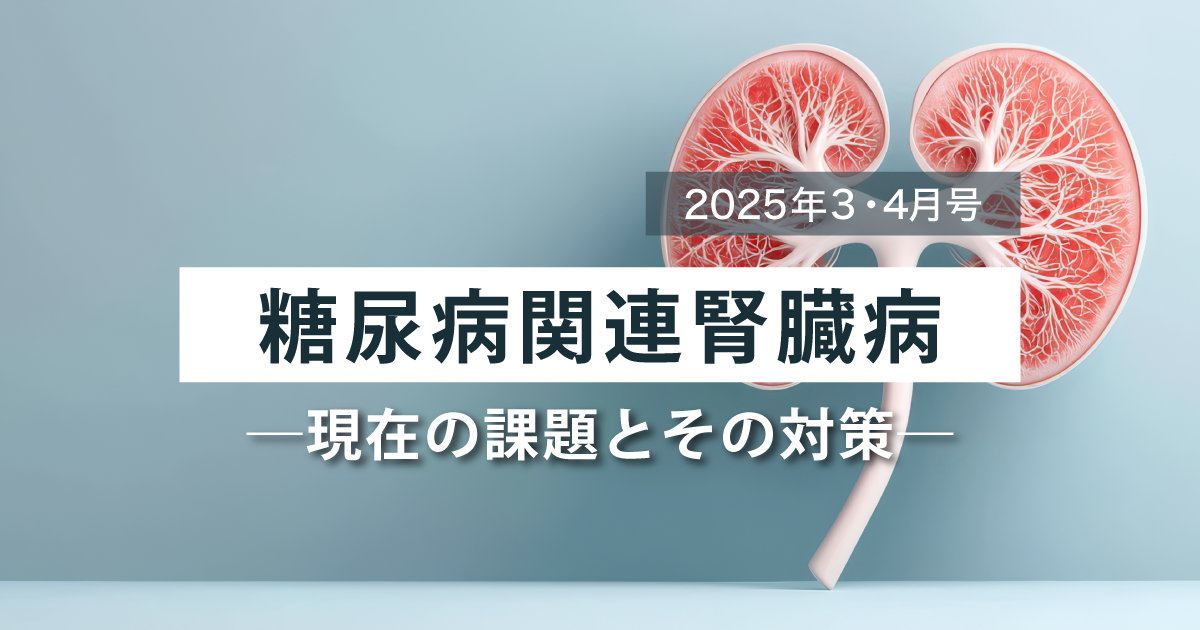
3.糖尿病関連腎臓病における低栄養とその対策
はじめに 糖尿病性腎症は、2011年に透析患者の主要原疾患の第一位となり、現在維持透析患者の約4割を占めるに至っている。さらに近年、典型的な糖尿病性腎症の臨床経過をたどらない症例を含めた糖尿病関連腎臓病(Diabetic Kidney Disease:DKD)という概念が提唱され話題を呼んでいる。糖尿病性腎症においては、腎症進行を抑制する目的でタンパク質の摂取制限が行われてきた。一方で社会の高齢化とともに、DKDを含む慢性腎臓病(Chronic Kidney Disease:CKD)患者におけるサルコペニア・フレイルが注目され、また進展したCKD・DKDでは特徴的な栄養障害であるprotein-energy wasting(PEW)も大きな問題となっている。従って、タンパク質摂取制限が望ましくない症例が増加している可能性がある。そのため、DKDの食事療法としては、腎機能と栄養状態の維持を両立させるためのプローチが求められている。本稿ではDKD進行予防のための食事療法やDKDにおける栄養障害、実際の食事療法の考え方について考える。 1.目標体重の目安 DKDの食事療法の目的は、腎機能低下を抑制するとともに良好な代謝・栄養状態を維持することにより、(生命)予後を改善することにある。従来、1989年代に実施された職域健診において、異常所見が最も少ないBMIが22であるとする研究結果からこれを標準体重としてきた。しかしながら、BMIと死亡率との関係を検討した最近の研究では、アジア人において最も死亡率が低いBMIは、20~25であるとが示されている 1)。2型糖尿病においても、日本人では総死亡率が最も低いBMIは20~25の範囲であり、75歳以上の高齢者ではBMIが25以上でも死亡率の増加は認められていない 2, 3)。また、BMIが非肥満の範囲であっても、脂質異常症や高血圧などメタボリックシンドロームの症候を有する場合には、健康な非肥満者と比較して死亡率が明らかに高くなるが 4)、メタボリックシンドロームのない肥満者では、死亡率の増加が認められないことから 5)、BMIのみでは健康状態を十分に評価できないと言える。つまり、死亡率を考慮する場合、望ましいBMIは20~25の範囲とされ、BMI 22を一様に厳守しなければならない基準とするのは適切ではない。また、目標とする体重は患者の年齢や病態、身体活動量などに応じて個別化して設する必要があるため、日本糖尿病学会のコンセンサスステートメントでは以下のように目標体重の初期設定が提唱されている。 <目標体重(kg)の目安> 65歳未満:[身長(m)]2×22 65歳から74歳:[身長(m)]2×22~25 75歳以上:[身長(m)]2×22~25※ ※75歳以上の後期高齢者では現体重に基づき、フレイル、(基本的)ADL低下、併発症、体組成、身長の短縮、摂食状況や代謝状態の評価を踏まえ、適宜判断する。
2025年03月21日 -
セミナー

薬物の生体内動態 ―代謝と排泄―
はじめに 薬物が生体に投与されると、その多くは小腸から吸収され、門脈を経て、肝臓を通過する。この過程で、薬物の一部は代謝される。その後、薬物は血流によって体内の各組織に分布し、標的分子に作用する。そして、尿中や胆汁中に排泄される。効果を発揮するために必要な作用部位における薬物濃度は、こうした薬物の体内動態により決定される。すなわち、副作用を抑え、十分な薬効を得るためには、薬物の体内動態を把握することが必要不可欠である。この過程は、吸収(absorption)、分布(distribution)、代謝(metabolism)、排泄(excretion)の頭文字をとってADMEと呼ばれる。本稿では、薬物の消失に関わる代謝および排泄について概説し、薬物の効果や薬物相互作用との関係について述べる。 1.薬物の代謝 生体にとって異物である薬物は、体内で排泄されやすい形に変えられる。その過程が代謝であり、主に肝臓に存在する薬物代謝酵素により触媒される。通常、薬物は親水性が増加するように代謝を受ける。親水性の増加により膜透過性が低下し、腎尿細管での再吸収の減少、排泄の増加につながる。薬物の中には、代謝を受けることで活性を示すようになるものもあり、こうした薬物はプロドラッグと呼ばれる。薬物代謝酵素は基質特異性が低いという特徴があり、ひとつの酵素が多くの薬物を代謝する。薬物の薬物代謝酵素に対する親和性や発現量、同じ薬物代謝酵素の基質となる薬物の共存などにより、薬物の代謝は大きく変化する。 肝臓では、血漿タンパク非結合型の脂溶性薬物が肝細胞に取り込まれ、そのうち薬物代謝酵素の基質となる薬物が代謝を受ける。すなわち、肝臓で代謝されるのは門脈血中の薬物の一部であり、肝臓を通過した血液中では、代謝され変化した代謝産物と代謝されなかった未変化体が共存する。活性を持つ薬物が代謝後どの程度残っているか、排泄されやすい親水性に変化した薬物がどの程度存在するかが、薬理効果の発現にとって重要である。薬物代謝は、第Ⅰ相反応である酸化、還元、加水分解と第Ⅱ相反応である抱合とに大別される。 第Ⅰ相反応では、薬物のヒドロキシ化、エポキシ化、脱アルキル、脱アミノなどの酸化や、ニトロ基、アゾ基、オキシドなどの還元、エステル、アミド、ヒドラジドなどの加水分解が起こり、ヒドロキシ基やアミノ基、カルボキシ基などの極性基が生成あるいは導入される。酸化反応の多くは、活性中心にヘム鉄を有するヘムタンパク質シトクロムP450(CYP)により行われる。CYPには多くの分子種が存在し、分子種ごとに代謝する薬物は異なるが、基質特異性は低い。CYPはアミノ酸の相同性に基づいて命名されており、接頭語のCYPに続いて、ファミリーを示すアラビア数字、サブファミリーを示すアルファベット、分子種を示すアラビア数字の組合せで表される。ヒトでの薬物代謝に主に関与しているCYPは、CYP3A4、CYP2D6、CYP2C9、CYP2C19、CYP2E1、CYP1A2の6つである。 第Ⅱ相反応である抱合では、極性基に生体内極性成分が結合して、さらに極性が増す。抱合には、①UDP-グルクロン酸(UDPGA)を補酵素としてUDP-グルクロン酸転移酵素(UGT)により触媒されるグルクロン酸抱合、②活性硫酸(PAPS)を補酵素として硫酸基転移酵素(ST)により触媒される硫酸抱合、③グルタチオンS-転移酵素(GST)によりグルタチオンと結合するグルタチオン抱合などがある。抱合により、極性が増すだけでなく負の電荷を帯びるため、腎近位尿細管において有機アニオントランスポーターにより分泌されて排泄が増加する。
2025年03月18日 -
特集
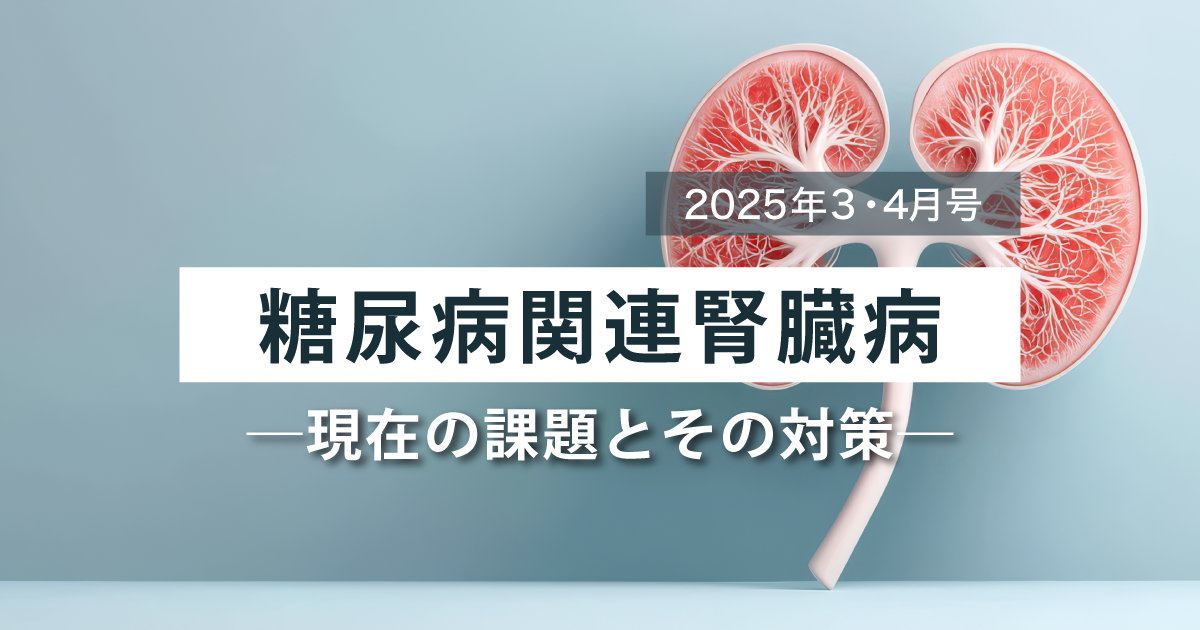
2.糖尿病関連腎臓病の病態多様性
はじめに 糖尿病を持つ方は、臨床的特徴、すなわち、病態、合併症の起こり方、治療反応性などが個々で異なるため、これらすべて考慮しながら、一人ひとりに最適な医療をすすめることが推奨される 1)。これを、糖尿病の個別化医療(personalized or individualized medicine)と呼ぶ 1)。糖尿病を持つ方の個別化医療を考える場合、合併症の病態と(発症と進展の)プロセスを明らかにすることが肝腎である。近年、糖尿病を持つ方の腎障害の多様性に注目が集まっている 2)。本稿では、糖尿病を持つ方の腎障害の多様性を、人工知能を用いた糖尿病分類という視点から考えてみたい。 1.糖尿病関連腎臓病:糖尿病による腎障害の多様性 糖尿病を持つ方が慢性腎臓病(chronic kidney disease:CKD)を合併・併発するパターンは、糖尿病性腎症(diabetic nephropathy:DN)、糖尿病性腎臓病(diabetic kidney disease:DKD)、慢性腎臓病を合併した糖尿病(Diabetes with CKD)の3つに分けられる 3)。典型的なDKDは、アルブミン尿・蛋白尿の出現後に糸球体濾過量(glomerular filtration rate:GFR)が低下することが特徴で、古典的なDKDあるいはDNとされる。近年、アルブミン尿・蛋白尿を伴わずにGFRが低下する非古典的なDKDが増加している。また、DKDの発症と伸展の経過を、古典的DKD(蛋白尿出現後eGFR低下≒DN)、非アルブミン尿性または非蛋白尿性DKD、アルブミン尿退縮、急速低下(rapid decliner)の4つの軌跡(trajectory)で分けることもある 2)。 金﨑らは、「DKD」の日本語訳として「糖尿病性腎臓病」を「糖尿病関連腎臓病」とすることを提唱した 4)(図1)。「糖尿病性」という用語は、全例が「糖尿病状態によって生じる慢性腎臓病である」という誤解を生む懸念があり、「糖病性腎臓病」の使用は、順次中止するとしている。糖尿病関連腎臓病は、糖尿病と関連する病態、併存疾患、治療の影響など、糖尿病状態が病態に影響を及ぼす可能性があるもの全てを含み、糖尿病を持つ方が一生の中で経験する全てのCKDと定義される。糖尿病状態に特有のDNは糖尿病関連腎臓病の中に含まれる。糖尿病に併存するその他のCKDは、糖尿病関連腎臓病と区別するが、糖尿病歴が長期になれば糖尿病状態の影響を受けるため、両者の鑑別はしばしば困難である 4)。
2025年03月13日