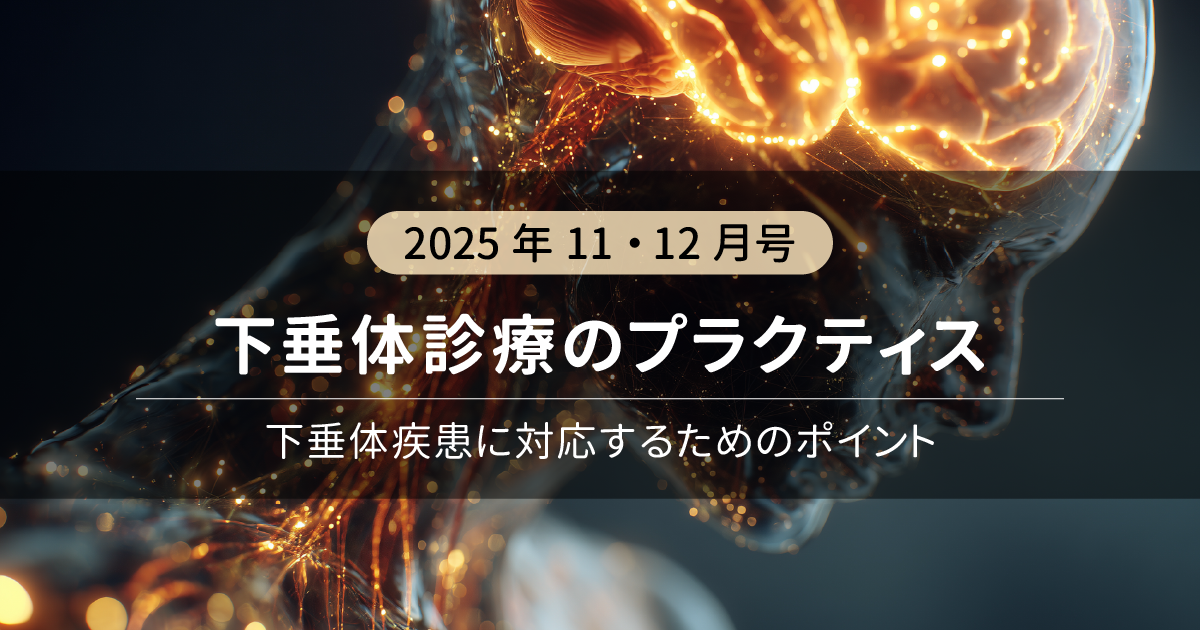- トップページ
- 新着論文一覧
新着論文一覧
-
セミナー

神経内分泌腫瘍の最新エビデンス
ポイント GEP-NENの病理学的分類では、組織学的な分化度と増殖能の面からNET G1, G2, G3, NECに分類する。 膵NENの約6%で、MEN1遺伝子の生殖細胞系列変異が確認される。消化管NENでは、十二指腸原発のガストリノーマの場合はMEN1型を積極的に疑う。 NENの画像診断において、欧米など諸外国での先進的施設ではSPECT/CT検査であるSRSに替わり、68Ga-DOTATOCなどのPET/CT検査が広がってきている。 GEP-NENへのCAPTEM療法、GEP-NECへのEP療法やIP療法、ソマトスタチン受容体陽性のNETへの177Lu-DOTA-TATEを用いたPRRTなど、近年治療法にはさまざまな進歩がみられる。 希少疾患であるGEP-NENにおいて、診療の集約化による質の担保とエビデンス創出、海外で有用とされる検査や医薬品の迅速な国内導入を図る施策が重要となる。 1.総論 神経内分泌腫瘍(Neuroendocrine Neoplasm:NEN)は神経内分泌細胞から発生し、ペプチドホルモンなどを産生・分泌する能力をもつ腫瘍で、比較的頻度の低い疾患ではあるが、消化管や肺・気管支、膵臓など多くの臓器で発症し得る。本稿では、膵・消化管のNENに焦点をあてて論じる。 本邦では、日本神経内分泌腫瘍研究会(Japan Neuroendocrine Tumor Society:JNETS)が2016年に開始された全国がん登録のデータを用いて、胃腸膵におけるNEN(Gastro-Entero-Pancreatic Neuroendocrine Neoplasms:GEP-NEN)の部位別発症率や年齢分布などを調査しており、人口10万人あたりの年間新規発症率は膵NENで0.70人、消化管NENで2.84人であった 1)。消化管の中では直腸が最も多く(1.82人)、胃がその次に多い(0.48人)1)(図1)。初回診断時の年齢の中央値は60~65歳で(図1)、十二指腸、虫垂、直腸のNENはほとんどが局所転移にとどまっていたが、食道、胃、結腸のNENは遠隔転移を示す傾向が強かった 1)。
2025年09月25日 -
特集
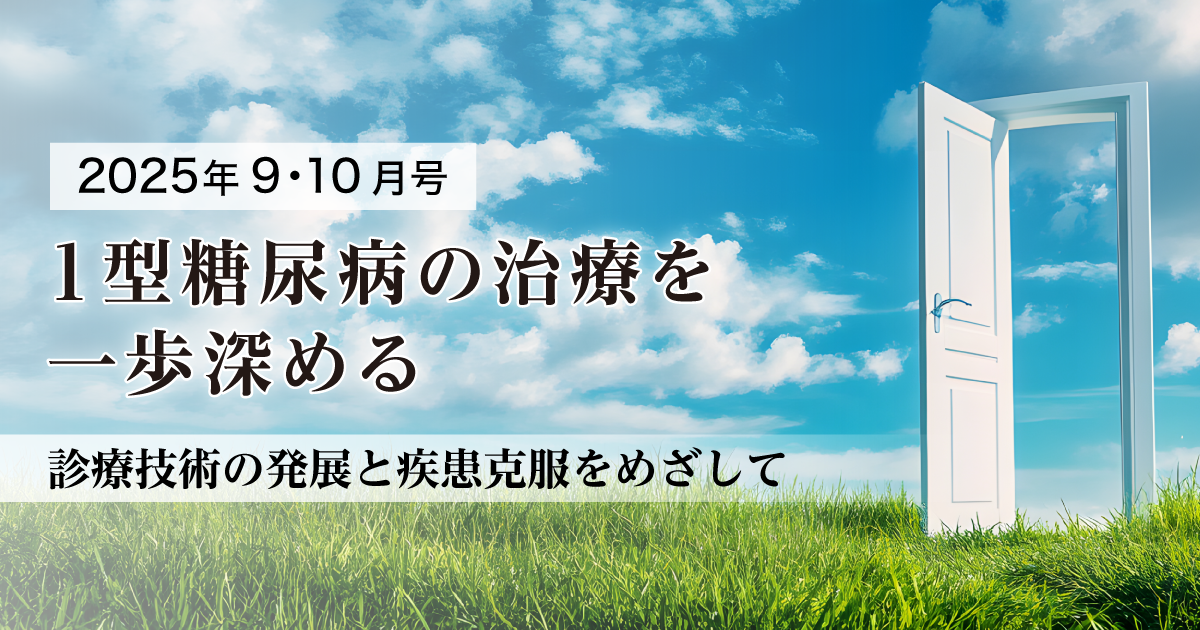
3.インスリンポンプとCGM ―外来でみるべきポイントは―
はじめに 近年、糖尿病治療に関わるテクノロジーの進歩は目覚ましく、中でも特に1型糖尿病の診療でテクノロジーの導入が進んでいるといえるだろう。代表的なものとしては持続血糖測定器(Continuous Glucose Monitoring:CGM)、インスリンポンプが挙げられ、本稿では主に両機器の概要、運用方法について述べていく。 1.CGM(Continuous Glucose Monitoring) 近年テクノロジーの発展により、精度の高いCGMが登場し、臨床での活用が普及している。直近では本邦で2024年にFreeStyleリブレ2(以降リブレ2)、Dexcom G7(以降G7)が上市された。CGMの精度の指標として平均絶対的相対的差異(MARD)があり、10%未満が血糖自己測定の代替となる目安とされている。G7では成人患者でMARDが上腕後部で8.2%、腹部で9.1%、リブレ2は上腕後部のMARDが9.2%であり、血糖自己測定と遜色ないレベルになっている(表1)。一方でCGMは皮下組織のグルコース濃度を測定するため(図1)、血糖値と5~10分のタイムラグが存在する。そのため血糖低下・上昇時には血糖値と乖離が発生しやすく、低血糖・高血糖の際には注意が必要である。 表1 FreeStyleリブレ2とDexcom G7の比較
2025年09月25日 -
セミナー

自律神経系とそれを対象とする薬理活性
はじめに 食事を摂ると唾液分泌や胃腸運動が活発になる。急に起き上がっても血圧はすぐ調節されて正常範囲に保たれる。これらの反応は全て無意識に行われる自律神経系の働きである。そのため、自律神経系は植物神経系あるいは不随意神経系ともいわれる。一方、人前で話す前には緊張して鼓動が高まる。心を落ち着かせると高まる鼓動も抑えられる。このように自律神経系は生体の恒常性の維持に重要な役割を担うだけでなく、意識や感情の影響も受ける。本稿では、自律神経系の基礎的事項を概説し、それを対象とする薬理活性について、特に循環系と泌尿器系を取り上げて説明する。 1.自律神経系の概要 生体にとって最も基本的な機能である循環、呼吸、消化、代謝、分泌、体温維持、排泄、生殖などを自律機能という。自律神経系は平滑筋、心筋、および腺を支配し、各種の自律機能を協調的に調節することにより、生体の恒常性(ホメオスタシス)の維持に重要な役割を担う 1~4)。 自律神経系は、内臓の感覚受容器からの情報を中枢神経系に伝える求心性神経(内臓の情報を伝えるので内臓求心性線維という)と、中枢神経系の指令を内臓器官に伝える遠心性神経よりなる。遠心性神経は交感神経と副交感神経に分けられる。
2025年09月18日 -
連載

第3回 DiRECT
今回の論文 Lean ME, Leslie WS, et al. : Primary care-led weight management for remission of type 2 diabetes (DiRECT): an open-label, cluster-randomised trial. Lancet. 2018; 391(10120): 541-551. [PubMed] はじめに GLP-1受容体作動薬が登場してから、肥満を有する2型糖尿病患者の血糖コントロールにおける体重減少の重要性が再認識されるようになりました。特にGIP/GLP-1受容体のdual agonistであるチルゼパチド投与により、著明な体重減少と同時にHbA1c 5.7%未満、つまりほとんど血糖を正常化することが実現可能であることが明らかにされました。一方で、bariatric surgery(肥満外科手術)の有効性を検討した臨床試験の結果からも、著明な体重減少により2型糖尿病患者の血糖コントロールがほとんど正常化できることが示されています。 GLP-1受容体作動薬とbariatric surgeryとは薬物療法と手術療法との違いがありますが、その血糖コントロール改善のメカニズムは摂取エネルギーの低下、つまりエネルギー制限に起因する体重減少と考えられます。GLP-1受容体作動薬が登場するまでは、外来でどうしても血糖コントロールがうまくいかなかった患者さんでも、入院して摂取エネルギーを制限すると血糖コントロールがみるみるよくなる経験をされた読者の方も多いと思います。 2型糖尿病はインスリン抵抗性とインスリン分泌不全とによるインスリン作用の低下がその病態であると考えられています。インスリン抵抗性とインスリン分泌不全のどちらが先かは、「鶏が先か卵が先か」で現在も議論が続いていますが、結論が出ていません。本試験の主任研究者の一人であるTaylorは、以前から2型糖尿病の病態は過剰なエネルギー摂取による肝内脂肪の蓄積と、その結果として生ずる膵島内中性脂肪の増加であるとする“Twin-Cycle Hypothesis”を提唱してきました 1)。これまで彼が実施したproof-of-concept試験において、発症早期の肥満を有する2型糖尿病患者に低エネルギー食(~800kcal/日)を基礎とした生活習慣介入を実施することで、著明な体重減少により2型糖尿病を“寛解(remission)”することが可能であることが示されてきました。ここで“寛解(remission)”は「血糖降下薬の投与なしでHbA1c 6.5%未満を3カ月以上維持できた状態」と定義しています。そこで、このアプローチの臨床的有用性を検討するために実施されたのが本試験です。生活習慣介入試験であり、新しい薬剤も使用されていないのであまり注目(宣伝?)されなかったようですが、肥満症治療薬としてのGLP-1受容体作動薬のプロモーションが盛んな今、古い試験ですが原点回帰する意味でも今回取り上げました。
2025年09月11日 -
特集
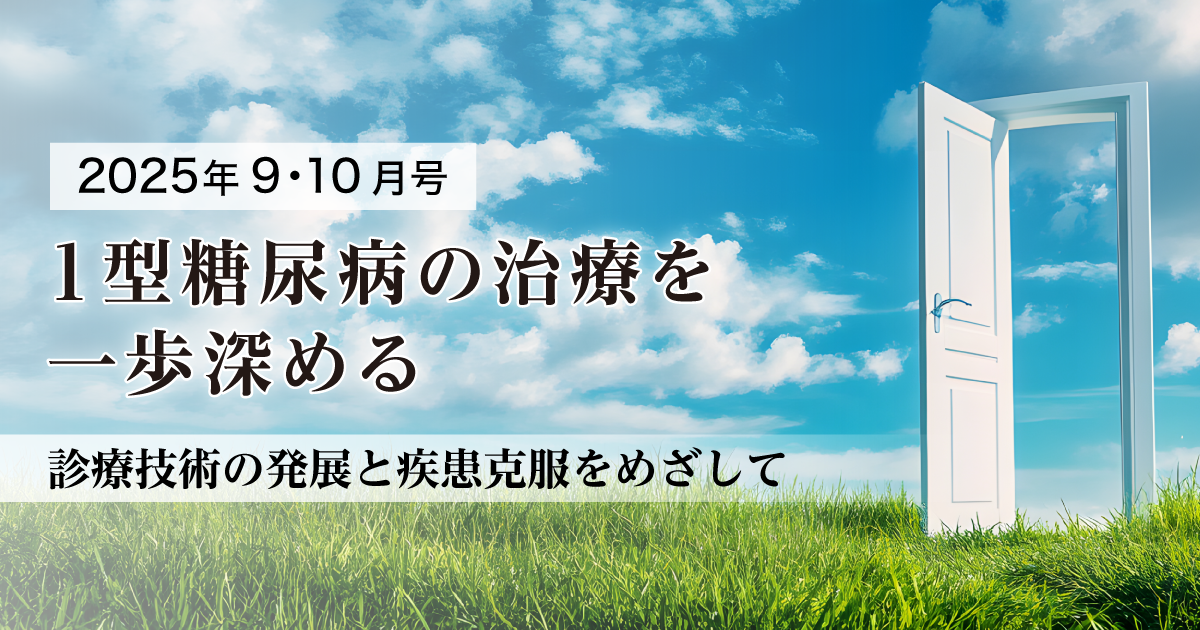
2.1型糖尿病への再生医療 ―現在地と将来展望、移植新章の幕開け―
はじめに 現在、本邦では1型糖尿病に対する再生医療として、保険適用下で膵臓移植、膵島移植が行われている。一方で、2020年代に入り各国で1型糖尿病に対する幹細胞由来細胞移植の臨床試験が開始された。長期成績についても報告が始まっており、移植新章の幕開けを予期させる結果となっている。本邦でも、京都大学とオリヅルセラピューティクス社にてiPS細胞由来膵島細胞シートの第1/1b相の医師主導治験を開始、2025年2月に第1例の移植を施行し、新たな時代を迎えた。また、遺伝子改変による免疫回避システムを利用した免疫抑制剤フリーの膵島移植も臨床応用フェーズに入っており、1型糖尿病における再生医療が目まぐるしく進歩を遂げている。膵臓移植、膵島移植の概説も併せ、糖尿病治療における再生医療の現状と今後の展望について解説を行う。 1.膵臓移植 膵臓移植は1966年の膵腎同時移植の成功を契機に発展し、免疫抑制剤や手術技術の進歩により欧米を中心に普及した。日本では1984年に筑波大学で初の脳死下膵移植が行われ、1997年の臓器移植法施行後より普及が進み、2006年には保険適用となり、現在では全国の認定施設で移植が実施されている。術式は、膵腎同時移植(simultaneous pancreas-kidney transplantation:SPK)、腎移植後膵移植(pancreas after kidney transplantation:PAK)、膵単独移植(pancreas transplantation alone:PTA)の3種類に分類される。SPK、PAKは腎不全を伴う糖尿病患者で腎臓移植の適応があり(または腎移植後)、かつ内因性インスリン分泌が著しく低下している症例、PTAは専門的な治療でも血糖安定性の乏しい1型糖尿病症例が適応となる。SPKは末期腎不全を伴う糖尿病に対し、血糖と腎機能の両面から有効であり最も多く行われる。日本ではIL-2RA(Interleukin-2 receptor antagonist)や抗胸腺グロブリン(anti-thymocyte globulin:ATG)を用いた導入療法、タクロリムス(tacrolimus:TAC)・ミコフェノール酸モフェチル(mycophenolate mofetil:MMF)・ステロイドを併用した維持療法が主流である。米国ではATG単剤導入が多く、ステロイドフリーの維持療法も進んでいる。 2000〜2023年に日本で行われた膵臓移植555例のうち、SPKが86%、PAKが11%、PTAが3%であった。患者生存率は1年で95.9%、5年で92.2%、膵グラフトの生着率は1年で86.4%、5年で76.7%であり、SPKがほかの術式に比べて良好な成績を示している。一方でPAK/PTAでは免疫調整の難しさから拒絶反応の頻度が高く(25.3%)、SPKが2.4%であるのに比べ、生着維持が困難な傾向にある。移植後の悪性腫瘍は32例で、9例(28%)がPTLD(移植後リンパ増殖性疾患)であり、注意深い長期フォローが求められる 1, 2)。米国では年間約900例が行われ、SPKが90%を占める。2022年に施行された膵移植の1年後の膵グラフト生着率はSPKで90.8%、PTAで87.5%、PAKで84.4%であった。若年レシピエントでは拒絶率が高く、またEpstein-Barrウイルス(EBV)未感染者ではPTLDリスクが高いため、感染歴も考慮した術後管理が重要とされる 3)。
2025年09月11日 -
特集
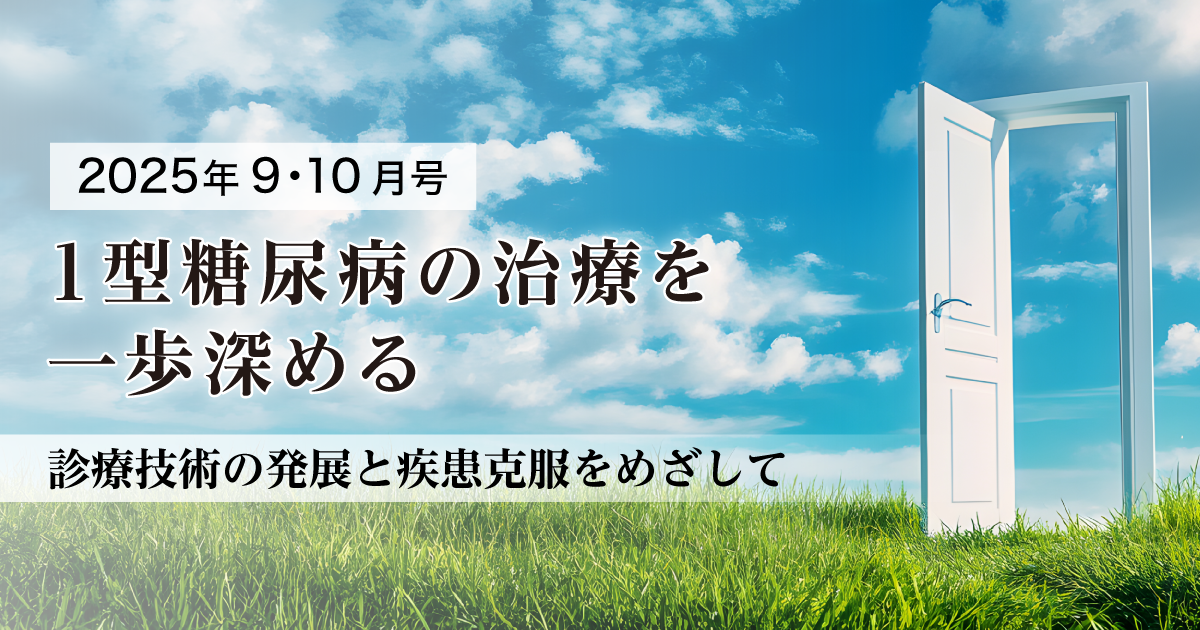
1.1型糖尿病の発症前介入 ―予防は可能か―
はじめに 現在、わが国における1型糖尿病の診断は、糖尿病の診断基準に基づく高血糖をもって行われており、治療としては、低下した自己インスリン分泌を補うインスリン自己注射療法もしくは膵・膵島移植が選択される。一方、欧米では発症早期の1型糖尿病に対して膵β細胞機能を保持させる目的で免疫修飾療法の臨床試験が盛んに行われていることに加え、臨床的発症以前のハイリスク者に対しても発症予防を目的とした免疫学的介入が試みられている。本稿では、予防的介入を前提とした1型糖尿病のステージ分類やスクリーニングを中心に、欧米の現状とわが国で始まりつつある取り組みについて概説する。 1.欧米における発症予防を目的とした臨床試験 これまで欧米では、1型糖尿病の発症予防を目的として、牛乳やグルテン曝露の回避、ニコチンアミドの投与、経口および経鼻的なインスリン抗原の投与、GAD-alum抗原の投与といった免疫学的介入に関する臨床試験が実施されてきたが(表1) 1)、2019年までは明らかな予防効果を示す報告はなかった。その後、2019年に欧米のTrialNet Study Groupより抗CD3抗体であるteplizumabの発症予防・遅延効果を示す画期的な試験結果が報告された。この試験では、リスク因子として(1)1型糖尿病の近親者、(2)膵島関連自己抗体を2個以上保有する、(3)耐糖能異常を有する(空腹時血糖値110〜125mg/dLまたは/かつ糖負荷2時間後血糖値140〜199mg/dL)、の3つの条件を満たす被験者に対してteplizumabが投与された。5年間の観察期間において、プラセボ投与群では32例中23例で1型糖尿病を発症したのに対して、teplizumab投与群では44例中19例の発症にとどまった(図1) 2)。発症を約2年遅らせる効果が得られたとして、同剤は米国においてFDAの承認を受けるに至った。
2025年09月04日 -
特集
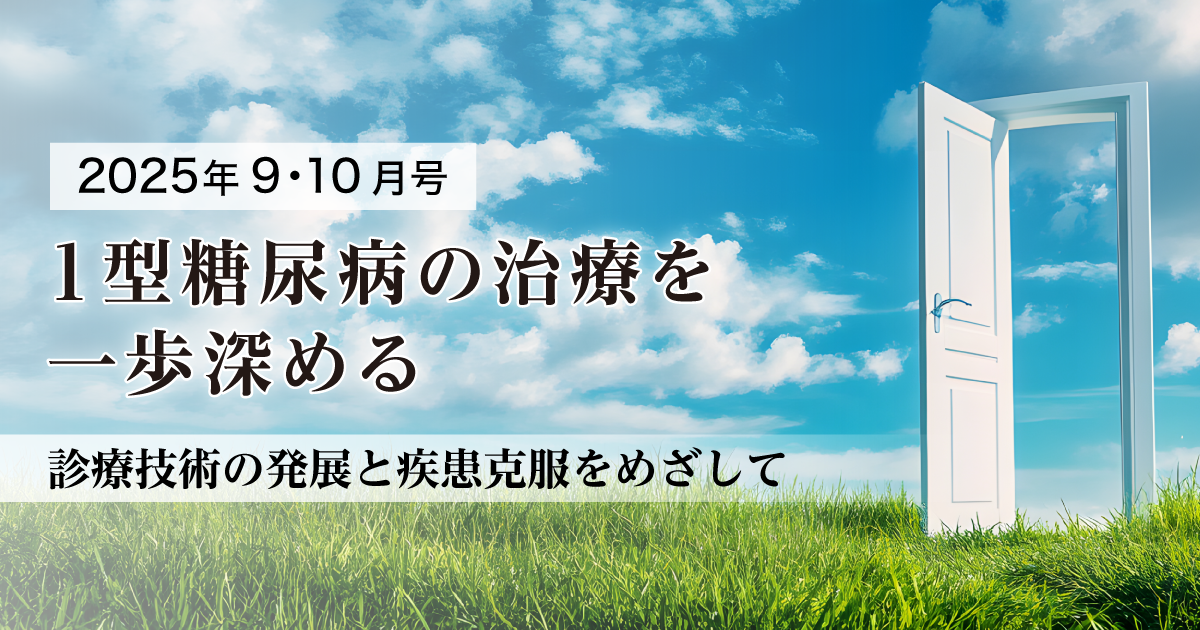
(扉)特集にあたって
糖尿病治療は近年飛躍的に進歩し、選択肢が大きく広がった。1型糖尿病についても、新規治療法の長期にわたる開発努力が国際的に進み、一部は実装に向かいつつある。同時に診療現場においては、実用化された技術や機器を活用するため、知識のアップデートが求められる。本特集の企画にあたっては、治療の変革がもたらす近未来像を提示することに加え、一般に経験が重視される1型糖尿病の診療において、質の向上に直接役立つ具体的な知識の共有を目的とした。 欧米では1型糖尿病の臨床的発症前の段階からステージ分類が確立され、teplizumabによる発症予防効果が立証されている。中條大輔先生には、わが国における臨床的発症前のスクリーニングやモニタリングに関する観察研究(PREP-T1D)の取り組みについて紹介していただいた。 iPS細胞由来膵島細胞シートを用いた1型糖尿病対象の医師主導治験は、大きな注目と期待を集めている。中村聡宏先生と藤倉純二先生には、従来の膵臓移植や膵島移植から、最新の幹細胞由来細胞移植や低免疫原性膵島移植に至る広範な再生医療について、現状と今後の展望を詳しく解説していただいた。 現状、先進医療機器の進歩の中核はAIDとCGMであり、これらを使いこなすことは1型糖尿病診療の質に直結する。菅井啓自先生には、インスリンポンプやCGMの運用方法について、概要の説明ならびに外来ですぐ使えるTIPSとしてレポートの使い方を教示していただいた。 1型糖尿病の治療が進歩した一方で、腎不全が進行し透析導入が必要となる人は今もなお多く、膵腎同時移植について適切な情報提供がなされる機会の確保が望まれる。加来啓三先生と中村雅史先生には、移植登録の流れを含め、制度やアクセス手段についてわかりやすく説明していただいた。 1型糖尿病の治療を実践する際に、しばしば直面する障壁の代表がカーボカウントである。茂山翔太先生と真壁昇先生には、基礎カーボカウントと応用カーボカウントについて、また調理習慣がなく外食中心の人にカーボカウントを実践してもらう「取っ掛かり」をつかむ工夫について、詳しく解説していただいた。 いずれの項目も非常に読み応えがあり、1型糖尿病の診療に関わる医療従事者としての新たな気づきが得られる内容になっている。執筆にあたられた皆様に深く感謝申し上げるとともに、本特集が読者にとって日々の診療の質向上に役立つことを心から願っている。 著者のCOI (conflicts of interest)開示:鈴木 亮;講演料(田辺三菱製薬、ノボ ノルディスク ファーマ、アステラス製薬、グラクソ・スミスクライン、日本イーライリリー、住友ファーマ、MSD、日本ベーリンガーインゲルハイム)、矢部大介;講演料(ノボ ノルディスク ファーマ、日本ベーリンガーインゲルハイム、日本イーライリリー、住友ファーマ、田辺三菱製薬)、研究費・助成金(テルモ、日本ベーリンガーインゲルハイム)、寄附講座(ノボ ノルディスク ファーマ、大正製薬、アークレイ) 本論文のPDFをダウンロードいただけます
2025年09月04日 -
特集
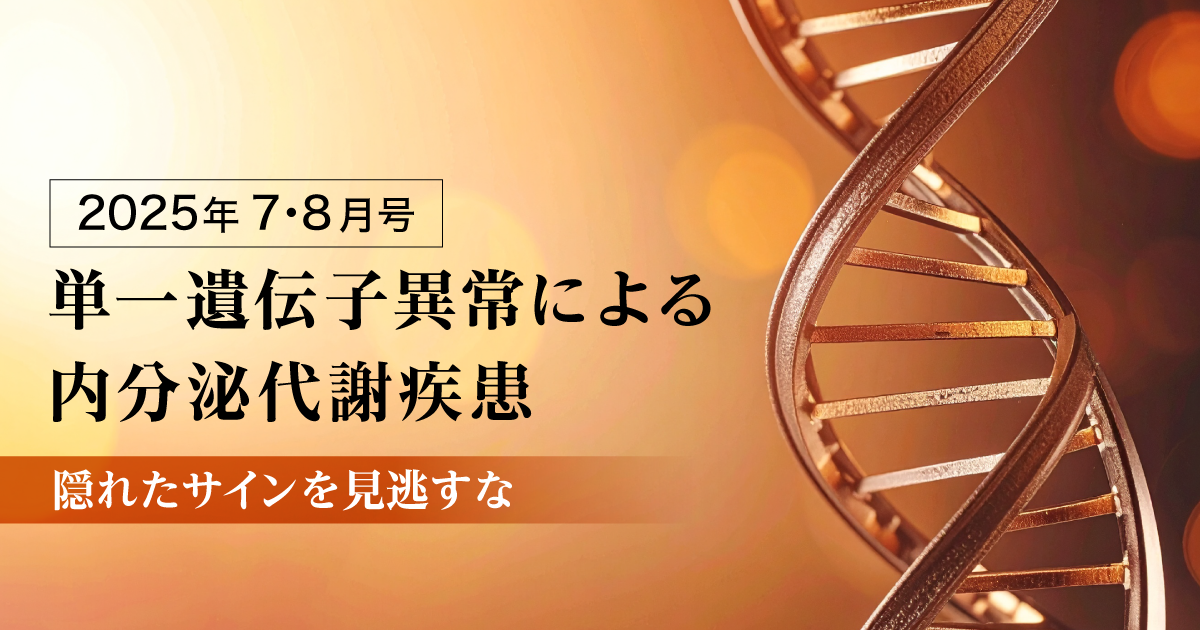
≪特論≫ウォルフラム(Wolfram)症候群
はじめに 希少遺伝子難病ウォルフラム症候群は、1938年に家族性の若年発症の糖尿病と視神経萎縮の合併としてWolframらによって報告された 1)。その後、尿崩症や感音性難聴および多彩な精神神経症状を呈することが報告され、主要な4徴候(diabetes insipidus:尿崩症、diabetes mellitus:糖尿病、optic atrophy:視神経萎縮、deafness:難聴)からDIDMOAD症候群とも呼ばれる。原因遺伝子WFS1が同定され 2)、遺伝子診断が可能となっている。本稿では、ウォルフラム症候群の病態、内分泌学的特徴および診断・治療ついて解説する。 1.ウォルフラム症候群の臨床像 ウォルフラム症候群では、10歳前後で発症するインスリン依存性の糖尿病が初発症状となる。やや遅れて視神経萎縮による視力障害が発症し、失明に至り得る。その後、中枢性尿崩症、聴力障害(感音性難聴)や尿路異常(水腎症、尿管の拡大)、神経症状(脳幹・小脳失調、けいれん)、精神症状(抑うつ、双極性障害など)を種々の組み合わせで進行性に合併し、尿路異常に伴う腎不全や、加えて神経症状を誘因とする種々の感染症などが生命予後を決定し得る 3)(図1)。経過は一般に進行性であるが、症例あるいは病期により、一部の症候のみを呈する場合がある。また、糖尿病発症後、視神経萎縮による症状が顕在化する前に尿崩症や難聴を診断される例や、比較的早期より精神神経症状が出現する場合や症状がなくても脳幹萎縮を呈する場合がある。このように症候が出現する順序に多様性が存在するため、尿崩症や感音性難聴、精神神経症状と糖尿病の合併をみた場合には、その後視神経萎縮が診断されることもあり、本症候群と疑い診療にあたることが重要である。一方、色覚異常と嗅覚障害が早期より出現する特異性の高い症状として、早期診断に有用である可能性が示唆されている 4)。日本での全国断面調査より、有病率は71万人に1人と推定されている 5)。 図1 ウォルフラム症候群の自然経過(文献4より改変) 治療は対症療法に限られ、平均死亡年齢は30歳(25~49歳)とされている。
2025年08月29日 -
連載

ないないづくしの糖尿病診療
はじめに 私が医学部を卒業したのは1975年。その当時の糖尿病外来診療を思い出してみる。 インスリン注射について インスリン自己注射はない 1975年当時は、インスリン自己注射は保険収載されていなかった。つまり患者さんは自己注射できなかった。その後、6年の年月とさまざまな紆余曲折を経て、1981年、インスリン自己注射はようやく正式に保険適用となった。 ヒトインスリンはない インスリンはブタの膵臓から抽出・精製された製剤であり、インスリン注射で治療している患者さんにはインスリン抗体はあるのが当たり前であった。 インスリンの種類 当時、中間型インスリンはNPHインスリンとレンテインスリンの2つがあり、レンテインスリンが主流であった。もう1種類はレギュラーインスリンがあるだけ。この2種類のインスリンの作用時間の違いにもとづいて、経口薬、食事療法、運動療法などの効果を頭の中で組み合わせて、治療方針法を組み立てるのが通例であった。 経口糖尿病薬について ビグアナイドはアメリカで行われた臨床研究の結果、乳酸アシドーシスの危険性が高いという解釈で使用が制限され、「フェンホルミンには該当するもののメトホルミンには該当しないにもかかわらず、統計の解釈に十分な区別がなされていなかった(らしい)」ため、使用禁止に近い状態。勇気のある先生はブホルミンを少数例処方されていた。スルホニル尿素(SU)薬はグリベンクラミドとトルブタミドが主流で、クロルプロパミドがまれに処方される状況であった。
2025年08月28日 -
連載

第79回 糖尿病と内分泌疾患に係る手術2025
はじめに 糖尿病においては、糖尿病網膜症や足病変など、また内分泌疾患においては、甲状腺や副腎疾患などで手術療法が必要になる場合がある。そして、「手術」は、「診療報酬の算定方法の一部を改正する告示」で医科点数表の算定点数が設定され、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)」で、各手術の算定要件が規定される。 よって今回は、糖尿病と内分泌疾患に係る「手術」について、医科点数表告示・通知を基に、算定要件について概説する。 1.K002 デブリードマン 1,2)(表1) 「K000 創傷処理」および「K000-2 小児創傷処理」の「注3」に規定されたデブリードマン加算は、汚染された挫創に対して行われるブラッシングまたは汚染組織の切除などであり、通常麻酔下で行われる程度のものを行った場合に算定する。しかしながら、「K002 デブリードマン」は、「K013 分層植皮術」から「K019 複合組織移植術」および「K020 自家遊離複合組織移植術(顕微鏡下血管柄付きのもの)」、「K012-2 粘膜弁手術」までの手術を前提に行う場合にのみ算定する。そして、通知(6)(7)に示すように、Ⅱ度以上の熱傷、糖尿病性潰瘍または植皮を必要とする創傷に対して、水圧式デブリードマン加算は水圧式ナイフを用いて、超音波式デブリードマン加算は超音波手術器を用いて、それぞれ組織や汚染物質などの切除、除去を実施した場合に、一連の治療につき1回に限り算定する。 表1 デブリードマンの告示・通知(文献1, 2より) 画像をクリックすると拡大します 表1 デブリードマンの告示・通知(文献1, 2より) $(".n0066_h1").modaal();
2025年08月28日 -
特集
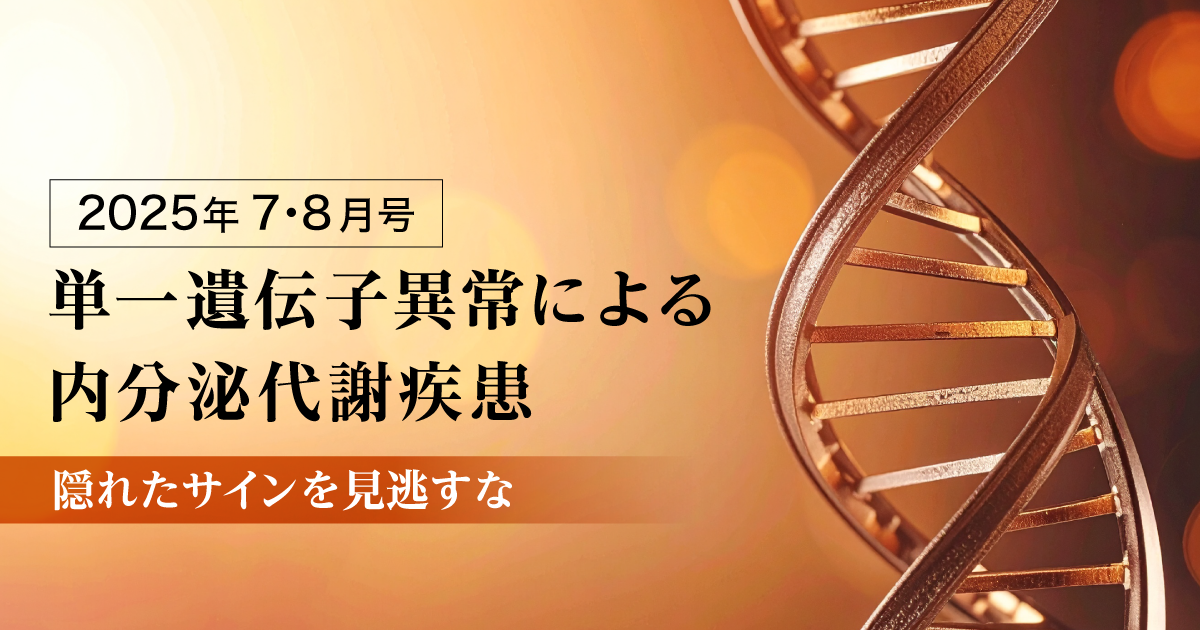
7.遺伝学的検査におけるSDM(shared decision making)
はじめに 遺伝医学の発展に伴い、多くの診療科において、遺伝学的検査が臨床検査の一部として行われるようになっている。遺伝学的検査はその特殊性として、生涯不変の遺伝情報が扱われること、将来発症する疾患を予測し得ること、血縁者などへの影響も生じ得ることなどから、患者・家族への心理的負担が非常に大きい。このため検査の実施に際しては、患者・家族の心理面への十分な配慮が必要とされる。特に、検査の実施を検討する際に生じる「遺伝性疾患の可能性を誰にどう伝えるのか」「検査の説明や実施の適切なタイミングはいつか」「受検への意思はどう確認すべきか」「未成年者の場合はどう考えるのか」などの問いについては、ひとつの正解があるわけではない。このため、患者にとっての最善とは何かを、患者・家族との対話を通じて共に考えていくプロセスが、一般診療科においても重要となる。この、対話を通じて共に考え意思決定に至るプロセスのことをSDM(shared decision making)という。日本語では共有意思決定などと訳されることもあるが、本稿ではSDMと表記する。 1.SDMとICの異同とそれぞれの役割 米国のNICE(National Institute for Health and Clinical Excellence)のガイドライン 1)によると、SDMとは「医療者と患者が協力してケアに関する意思決定を行うプロセス」であり、「エビデンスと、個々の患者の希望・信念・価値観の両方に基づいて、検査や治療を選択する」「医療者との話し合いを通じて、さまざまな選択肢のリスクとベネフィット、そして起こり得る結果を患者が理解できるようにする」と説明されている。つまり、検査や治療の意思決定に際し、医療者はEBM(evidence-based medicine)の視点だけでなく、患者の語りに耳を傾け、患者の希望・信念・価値観を十分に理解し、それに即した医療を実現しようとするNBM(narrative-based medicine)の視点をもつことが求められている。 IC(informed consent)とSDMの異同について、京都大学の中山は以下のように説明している。 ICは医療者が専門知識と経験で、(一般論として)良いとされる「答え」を知っている場合のコミュニケーションであり、患者は「医療者が示す(ほぼ唯一の)選択肢」を受け入れることが期待される。一方、SDMは、望ましい選択肢を示す研究の成果が不十分、すなわち「エビデンスの確実性が高くない」場合に特に大切になる。そのような状況では、患者も医療者も、どこに着地するか当初はわからないが、双方向のコミュニケーションを通して、目指す目標と、そこに近づく方法が次第に共有され、意思決定と合意に至る 2)。 すなわち、ICとSDMはどちらも医療における意思決定・合意形成において重要なものであるが、ICは選択肢がひとつしかない(確実性が高い)状況に適用され、SDMは選択肢が複数ある(不確実性が高い)状況で必要ということになる。なお、ICによる面接とSDMを目指す面接の違いは、表1のように整理できる。
2025年08月21日 -
連載

第2回 認知症の感情失禁(イライラ)への抑肝散
はじめに 認知症患者における感情失禁(イライラ)は、患者本人の生活の質(QOL)を低下させるだけでなく、介護者の負担を著しく増大させる症状である。特に糖尿病のある人においては、服薬や食事・運動療法の実施率が低下して血糖マネジメントが困難になるため、その対応は重要である。今回は、「抑よく肝散かんさん」の認知症に伴う感情失禁に対する効果について、糖尿病治療における臨床的な立場から解説する。 1.認知症と糖尿病の関連性 糖尿病と認知症は密接な関連性を持つことが近年の研究で明らかになっている。糖尿病では糖尿病のない人と比較して、アルツハイマー型認知症の発症リスクが約1.5倍、血管性認知症のリスクが約2倍高いとされている。この背景には、脳内のインスリン抵抗性によるインスリンシグナルの障害や酸化ストレス、慢性炎症などさまざまな機序が関連している 1)。 認知症では、記憶障害や見当識障害などの中核症状だけでなく、幻覚、妄想、焦燥、徘徊、暴力、抑うつ、睡眠障害、感情失禁、易怒性、社会的逸脱行動など周辺症状といわれるBPSD(Behavioral and Psychological Symptoms of Dementia:行動・心理症状)が付随してみられることが多く、患者のQOLや介護者の負担に大きく影響する。 糖尿病に伴う認知機能障害では、前頭前野の機能低下が比較的早期から生じることが知られていることから、前頭前野は感情制御や行動抑制に深く関与しており、その障害がBPSDの出現、特に易怒性や感情失禁に関連する 2, 3)。
2025年08月21日 -
TRENDS

アンドロゲンによる糖代謝制御と前立腺がんへのアンドロゲン抑制療法
はじめに アンドロゲン(男性ホルモンの総称)は、性機能にとどまらず、さまざまな代謝調節機能を持ち、特に糖代謝やインスリン感受性に深く関与する。前立腺がん治療で広く用いられるアンドロゲン抑制療法は、副作用として糖代謝異常やメタボリックシンドロームの発症リスクの上昇が指摘されている。 1.アンドロゲンの糖代謝への影響 アンドロゲンが糖代謝に及ぼす影響は、男性性腺機能低下症患者を対象とした研究や、テストステロン補充療法の研究によって検討されている。アンドロゲンは、除脂肪体重を増加させ、体脂肪量を減少させ、インスリン感受性を高める作用を持つ。テストステロン補充療法は、これらの体組成の変化を通じて、インスリン抵抗性を改善し、糖代謝を改善する可能性が報告されている 1)。また、アンドロゲンには遊離脂肪酸を減少させ、炎症を抑制する作用もあり、これらもインスリン抵抗性の改善に関与すると考えられている 2)。さらに、アンドロゲンは骨格筋、肝臓、脂肪組織におけるグルコースの取り込みやインスリンシグナル伝達を直接的に調節することが明らかとなっている 2)。アンドロゲンの糖代謝への影響は、多様な要因が関与し、複数のメカニズムが関わる複雑なものである。
2025年08月14日 -
特集
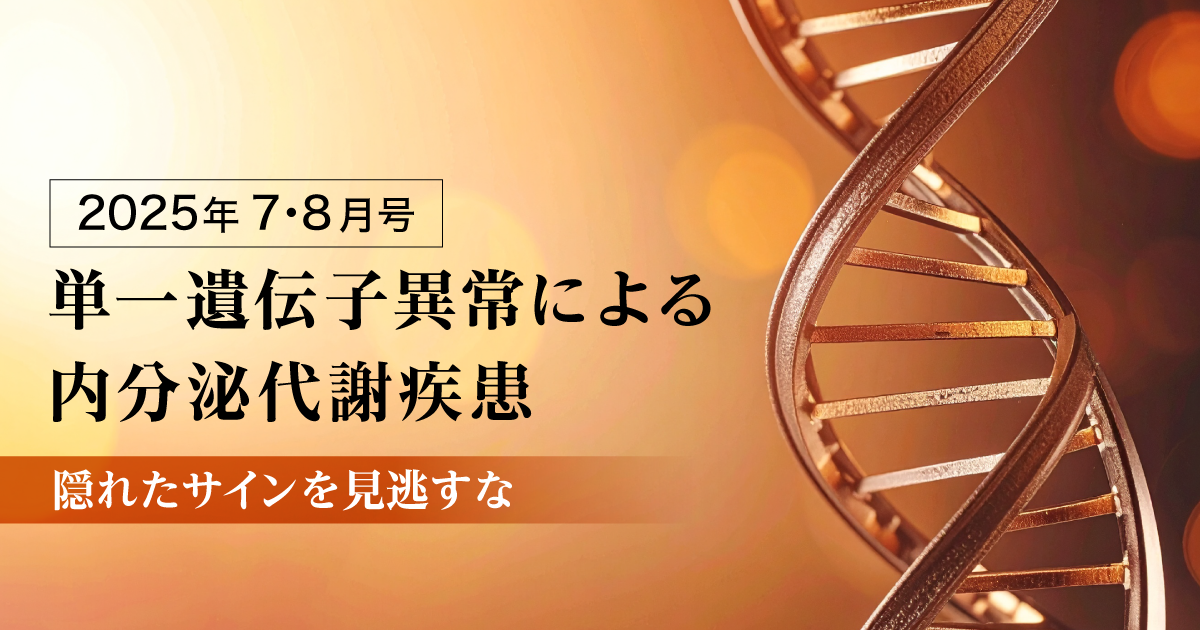
6.内分泌代謝疾患における遺伝医療と医療倫理
はじめに 近年、わが国における遺伝学的検査の体制は急速に整備されており、先天性・遺伝性疾患の診断を目的とした検査は、医療機関のみならず、多様な提供形態を通じて実施されるようになっている。内分泌代謝疾患を専門とする医師を含む医療従事者が日常診療において遺伝性疾患に直面する機会は年々増加しており、診療現場では、遺伝学的検査や遺伝カウンセリングに関する基礎的かつ実践的な知識が求められる場面が増加している 1)。さらに、疾患の遺伝形式に関する説明や遺伝学的診断にとどまらず、保因者診断、出生前診断、発症前診断などの多様な対応が求められることがある。検査結果を説明した患者およびその家族に対しては、社会的・心理社会的背景を踏まえ、将来的な生活設計(ライフプラン)について共に検討していくことも、医療者の重要な役割のひとつである。本稿では、内分泌代謝専門医が日常診療で遭遇することの多い遺伝性疾患に対する遺伝学的検査の現状と、その適切な取り扱いに関する基本的な考え方について概説する。 1.内分泌代謝疾患における遺伝性疾患 2, 3) 1)概要 環境要因によって生じる外傷後の合併症や手術後の内分泌異常、ビタミン欠乏症などを除くと、多くの内分泌代謝疾患は多因子遺伝病として位置づけられる。一方で、単一遺伝子の病的バリアントによって発症する大多数の内分泌代謝疾患はそれぞれの疾患の有病率は低く、希少疾患に分類されるものの、その原因遺伝子の数は非常に多い。また、染色体異常に起因する症候群の一部では、内分泌疾患を合併することが知られている。これらの疾患の中には、遺伝学的診断が治療方針の決定や介入に直結するものも少なくない。 疾患の診断には、診察による理学所見に加えて、内分泌学的検査を含む体系的な臨床検査の実施が基本となる。加えて、発症年齢の特徴を理解し、遺伝学的検査を実施する時期(生後日齢や月齢など)について留意することも重要である。 遺伝子検査が臨床症状の出現よりも先行して行われる場合(例:発症前診断や胎内診断)には、一般的な診療の枠組みを超える対応が求められ、臨床遺伝専門医による適切な遺伝カウンセリングの提供が不可欠である。
2025年08月14日 -
セミナー

低血糖
Q&A編はこちら はじめに 低血糖は糖尿病患者の血糖管理において大きな障壁であり、できる限り避けたい副作用である。以前より低血糖はけいれん、意識障害につながるだけでなく、放置すれば死につながる危険な状態であることが認識されている 1)。さらに、最近では低血糖の中でもより重篤な重症低血糖が心血管イベントと死亡と関連することが報告され、その予防や対応がより一層重要になってきている。本稿では低血糖の危険性や原因、低血糖時の対処法、低血糖を予防するためのポイントを中心に解説する。 1.厳格な血糖コントロールのリスク 低血糖を考える上で、まずは今までの血糖コントロールに関する臨床試験を振り返りたい。1型糖尿病を対象にしたDCCT(Diabetes Control and Complications Trial)において、厳格に血糖管理を行うことで糖尿病網膜症や糖尿病腎症の進展を有意に抑制することが示された 2)。さらに、2型糖尿病を対象にしたUKPDS33においても、厳格な血糖管理により糖尿病網膜症や腎症といった細小血管症を有意に抑制することが報告された 3)。そこで、さらに厳格に血糖を管理することで心筋梗塞や脳卒中といった糖尿病患者の生命予後に大きな影響を与える大血管症も抑制することができるのではないかと考えられ、大規模なランダム化比較試験が施行された。しかし、その一つである心血管リスクの高い2型糖尿病患者を対象にしたACCORD試験において、予想とは逆に、より厳格に血糖を管理された強化治療群のほうが通常の標準治療群に比べて経過途中で死亡リスクが有意に高くなり、試験自体が中止されるという結果になった(図1) 4)。さらに死亡に関しても強化治療群において全死亡が有意に増加していただけでなく、心血管死も有意に増加していた。ACCORD試験の結果は、糖尿病診療に関わる多くの医療者にとって衝撃的なものであった。 図1 厳格な血糖管理と標準的な血糖管理に対する死亡率(文献4より)
2025年08月07日 -
特集
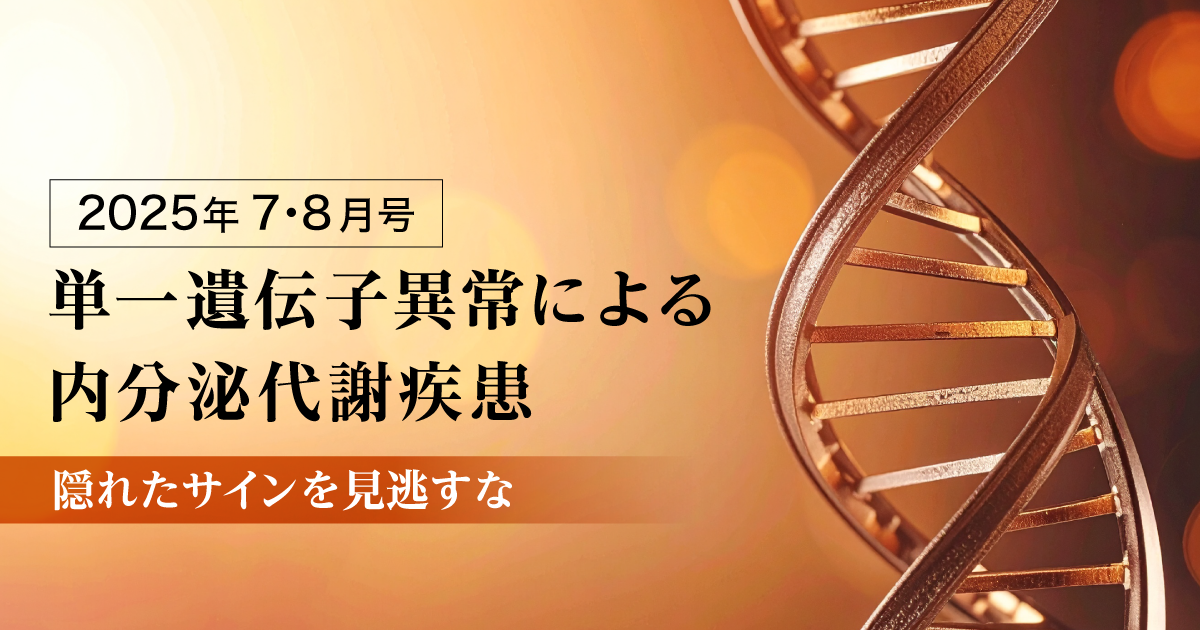
5.骨代謝疾患、骨系統疾患
はじめに 骨代謝疾患はカルシウムやリン、ビタミンDなどの代謝障害により、また骨系統疾患は骨や軟骨の発生、成長、分化の障害により骨格の形態や構造に異常をきたす疾患の総称である。骨系統疾患の多くが単一遺伝子疾患であり、個々の疾患単位としてはまれだが、最新版である2023年の国際分類においては41グループに分けられ、771疾患もの分類が記載されている 1)。疾患により骨形態の異常や低身長、関節の機能不全、易骨折性、骨変形などさまざまな症状・合併症を呈し、患者の日常生活にも支障をきたす。従来は対症療法が主であったが、近年では病態の解明に伴い治療薬の開発が進む疾患もいくつか存在する。本稿では、比較的疾患頻度の高い骨代謝疾患である低リン血症性くる病と、代表的骨系統疾患として低ホスファターゼ症、骨形成不全症、大理石骨病やその類縁疾患について概説する。 1.低リン血症性くる病と高リン血症性腫瘍状石灰沈着症 くる病・骨軟化症はいずれも骨石灰化障害により類骨が増加した病態であり、骨端線の閉鎖前・後でそれぞれくる病・骨軟化症と分類される。骨量全体が減少する骨粗鬆症とは異なる病態であり、くる病・骨軟化症では骨密度が低下しない症例も多いことに注意したい。くる病では、成長障害やO脚・X脚などの骨変形が特徴的であり、X線検査で骨端線の拡大や毛羽立ち、骨幹端における杯状陥凹(cupping)などが確認される。骨軟化症では、骨形成の低下によるマイクロクラックの蓄積に起因する偽骨折が多発し、全身の骨痛および歯髄炎や歯肉膿瘍を呈する。肋骨、大腿骨頭、長管骨の骨幹部、踵骨、中足骨などに偽骨折に伴う疼痛が多発し、骨シンチグラフィーで上記の特異的な箇所の骨折や偽骨折部位への集積を確認することが、骨粗鬆症やほかの全身性に疼痛を生じ得る疾患との鑑別に有用である。 先天性低リン血症性くる病の原因として、線維芽細胞増殖因子(fibroblast growth factor:FGF)23関連疾患、腎尿細管障害、ビタミンD代謝異常が挙げられ、それぞれに複数の原因遺伝子が知られている(表1) 2)。PHEX遺伝子が原因でFGF23関連低リン血症を惹起するX染色体連鎖性低リン血症性くる病(X-linked hypophosphatemic rickets:XLH)は国内外でおよそ2万人に1人の有病率と推定され、先天性低リン血症性くる病の中で最多である 3)。 くる病・骨軟化症が上述の症状および画像検査から診断された場合、原因の精査として図1のように血清P(およびアルブミン補正Ca)、アルカリフォスファターゼ(ALP)や骨型ALP(BAP)、副甲状腺ホルモン(PTH)、25(OH)ビタミンD、1,25(OH)2ビタミンD、intact FGF23を適宜測定し、蓄尿または尿中クレアチニンなどで補正した尿中P排泄を評価して診断を進める 4)。XLHなどのFGF23関連低リン血症の遺伝子検査はかずさDNA研究所で実施可能だが、保険適用にはなっていない。またlarge deletionなどによる病態も多く、エキソーム解析のみでは診断感度に限界があることに注意したい。 FGF23関連疾患に対する治療として、完全ヒト型抗FGF23モノクローナル抗体(ブロスマブ)が病態に即しており、標準治療として確立されつつある。ビタミンD依存症に対しては、天然型および活性型ビタミンD製剤を適宜選択し治療を行う。その他の尿細管障害による慢性低リン血症などの治療では、経口リン製剤と活性型ビタミンD製剤が使用される。ただし経口リン製剤の過剰投与は長期的に二次性・三次性副甲状腺機能亢進症、および高Ca尿症に伴う尿路結石症と尿濃縮力障害による腎前性腎不全を繰り返すことで慢性腎臓病の進展リスクが高まるため注意が必要である。経口リン製剤による血清リン濃度の上昇は1~2時間程度しか認められないため、1日4〜6回に分けて投与する必要がある。また上記合併症の発症リスクを低減させるため、投与後約1時間で血清リン濃度が基準範囲下限前後となる程度に1回あたりの投与量を調整することが望ましい。経口リン製剤や活性型ビタミンD製剤の長期服用中は血液検査で二次性、三次性副甲状腺機能亢進症をモニターし、三次性副甲状腺機能亢進症発症時には即座に副甲状腺摘出術やカルシウム感知受容体作動薬の開始を検討することが推奨される。 高リン血症性家族性腫瘍状石灰沈着症(hyperphosphatemic familial tumoral calcinosis:HFTC)はGALNT3、FGF23、KLOTHO遺伝子の両アレルにおける機能喪失型バリアントが原因の遺伝性疾患である。本疾患では、FGF23作用障害による慢性高リン血症が大関節周囲に粗大な皮下石灰沈着を惹起し、低リン血症性くる病・骨軟化症とは対極をなす病態といえる 5)。
2025年08月07日 -
セミナー

糖尿病網膜症などで視力障害のある患者およびその家族に対する療養支援の留意点
Q&A編はこちら はじめに 糖尿病患者を介した眼科医と内科医などで連携する手帳が、2種存在する。1つ目は日本糖尿病協会による「糖尿病連携手帳」である。ホームページによると、年間発行部数は約200万部、累計約2,000万部の発行実績である 1)。一方は、日本糖尿病眼学会による「糖尿病眼手帳」である。2020年3月末時点で280万部以上が発行 2)とのことで、眼科医の筆者としても、臨床上の実感に合致する。今回、2種の手帳の記載項目を比較し、視力障害の療養支援、特に歩行、生活訓練の観点から検討してみる。 1.糖尿病連携手帳 糖尿病連携手帳(図1)にしかない項目が「光凝固:未・済」である。実はこれが、注目すべき項目で求心性視野障害が想起される。増殖網膜症患者で汎網膜光凝固術が施行された場合に、中心10度程度の求心性視野障害を合併することがある。ただし、増殖網膜症でない(単純、増殖前網膜症)の場合には、汎網膜でなく、局所網膜での光凝固術であることが多く、視野障害は生じにくい。増殖網膜症で光凝固済のケースでは、求心性視野狭窄による歩行障害を確認する必要がある。
2025年07月31日 -
特集
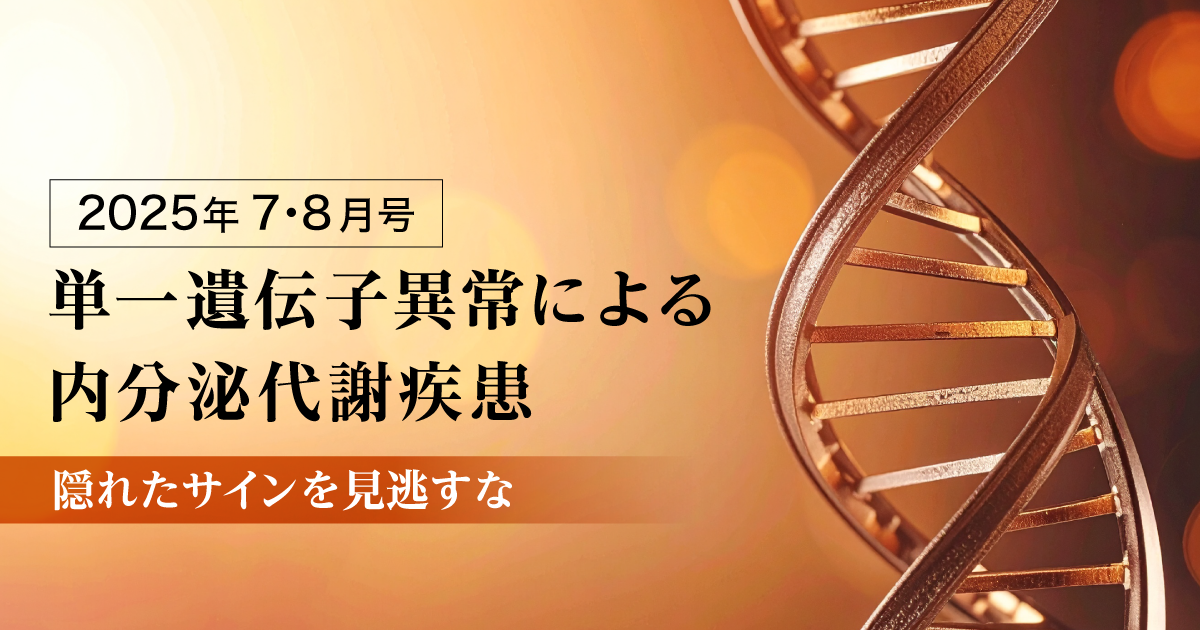
4.家族性高コレステロール血症
はじめに 家族性高コレステロール血症(FH)は、①高LDLコレステロール(LDL-C)血症、②早発性冠動脈疾患、③腱・皮膚黄色腫を3主徴とする常染色体遺伝性疾患である。FH患者では生下時から高LDL-C血症が持続し、若年時から冠動脈硬化症の進展を認めるため、FHは単独できわめて冠動脈疾患のリスクが高い疾患である。未治療のFHヘテロ接合体(HeFH)では、冠動脈疾患発症リスクが約13倍高いことが報告されている。 日本人においても他国と同様300人に1人という高頻度でHeFHが存在し、30万人以上の患者がいると考えられる。早期診断により適切な治療につなげることで、FHは確実に予後を改善できる病気であることを念頭に診療にあたり、本人、さらには家族スクリーニング(カスケードスクリーニング)を実施することにより、若年死の予防が可能になる。 1.FHの病態 1)高LDL-C血症 日本人HeFHの未治療時の平均LDL-Cは248mg/dLで、男女差は認めなかった 1)。HeFHの血清総コレステロール値は正常者の約2倍、FHホモ接合体(HoFH)は約4倍の値を示す。LDL-C値が高い場合、特に薬物治療への反応が悪い場合にはFHを疑うべきである。 2)早発性冠動脈疾患 早発性冠動脈疾患患者は全てFHの可能性がある。高LDL-C血症があれば、FHの可能性が高い。急性冠症候群(ACS)の急性期にはLDL-C値が低下することが知られており、注意が必要である。 3)腱・皮膚黄色腫 FHの診断において、腱黄色腫や皮膚黄色腫の存在が重要である。特にHoFHでは若年から黄色腫が顕著になるが、黄色腫がない場合でもFHを否定するべきではなく、遺伝学的検査が診断上重要な位置を占める。 4)角膜輪 50歳未満のFH患者に見られる角膜輪は診断的価値が高いが、高齢者にも類似の症状が見られ、鑑別が必要である。 5)FHにおけるその他のリスク因子 HeFHにおける冠動脈疾患のリスク因子として、糖尿病、低HDL-C血症、喫煙、高LDL-C、アキレス腱肥厚、高トリグリセライド(TG)血症などが挙げられる。また、高Lp(a)血症がリスク因子であることも報告されている。これらにより、動脈硬化のリスクを評価して、制御できるリスクをできる限り低下させることが重要である。
2025年07月31日