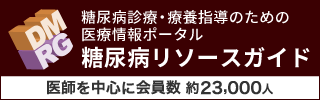- トップページ
- 新着論文一覧
新着論文一覧
-
セミナー
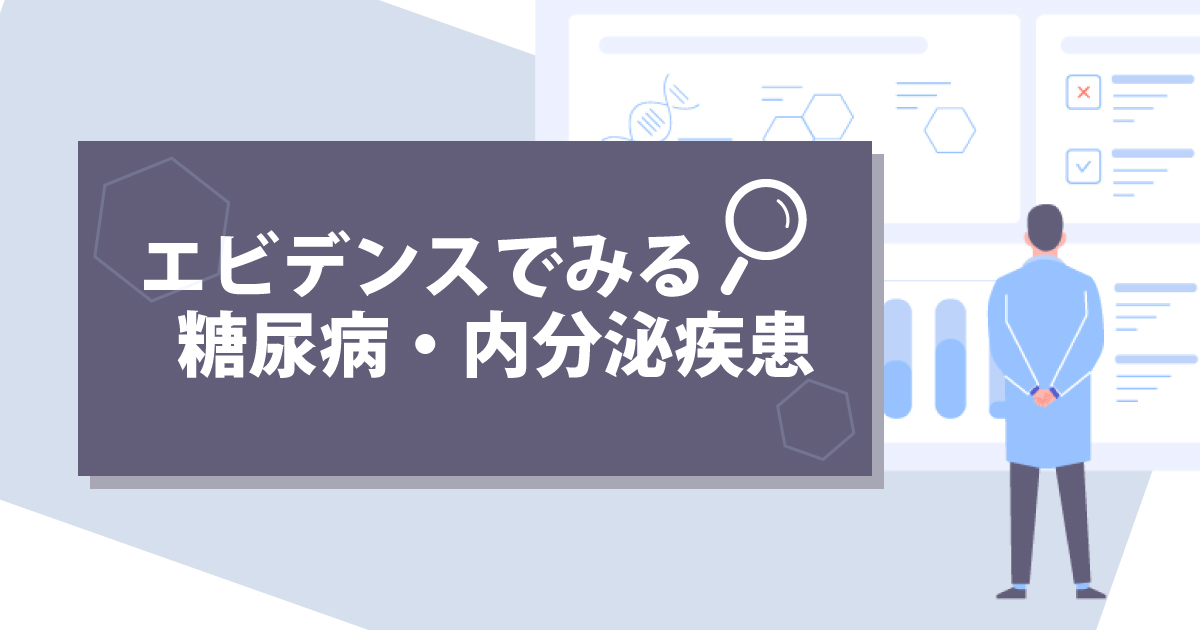
骨粗鬆症の治療―骨粗鬆症治療薬の最新エビデンス―
1.ポイント 骨折リスクの高い患者に対しては、骨粗鬆症治療薬の有効性評価を参考にするなど、骨折抑制効果が認められている治療薬を選択する。 骨粗鬆症の診断基準とは別に治療開始基準が定められており、骨粗鬆症性骨折リスクが高い場合には骨折予防を目的とする薬物治療の対象とする。 副甲状腺ホルモン製剤、抗RANKL抗体製剤、抗スクレロスチン抗体製剤を含め、わが国における骨粗鬆症治療薬の種類も増えてきている。 今後、わが国における高齢者や男性を含めた骨粗鬆症薬物治療のさらなるエビデンス構築が期待される。 2.総論 骨粗鬆症は「骨強度の低下を特徴とし,骨折のリスクが増大しやすくなる骨格疾患」と定義されている。骨粗鬆症の薬物療法に際し、骨折リスクの高い骨粗鬆症患者に対しては、骨粗鬆症治療薬の有効性評価を参考にするなど、できるだけ骨折抑制効果が認められている治療薬を選択する。また、骨粗鬆症の診断には至らず骨量減少と判定された場合でも、骨粗鬆症性骨折リスクが高い場合には骨折予防を目的とする薬物治療の対象とし、骨粗鬆症の診断基準 1)とは別に治療開始基準が定められている 2)。原発性骨粗鬆症の診断基準に基づいて骨粗鬆症と診断された場合、ならびに骨密度がYAMの70〜80%の閉経後女性および50歳以上の男性において脆弱性骨折がなく、大腿骨近位部骨折の家族歴またはFRAX 3)の将来10年間の主要骨粗鬆症性骨折発生確率が15%以上である場合には、薬物治療の開始を検討する。
2023年08月18日 -
セミナー
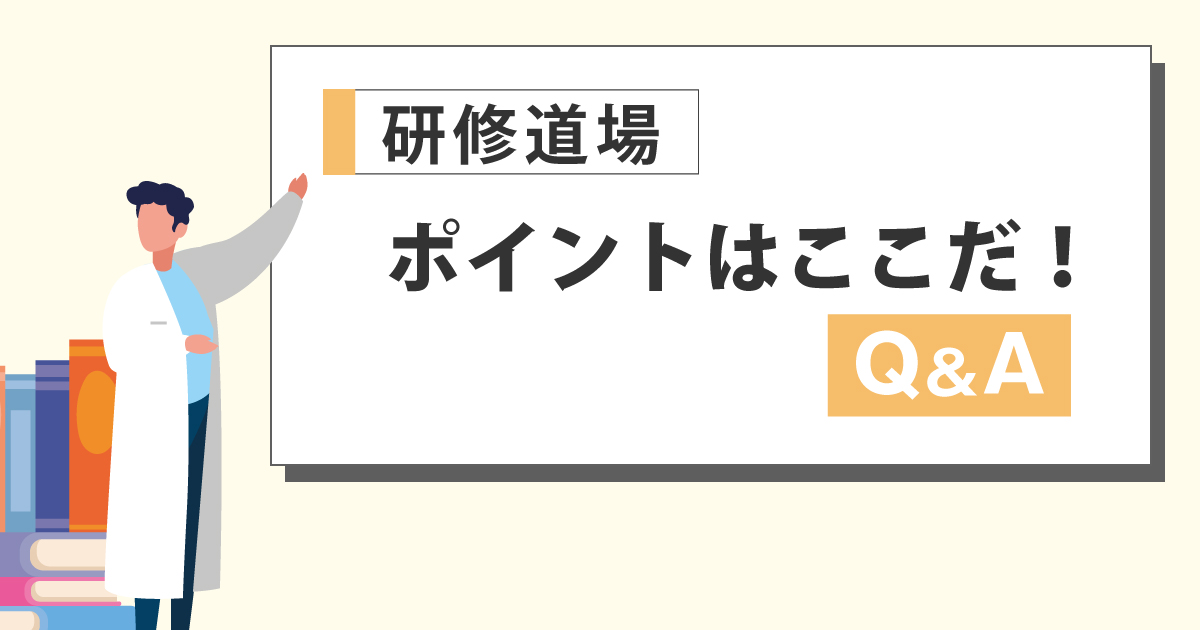
二次性高血圧の鑑別
Q&A編はこちら はじめに 二次性高血圧は特定の原因による高血圧であり、本態性高血圧とは病態や治療方針が全く異なるため適切に診断することが極めて重要である。二次性高血圧の有病率は以前考えられていたよりも高く、少なく見積もっても高血圧全体の10%以上が二次性高血圧であるとされる 1, 2)。特に原発性アルドステロン症は近年診断数が増加しており、高血圧患者の5~10%前後との報告もあるため念頭に置く必要がある。本稿ではどのような症例で二次性高血圧を疑うかについて、自験例を提示しながら解説する。また、近年新しくなった原発性アルドステロン症のスクリーニング、診断方法についても概説する。 1.症例 【現病歴】35歳女性。30歳時に高血圧を指摘され、以降アムロジピンベシル酸塩 10mg/日による治療を開始した。35歳時に人間ドックの腹部単純CT検査で左副腎偶発腫(18mmの低吸収結節)を指摘されて当院を紹介受診し、高血圧の精査目的で入院となった。【既往歴】30歳時に高血圧(二次性高血圧の精査は未施行)【内服歴】アムロジピンベシル酸塩 10mg/日【家族歴】特になし【生活社会歴】飲酒、喫煙なし、運動習慣なし、いびきなし、日中の眠気なし、体重変化なし【入院時検査所見】身長 153cm、体重 62kg(BMI 26.5)、診察室血圧 136/78mmHg(アムロジピンベシル酸塩 10mg内服下)、明らかなクッシング徴候を認めない。甲状腺腫大なし。胸部聴診上、呼吸音、心音ともに異常なし。腹部は平坦、軟で圧痛なし。腹部血管雑音なし。下腿浮腫は認めない。血液検査所見(午前9時に採取):血算に異常なし、低K血症なし、耐糖能異常なし、血漿アルドステロン濃度(PAC〔CLEIA法〕) 207pg/mL、血漿レニン活性(PRA) 0.5ng/mL/hr、PAC/PRA(ARR) 414、ACTH 7.5pg/mL、コルチゾール 16.0μg/dL、血中カテコラミン正常、随時尿中メタネフリン・ノルメタネフリン正常
2023年08月08日 -
連載

第2回 妻もバセドウ病―ブッシュ大統領―
第41代アメリカ合衆国大統領を務めたジョージ・ハーバート・ウォーカー・ブッシュ、いわゆるパパ・ブッシュ(図)は1924年6月12日マサチューセッツ州に生まれた。その父のプレスコット・ブッシュは裕福な実業家で、後に上院議員に選出される。家系をさかのぼればイギリス王室にいきあたるような名門であった。ブッシュは私立の有名高校在学中に兵役につき海軍で最も若いパイロットとなる。日本軍の砲撃を受けパラシュートで洋上に脱出し味方の潜水艦に救出された経験もある。復員しイェール大学に入学する直前、バーバラ・ピアースと結婚した。卒業後はテキサス州に移り、石油で富を築くと政界に進出、1964年の上院議員選挙は落選したが、2年後に下院議員に選出された。その後、国連大使、CIA(中央情報局)長官を経て、1980年の大統領選では予備選でレーガンに敗れたものの副大統領に指名され、1988年よりアメリカ大統領となった 1, 2)。 図 ジョージ・ハーバート・ウォーカー・ブッシュ(https://catalog.archives.gov/id/6630729より)
2023年08月04日 -
特集

4.甲状腺機能低下症の鑑別診断と治療
はじめに 甲状腺ホルモンの作用は「代謝の亢進」であり、全身の諸臓器に作用する。甲状腺機能低下症とは、甲状腺ホルモンの作用が不足している状態であり、臨床症状として、全身倦怠感、無気力、動作緩慢、耐寒性の低下、傾眠、体重増加、浮腫、便秘、嗄声、徐脈などを呈する。甲状腺ホルモンは視床下部-下垂体-甲状腺系により制御され、障害部位によって甲状腺におけるホルモン産生・分泌障害に起因する原発性甲状腺機能低下症と、視床下部・下垂体障害による中枢性甲状腺機能低下症に大別される。また重症度により顕性と潜在性に分類され、潜在性甲状腺機能低下症を含めると人口のおよそ10%を占める頻度の高い疾患である。多くは慢性甲状腺炎による原発性甲状腺機能低下症だが、病型や患者背景によって治療目標や治療上の注意点が異なるため、鑑別診断が重要である。 1.検査の組み立て方 甲状腺機能低下症の診断ガイドラインを表1に示す 1)。びまん性の甲状腺腫を認める場合や、甲状腺機能低下症を示唆する症状(易疲労感、耐寒性低下、便秘、体重増加、浮腫、不妊)や一般生化学・生理検査の異常(総コレステロール高値、クレアチンキナーゼ高値、肝機能異常、貧血、徐脈、心拡大など)があれば、遊離サイロキシン(FT4)、甲状腺刺激ホルモン(TSH)を測定する。FT4が低値を甲状腺機能低下症と診断し、同時に測定したTSHが高値なら原発性甲状腺機能低下症、低値~正常値であれば中枢性甲状腺機能低下症と診断する。中枢性甲状腺機能低下症の場合は、他の下垂体前葉ホルモンの分泌異常がないかを確認し、下垂体MRIにより腫瘍や炎症、外傷の有無を評価する。 表1 甲状腺機能低下症の診断ガイドライン(日本甲状腺学会: 甲状腺疾患診断ガイドライン2021(https://www.japanthyroid.jp/doctor/guideline/japanese.html#teika)より)
2023年08月02日 -
特集

3.甲状腺中毒症の鑑別診断と治療
はじめに 甲状腺中毒症の鑑別は、甲状腺摂取率検査が施行できれば比較的容易であるが、施行できる施設は限られている。本稿では、甲状腺摂取率検査が施行できない状況下での鑑別の進め方、特にバセドウ病と無痛性甲状腺炎の鑑別について解説する。甲状腺中毒症の治療に関しては、バセドウ病の抗甲状腺薬(ATD)による治療を中心に解説する。 1.甲状腺中毒症とは 甲状腺中毒症とは、血中の甲状腺ホルモンが過剰になる状態をいう。血中の甲状腺ホルモンが過剰になる原因には二つある。一つは甲状腺ホルモンの合成・分泌が高まった状態(甲状腺機能亢進症)、もう一つは何らかの原因により甲状腺濾胞が破壊され甲状腺ホルモンが漏出する状態(破壊性甲状腺中毒症)である。甲状腺中毒症では、甲状腺ホルモンである遊離サイロキシン(FT4)、遊離トリヨードサイロニン(FT3)が高値になり、甲状腺刺激ホルモン(TSH)は低値となる。FT4・FT3は正常だがTSHが低値の状態を潜在性甲状腺中毒症という。
2023年07月28日 -
セミナー

神経内分泌による行動制御とストレス
はじめに ストレスは食欲や睡眠といった生理現象に大きな影響を与え、行動面での変化にもつながる。こうした生理応答や行動変容においては、ストレスによって脳内で分泌される神経ペプチドが重要な役割を果たしている。ここでは、①神経内分泌とは何か、②神経内分泌はどのように生理現象や行動を制御しているのか、③ストレスによる神経内分泌の変化はどのような生理応答・行動変容をもたらすのか、の3点について解説する。脳内で分泌される神経ペプチドは100種類を超えるが、ここでは、オレキシン、オキシトシン、バソプレシン、コルチコトロピン放出ホルモン(CRH)など視床下部の神経分泌細胞によって分泌されるいくつかの神経ペプチドに絞って説明する。 1.神経内分泌とは何か? 脳は重要な内分泌器官であり、そして体内で分泌されたホルモンの重要な標的器官でもある。内分泌器官はホルモンを分泌し、分泌されたホルモンは血液や体液を介して遠方の細胞に作用する。視床下部にある神経分泌細胞はニューロンの形態を持ちながら、ホルモンとして作用する物質を分泌している。この神経分泌細胞による制御、さらに自律神経による内分泌制御を含めたシステムが、神経内分泌制御である。神経分泌細胞が産生するホルモンとして、具体的には各種の神経ペプチドが挙げられる。ヒトゲノムには90種類を超える神経ペプチド前駆体をコードする遺伝子が知られており、100種類を優に超える神経ペプチドが体内で分泌されている 1)。ここでは視床下部で産生されるいくつかの神経ペプチドを主に解説する。 オレキシン(orexinもしくはhypocretin)は、視床下部の外側野で産生される33(orexin-A)もしくは28のアミノ酸(orexin-B)からなる神経ペプチドで、主に睡眠・覚醒の制御における機能が知られている 2)。オキシトシン(oxytocin)は視床下部の室傍核および視索上核で産生される9アミノ酸からなる神経ペプチドで、社会行動の制御に関与している 3)。バソプレシン(arginine vasopressin:AVP)も視床下部の室傍核および視索上核で産生される9アミノ酸からなる神経ペプチドで、攻撃行動の制御などに関与している 4)。オキシトシンとバソプレシンの違いはわずか2アミノ酸であり、元々は共通の遺伝子から派生したものと考えられている。こうした神経ペプチドを産生するニューロンは、脳内のさまざまな領域に軸索を伸ばしており、神経ペプチドの分泌は広範囲に及ぶ。脳内で働く神経伝達物質としては、グルタミン酸やGABAなどがよく知られているが、これらは軸索末端のシナプス近傍で局所的に放出され、放出後すぐに分解されてしまう。一方、神経ペプチドが分泌されるのは軸索末端のシナプスだけには限らず、細胞体や樹状突起でも分泌される。さらに、神経ペプチドは脳内での半減期が比較的長く(例えば、オキシトシンの脳内での半減期は20分程度)、分泌部位から離れた脳領域にある受容体にも作用し得る。
2023年07月24日 -
特集

2.甲状腺機能検査を知る
はじめに 甲状腺機能検査は、主に血清のTSH値と血清甲状腺ホルモン値、特に遊離T4(FT4)値によって評価される。病態によっては、遊離T3(FT3)値も有用な場合がある。血清TSH値や血清甲状腺ホルモン値の測定にはさまざまなキットが使用され、そのキットごとに使用する測定機器も異なる。それぞれのキットには特性があり、また種々の因子が測定値に影響を及ぼす。本稿では、主に最近の筆者らの研究から得られた結果をもとに、これらの因子について概説する。 1.甲状腺機能の評価法と疾患の診断基準 甲状腺機能の評価は通常、血清TSH値とFT4値によって決定される(図1)。基本的には、両者が共に基準値範囲内であれば甲状腺機能正常、血清TSH値低値・FT4値高値であれば顕性甲状腺亢進症(中毒症)、一方、血清TSH値高値・FT4値低値であれば顕性甲状腺機能低下症と判断する。 また、血清TSH値は測定系が高感度であるため、血清FT4値よりも鋭敏に甲状腺機能を反映し、血清FT4値が基準値内でありながら血清TSH値のみが異常値を示す病態の潜在性甲状腺機能異常症が診断される。血清FT4値が基準値内で血清TSH値のみ上昇した状態を潜在性甲状腺機能低下症、逆に血清TSH値のみが低下した病態を潜在性甲状腺機能亢進症(中毒症)と診断する。 図1 甲状腺機能評価と疾患(筆者ら作成)
2023年07月20日 -
セミナー

多職種連携による肥満治療の効果的な動機付け
Q&A編はこちら はじめに 近年、飽食の時代の到来ともにわが国でも肥満人口が増加し、内臓肥満を基盤に複数の生活習慣病が集積するメタボリックシンドローム(MetS)が予備群合わせて、成人男性の2人に1人、女性の5人に1人にのぼる 1)。国内外の疫学研究より、MetSの危険因子が重積するほど心血管病(CVD)リスクが上昇し、脳卒中、CVDや慢性腎臓病(CKD)の発症率が有意に高くなることが示された 2, 3)。糖尿病においても肥満が原因で発症する患者が急増していたため 4)、当院の糖尿病センターでは、2001年に「肥満・運動療法外来」を開設し、2004年以降は「肥満・メタボリック症候群外来」と改称して、22年にわたり、肥満を専門とした生活習慣病の診療を行ってきた。本稿では、22年来の多職種連携による肥満・メタボ診療の経験に基づいて、効果的な肥満治療の動機付けについて概説する。 1.日本人肥満症の実態―国立病院機構多施設共同研究の成績から― 国民健康づくり運動「健康日本21」の最終報告では、日常生活の歩数や肥満者の割合などの目標値に対する達成状況が非常に悪く、肥満者の「生活習慣の是正」や「減量すること」の難しさがうかがえる。われわれが2006年より構築してきた国立病院機構(NHO)多施設共同肥満症コホート(NHO Japan Obesity & Metabolic Syndrome Study:JOMS〔図1〕)ではMetS危険因子が重積するほど高感度CRPや動脈硬化指標(CAVI)などのCVDリスクやCVDイベントが有意に上昇することを認めた 5, 6)。また、3カ月の減量治療でもCVDやCKDリスクが有意に改善しており(図2) 5~7)、減量治療の重要性が示されたが、日本肥満学会の肥満症診療ガイドライン2022では、減量目標は3~6カ月で現体重の3%減と明記されている 8)。一方、われわれのNHO-JOMSコホートにおける5年の追跡調査では、MetS・CVDリスクの改善には長期では7%以上の減量が必要であることが示された 9)。 図1 国立病院機構(NHO)肥満症ネットワーク研究 わが国のメタボリックシンドロームにおける減量効果に関する多施設共同研究 2006~2011年
2023年07月11日 -
特集

1.甲状腺疾患診療の基礎知識
はじめに 甲状腺疾患の特徴は、甲状腺腫と甲状腺機能異常に基づく多彩な症状を呈することである。表1は、種々の甲状腺疾患を甲状腺腫(びまん性または結節性)の有無と甲状腺機能によって分類したものである。それぞれの疾患の詳細は各論を参照されたい。 表1 種々の甲状腺疾患の甲状腺機能と甲状腺腫 画像をクリックすると拡大します 表1 種々の甲状腺疾患の甲状腺機能と甲状腺腫 $(".vol4_t1_01").modaal(); 1.甲状腺疾患の頻度 甲状腺疾患は、頸部の腫れや甲状腺機能異常の症状で自ら医療機関を受診し診断される場合と、検診や人間ドックで無症状(または有症状と自覚していない)ながらも医師によって甲状腺ホルモン疾患が疑われて検査・診断される場合がある。したがって、頻度を考える場合は、母集団の選び方によるバイアスを考慮しなければならない。たとえば、ドックによる検出では、有症状ですでに医療機関を受診している集団があらかじめ除外されている可能性がある。逆に、潜在性の甲状腺機能異常症はドックや健診でないと見過ごされてしまう。そのことを意識しながら以下の統計を参考にされたい。 1)甲状腺機能異常の頻度 (1)人間ドック ある施設の調査では、2,074人中、顕性甲状腺機能低下症0.5%、潜在性甲状腺機能低下症4.7%、顕性甲状腺機能亢進症0.4%、潜在性甲状腺機能亢進症0.8%で、抗サイログロブリン抗体(TgAb)陽性9.5%、抗甲状腺ペルオキシダーゼ抗体(TPOAb)陽性16.0%であった 1)。別の施設の調査では、1,818人中、顕性甲状腺機能低下症0.7%、潜在性甲状腺機能低下症5.8%、顕性甲状腺機能亢進症0.7%、潜在性甲状腺機能亢進症2.1%であった。TgAbまたはTPOAbがいずれか陽性は、男性で17.7%、女性で31.4%であった 2)。
2023年07月06日 -
特集

(扉)特集にあたって
甲状腺疾患は内分泌疾患の中での頻度は高いものの、甲状腺ホルモン測定が一般血液検査に含まれない特殊検査であるため、疑って測定しない限りは診断に至りにくい現状がある。そこで、日常診療において甲状腺疾患の可能性を想起するために必要な基礎知識として、甲状腺疾患の頻度、甲状腺疾患を疑うべき症状、見逃さないポイントを京都医療センター 田上哲也先生に解説していただいた。次に、甲状腺機能検査を行った際の評価の注意点、性別や年齢別の評価、偽高値を疑うポイントを群馬大学 山田早耶香先生・堀口和彦先生・山田正信先生に最新の知見を交えてご紹介いただいた。 甲状腺ホルモンが過剰な状態は、全身にさまざまな症状を引き起こす。しかしその原因疾患によって治療法が異なる。教科書には鑑別診断における甲状腺摂取率検査(シンチグラフィ)の重要性が記載されている。しかし、本検査は実施が難しい施設が多いため、その観点から検査の組み立て方、治療法について田尻クリニック 濱田勝彦先生に紐解いていただいた。甲状腺ホルモンが不足する機能低下症についても、検査の組み立て方、原発性と中枢性甲状腺機能低下症、補充療法の仕方や治療の指標について長崎大学病院 中嶋遥美先生、放射線影響研究所 今泉美彩先生に項目を分けて提示いただいた。 頸部超音波にて甲状腺内に結節を認めた際には、対応に戸惑うことがあるかと思われる。甲状腺外科の立場から超音波検査での良悪性の判断、穿刺吸引細胞診を施行する基準、細胞診の実際、病理組織分類、手術適応について伊藤病院 北川 亘先生に図表豊富に指南していただいた。 甲状腺機能異常は妊娠可能年齢の女性に多いことから、妊娠との関連については診療ではよく尋ねられると思われる。甲状腺疾患を持つ女性における妊娠・出産での留意点について国立成育医療研究センター 荒田尚子先生にガイダンスをお願いした。 今回の特集は甲状腺疾患診療において第一線でご活躍の先生方に執筆いただいた。日々の診療に、実践的に活かせるエッセンスが詰まっている。日常の診療の中で甲状腺疾患を疑い、不安なく診断・治療へとつなげる一助になることを願ってやまない。 著者のCOI (conflicts of interest)開示:本論文発表内容に関連して特に申告なし 本論文のPDFをダウンロードいただけます
2023年07月06日 -
連載

第66回 糖尿病の内服薬2022
はじめに 厚生労働省の2013年度から2017年度の調査 1)によると、SU薬(スルホニル尿素薬)、α-GI(α-glucosidase inhibitor:α-グルコシダーゼ阻害薬)、チアゾリジン薬の薬剤料は減少傾向であるが、BG薬(ビグアナイド薬)、速効型インスリン分泌促進薬、GLP-1受容体作動薬(Glucagon-like peptide-1受容体作動薬)、DPP-4阻害薬(選択的Dipeptidyl peptidase-4阻害薬)、 SGLT2阻害薬(選択的Sodium glucose cotransporter-2阻害薬)、糖尿病配合薬の薬剤料は、徐々に増加傾向である。そして2017年度の血糖降下薬の薬剤料 1)は総額4,271億円であり、その内訳は、DPP-4阻害薬が1,873億円、インスリン製剤が624億円、SGLT2阻害薬が493億円、配合薬が357億円、α-GIが259億円である。そして糖尿病市場規模の予測は、2022年度は6,810億円、2025年度は7,000億円を突破すると予測される 2)。 このような現状の糖尿病治療薬について、2022年12月の薬価基準収載品目リスト 3)を中心に、今回は糖尿病と合併症が適応の内服薬の種類や効能・効果 4, 5)、および薬剤の処方に係る診療報酬の算定 6~9)について概説する。各医薬品の詳細については、本誌の各特集などを参考にされたい。 1.インスリン分泌促進薬SU薬、速効型インスリン分泌促進薬、DPP-4阻害薬、経口GLP-1受容体作動薬およびイメグリミンについて(表1~4) 表1に示すように、SU薬は第1世代、第2世代、第3世代に分けられる。効能・効果は、食事・運動療法のみで十分な効果が得られない場合の、第1・第2世代では「インスリン非依存型糖尿病」、第3世代では「2型糖尿病」である。そしてグリベンクラミドとグリクラジドの後発品は「外来後発医薬品使用体制加算」の算定対象となる。 表1 SU薬(スルホニル尿素薬)について(文献3~5より) 画像をクリックすると拡大します 表1 SU薬(スルホニル尿素薬)について(文献3~5より) $(".vol3_r13_01").modaal();
2023年06月29日 -
セミナー

骨粗鬆症~治療薬の適正使用推進・リスク薬剤の共有に向けて~
Q&A編はこちら はじめに 骨粗鬆症治療の目的は、骨折を予防しQOLの維持・向上を目指すことにある。骨粗鬆症では一度骨折を起こすと次々と骨折を起こすようになるため、一次骨折(最初の脆弱性骨折)を予防することが肝要であるが、二次骨折(既存骨折がある患者で新たに起こった骨折)を予防することも重要である。 二次骨折を予防するための取り組みである骨折リエゾンサービス(Fracture Liaison Service:FLS)は1990年代後半にイギリスで開始され、以降、世界の国々で発展している。日本では骨粗鬆症による脆弱性骨折防止のための取り組みとして骨粗鬆症リエゾンサービス(Osteoporosis Liaison Service:OLS)が展開されているが、特に脆弱性骨折患者における二次骨折予防に対しては重点的な対策が必要であることから、2019年に「日本版 二次骨折予防のための骨折リエゾンサービス(FLS)クリニカルスタンダード」(FLSクリニカルスタンダード作成ワーキンググループ)が策定された。また、2022年4月の診療報酬改定では大腿骨近位部骨折患者の二次骨折予防に対する取り組みを評価した「二次性骨折予防継続管理料」が新設 1)されたことから、今後FLSに対する取り組みがより一層広がっていくと考えられる。 今回は、骨粗鬆症を治療する観点から各薬剤の特長・使用上の注意について再確認していくとともに、骨粗鬆症を予防する視点から骨粗鬆症のリスクや転倒のリスクとなる薬剤について紹介する。 1.骨粗鬆症治療薬 「骨粗鬆症の予防と治療ガイドライン2015年版」 2)では、各薬剤の「骨密度上昇効果」「椎体骨折抑制効果」「非椎体骨折抑制効果」「大腿骨近位部骨折抑制効果」についてエビデンスに基づいて評価されている(表1)。 以下に一部の薬剤について特長と使用上の注意点について述べる。 表1 骨粗鬆症治療薬の有効性の評価一覧(文献2より) 画像をクリックすると拡大します #1:骨粗鬆症は保険適用外 #2:疼痛に関して鎮痛作用を有し、疼痛を改善する(A)骨密度上昇効果A:上昇効果があるB:上昇するとの報告があるC:上昇するとの報告はない骨折発生抑制効果(椎体、非椎体、大腿骨近位部それぞれについて)A:抑制するB:抑制するとの報告があるC:抑制するとの報告はない 表1 骨粗鬆症治療薬の有効性の評価一覧(文献2より) #1:骨粗鬆症は保険適用外 #2:疼痛に関して鎮痛作用を有し、疼痛を改善する(A)骨密度上昇効果A:上昇効果があるB:上昇するとの報告があるC:上昇するとの報告はない骨折発生抑制効果(椎体、非椎体、大腿骨近位部それぞれについて)A:抑制するB:抑制するとの報告があるC:抑制するとの報告はない $(".vol3_k9_01").modaal();
2023年06月23日 -
特集
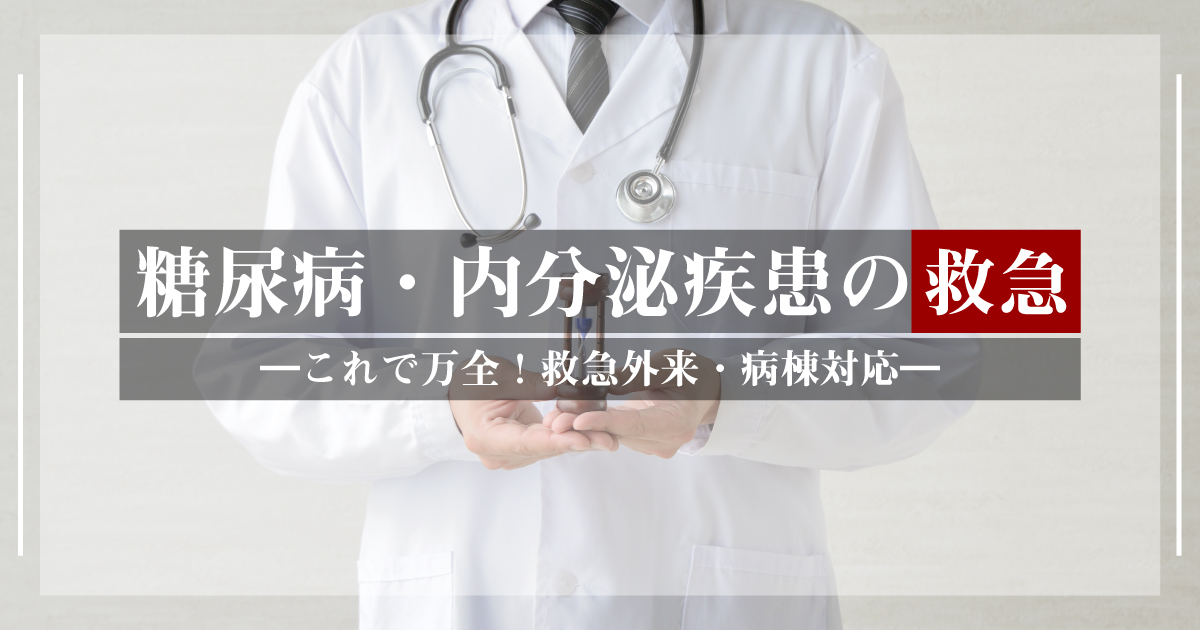
7.カルシウム代謝と緊急症―高/低Ca血症の鑑別診断と緊急時対応のポイント
はじめに 血清Ca濃度は、i)腸管からのCa吸収、ii)骨吸収によるCa動員、および iii)腎尿細管でのCa再吸収で規定され、共用基準範囲は8.8~10.1mg/dLである。このうち生理作用に関わるのは約50%を占める遊離イオン化Caだが、血清蛋白の影響を受けるため、アルブミン濃度が4.0mg/dL未満では以下のように補正して評価する。 補正Ca濃度(mg/dL)=実測Ca濃度(mg/dL)+〔4 -血清アルブミン濃度(g/dL)〕 軽度で緩徐な基準範囲の逸脱は気付かれないことが多い。一方、症状を伴う血清Caの異常値は適切な対応を必要とする緊急症である。 1.高Ca血症 1)症状・症候 軽度の高値や慢性経過例では、ほとんど自覚症状がないか、食欲不振や易疲労感、便秘などの非特異的症状であり気付かれにくい。尿濃縮障害による低張性多尿が存在するため、脱水症になりやすく、尿Ca排泄量が低下すると血清Caが上昇し、記憶障害や傾眠などの中枢神経障害に至る。表1に高Ca血症の症候を示す 1)。 表1 高Ca血症の主要症候(文献1より) 2)病態生理 血清Ca濃度は、主に副甲状腺ホルモン(parathyroid hormone:PTH)と活性型ビタミンD(1α, 25(OH)2 vitamin D)によって恒常性が維持されている。これらの液性因子が標的臓器に作用し、腸管からのCa吸収、破骨細胞を介する骨吸収によるCa動員および腎からのCa再吸収による体内Ca増加量が、腎排泄量を上回ると高Ca血症に至る。高Ca血症では腎近位尿細管のヘンレループ上行脚のCa感知受容体が活性化され、抗利尿ホルモン(antidiuretic hormone:ADH)作用とCa再吸収が抑制される。この結果、尿量および尿中Ca排泄が増加し、短期的には高Ca血症に対し抑制的に作用する。しかし二次性の腎性尿崩症による多尿は脱水症を招き、体液喪失により尿量が低下すると腎Ca排泄低下がさらに低下し血清Caが急激に上昇する悪循環に至る。
2023年06月19日 -
特集
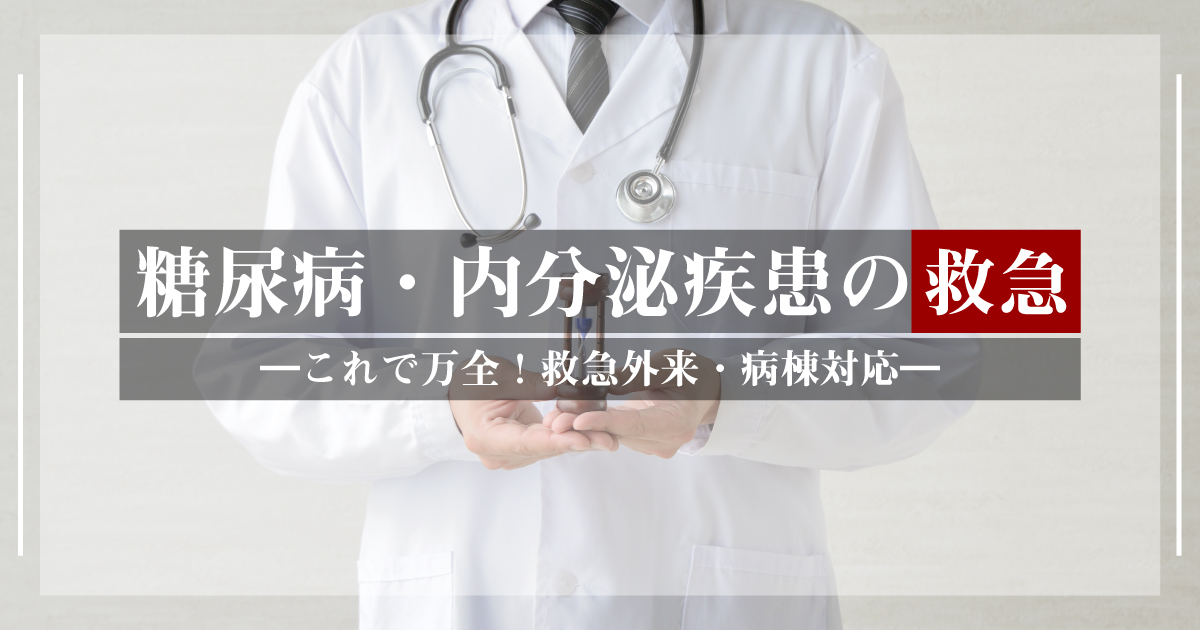
6.カリウム代謝と緊急症―高/低K血症の鑑別診断と緊急時対応のポイント
はじめに ナトリウムイオン(Na+)が細胞外液の主要な陽イオンであるのに対し、カリウムイオン(K+)は細胞内液の主要な陽イオンである。全身のK貯蔵量は約3,000mEq(50~75mEq/kg体重)であり、細胞内にはこの約98%が存在することになる。細胞内K濃度は約150mEq/L、また細胞外は約3.5~5.5mEq/Lであり、この濃度勾配が細胞の静止膜電位の最重要形成因子である 1)。これは細胞膜に存在するNa-K-ATPaseにより、能動的に細胞内へ2つのK+を取り込み、細胞外へ3つのNa+を放出することによって成立している。静止膜電位は正常な神経・筋の機能に不可欠な活動電位発生に寄与しており、細胞外K濃度が低くなると静止膜電位はより陰性になり(=過分極)、細胞外K濃度が高くなると静止膜電位は陰性が減弱する(=脱分極)。この変化に最も影響を受ける臓器は筋肉と心臓であり、低K血症と高K血症は共に麻痺、痙攣、あるいは致命的な不整脈を引き起こし得る。ここではその診断と緊急時の対応について述べることとする。 1.体内のカリウム調節機構 Naと違い、細胞外液のK濃度は約4mEq/Lと低い濃度にコントロールされており、Kの摂取はその濃度の急上昇につながりかねない。そのため、体内にはいくつかのカリウム調節機構が存在する。急性調節機構(分単位)として細胞内Kシフトを行い、慢性調節機構(時間単位)として腎臓あるいは腸管からK排泄を行っている。そのため、低K血症あるいは高K血症はこれらの調節機構に異常をきたした場合に発症する。 細胞内Kシフトには主に3つの関連因子が存在し、それはインスリン、β2カテコールアミン(甲状腺ホルモン)、および酸塩基平衡異常である。インスリンは細胞膜上のインスリン受容体に結合することでNa/H交換輸送体が活性化して細胞内Na濃度が上昇し、そのためNa-K-ATPaseが活性化されKの取り込みが亢進する。インスリンと同様に、β2カテコールアミン(および甲状腺ホルモン)は骨格筋のNa-K-ATPaseを活性化し、Kの取り込みを亢進する。また、β2カテコールアミン受容体は内向きのNa-K-2Cl共輸送体も活性化し、カテコールアミンに対するK取り込み反応の3分の1を占めると考えられている 2)。酸塩基平衡異常に関して、まず代謝性アルカローシスにおいては電気的中性を維持するために細胞内からH+が細胞外に移行し、Na/H交換体が活性化し、Na-K-ATPaseが活性化されK+の取り込みが亢進する(=低K血症をきたす)。代謝性アシドーシスにおいてはその原因によりK+の移動が異なる。尿細管アシドーシス(RTA)や下痢などに代表される無機酸アシドーシス(すなわちアニオンギャップ非開大性代謝性アシドーシス)では、H+に伴う陰イオン(Cl- など)が細胞内に取り込まれず、H+のみが細胞内に入るために、代わりにK+が細胞外に移動する(=高K血症をきたす)。しかしながら乳酸アシドーシスや糖尿病性ケトアシドーシス(DKA)に代表される有機酸アシドーシス(すなわちアニオンギャップ開大性代謝性アシドーシス)では、その有機アニオンがH+を伴って細胞内に入るため、K+の移動はきたさない。この移動にはNa-有機アニオン共輸送体(sodium-organic anion cotransporter)の関与が論じられている 3)。呼吸性の酸塩基平衡異常に関しては、その血清K変動は極めて小さいことが報告されているが 4)、メカニズムはよく分かっていない 3)。 次に主な慢性調節機構である腎臓でのカリウム排泄について簡単に述べる。糸球体で濾過されたK+はそのほぼ全てが近位尿細管とヘンレループの上行脚で再吸収されるため、排泄されるK+は遠位尿細管から主に皮質集合管の主細胞から分泌されたものに由来する 5)。そのため、腎臓におけるカリウム排泄には皮質集合管における3つの因子が重要とされ、図1に示す。1つ目が皮質集合管腔における非吸収性陰イオンの存在で、皮質集合管腔に多くの陰イオン(HCO3-や一部のケトン体など)があると、これに引っ張られてK+分泌が増加する。2つ目がアルドステロン作用で、図1のようにアルドステロンはENaC(アミロライド感受性上皮型Naチャンネル)、ROMK1、およびNa-K-ATPaseのそれぞれの発現数を増加させ活性化して尿中へのK排泄を増加させる 6~8)。3つ目が皮質集合管への十分なNaと水の到達することであり、皮質集合管へのNaの十分な到達(distal Na delivery)は、ENaCでの十分なNa再吸収とこれに伴うROMK1でのK排泄に関与しており、十分な水の到達は尿流の増加によってK分泌を促進するbig K+ channel(BK)に関与する。
2023年06月15日 -
セミナー
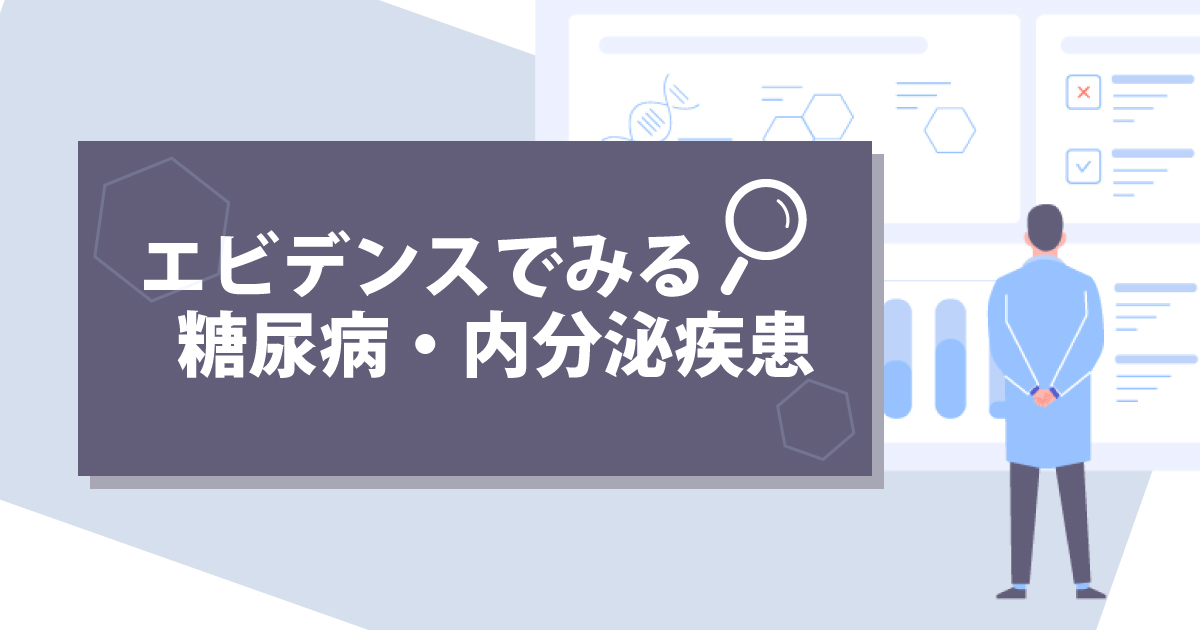
褐色細胞腫の診療―褐色細胞腫・パラガングリオーマの検査と治療の最新エビデンス―
1.ポイント ・約90%は副腎に発生する褐色細胞腫、約10%は傍神経節に発生するパラガングリオーマである。・転移・再発の予測が極めて困難であり、転移の可能性がある腫瘍に分類されている。全例で生涯にわたる再発・転移の経過観察が必要である。・診断において、カテコールアミンと比べてカテコールアミン代謝産物であるメタネフリン・ノルメタネフリンの感度・特異度が高い。・転移性褐色細胞腫・パラガングリオーマ(pheochromocytoma/paraganglioma:PPGL)の根治治療はいまだ存在しない。カテコールアミン過剰症状のコントロール、無増悪生存期間の延長を目標として集学的治療を行う。 2.総論 PPGLはクロム親和性細胞から発生する腫瘍である。約90%の症例で腫瘍がカテコールアミンを産生し、発作性の高血圧、頭痛、動悸などの症状を呈する。高カテコールアミン血症を放置すると致死性不整脈や冠動脈攣縮、高血圧クリーゼを発症し突然死の危険があるため、早期診断、早期治療が必要である。 PPGLの約90%は副腎に発生し褐色細胞腫、約10%は傍神経節に発生しパラガングリオーマ(傍神経節細胞腫)と称される。副腎原発の約10%、パラガングリオーマの約10~30%が局所浸潤や遠隔転移をきたすが(図1)、生化学的あるいは病理学的に転移・再発の予測が極めて困難である。このため2017年改訂のWHO内分泌腫瘍分類 1)以降は、全例が転移・再発の可能性を有する腫瘍であると定義され、良性悪性の分類がなくなった。全例で生涯にわたる再発・転移の経過観察が必要である。 図1 本邦における原発腫瘍の局在と転移の有無 厚生労働省難治性疾患克服研究事業「褐色細胞腫の実態調査と診療指針の作成研究班」(研究代表者 成瀬光栄)による全国調査結果褐色細胞腫の実態調査と診療指針の作成 研究報告書より作図総症例数1108例 診断のために、画像検査でPPGLを示唆する腫瘍を確認するか、摘出した腫瘍の病理検査でPPGLに特徴的な所見を確認し、加えてカテコールアミン過剰を確認する 2)。PPGL診断において、アドレナリン・ノルアドレナリンと比べてカテコールアミン代謝産物であるメタネフリン・ノルメタネフリンの感度・特異度が高いことが報告されている。 診断が確定したら交感神経α遮断薬およびβ遮断薬による高血圧、頻脈治療を開始し、摘出可能な腫瘍は速やかに外科的摘出術を施行する。転移例や切除困難例は化学療法や131I-MIBG内用療法、骨転移巣の疼痛・骨折予防のための放射線外照射などが施行される。
2023年06月13日 -
特集
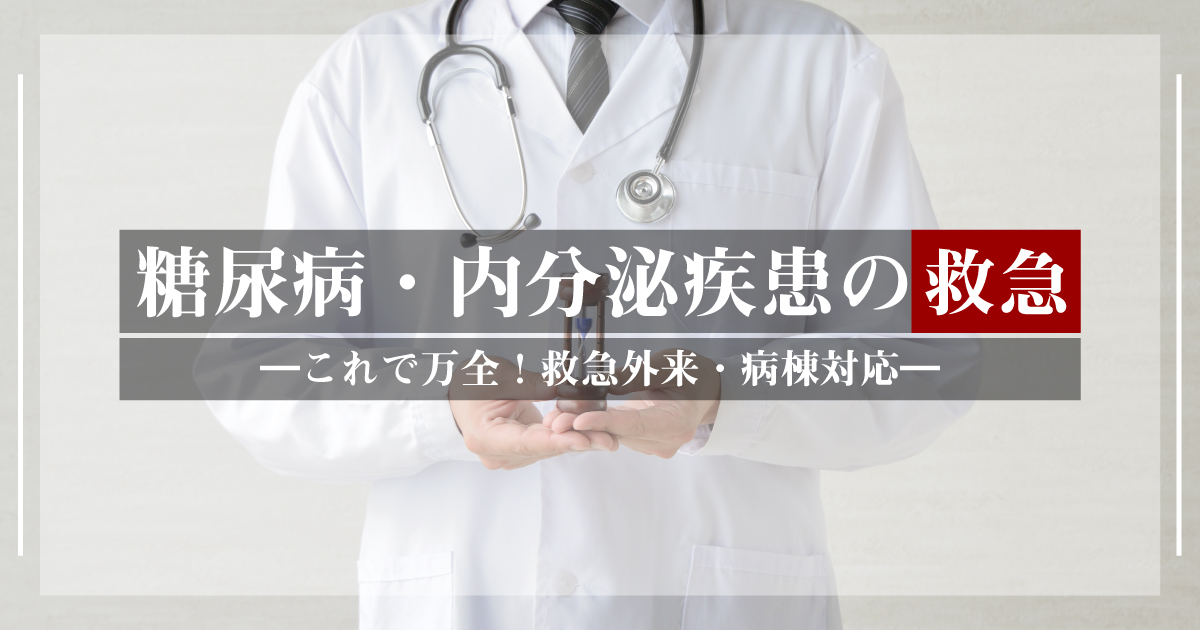
5.ナトリウム代謝と緊急症―高/低Na血症の鑑別診断と緊急時対応のポイント
はじめに 血清ナトリウムの異常は最も頻度の高い電解質異常である。本稿では、低ナトリウム血症と高ナトリウム血症の病態、症状、鑑別診断、治療について、原因となる代表的な内分泌疾患とともに述べる。 1.低ナトリウム血症 1)病態 血清ナトリウム濃度は総ナトリウム量と細胞外液量によって規定され、低ナトリウム血症は血液中のナトリウムの量より水分の量が相対的に多くなっている病態である。低ナトリウム血症は、細胞外液量減少、細胞外液量ほぼ正常(ないし軽度増加)および細胞外液量増加に伴うものの3つに分類される。細胞外液量の減少を伴う低ナトリウム血症では、腎性もしくは腎外性のナトリウム喪失により二次的に細胞外液量が減少するため、脱水所見が認められる。腎性ナトリウム喪失は、利尿薬投与、塩類喪失性腎症、原発性副腎皮質機能低下症などが、腎外性ナトリウム喪失は、嘔吐・下痢、熱傷、急性膵炎などが原因となる。細胞外液量がほぼ正常な低ナトリウム血症には、抗利尿ホルモン不適合分泌症候群(syndrome of inappropriate secretion of antidiuretic hormone:SIADH)、続発性副腎皮質機能低下症が含まれる。細胞外液量の増加を伴う低ナトリウム血症は、うっ血性心不全、肝硬変、ネフローゼ症候群などであり、有効循環血漿量はむしろ低下しているため腎臓でのナトリウムと水の再吸収が増加するが、総ナトリウム量の増加を上回る水貯留のため希釈性低ナトリウム血症をきたす。 2)症状 低ナトリウム血症では脳浮腫による中枢神経症状を呈するが、その症状は低ナトリウム血症の程度と進行速度によって異なる。血清ナトリウム濃度が120mEq/L以上では全身倦怠感、頭痛、食欲低下などの症状にとどまることが多いが、110mEq/L以下になると意識障害や痙攣、昏睡を呈し、さらには脳浮腫による脳ヘルニアを合併することもある。一方で、低ナトリウム血症が急速に進行する症例では、血清ナトリウム濃度が120mEq/L程度であっても、意識障害などの重篤な症状を呈することがある。逆に慢性の経過では、重度の低ナトリウム血症でも無症状から軽度の症状であることが多い。 3)鑑別診断 細胞外液量の評価を行い、細胞外液量減少、細胞外液量ほぼ正常(ないし軽度増加)および細胞外液量増加に伴う低ナトリウム血症を鑑別するが、実臨床では低ナトリウム血症の鑑別診断は困難を伴うことが多く、特に細胞外液量の減少とほぼ正常との間の鑑別が問題となる。細胞外液量減少を示唆する所見として、口腔粘膜乾燥、皮膚ツルゴール低下、体重減少、血圧低下・頻脈、BUN/Cr比上昇、血清尿酸値上昇などが知られているが、実際には治療前には確定的な診断には至らず、治療に対する反応を振り返りながら治療後に鑑別していく症例も少なくない。
2023年06月08日 -
特集
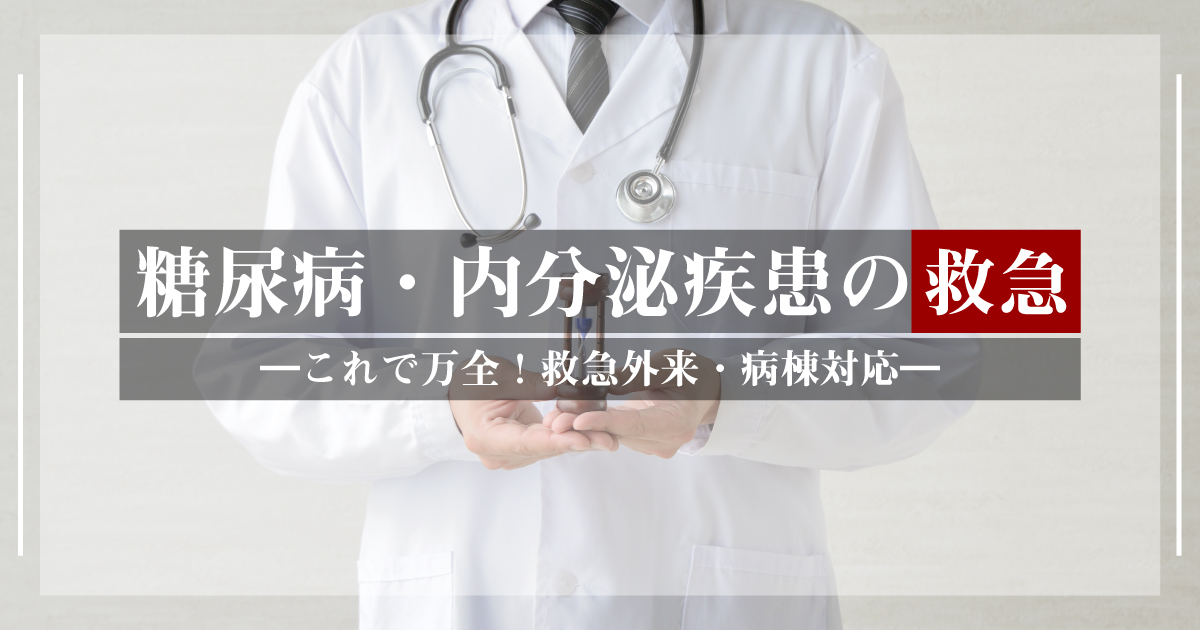
4.甲状腺疾患による緊急症―甲状腺クリーゼと粘液水腫性昏睡
はじめに 甲状腺クリーゼと粘液水腫性昏睡は、甲状腺疾患(主にバセドウ病や橋本病)を基盤に発症する致死的な内分泌緊急症(死亡率は前者が約10%、後者が約30%)であり、的確な早期診断と迅速な集学的治療の開始が患者の生死を左右する。しかしながら、両緊急症の疫学的データの不足により、2005年ごろに診断基準や治療指針が国際的にも未確立であった経緯があり、日本甲状腺学会は両緊急症の診断基準と治療指針の作成を臨床重要課題に指定した(甲状腺クリーゼは日本内分泌学会でも指定)。甲状腺クリーゼは、全国疫学調査で収集した臨床データをもとに診断基準と治療指針が作成され、「甲状腺クリーゼ診療ガイドライン2017」として刊行されている 1)。粘液水腫性昏睡は、日本甲状腺学会員を対象とした2008年の実態調査により収集した臨床データをもとに診断基準第3次案と治療指針案が作成・公表されている。両緊急症ともに死亡率が高く、緊急治療が必要な病態であるため、救急医・一般内科医・循環器内科医などの非甲状腺専門医が初期診療にあたるケースが多い。そのため、救急診療に携わる医療従事者は本症の診断や治療法についてよく理解しておくことが重要である。本稿では両緊急症の診断基準と治療指針を中心に概説する。 1.甲状腺クリーゼ 1)病態 甲状腺ホルモン過剰症(甲状腺中毒症)の原因となる未治療もしくは管理不良な甲状腺基礎疾患(主にバセドウ病)のある患者に、感染症や手術などの種々のストレスが加わり、甲状腺ホルモン作用の過剰に対する生体の代償機構が破綻して多臓器不全に陥った緊急病態である。 2)疫学と発症の誘因 本邦における全国疫学調査の結果、本症の発症率は年間入院患者10万人あたり0.2人であった 2)。発症の誘因としては、バセドウ病患者における服薬コンプライアンスの不良や治療の自己中断が最も多い。これらの原因の根底には病識の欠如があるため、「治療をおろそかにするとクリーゼに陥る危険性がある」ことを、バセドウ病患者へ指導するべきである。他に感染症(特に上気道炎、肺炎)、外傷、手術、妊娠・分娩、種々の急性疾患(糖尿病ケトアシドーシス、副腎不全、虚血性心疾患、脳血管障害、肺血栓塞栓症など)も誘因として知られている。 3)症状 多臓器不全による全身性症候、臓器症候に加え、甲状腺関連の局所症候を認める。全身性症候として、発熱・頻脈・不整脈(特に心房細動)・多汗・ショック・体重減少などが、臓器症候として、不穏・せん妄・傾眠などの中枢神経症状、肺水腫や心原性ショックなどの心不全を中心とした循環器症状、下痢・嘔吐などの消化器症状がある。局所症候としては、甲状腺腫大や甲状腺眼症などが特徴的である。
2023年06月06日 -
セミナー
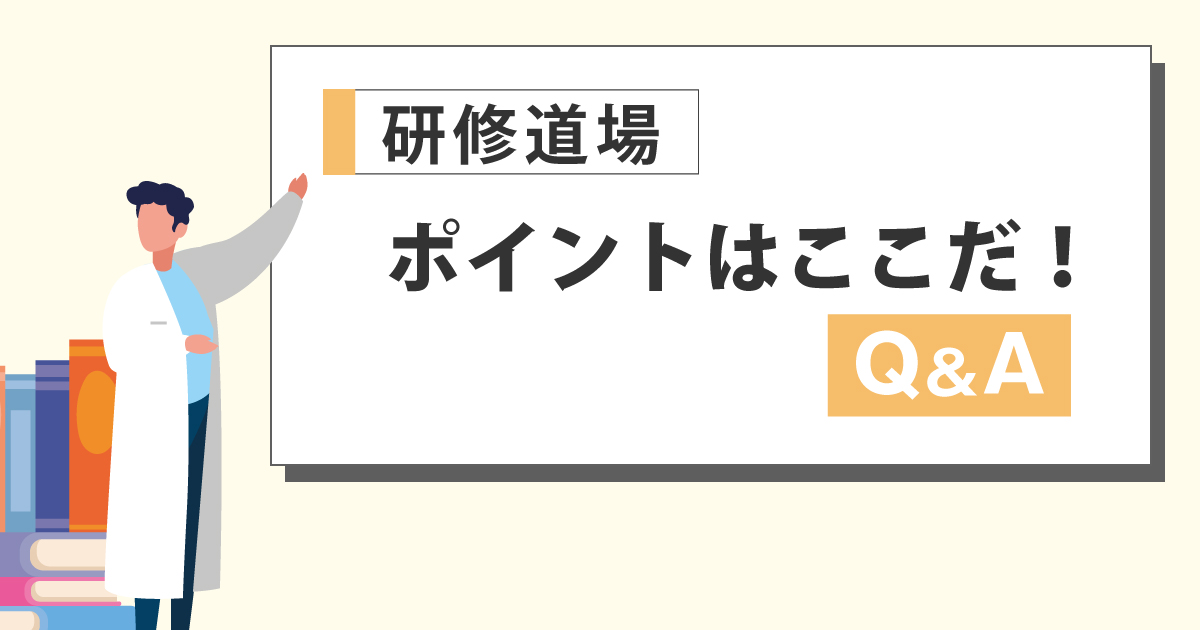
1型糖尿病の治療選択肢(インスリンポンプや持続血糖測定器など)
Q&A編はこちら 2023年7月31日に訂正した。訂正内容については、下記を参照されたい。https://practice.dm-rg.net/correction/0103_a0044 はじめに インスリン発見から100年の時を経て、近年のインスリン製剤やデバイスは著しい進化を遂げている。インスリン製剤やデバイスの組み合わせによって治療法にも選択肢が増え、1型糖尿病においてもオーダーメイド医療が意識されるようになってきた。血糖コントロールは、食事、運動量、ストレスなど、生活のすべてが影響する。患者のライフスタイルに合わせた治療法を提案するためには、インスリン製剤やデバイス類に精通し、それぞれのメリット・デメリットを把握しておく必要がある。本稿では、現在本邦で行うことのできる1型糖尿病の治療法についてデバイスを中心に述べる。 1.インスリン療法 1)強化インスリン療法 1990年代に1型糖尿病患者を対象として、強化インスリン療法による厳格な血糖コントロールが細小血管障害の発症および進展予防になるか検討したDCCT/EDIC(The Diabetes Control and Complications Trial)の結果が公表された。これによると、強化インスリン療法(ペン型注入器を用いた1日3回以上のインスリン頻回注射療法[Multiple Daily Injection:MDI]またはインスリンポンプを用いた持続皮下インスリン注入[Continuous Subcutaneous Insulin Infusion:CSII]療法)による厳格な血糖管理が従来の1日1~2回のインスリン療法と比較してHbA1cの改善や細小血管障害の発症・進行抑制に有効であることが示された 1)。以降、1型糖尿病の治療の主流は強化インスリン療法である。 2)MDI療法 vs. インスリンポンプ療法 MDI療法とCSII療法を比較した試験結果はいくつも発表されているが、いずれもDCCT/EDICほど厳密ではなく、小規模で短期間のものが多い。しかしながら、これらの研究結果のメタ解析やシステマティックレビューによると、CSII療法はMDI療法よりもHbA1cを-0.3%(95%信頼区間-0.58~-0.02%)改善させ、重症低血糖を減らしたと報告されている 2)。ただし、CSII療法の優位性はわずかなものであり、米国糖尿病学会(ADA)のガイドラインでもどちらを選択するべきかは各個人の状況に応じて決定するべきと結論付けている 3)。 しかしながら、MDI療法、CSII療法のいずれにおいても、持続血糖測定器(Continuous Glucose Monitoring:CGM)と併用することで、低血糖が減り、なおかつHbA1cが改善することが報告されている 4)。 今後インスリンポンプ療法の中でもCSII療法ではなく、後述するリアルタイムCGM(real-time CGM:rtCGM)と連動するインスリンポンプ療法が主流となった場合、インスリンポンプ療法の有意性が高まる可能性がある。 3)インスリンポンプの適応 厳格な血糖コントロールが求められる人や日によって活動量や生活スタイルに変化が大きい人、血糖コントロールが不安定な人に特によい適応である。 具体的には、妊活中・妊娠中妊娠希望の女性、食べムラが大きく必要なインスリン量が少ない小児、部活動・試験期間などで日々の活動量が大きく変わる学生、シフトワークや出張の多いビジネスマン、暁現象が顕著な人、無自覚低血糖が多い人などが挙げられる。
2023年06月02日