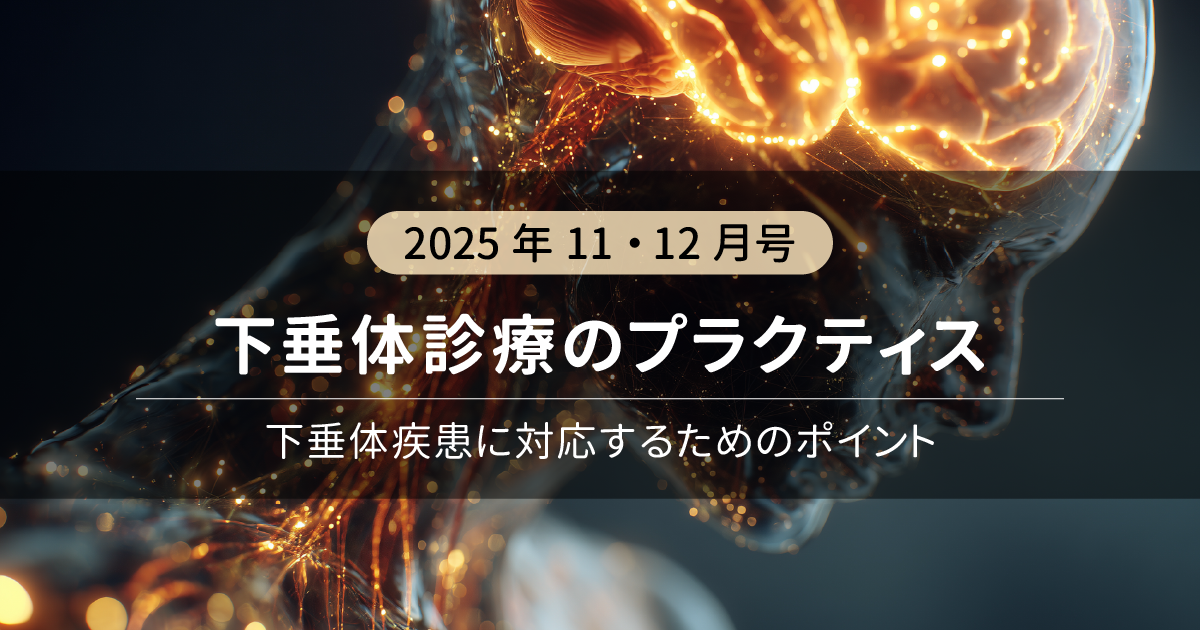- トップページ
- 新着論文一覧
新着論文一覧
-
特集

≪Ⅱ 臨床現場におけるスポーツとホルモン≫ 4.糖尿病、特に1型糖尿病患者におけるスポーツの楽しさと低血糖との関連
はじめに 糖尿病患者、とりわけ1型糖尿病を持つ者が直面する課題として、スポーツと低血糖との関係は重要である。1型糖尿病を持つ者は日々、インスリンの自己管理を行いながら生活しており、適度な運動は健康維持に不可欠であると同時に、低血糖のリスクを高める要因でもある。このような背景から、インスリン治療を受けている患者がスポーツを安全に楽しむための方法を個別に設定することが、臨床医や医療スタッフにとっての大きな目標となっている。本稿では、特に持続血糖モニター(CGM)を用いた低血糖予防策に焦点を当て、1型糖尿病患者がスポーツを安全に楽しむための具体的な方法を探求する。 1.1型糖尿病を持つアスリートの活躍とアドボカシー活動 1型糖尿病を持ちながらも、各スポーツ界で活躍するアスリートたちのエピソードは、多くの人々にとって大きな勇気と希望の源である。彼らは、日々の血糖管理の中でスポーツに情熱を注ぎ、トレーニングを通して自らの限界を超えることができるという可能性を示してくれる。元阪神タイガース投手の岩田稔氏は、プロ野球界で活躍した1型糖尿病のアスリートである 1)。岩田氏は、1型糖尿病の診断後も、プロ野球選手としてのキャリアを諦めず、病気と向き合いながらプレーを続けた。試合前に血糖値をチェックし、試合中も常に血糖値を意識しながらマウンドに立っていたそうだ。引退後は、さまざまな方の希望になるべく、株式会社 Family Design Mを立ち上げ、各種メディアへの出演を通して、あるいは患者向けのセミナーや学会の市民公開講座などで、自身の豊富な経験を発信している。また、エアロビクスの元ジュニア世界チャンピオンである大村詠一氏も1型アスリートである 2) 。大村氏は、8歳で1型糖尿病を発症し、思春期に血糖管理に大変な苦労をしながらも粘り強く競技生活を続け、ついにはエアロビクスにおける高度な技術と芸術性を体現した。今でもエアロビクス競技の普及と競技レベルの向上に努めながら、患者教育・支援活動に従事し、八面六臂の活躍を見せている。この二人の著書は、病気を抱えながらも自分の限界を超えることのできる強い心を持つことの重要性を教えてくれる。さらに、彼らは互いに協力して患者交流イベントを日本全国で展開しているのでぜひ応援したい。 日本糖尿病協会もアドボカシー活動として運動の重要性に着目している。当院の南昌江院長によって創設された協会公式のマラソンチーム「Team Diabetes Japan」は、患者とその支援者たちが一緒にマラソンを走ることで、1型糖尿病の認知度を高め、同じ病を持つ人々へ元気を届ける活動を長年行っている。最近、同協会が糖尿病治療における運動療法の重要性の啓発、普及に貢献した者に授与する「南昌江賞」が設立され、運動を通して社会に啓発を行う機運がますます高まっている。
2024年06月25日 -
連載

G7と旅の始まり 日本橋~品川宿
2024年5月15日、第67回日本糖尿病学会年次学術集会の開催直前に、Dexcom G7 CGMシステムのセンサーが発売となった。同日さっそく処方してもらい使用を開始したので、まずはこのG7の使用感についてレポートしようと思う。 これまでG6では1箱に3個のセンサーが梱包されていたのに対して、G7では個包装となり、圧倒的な省スペースが達成された(写真1)。また、G6では3カ月間使用するトランスミッターをセンサー装着後にはめ込み、それに先だってトランスミッター、センサーをそれぞれスマートフォンやモニターとペアリングしておかなければいけなかったのだが、G7ではトランスミッターを内蔵したセンサーになったので、あとではめ込むトランスミッターが不要となった。G6のトランスミッターは3カ月ごとに渡さなければいけなかったので、その分の費用負担が医療機関側に課せられていたのだが、それが必要なくなった。ユーザー側にとっても、トランスミッターは箱がマトリョーシカ状態で、大きな箱の中に小さな箱があり、その中にさらに小さなトランスミッターが入っていたため、余計な荷物となっていた。 写真1 G7センサーは個包装 G7の装着方法は極めて簡便で、アプリケーターのキャップをねじって外せば(動画1)、そのまま皮膚に直接当ててボタンを押すだけでよい(動画2)。センサー装着部位については、上腕後部が推奨位置として追加された。G6では装着前に行っていたペアリングは、装着後にアプリケーターの側面にあるQRコードを読み込むだけでよくなった(写真2)。装着のための操作としては、FreeStyleリブレよりもステップが少ない。センサーの大きさは長さ24.1mm×幅27.4mmで厚さ4.7mmと、直径35mm×厚さ5mmのリブレよりも二回りほど小さく、やや薄めになっている。G6では長さ12mmの電極フィラメントを斜めに留置していたのだが、G7では長さ6mmのフィラメントが皮膚面に対して垂直に留置される。同じく垂直留置のリブレより2mm長いので、皮下脂肪が薄い人の場合は気をつけたほうがよい。
2024年06月20日 -
特集

≪Ⅱ 臨床現場におけるスポーツとホルモン≫ 3.スポーツと水電解質異常
はじめに スポーツ飲料の宣伝を目にすることが多くなった。猛暑が続いており、2022年のスポーツドリンク販売金額は3,367億円、前年比113.7%で前年を上回っている(全国清涼飲料連合)。多くの方が、スポーツというと、脱水予防、と思いつかれるかもしれないが、注意点もある。以下にスポーツにおける、水電解質の変化を述べてみたい。 1.運動強度と血漿電解質 血漿量は運動強度に比例して減少し、最大運動強度では15%低下する(図1A) 1)。これは、活動する筋肉へ血症水分が移動するためである。 一方、血漿タンパク質濃度は上昇する(図1B) 1)。これは、Starling力によって活動筋へ過剰な水分が移行するのを防止するためである。 血漿電解質は、最高酸素摂取量の約50%以上で、血漿Na・Clは上昇し(図2A)、血漿乳酸は上昇、炭酸イオンは低下する(図2B) 1)。 興味深いことに、抗利尿ホルモン(AVP)は最大酸素摂取量56%以上の運動強度で、血漿濃度が上昇している(図3) 1)。295mOsm/kg H2Oが閾値で、これは安静状態よりも高値である。これが運動後の血症Na上昇の一因であるかもしれない。また、運動トレーニングにより血漿浸透圧変化に対するAVP分泌の感受性が変化し、それがトレーニング後の体液量増加を引き起こすという報告もある 2)。 図1 相対運動強度と血漿量(A)、血漿タンパク質濃度変化(B)(文献1より)
2024年06月17日 -
特集

≪Ⅱ 臨床現場におけるスポーツとホルモン≫ 2.男性ホルモンとスポーツ
はじめに 過度で持続的な運動は視床下部~下垂体~性腺系を抑制し性腺機能低下症を引き起こす可能性があり、女性アスリートにおいては無月経の原因となる。無月経に加えて、骨密度の低下、摂食障害を合わせて女性アスリートの三主徴(Female Athlete Triad:Triad)として報告されている 1)。しかし、男性アスリートにおける精巣機能の変化については十分明らかにされてはいない。一方、市民レベルでジョギングなどの有酸素運動や筋肉トレーニングは血中テストステロン上昇につながることも報告されている 2)。 本稿では男性ホルモンとその作用、男性ホルモン低下により出現する症状、運動による男性ホルモン低下、男性ホルモン補充療法のエビデンスなどについて概説する。 1.男性ホルモンの産生と生理作用 男性ホルモンのほとんどはテストステロンであり、主に精巣の間質にあるLeydig細胞で産生される。血中においてテストステロンは、性ホルモン結合グロブリン(sex-hormone binding globulin:SHBG)結合型(35~75%)、アルブミン結合型(25~65%)、遊離型(1~2%)と3つの型に分かれるが、アルブミン結合型と遊離型テストステロンが生物活性を有する。加齢によってSHBGが漸増するので、生物学的活性テストステロンは相対的に減少する。 テストステロンの生理作用は全身の多臓器に及ぶ。2次性徴における陰茎増大、前立腺の発育による精液産生、精巣での精子形成促進、声帯成長に伴う変声、陰毛・髭・腋毛など全身の体毛増加などがある。骨に対しては骨形成促進、骨吸収抑制の両面の作用があるとされている。骨髄での赤血球産生刺激作用もある。蛋白同化ステロイドとして筋肉量の増加作用がある。代謝に関してはインスリン抵抗性改善や糖代謝改善 3)、総コレステロールと中性脂肪の低下が報告されている 4)。
2024年06月13日 -
セミナー

クッシング症候群―診断・治療の最新エビデンス―
ポイント クッシング症候群は症状が非特異的と考えられており、診断が遅れがちな疾患である。しかしながら、診断に役立ついくつかの典型的な身体所見、症状を知っていると診断を早めることができる。クッシング症候群を疑った際の確定診断は、①病的な高コルチゾール血症があることの診断、②血中ACTH値測定によるACTH依存性の有無の確認、③ACTH依存性の場合はクッシング病と異所性ACTH産生腫瘍との鑑別、というように、順を追って行う。 診断確定に時間をかけて、その間に日和見感染症を発症させないことが大事である。著しい高コルチゾール血症(例えば40μg/dL以上など)が見出された場合は、ただちに治療を始めることによりカリニ肺炎や日和見感染症などの重症感染症の発症を予防する必要がある。診断は高コルチゾール血症をコントロールしたのちに行ってもまったく支障はない。この際の治療は、副腎酵素合成阻害薬による自発性コルチゾール分泌を強力に抑制するとともに、コルチゾールが低下してきたらコルチゾールの補充を加える「block and replace療法」で行うことが事故を少なくする秘訣である。 1.総論 1)診断に役立つ症状、所見 高コルチゾール血症による身体所見は皮膚萎縮と近位筋萎縮が重要で、満月様顔貌、鎖骨上脂肪沈着、水牛様脂肪沈着、中心性肥満などが認められる。 本症の患者は耐糖能障害や糖尿病、高血圧、骨粗鬆症の患者の中に隠れているので、これらの患者では皮膚萎縮の有無や筋肉量を診察することでクッシング病を鑑別することが重要である。 2)典型的なクッシング症候群の症状、所見 クッシング症候群の症候は、以下に分けて考えるとよい。 慢性の高コルチゾール血症による症状 ACTH分泌亢進に伴う症状(ACTH依存性クッシング症候群) ACTH分泌抑制に伴う症状(ACTH非依存性クッシング症候群) (1)慢性の高コルチゾール血症による症状 中心となる症候である。2つの症候(皮膚萎縮と近位筋の委縮)が特に診断に有用である。
2024年06月11日 -
セミナー

糖尿病性腎症患者に対する療養支援
Q&A編はこちら はじめに 糖尿病性腎症は透析導入原因疾患の38.7%を占め、最多である 1)。また、糖尿病は透析患者の死因の26.4% 1)を占める心血管死の原因とも深く関わり、腎予後・生命予後の観点からも糖尿病治療は重要である。治療経過は長く、薬物療法以外に食事療法、運動療法、生活習慣管理などさまざまな介入を長期間に渡り継続することが必要となる。 本稿では医師、看護師、栄養士、薬剤師などから構成されるチームの糖尿病性腎症患者への療養支援について記載する。 1.多職種介入の必要性 糖尿病性腎症の予防・重症化抑制を目的に、2017年に日本腎臓学会と日本糖尿病学会はSTOP-DKD宣言 2)を採択し、かかりつけ医、専門医、他職種、行政などによる連携の重要性を提示した。糖尿病患者は高血圧症、脂質異常症、高尿酸血症、肥満など複数の生活習慣病を有することが多く、血糖コントロールだけでなく、生活習慣を含めた集学的な管理の重要性が示されている 2)(表1)。生活習慣病管理は薬物療法、生活指導、食事療法など多職種連携が必要不可欠で、患者指導も含め初期から介入し、長期間にわたり指導を継続していく。また、糖尿病性腎症の初期は自覚症状に乏しく、病識の乏しい患者も多い。教育入院を行い集中した指導、患者教育を行い、行動変容を促すことも有効である。多職種の情報共有が必要であり、多職種カンファレンスで情報共有を、共通認識を持ち介入を継続していく。 表1 糖尿病性腎症に対する集学的治療(文献2より作成)
2024年06月07日 -
特集

≪Ⅱ 臨床現場におけるスポーツとホルモン≫ 1.女性アスリートにおけるスポーツと性ホルモン
はじめに 女性アスリートは無月経や月経随伴症状など、女性特有の健康問題を抱えながら競技生活を送っていることが少なくない。これらは競技パフォーマンスだけでなく生涯の健康に関わる可能性もあるため、アスリート自身はもちろんのこと、指導者や医療従事者を含む支援者が早期に問題に気付き、対応することが重要となる。本稿では、女性ホルモンと関わりの深い女性アスリートにおける医学的問題について、無月経と月経随伴症状を中心に概説する。 1.女性アスリートの無月経 競技レベルを問わず、約4割のアスリートに月経周期異常(無月経と月経不順)がみられる 1)。無月経の原因はさまざまあるが、女性アスリートの場合、一般女性に比べて「利用可能エネルギー不足(low energy availability:LEA)による視床下部性無月経」が問題となることが多い。 LEAになると、視床下部からのゴナドトロピン放出ホルモン(gonadotropin releasing hormone:GnRH)、下垂体からの黄体化ホルモン(luteinizing hormone:LH)・卵胞刺激ホルモン(follicle stimulating hormone:FSH)が抑制され、卵巣からのエストロゲンの分泌も抑制される。その結果、排卵が停止し、無月経となる。エストロゲンは子宮や乳房といった女性特有の臓器だけでなく、骨、筋肉、心臓、血管、脳、皮膚などさまざまな臓器に作用しており(図1) 2, 3)、長期間の低エストロゲン状態は全身に影響を及ぼす(表1)。 図1 エストロゲンが作用する臓器(文献2より)
2024年06月05日 -
特集

≪Ⅰ 運動とホルモン環境の変化≫ 3.スポーツと骨代謝関連ホルモンとの関連
はじめに 最近の一連の研究では、骨が自身からのホルモン分泌を介して全身の対処に影響を及ぼす内分泌臓器としての位置が確立してきている。骨由来の4種のホルモン、オステオカルシン(osteocalcin:OC)、リポカリン2(lipocalin 2:LCN2)、スクレロスチン(sclerostin:Scl)、fibroblast growth factor 23(FGF23)が心血管機能に影響を及ぼし、2型糖尿病(type 2 diabetes:T2DM)や心血管疾患(cardiovascular disease:CVD)など種々の代謝性疾患の発症に関与するとの報告がみられる。 1.心血管系への影響 骨はその構造と強度に基づき、身体の保護や運動のための起点としての役割を担うと考えられてきた。しかし最近の研究では、内分泌臓器として種々のホルモンを分泌し、全身の代謝に影響を及ぼす臓器として捉えられている 1)。骨由来のホルモンによって調節を受ける全身機能として、OCによる糖/エネルギー代謝、男性の生殖能力、脂肪沈着、骨格筋代謝および認知機能、LCN2による食欲制御などが挙げられる 2)。
2024年05月30日 -
連載

第72回 糖尿病と診療報酬改定DX・2024
はじめに 超高齢社会に直面したわが国では、社会保障制度を持続可能なものとすることが不可欠である。また、自然災害の発生や新型コロナウイルス感染症の流行により安全保障や危機管理の観点からも、これらの情報の利活用推進、および医療分野のセキュリティ対策の強化が必須である。2022年6月7日閣議決定の「経済財政運営と改革の基本方針 2022」において、「全国医療情報プラットフォームの創設」、「電子カルテ情報の標準化等」および「診療報酬改定DX(Digital Transformation)」の取組を行政と関係業界が進めることとし、内閣総理大臣が本部長になり関係閣僚により構成される「医療DX推進本部」が設置され、政府を挙げて施策を推進していく旨が打ち出された 1)。そして、進化するデジタル技術を最大限に活用し、医療機関などにおける負担の極小化を目指すことを最終ゴールとした「診療報酬改定DX対応方針」が示された 2)。 今回は、このような「医療DX」の推進、および「診療報酬改定DX」について、2024年度診療報酬改定の答申を踏まえ、診療報酬改定DXおよび糖尿病とのかかわりについて概説する。 1.医療DXの基本的な考え方(図1) 「DX」とは、図1に示すようにデジタル技術によって、ビジネスや社会、生活の形・スタイルを変える(Transformする)ことである。これを踏まえ「医療DX」については、「保健・医療・介護の各段階(疾病の発症予防、受診、診察・治療・薬剤処方、診断書等の作成、診療報酬の請求、医療介護の連携によるケア、地域医療連携、研究開発など)において発生する情報やデータに関し、全体最適された基盤を構築し、活用することを通じて、保健・医療や介護関係者の業務やシステム、データ保存の外部化・共通化・標準化を図り、国民自身の予防を促進し、より良質な医療やケアを受けられるように、社会や生活の形を変えていくこと」と定義 3)されている。クラウドを活用した業務やシステム、データ保存の外部化・共通化・標準化のために、「オンライン資格確認」と「マイナポータル活用」、「電子カルテ情報の標準化」、「診療報酬DX」などを構築する。そして、医療DXに関する施策を推進することで、以下の5点の実現 1)を目指す。 ①国民の更なる健康増進:生涯にわたる保健・医療・介護の情報をPHR(Personal Health Record)として自分自身で一元的に把握可能となり、健康増進や安全・安心な医療への受療、疾病の予防に寄与する。 ②切れ目なくより質の高い医療等の効率的な提供:本人の同意を前提として、必要に応じて全国の医療機関が診療情報を共有することで、より質の高い医療の効率的な提供が可能となる。さらに、災害時や救急時、感染症危機を含め、全国どの医療機関にかかっても、必要な医療情報が共有されることとなる。 ③医療機関等の業務効率化:デジタル化の促進により業務効率化が進む。ICT(Information and Communication Technology)機器やAI(Artificial Intelligence)技術の活用による業務支援や、業務改善・分析ソフトによる合理化を通じて、医療機関自身がデジタル化に伴う業務改革を行うことにより、魅力ある職場が実現していく。 ④システム人材等の有効活用:診療報酬改定に関する作業が効率化されることにより、医療情報システムに関与する人材の有効活用や費用の低減を実現し、医療保険制度全体の運営コストの削減が可能となる。 ⑤医療情報の二次利用の環境整備:民間事業者との連携も図りつつ、保健医療データの二次利用により、創薬、治験などの医薬・ヘルスケア産業の振興に資することが可能となり、国民の健康寿命の延伸に貢献する。
2024年05月27日 -
セミナー
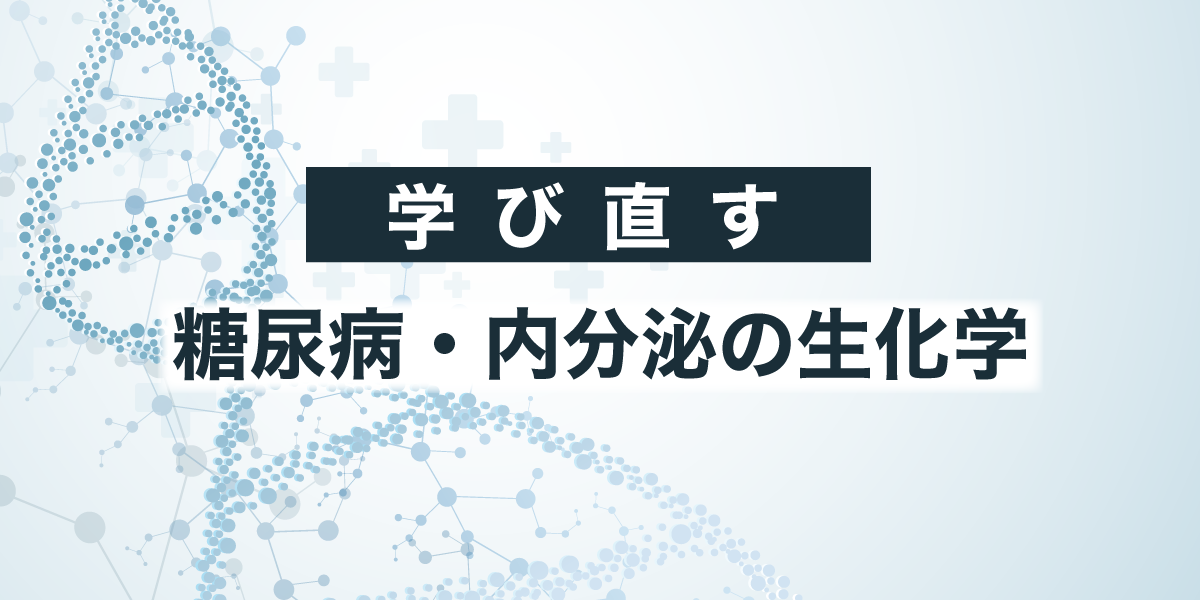
タンパク質とアミノ酸の代謝
はじめに タンパク質は三大栄養素の一つで、グラム当たりのカロリーは炭水化物と同じく4kcal程度である。脂質は中性脂肪として脂肪組織に、炭水化物はグリコーゲンとして肝臓および筋肉に貯蔵されるのに対して、タンパク質のエネルギー源としての貯蔵を目的とした特定の分子は知られていない。 タンパク質はアミノ酸のポリペプチド結合によって構成され、そのアミノ酸の数は、タンパク質の種類によって100程度 1)のものから3万個以上に及ぶもの(筋肉に発現するタイチン) 2)まで多様である。それぞれのタンパク質のアミノ酸配列は、遺伝情報(ゲノム塩基配列)により規定されていて、個々のタンパク質はその特異的な構造に基づいた何らかの機能を担い、生体機能の維持に重要な役割を果たしている。ヒトにおいてタンパク質は体重の13~16%を占める 3)。 1.タンパク質とアミノ酸 食物として摂取されたタンパク質は、消化酵素(ペプチダーゼなど)の働きによってアミノ酸レベルまで分解された後に吸収され、タンパク質の合成に利用、あるいはエネルギーとして消費される。生体を構成するタンパク質もまたアミノ酸レベルまで分解されたのち、食物由来のアミノ酸と同様に利用・消費される。ほとんどのタンパク質は20種類のアミノ酸により構成されているが、これらのアミノ酸の血漿中の濃度は、刻々と変化する生体タンパク質の合成・分解のバランスや、食事を介した摂取による変動の影響を受けながらも、おおむね一定の範囲に保たれている(図1)。なお、栄養学的にはアミノ酸は、体内で合成することができない必須アミノ酸と、合成できる非必須アミノ酸に分類される。図1では、ヒトにおける必須アミノ酸9種類に下線を付してあるが、現代の日本において通常の食事をしていれば不足することはないと言われている 4)。 図1 アミノ酸の構造とヒトにおける血漿中濃度(µM) 血漿中濃度の基準範囲はSRL総合検査案内を参考とした(2023年11月閲覧)。なお総アミノ酸濃度は2.0~3.5mMで、およそ22~38.5mg/dLに相当する。一方、総蛋白は6.7~8.3g/dLであるため、遊離アミノ酸の2~300倍のアミノ酸がタンパク質(グロブリンやアルブミンなど)として血漿中に存在することになる。 画像をクリックすると拡大します 図1 アミノ酸の構造とヒトにおける血漿中濃度(µM) 血漿中濃度の基準範囲はSRL総合検査案内を参考とした(2023年11月閲覧)。なお総アミノ酸濃度は2.0~3.5mMで、およそ22~38.5mg/dLに相当する。一方、総蛋白は6.7~8.3g/dLであるため、遊離アミノ酸の2~300倍のアミノ酸がタンパク質(グロブリンやアルブミンなど)として血漿中に存在することになる。 $(".vol3_k8_z1").modaal();
2024年05月21日 -
特集

≪Ⅰ 運動とホルモン環境の変化≫ 2.スポーツと骨格筋ホルモンの代謝への影響
はじめに 運動は糖尿病や肥満症、高血圧症、脂質異常症などの心血管リスクファクターの改善、QOLやうつ状態、認知機能障害の改善、がんの予防効果など、さまざまな作用が知られている(図1)。運動が健康につながるメカニズムは未解明な部分が多いが、筋肉量と寿命とに有意な相関があることが数多くの疫学的研究で報告されるなど 1)、運動の中心的役割を担う器官である骨格筋がその鍵となる可能性が示唆されている。骨格筋は体重の約40%を占め、運動器としての役割以外にも、多臓器と連関し、全身に影響を与えていると考えられており、特にマイオカインが運動と健康のメカニズムを解明する上で注目されている。マイオカインは、ギリシャ語のmyo-(筋)とkine-(作動物質)から作られた造語であり、骨格筋から分泌され、オートクライン、パラクライン、エンドクライン作用により骨格筋自身や遠隔の臓器、組織に作用する生理活性物質の総称である 2)。現在までに数多くのマイオカインが発見され、これらが骨格筋を中心とした多臓器連関として、健康維持や疾患改善に役立っていることが明らかになっている(図2)。本稿では運動によって分泌が変化するマイオカインに着目し、骨格筋や代謝への影響と今後の展望を中心に概説する。 図1 運動のさまざまな効果 図2 骨格筋の多臓器連関
2024年05月15日 -
特集

≪Ⅰ 運動とホルモン環境の変化≫ 1.スポーツとメンタルヘルス関連ホルモン
はじめに 現代社会では、科学技術の発達と生活の利便性向上により身体を動かす機会が減少し、種々の生活習慣病を発症させる要因となっている。また、information technology(IT)の普及に伴い、巷に溢れた情報が精神的な負担となり、うつやストレスの原因となっている。こういった健康を蝕むさまざまな脅威に直面する現代人にとって、主体的に運動・スポーツに親しむことは、体力の維持・増進、疾病やうつの予防、ストレスの軽減など、心身の健康に大きな効果をもたらすことが期待されている 1)。 心身での健康は脳と身体が互いにうまく調節し合って達成できるが、これらを仲介するルートの一つが血流であり、ホルモンをはじめとする種々の化学物質を運んでいる。古典的には、脳の視床下部と下垂体からは、ストレス応答に関わる副腎皮質をはじめ、甲状腺、生殖器などの内分泌器官にホルモンを分泌させるための指令(分泌刺激ホルモン)を血中に放出することが知られてきた。しかし、近年、視床下部をはじめ脳中枢は、消化管から血中に分泌されるグレリンやpeptide YY(PYY)、glucagon-like peptide-1(GLP-1)といったホルモン、脂肪組織から分泌されるレプチンなどの情報を身体から受け取り、空腹・満腹感といった食欲や身体のエネルギー状態を調節する働きを有するなど 2)、脳と身体の連関に関わる多くのホルモン群が注目されてきた。さらに、こうした脳と身体の関わりは、視床下部など限られた脳領域でなく、海馬もさまざまなホルモンや液性因子による身体からの刺激を敏感に受けて、また海馬自らもこれらを産生し、構造的・機能的に変化して(萎縮や神経可塑性)、認知機能に正負の影響を与えることも明らかになってきている 3)。 以上に挙げたように、ストレス応答、食欲、認知機能に影響を与えるホルモンは、いずれもヒトのメンタルヘルスに関わると考えられるが、興味深いことに、これらの作用は身体を動かすことにより修飾されることが分かってきている。そこで、本稿では種々の運動・スポーツが脳と身体をつなぐ、これらのメンタルヘルス関連ホルモンに対して与える影響について紹介する。 1. ストレスホルモンとスポーツの関係 ストレスとは、外部からのさまざまな圧力(ストレッサー)によって、生体の恒常性(ホメオスタシス)が崩れた状態とそれに伴う動的適応反応(アロスタシス)を指す 4)。ストレッサーには、物理化学的なストレッサー(暑さ、騒音、薬物など)のほか、心理・社会的ストレッサー(仕事・家庭での問題、人間関係など)がある。運動も人体のほとんどのシステム(循環器、呼吸器、筋骨格など)に負荷をかけるストレス状況を生む。どのような原因のストレスであっても、中枢から末梢にまで存在する共通の神経内分泌系により処理されている。このストレス反応を担う系には、主に、視床下部から下垂体-副腎皮質へとつながるhypothalamus pituitary adrenal axis (HPA系)と、脳幹部の青斑核/ノルアドレナリン細胞から遠心性交感神経-副腎髄質へとつながる系が知られている。特に前者に関しては、下垂体前葉から副腎皮質刺激ホルモン(adrenocorticotropic hormone:ACTH)やβ-エンドルフィンが、さらにACTHの刺激により副腎皮質から糖質コルチコイドの一種であるコルチゾールがそれぞれ血中に分泌される。コルチゾールは、脂肪細胞の中性脂肪を遊離脂肪酸とグリセロールに加水分解させるほか、肝臓での糖新生を促し、エネルギー源としてさらなる糖質を供給する。そのほか、運動中では血管機能を調節し、免疫/炎症反応を制御することにより、運動誘発性の筋肉損傷の重症度を軽減する。β-エンドルフィンは神経伝達物質であり、一部は末梢血中に放出されるが、その作用は基本的に脳中枢で発揮される。HPA系や脳脊髄への上行性伝導を阻害することで、ストレスや疼痛を緩和させ、快楽を感じさせる方向に働く。また、長距離走などで苦しい状態が続くと、β-エンドルフィンが脳内で産生されて、それにより快感を覚えるようになるという「ランナーズ・ハイ」と呼ばれる現象が有名である。
2024年05月10日 -
特集

(扉)特集にあたって
「スポーツ」と聞いて何を思い浮かべるだろうか…? 春であれば新たなシーズンが始まる野球、サッカー、冬であればラグビー、スキーなどさまざまな競技スポーツを思い起こす方が多いのではないかと思う。柔道、剣道、相撲、レスリングなどの格闘技や、バレーボール、バスケットボールなどの球技を想起される方もいらっしゃると思う。しかし、中世の英国では狩猟、乗馬、釣りがスポーツであった。スポーツ(sport)の語源はラテン語の“deportare(運び去る、運搬する)”という言葉である。つまり、気分の転換、仕事や家事などの日常生活からの解放こそがスポーツ、スポーツは遊ぶことであり、楽しむことなのである。 しかし日本では運動嫌いの人たちが少なくない。その理由の一つとして、体育の授業が挙げられる。私自身も鉄棒では前方支持回転ができずに劣等感に打ちひしがれたし、授業中に「達成感」を実感したこともない。一部の教師は何をするにも命令口調で、辟易とした覚えがある。大学ではサッカー部に所属し、有能な先輩たちの活躍で東日本医科学生総合体育大会での優勝も経験したが、私がスポーツとして心から楽しむことができたのは、40歳の中盤から始めたフルマラソンだった。 ゴルフの際になかなか人数が集まらなかったので、一人でできるジョギングを始めた。手始めに10kmのロードレースを走り、3カ月後には、ハーフマラソンを経験した。そして、半年後に無謀にもホノルルマラソンに挑戦したのである。フルマラソンはハーフマラソンの「2倍」の距離を走るレースだが、苦しさと辛さは、5倍にも10倍にも思えた。レースの後半には、もう2度とマラソンなんか走らない…と繰り返し呟いていた。しかし、レースが終わって数時間経つと、何とも言えぬ達成感と充実感を覚えたのである。そして、その後もマウイマラソン、シドニーマラソン、NAHAマラソン、北海道マラソンなど30を超える大会に参加した。走るということが、何も考えずに自由になれる、楽しいものだと実感したのである。スポーツはまさに遊ぶことであり、楽しむことなのである。 ひとが遊び、楽しむことのサイエンスをまとめてみたいと思い「スポーツと内分泌疾患」というタイトルの特集を組んでみた次第である。遊び好きの私が原案を作り、まじめで勉強家の細井雅之先生が多くのエキスパートの先生たちに声をかけてくださり、今回の特集が出来上がった。 メンタルヘルス、骨格筋・骨関連ホルモン、ジェンダー、水電解質、糖代謝異常など多くの側面からのスポートロジーをお楽しみいただきたい。 著者のCOI (conflicts of interest)開示:細井雅之;講演料(サノフィ、住友ファーマ、日本イーライリリー) 本論文のPDFをダウンロードいただけます
2024年05月10日 -
特集
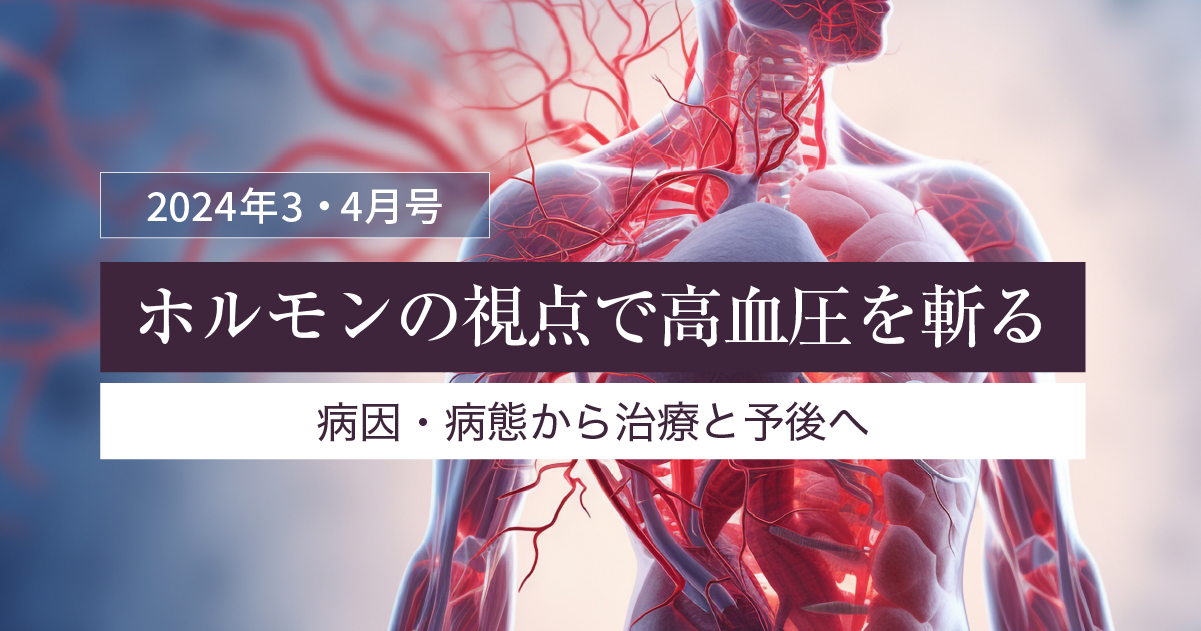
7.CKD合併高血圧のマネージメント(降圧薬治療)
はじめに 慢性腎臓病(chronic kidney disease : CKD)は、日本の成人の12.9%、約1,330万人以上が罹患していると報告されており、一般診療で遭遇することの多い疾患である。CKD患者の多くは高血圧を合併しており、高血圧の合併はさらなる腎機能低下へつながるため、CKD合併高血圧患者では適切な血圧管理が求められる。本稿では、CKD合併高血圧の薬剤治療について解説する。 1.高血圧とCKDの関連 高血圧とCKDは密接に関連している。高血圧はCKDの原因となり既存のCKDを悪化させる一方で、CKDは高血圧の原因となり既存の高血圧を悪化させる。高血圧が持続すると腎血管が動脈硬化を起こし、腎実質への血流が低下する。そのため腎組織線維化や糸球体硬化を介して腎機能障害へと進展する。腎機能障害が進行すると、腎臓からのNa排泄障害による体液量の増加、レニン・アンジオテンシン(renin-angiotensin : RA)系の活性化、交感神経系の活性化が生じることで、高血圧が増悪する。CKDの進展や高血圧の管理不良は、心筋梗塞や脳卒中などの心血管疾患(cardiovascular disease : CVD)発症のリスク因子である。この悪循環を未然に防ぎ、CVD発症リスクを低下させるために、血圧の管理は大変重要である。高血圧への対策としては、食事療法、運動療法、薬剤治療があり個々の状態に応じて必要な治療を選択する必要がある。 2.糖尿病とCKDの関連 糖尿病も高血圧と同様にCKDに合併しやすい生活習慣病であり、糖尿病性腎症は本邦における末期腎不全の原疾患の第一位である。また高血圧と糖尿病は高率に合併する。糖尿病性腎症は微量アルブミン尿で発症し、持続性蛋白尿、腎臓機能低下へと進行する疾患である。糖尿病性腎症の治療は厳格な血糖調整に加え、アルブミン尿・蛋白尿を軽減させるため、糸球体への負担(糸球体高血圧)への対応が必要である。その治療としてRA系阻害薬が有効であることがさまざまな臨床試験で示されている。
2024年04月30日 -
連載
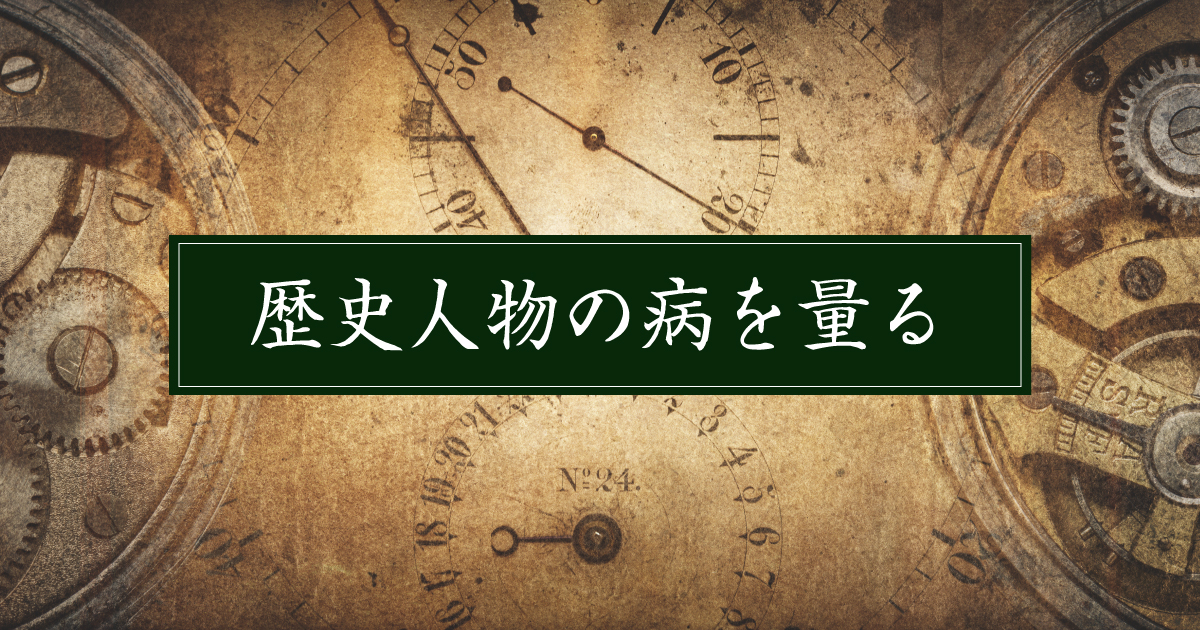
第4回 オノレ・ド・バルザック ―長時間の座位と糖尿病
『人間喜劇』で知られるフランスの小説家、オノレ・ド・バルザック(図)は1799年5月20日、フランス中央に位置するトゥールに生まれた。出生証明書はトゥールの市役所に現在も保管されているが、貴族の称号である「ド」は見当たらず自称である。父のベルナール・フランソワは農民の出身であったが、故郷を出て成り上がり、第22師団の兵站(補給部隊)部長であった。母は父よりも30歳以上年下であった。 バルザックは生まれてすぐ乳母のところに4年間預けられ、8歳からは修道会の寄宿舎に入った。病気のため15歳で退学、その後パリの学校の寄宿制となった後、法学部に進学した。代訴人の事務所に入ったバルザックであったが、20歳のときに文筆で身をたてると宣言し、交渉の末、父親から2年の猶予と仕送りをもらうこととなった。しかし2年で著名な作家となることは叶わず、ペンネームを用いて大衆小説を量産し、生活費を得ることとなった。1829年3月に本人名義で「最後のふくろう党員」を出版、翌1830年に発表した「あら皮」で文壇での地位を確立した 1, 2)。 図 オノレ・ド・バルザック(Paul Nadar, Public domain, ウィキメディア・コモンズより)
2024年04月26日 -
特集
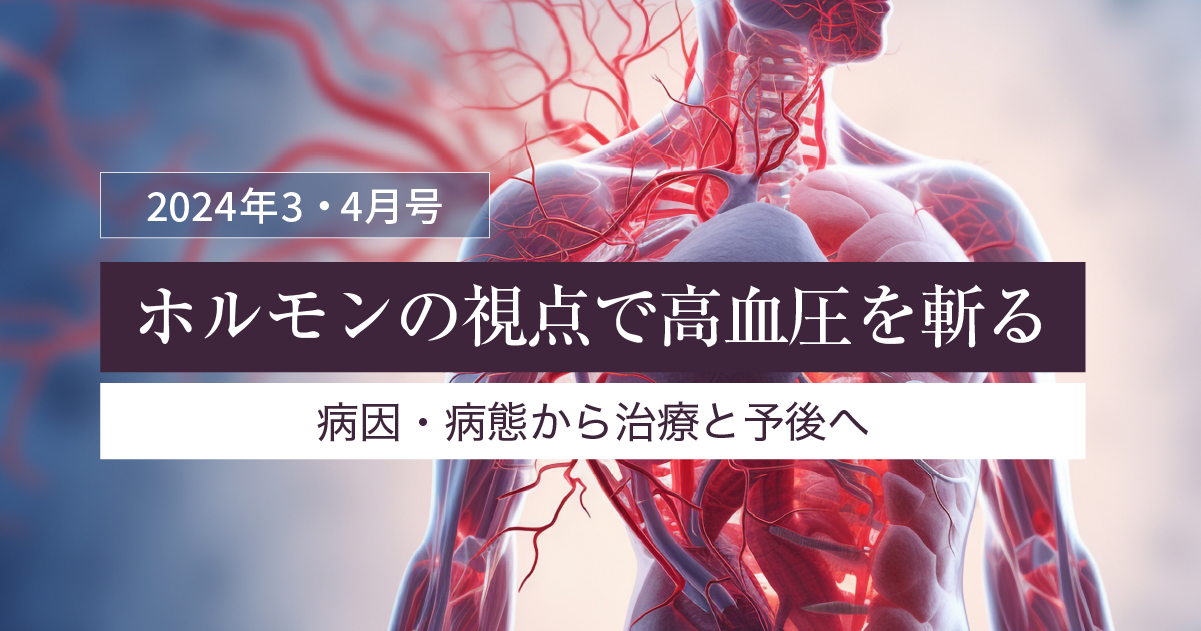
6.CKD合併高血圧のマネージメント(生活習慣修正)
はじめに 食塩制限は栄養指導の中でも最も基本となるところであり、多くの慢性腎臓病(CKD)患者は食塩制限を指導されている。CKD患者にとって食塩制限は非常に理にかなっていそうだが、臨床研究に裏打ちされたエビデンスはどの程度あるのだろうか。2023年に日本腎臓学会による「エビデンスに基づくCKD診療ガイドライン2023」が発行されたが 1)、筆者は「CKD患者への食塩制限は推奨されるか?」に対するステートメントに対してシステマティックレビューの取りまとめを担当させていただいた。本稿ではCKD患者の高血圧管理に関して、食塩制限を中心に概説したい。 1.食塩制限 ―Salt(食塩)と Sodium(ナトリウム) まず基本的なことではあるが、用語の確認である。「Salt(食塩)」 と「Sodium(ナトリウム)」は異なる。日本では通常「Salt(食塩)」と表記されるが、英語では「Sodium(ナトリウム)」と表記されることが多い。例えば英語表記で「Dietary sodium should be restricted to no more than 3g per day.」とあった場合に「食塩摂取は3g/日未満」と誤解する医師は少なくない。「Salt(食塩)」 と「Sodium(ナトリウム)」は表1のように換算されるわけで、この英語表記は「食塩摂取は7.5g/日未満」ということになる。 この誤解を避けるため、ガイドライン中では「塩分」や「減塩」という用語は使用せずに、「食塩」(すなわちNaCl)や「食塩制限」で統一することにした。 表1 Salt(食塩)とSodium(ナトリウム)は違う
2024年04月23日 -
セミナー

甲状腺結節の日常臨床での取り扱い―甲状腺結節の診断・経過観察の最新エビデンス―
ポイント 甲状腺のしこりを「甲状腺結節」、結節により甲状腺が腫れている状態を「結節性甲状腺腫」という。 経過観察期間についてのエビデンスは乏しいが、ACR-TIRADSでは5年としている。 欧米では細胞診検体による遺伝子パネル検査が実用化され、診断的治療を目的とした甲状腺手術は抑制される方向になりつつある。 多結節性甲状腺腫は遺伝性疾患に関連していることがあり、該当する疾患を知っておくことが必要である。 1.用語について 甲状腺内のしこり(腫瘤性病変)は慣習的に「結節」が使用され、臓器名と合わせて「甲状腺結節」と呼称される。結節により甲状腺が腫脹している状態を「結節性甲状腺腫」といい、バセドウ病や橋本病など結節を伴わずに甲状腺全体が腫脹する「びまん性甲状腺腫」と対比して使用される。同様の成り立ちの用語は他領域ではまれで、混乱を招きやすいが、しこりがあることの臨床的・暫定的診断名であると考えれば理解しやすい。多発している場合に「多結節性甲状腺腫」、甲状腺機能亢進症を伴う場合には「中毒性結節性甲状腺腫」や「機能性甲状腺結節」、超音波・細胞診検査などを経て良性の可能性が極めて高い場合には「甲状腺良性結節」などの派生した用語がある。 また類似した用語に「濾胞性腫瘍」があるが、超音波検査や細胞診の結果により、濾胞癌との鑑別が困難な病変であることを強調した用語である。濾胞癌は定義上、手術により病変全体を切除し、組織検査を行わなければ診断の確定は不可能であるため、こちらも術前の暫定診断として使用される。 甲状腺結節の多くは腺腫様甲状腺腫をはじめとする良性疾患であり、また仮に悪性腫瘍が合併していても乳頭癌をはじめとして、悪性度が低く、予後も良好なものが多い。このため、近年は超音波検査をはじめとする画像診断機器の高精度化に伴う過剰診断・過剰治療がむしろ問題となっている。また有病率は高いが、予後良好であるがゆえに、RCTなど質の高いエビデンスはほとんどない。こうした点が理解を妨げ、専門家以外には扱いづらい疾患になっていると思われる。本稿では日常臨床で最もよく遭遇する甲状腺中毒症を伴わない、嚢胞以外の甲状腺結節、特に細胞診で悪性の疑いに至らない結節の扱いについての現状を、限られたエビデンスとともに述べる。
2024年04月18日 -
連載

東海道五十三次?
新型コロナウイルスの脅威がすっかり過ぎ去ったかのような社会全体のムードに伴って人々が行き交うようになり、学会や講演会も現地で開催されることが増えてきた。昨年12月には2週連続で週末開催の学会に参加し、リアルタイム(rt)CGMに関するランチョンセミナーでの講演を行ってきた。 1週目は、熊本で開催された第61回日本糖尿病学会九州地方会である。飛行機で当日向かうか前泊するかの選択を迫られたのだが、そこは鉄人の意地として、鉄路での移動以外に選択の余地はない。特に岡山より西へ行くときには、必ず寝台特急「サンライズ瀬戸・出雲」に乗ると決めている(写真1, 2)。今回は久しぶりにシングルデラックスという比較的広い個室を予約することができた(写真3)。岡山からの新幹線では、下調べをしていたわけではないのだが、幸運にも500系に乗車することができた(写真4)。熊本は2013年の日本糖尿病学会年次学術集会以来の10年振りであったが、贔屓にしている「黒亭」で熊本ラーメンをいただいた(写真5)。 写真1 サンライズ@東京駅写真2 乗車前
2024年04月16日