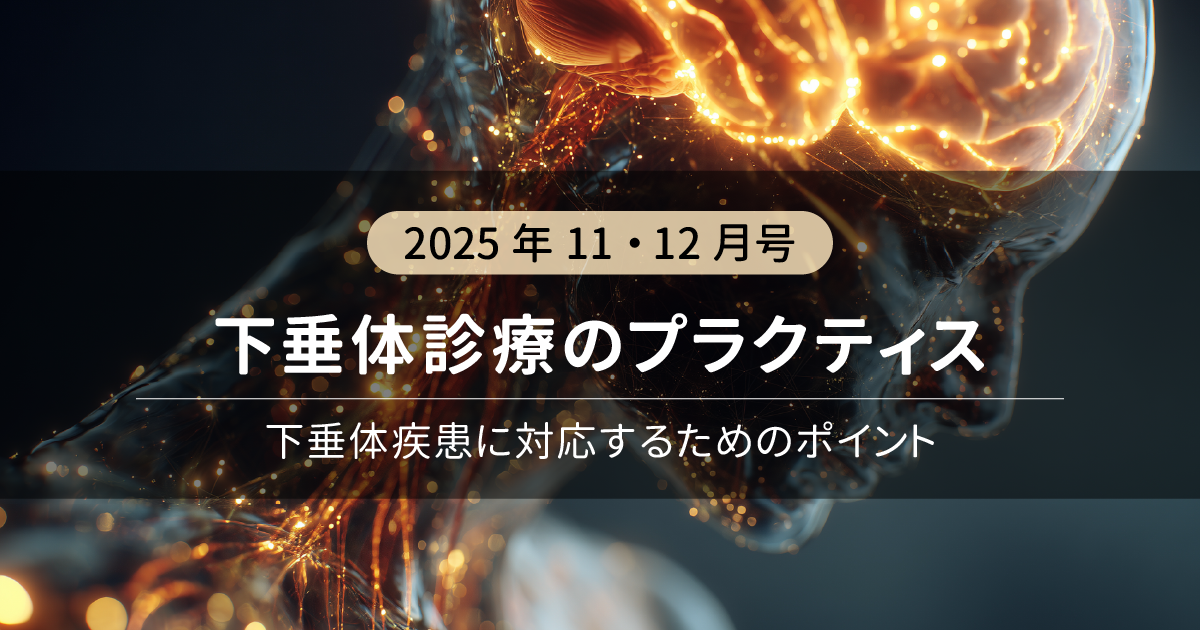- トップページ
- 新着論文一覧
新着論文一覧
-
特集
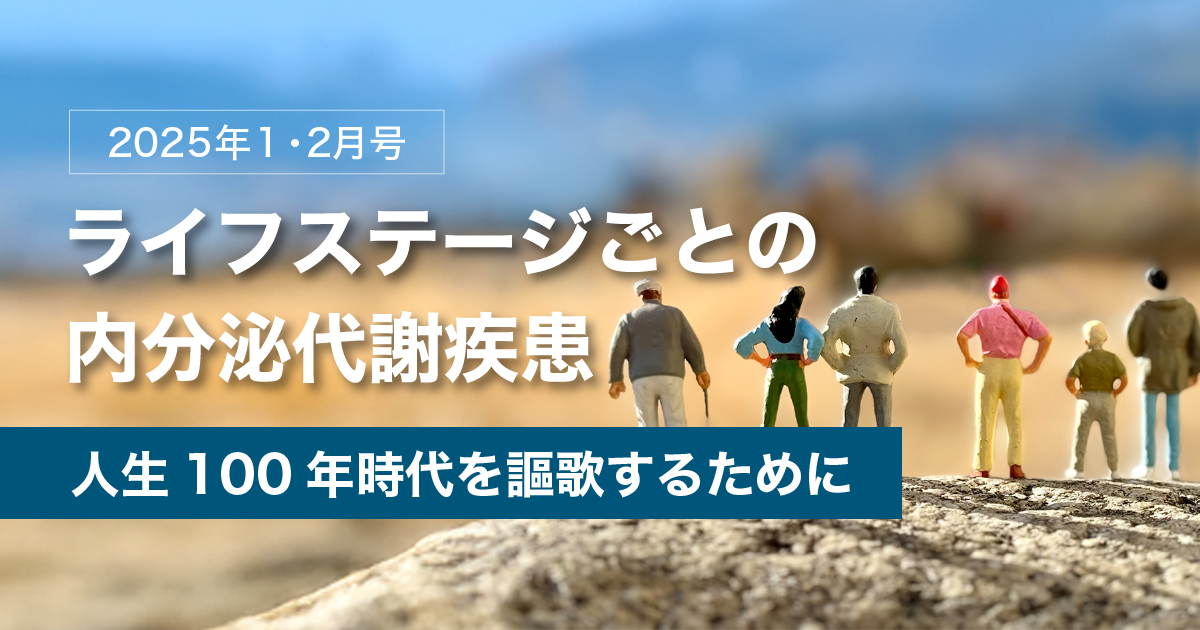
5.LOH症候群とテストステロン補充療法
はじめに 男性においては、加齢に伴う性ホルモン低下と男性更年期障害との関連性が知られており、中には骨強度低下、筋肉量減少、筋力低下を伴うことにより運動機能や身体機能の低下を引き起こすことが指摘されている。加齢に伴うさまざまな機能変化の中でも、運動機能、歩行能力などの人間の身体機能、生理機能は年齢とともに低下していくことが知られている。また、生殖内分泌器官の機能低下により性ホルモンの動態も大きく変化し、性ホルモンレベルの低下、アンドロゲン受容体(AR)をはじめとする性ホルモン受容体シグナルの減弱が考えられる。男性において、加齢による性ホルモン低下は、抑うつ、性欲低下、性機能の減退、知的活動や認知機能の低下、睡眠障害をはじめとする男性更年期障害とも関連し、Partial androgen deficiency in aging male(PADAM)あるいはLate-onset hypogonadism(LOH)という概念が提唱されている。また、加齢に伴い骨強度の低下、筋肉量の減少、筋力低下(サルコペニア)を認め、高齢者の身体機能は一層低下し、activities of daily life(ADL)の自立がより困難となり、結果的に転倒、骨折による要介護状態に陥る場合も多い。このように、骨粗鬆症に伴う脊椎圧迫骨折、大腿骨頸部骨折やサルコペニアなどは、運動機能、身体機能を低下させるばかりでなく、生命予後、ADLを規定し、高齢者本人、介護者のquality of life(QOL)を低下させてしまう場合が多く、その対策は重要である。 1.LOH症候群とは LOH症候群の症状、徴候としては、①抑うつ、不安、疲労感などの「精神症状」、②睡眠障害、記憶や集中力の低下、肉体的疲労感、筋肉量と筋力の低下、骨塩量の低下などの「身体症状」、③性欲低下、勃起障害などの「性機能関連症状」の3つに大別される 1)。 LOH症候群では、不定愁訴で受診する場合も少なくなく、質問紙を通じた問診、スクリーニング、他疾患との鑑別を実施し、血中テストステロン濃度の測定をはじめとするホルモン学的検査を中心に、性腺機能を評価することが重要である。一般に、男性ではテストステロンは主として精巣ライディッヒ細胞より分泌され加齢とともに低下する一方で、その程度には個人差を認める場合が多い。また、性ステロイドの前駆体であるデヒドロエピアンドロステロン(DHEA)は、その硫酸抱合体である。 DHEA-sulfate(DHEA-S)とともにそのほとんどが副腎で産生され、それ自体が弱いアンドロゲン活性を有することから副腎アンドロゲンといわれている。DHEA、DHEA-Sは20代以後加齢とともに直線的に減少することが明らかとなってきている。加齢に伴い、テストステロン血中濃度は徐々に低下する一方で、性ホルモン結合グロプリン(SHBG)の増加を認め、生理活性の強い遊離テストステロンの加齢による低下はより顕著となる 2)(図1)。これらの結果として、男性におけるテストステロンの低下は、うつ症状、性欲低下、勃起障害といった男性更年期障害(PADAM、LOH)や、サルコペニア・フレイル、骨粗鬆症、肥満、脂質異常症、認知症をはじめとする老年疾患や生活習慣病と関係することが指摘されている。
2025年02月27日 -
連載

第76回 糖尿病に係る在宅療養指導管理料と在宅療養指導管理材料加算2024
はじめに 医科診療報酬点数表の第2部在宅医療は、第1節在宅患者診療・指導料、第2節在宅療養指導管理料、第3節薬剤料、第4節特定保険医療材料料に分かれ、その第2節の第1款が在宅療養指導管理料(35項目)、第2款が在宅療養指導管理材料加算(33項目)である。今回は、在宅自己注射指導管理料をはじめとする糖尿病に係る在宅療養指導管理料と在宅療養指導管理材料加算について概説する。 1.在宅療養指導管理料の通則について(表1)1, 2) 在宅療養指導管理料は、医師が療養上必要な事項について適正な注意および指導を行った上で医学管理を十分に行い、かつ、各在宅療養の方法、注意点、緊急時の措置に関する指導などを行い、併せて必要十分な量の衛生材料および保険医療材料を支給した場合に算定する。衛生材料または保険医療材料の支給に当たっては、訪問看護事業者から、訪問看護計画書により必要量の報告があった場合、医師は、その報告を基に衛生材料などを支給する。訪問看護報告書により衛生材料などの使用実績について報告があった場合は、医師は、衛生材料の量の調整、種類の変更などの指導管理を行う。また医師は、訪問看護計画書などを基に衛生材料を支給する際、保険薬局に対して、必要な衛生材料の提供を指示することができる。 在宅療養指導管理料は、特に規定する場合を除き月1回に限り算定するが、1月以内に指導管理を2回以上行った場合は、第1回の指導管理の時に算定する。2以上の在宅療養指導管理を行った場合は、主たる指導管理の所定点数のみを算定し、在宅療養を指示した根拠、指示事項、指導内容の要点を診療録に記載する。 入院中の患者に対して、退院時に退院後の在宅療養指導管理を行った場合は、退院日1回に限り、在宅療養指導管理料の所定点数を算定できるが、退院月に外来、往診または訪問診療にて行った指導管理の費用は算定できない。死亡退院および他の病院・診療所へ入院するため転院した場合も算定できない。よって、退院日に在宅療養指導管理料を算定していない場合に限り、退院月に外来、往診または訪問診療において在宅療養指導管理を行った場合は在宅療養指導管理料を算定することができる。また、退院日に在宅療養指導管理料を算定した保険医療機関以外の保険医療機関において在宅療養指導管理料を算定する場合には、診療報酬明細書の摘要欄に当該算定理由を記載する必要がある。 表1 在宅療養指導管理料の通則(文献1, 2より) 画像をクリックすると拡大します 表1 在宅療養指導管理料の通則(文献1, 2より) $(".n0015_h1").modaal();
2025年02月25日 -
セミナー

災害時の糖尿病チーム医療
Q&A編はこちら はじめに 本邦では毎年のように、さまざまな場所で、さまざまな災害が発生している。糖尿病患者は大規模災害に被災した際には、糖尿病をもつ人として生きることよりも生き延びることが最優先され、特に食事・運動療法の継続が困難となり、血糖管理状況が悪化することが報告されている 1)。そのため、災害発生時に糖尿病患者が困らないように普段から指導や教育を行うことが重要であり、いざ災害が発生したら、可及的速やかに支援することが望まれる。そこで、日本糖尿病学会と日本糖尿病協会が協働して、糖尿病医療支援チーム(Diabetes Medical Assistance Team:DiaMAT)の体制構築を進めている。各都道府県に災害対応チームを設置すると同時に、インスリン依存状態の糖尿病患者の登録や情報発信、メディカルスタッフへの教育や登録などを準備している。今後、起こり得る大規模災害に医療者全員が自分事として捉え、まずわれわれ自身が準備をし、加えてわれわれが直接関わる患者も災害に対する準備をするように働きかけることが大事である。本稿では、糖尿病をもつ人たちが、災害発生時にできるだけ困らないようにするために、私たち医療者がチームとしてどのように関わるべきか、活動すべきか概説する。 1.DiaMATについて DiaMATは、災害の事前準備のための医療者および患者への災害教育や災害発生時に、当該都道府県および地区の関係団体と連携して迅速な被災者支援を行うことにより、糖尿病に伴う災害関連死を防ぐことを目的に創設され、災害が起こる前の防災訓練から発災時の支援まで、トータルに糖尿病患者を災害から守るチームである。DiaMATを構成するのは、日本糖尿病学会、日本糖尿病協会を中心に、各地域のそれぞれの支部とその関係者、そして日本糖尿病療養指導土(CDEJ)や地域糖尿病療養指導士(CDEL)の有資格者である 。 DiaMATの活動には、平時に行うものと災害発生時に行うものに分けられる(図1)。平時には、糖尿病患者や医療スタッフへの災害教育や、行政や医師会(日本医師会災害医療チーム:JMAT)との連携、患者登録システムの構築、治療薬や医療機器の備蓄などを行う。特に患者への災害教育は重要であり、患者に災害時における対応策を定期的に、かつ集団だけでなく個別化した形で教育を行うことが必要がある。 図1 平時および災害時の糖尿病医療支援チーム(DiaMAT)の活動内容
2025年02月21日 -
セミナー

糖尿病合併妊娠・妊娠糖尿病の管理
Q&A編はこちら 1.糖代謝異常妊娠の定義 妊娠中の糖代謝異常は、①妊娠糖尿病、②妊娠中の明らかな糖尿病、③糖尿病合併妊娠に分類される。また糖尿病合併妊娠は、①妊娠前にすでに診断されている糖尿病、②確実な糖尿病網膜症があるものに分けられる(表1)。 妊娠糖尿病(gestational diabetes mellitus:GDM)は妊娠中に初めて発見または発症した糖尿病に至っていない軽い糖代謝異常であり、現在の定義と診断基準は、The International Association of the Diabetes and Pregnancy Study Groups(IADPSG)が The Hyperglycemia and Adverse Pregnancy Outcome(HAPO) Study 1)をもとに、世界統一の妊娠糖尿病診断基準を提唱したのち 2)、わが国でも2010年7月から取り入れられた。2015年8月に、日本糖尿病学会の診断基準と日本産科婦人科学会、日本糖尿病・妊娠学会の診断基準の一部不一致を統一し、現在の診断基準に至っている 3)。 表1 妊娠中の糖代謝異常と診断基準(日本糖尿病・妊娠学会と日本糖尿病学会との合同委員会: 妊娠中の糖代謝異常と診断基準の統一化について. 糖尿病. 2015; 58(10): 801-803より) 2.糖尿病合併妊娠について 糖代謝異常合併妊婦は正常妊婦と比べて周産期合併症のリスクが高いため、妊娠前からの厳重な血糖管理を行い、計画的な妊娠が必要である。妊娠中には週数に応じた急激な変化に合わせて厳格に血糖管理をしていく必要がある。本項では妊娠前のプレコンセプションケアから糖代謝異常合併妊娠の周産期の管理、そして産後の管理についても触れたい。
2025年02月18日 -
特集
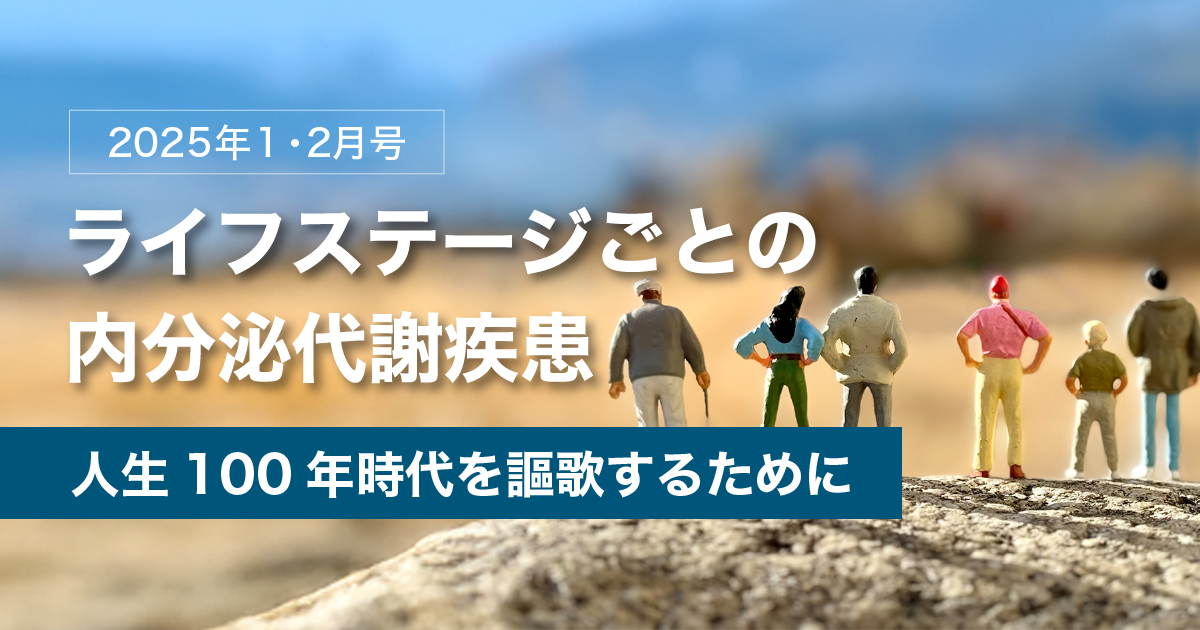
4.女性の更年期障害とホルモン補充療法
はじめに 女性は、卵巣から分泌されるエストロゲンの影響を大きく受ける。10代の思春期にはエストロゲン分泌が増加し二次性徴や初経が発来する。20〜30代の性成熟期を経て40代になると卵巣機能は急激に低下しエストロゲン分泌が低下する。卵巣機能の低下によって、月経が1年間発来せず、永久に停止すると「閉経」となる。日本人女性の平均閉経年齢は約50歳であり、閉経の前後5年ずつの合計10年を更年期と呼ぶ 1)。この更年期の時期に出現するさまざまな症状を更年期症状といい、そのうち日常生活に支障をきたすものを更年期障害という。更年期障害はいわゆる不定愁訴と呼ばれ、さまざまな要因が絡み合って生じることが指摘されているが、卵巣機能低下によるエストロゲン分泌の低下が主な要因である。本稿では、女性の更年期障害の病態と診断・治療について解説する。 1.女性の更年期障害の病態 女性におけるエストロゲンは、子宮・乳房などの成熟、骨密度の上昇、周期的な排卵・月経、妊娠・分娩といった女性特有の生理機能に重要な役割をもつ。卵巣の原始卵胞数は生涯で増加することなく年齢とともに徐々に減少し、35~38歳を過ぎた頃から急激に減少する 2)(図1)。この急激な卵巣機能の低下によってエストロゲン分泌が低下することが更年期障害の原因の一つである。この時期のエストロゲンは直線的に低下するのではなく、視床下部-下垂体-卵巣軸のホルモン動態の影響を受けてエストロゲン分泌は「ゆらぎ」を生じる 3)(図2)。この「ゆらぎ」の影響を受けて出現するのも更年期障害の特徴である。さらに、エストロゲン受容体は女性の全身のあらゆる部分に存在するため、更年期障害は多岐にわたる。 図1 年齢による卵巣の原始卵胞数の推移(文献2より作成)
2025年02月12日 -
TRENDS

運動腫瘍学
はじめに Exercise Oncology(運動腫瘍学)は、がん治療の各段階において身体活動や運動が及ぼす影響を評価し、適切な運動処方を目指す新しい学問分野である。近年の研究により、がんサバイバーに対する運動療法は、身体機能の向上だけでなく、精神心理面や生活の質(QOL)の改善、有害事象の減少、生命予後の改善など、多面的な効果があることが明らかになってきている 1)。 1.診療ガイドラインなど、国内外の動向 国際的な診療ガイドラインとして、American Cancer Society(ACS) 2)、American College of Sports Medicine(ACSM) 3)、American Society of Clinical Oncology(ASCO) 4)が、がん患者への運動療法に関する推奨を発表している。ASCOは2022年に発表したガイドラインで、がん治療の副作用軽減のために積極的治療中の運動を推奨している。日本でも2019年に『がんのリハビリテーション診療ガイドライン』が改訂され、がん種や治療目的別の運動の推奨が示されている 5)。 これらのガイドラインで推奨される運動量は、週150分の中強度~高強度の有酸素運動と週2~3回の筋力トレーニングでおおむね一致している。運動療法は一般的に安全であり、有害事象の報告は少ないとされているが 6, 7)、乳がんサバイバーのリンパ浮腫患者では弾性着衣の装着が必要となるなど、特定の状況での注意点も示されている。
2025年02月07日 -
特集
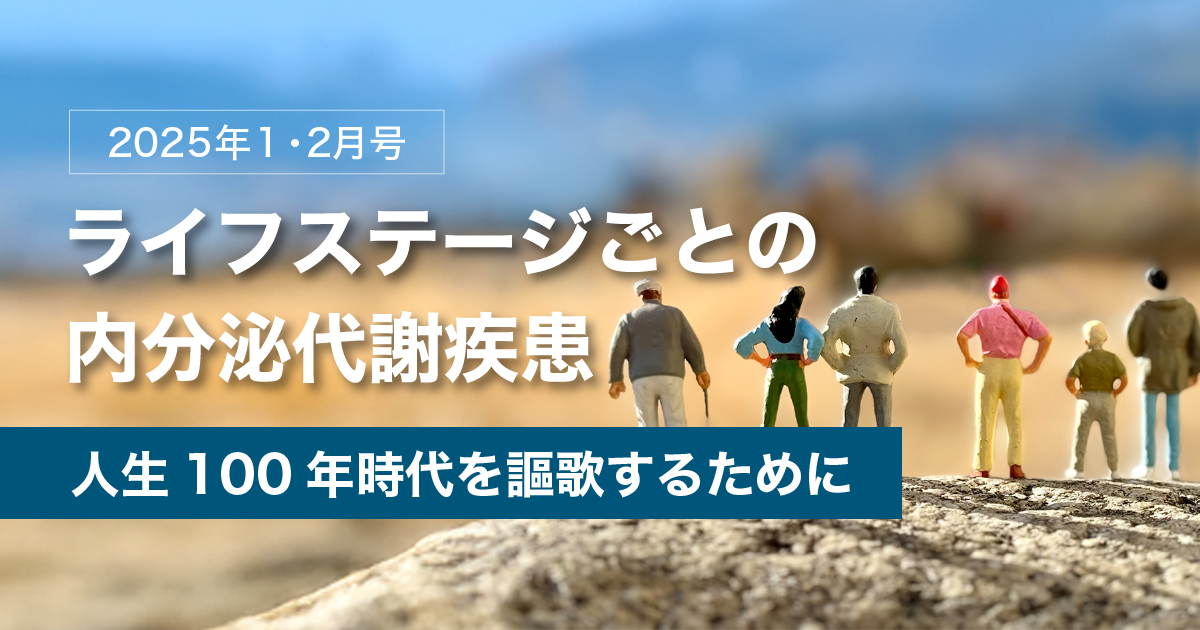
3.小児・思春期1型糖尿病患者・家族への看護師からの指導・支援
はじめに 令和5年(2023年)の日本人の平均寿命は、男性81.1年、女性87.1年となり、女性は90歳で約半数が生存するなど 1)、人生100年時代を迎えている。また、糖尿病のある症例の平均死亡年齢は、男性74.4 歳、女性77.3 歳で、日本人一般の平均寿命に比して短命ではあるものの、その差は縮まってきている 2)。人生は長くなっても小児の成長発達のスピードは変わらないため、相対的に短くなった小児・思春期の中で、その後の長い人生の基礎が培われるようになったといえる。近年、糖尿病医療は、持続皮下インスリン注入療法(continuous subcutaneous insulin infusion:CSII)と持続血糖モニター(continuous glucose monitoring:CGM)を組み合せたSAP(sensor-augmented pump)療法、CGMと連動しグルコース値に応じてベーサルインスリン量を自動的に増減する機能をもつHCL(Hybrid Closed Loop)が開発されるなど、急速に進歩している。1型糖尿病のある小児を取り巻く社会や医療が大きく変化する中で、小児期から成人期への移行を見据え、小児自身が力をつけていくための支援について看護師の立場から述べていきたい。 1.成長発達を中心に据えた支援 1型糖尿病はどの年代でも発症し、生涯にわたり生活の中で管理していくことが求められる。また、1型糖尿病はライフステージや罹病期間が変化しても、インスリンの補充と血糖モニタリング、そして食事や運動、ストレス管理などの健康的な生活が療養の基本となる。成人では年齢というより、生活習慣や糖尿病管理、慢性合併症などの状況、セルフケア能力などをアセスメントし支援が行われる。一方、成長発達の途上にある小児では、成長発達段階により身体の構造や生理・機能、認知機能や社会性などが大きく異なるため、成長発達段階を中心に据えて支援が行われる特徴がある。 1型糖尿病発症時の成長発達段階により、発症時に必要な支援だけでなく、思春期に必要となる支援も異なってくる。幼児期から小学校低学年の年少で発症した思春期患者では、糖尿病のある生活体験が豊富で疾患管理が普通になっており、成長とともに少しずつ疾患管理ができるようになっている。一方で、親や周囲からサポートされてきたことで、思春期に自ら説明したり医療者と直接話すことに困難を生じやすく、小児自身で判断し行動できるような支援が重要となる。思春期発症の患者では、発症時に本人が大きなショックを受けやすく、短期間で基本的な疾患管理ができるようになっても、退院と同時に多様な場で適切な疾患管理を求められ、状況に応じたインスリン調整や生活の工夫、周囲への説明やストレス対処などが必要となり、周囲からのサポートを必要としている。その一方では、医療者と親を介さずに話ができ、疾患管理が役立つと認識できると前向きに捉えられる強みもある 3)。患者がCSIIやCGMなどの知識や技術を習得していても、患者の気持ちや生活での困りごと、周囲のサポートについてよく話を聞き、本人の望む生活が実現できるように具体的に情報提供をしたり相談に乗る支援が重要になる。 疾患管理の基盤となる生活習慣についても、小児は生活習慣を築いていく過程にあり、糖尿病の有無によらず、生きるための基本で小児の健全育成に必須となる健康的な生活習慣を育む視点が重要である 4)。小児期に獲得された生活習慣は生涯にわたり継続されやすいとされており、小児期に健康的な生活習慣を育む支援は、成人期以降の健康的な生活習慣のためにも必要である。
2025年02月03日 -
連載

第1回 FLOW
今回の論文 Perkovic V, Tuttle KR, et al. ; FLOW Trial Committees and Investigators : Effects of Semaglutide on Chronic Kidney Disease in Patients with Type 2 Diabetes. N Engl J Med. 2024; 391(2): 109-121. [PubMed] はじめに 今回から3回にわたって「エビデンスの裏側 ―眼光紙背に徹す論文読解学―」として論文を読んでいきます。エビデンスにはいくつかのレベルがあり、専門家の意見(expert opinion)もエビデンスに含まれますが、最も信頼度の低いエビデンスに分類されます。逆に最も信頼度が高いのは複数のランダム化比較試験(RCT)のメタ解析とされます。しかし、専門家の査読(peer review)を経て学術ジャーナルに発表された臨床論文を正しく解釈することが肝要です。 臨床試験にはいろいろな試験デザインがありますが、RCT以外の臨床試験は介入と結果との因果関係を考察できないので、本連載ではRCTのみを取り上げます。臨床的問題を解決するために論文を選択して読む方法論としては、EBMの手順を使用することが便利です。EBM(Evidence Based Medicine)の実践手順は「STEP1:臨床問題の定式化」、これはPICO(Patient, Intervention, Comparison, Outcome)を用います。「STEP2:情報収集」、これは具体的には論文検索ですがPubMedにこだわらずGoogleでも十分可能です。「STEP3:論文の批判的吟味」、ここでは後述する論文の内的妥当性(internal validity)を評価します。「STEP4:情報の患者への適用」、ここでは結果の一般化可能性(generalizability)も評価します。そして「STEP5:STEP1~4のフィードバック」の5STEPになります 1)。 糖尿病性腎症(DN)は糖尿病の3大合併症の一つで、現在でも透析導入の主要原因疾患の一つです。しかし近年では疾患概念としては古典的なDNではなく、糖尿病関連腎臓病(DKD)とする捉え方が広まりつつあります。以前は蛋白尿を呈したDKDに対する薬物療法としてはレニン・アンジオテンシン系(RAS)阻害薬(アンジオテンシン変換酵素〔ACE〕阻害薬/アンジオテンシンⅡ受容体拮抗薬〔ARB〕)のみでしたが、ご存じのようにここ数年はRAS阻害薬の次の一手としてのSGLT2阻害薬の位置づけがほぼ確立しました。さらに非ステロイド型ミネラルコルチコイド受容体拮抗薬(MRA)フィネレノンの有効性も明らかになっています。 一方、GLP-1受容体作動薬は体重減少作用に加えて動脈硬化性心血管疾患(ASCVD)の再発抑制作用が明らかにされてきました。リラグルチドのLEADER試験はGLP-1受容体作動薬の総死亡抑制効果を初めて示した試験ですが、その試験の後付け解析でリラグルチドのDKD進展抑制効果が報告されました 2)。その後も複数の心血管アウトカム試験CVOT(cardiovascular outcome trials)のメタ解析でGLP-1受容体作動薬のDKD抑制効果が示唆されましたが、臨床的腎アウトカムを主要評価項目としたRCTはこれまで報告がありませんでした。それに答えたのが本試験FLOW(Evaluate Renal Function with Semaglutide Once Weekly)になります。
2025年01月28日 -
セミナー

薬物の生体内動態 ―吸収―
はじめに 生体に投与された薬物が効果を出すためには、何らかの方法によって薬物が目的とする作用部位へと到達する必要がある。薬物の投与方法にはさまざまなものがあるが、全身に薬物を運ぶ血流に直接薬物を乗せる静脈投与や動脈投与以外の方法で薬物が投与された場合、例えば臨床で利用されている経口投与や筋肉注射、坐剤による直腸内投与などの場合には、投与された部位から血流に薬物が乗るために「吸収(absorption)」という重要なプロセスを踏む。生体に投与された薬物は、その後「分布(distribution)」、「代謝(metabolism)」、「排泄(excretion)」という働きかけを生体により受ける。生体が薬物に対して行うこれら4つの作用について、それぞれの頭文字をとってADME、あるいは薬物動態と呼ぶ。薬物が生体に投与された後、薬物動態の第一段階としてどのように吸収されるかは臨床現場で薬物治療を行う際に重要な情報である。 1.生体膜の透過性 薬物の吸収は、その他の薬物の体内動態様式である分布・代謝・排泄と同様に、細胞膜を通して行われる。その細胞膜を薬物が通過する際に重要なのは、薬物の分子の大きさと形、溶解性、タンパク結合率、イオン化の程度、脂溶性などである。一般に細胞膜を通過できる薬物は非イオン型で、タンパクと結合していない遊離型である。また、分子量が100〜200以下の薬物はイオン型でも細胞膜の細孔を通って膜を通過できる。細胞膜は脂質の二重構造の中にタンパク質が浮かぶ形をとっている。このような構造上の特徴から、水溶性の薬物より脂溶性の薬物のほうが膜を通過しやすい。多くの薬物は膜の両側の濃度の差(電気化学ポテンシャル)に従って受動拡散(passive diffusion)するか、あるいは油・水分分配係数に比例して膜に溶解して浸透する。 薬物動態を考えるにあたり、さらに重要な膜透過の機序は(輸送)担体(トランスポーター)の介在する膜輸送(carrier-mediated transport)である。このメカニズムには二種類があり、①エネルギーを必要とする能動輸送(active transport)と、②エネルギーを必要としない促進拡散(passive facilitated diffusion)がある。両者に共通する特徴は、薬物の選択性、類似物質による競合的阻害、輸送速度の限界(可飽和性)である。トランスポーターの介在する膜輸送は、投与された薬物の吸収のみならず、薬物の作用機序や内因性物質の膜透過に重要な役割をもっている。 薬物はその多くが弱酸または弱塩基を示し、溶液中では非イオン型とイオン型分子が平衡状態を保って存在している。一般に薬物分子は分子量が小さいため、膜の脂質成分を介する拡散により膜を透過する。非イオン型は通常脂溶性であり細胞膜を通過できるが、イオン型は水溶性が高く容易に膜を通過できない。 薬物には固有のpKaがあり、周囲のpHとともにその薬物の非イオン型とイオン型の割合が決定される(Henderson-Hasselbalchの式)。 Henderson-Hasselbalchの式 酸性薬物:pKa=pH+log(非イオン型モル濃度/イオン型モル濃度) 塩基性薬物:pKa=pH+log(イオン型モル濃度/非イオン型モル濃度)
2025年01月24日 -
特集
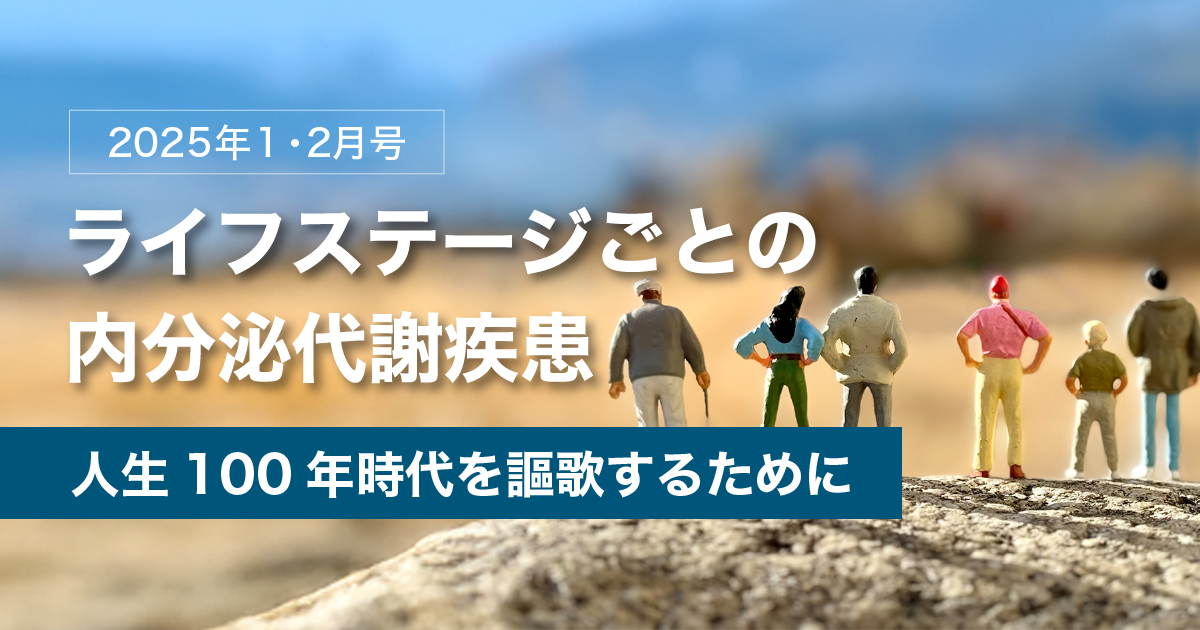
2.Childhood Cancer Survivor(CCS)の小児期から成人にかけての内分泌診療
1.小児がん診療の現況 近年のがん診療の進歩に伴い、予後の改善が目覚ましい。とりわけ、治療感受性の高い血液腫瘍、脳腫瘍の多い小児がんにおいては成人のがんに先駆けて高い生存率を示しており、2002~2006年の時点ですでに80%近い発症時5年生存率を示してきた 1)。わが国の小児がん発生率を年間2,000~2,300人 2)とすると、各年齢層の約500~600人に1人が小児がんサバイバー(Childhood Cancer Survivor:CCS)ということになる。また、生物学的に悪性腫瘍ではない頭蓋咽頭腫なども治療後合併症の多さから慣例的にCCSの一部として扱われる。 2.内分泌後遺症の実態 高い生存率は達成されたが、その全てが後遺症なく治癒したわけではない。がん自体、またはその治療による後遺症はさまざまな臓器に及ぶが、中でも内分泌合併症は最も高頻度である 3)。小児がんは成人発症のものと異なる疾患スペクトルを持ち(図1)4)、小児期に多い白血病、脳腫瘍、リンパ腫や乳児期に多い肝芽腫、ウィルムス腫瘍、網膜芽腫などが特徴的である。脳腫瘍のうちでも小児期はmidlineの腫瘍(胚細胞腫、頭蓋咽頭腫、髄芽腫など)が多いことが知られている。主要な内分泌晩期合併症の概略を以下に述べる。疾患の種類、治療の種類によってあらかじめ起こり得る内分泌異常を予測し、モニタリング、加療することは極めて重要で、詳細については日本小児内分泌学会編『小児がん内分泌診療の手引き』 5)(以下、手引き)に記載されている(表1)。小児がんの内分泌診療について、治療中から治療後に至るまでのモニタリング、診断から具体的な治療方法に至るまで詳述されている。 図1 地域がん登録における小児・AYAがんの内訳(2009~2011年)(がん研究振興財団: がんの統計2023. 2023, p.105より作図)
2025年01月21日 -
セミナー

インクレチン(GLP-1・GIP/GLP-1)受容体作動薬の最新エビデンス
ポイント インクレチン(GLP-1・GIP/GLP-1)受容体作動薬には注射薬と経口薬がある。 セマグルチドには2型糖尿病治療薬と肥満症治療薬がある。 チルゼパチドはGIP/GLP-1受容体作動薬であり、GLP-1受容体作動薬とは異なる。 各剤の評価のポイントは血糖降下作用、体重への影響、心血管イベントや腎イベント抑制など。 はじめに 日本で初めてGLP-1受容体作動薬のリラグルチドが発売されたのは2010年である。その後、エキセナチド(バイエッタ、ビデュリオン)、リキシセナチド(リキスミア)、デュラグルチド(トルリシティ)、セマグルチド注射薬(オゼンピック、ウゴービ)と経口セマグルチド(リベルサス)と開発が進むにつれ、注射投与間隔が毎日から週一回に延び、経口薬の選択肢も出てきて投与のハードルが下がった。また、注射薬の投与デバイスの開発も並列して進み、よりいっそう使いやすいデバイスになった。もはや糖尿病の注射治療といえばインスリン、という時代ではない。 GLP-1受容体作動薬やGIP/GLP-1受容体作動薬(以下、合わせてインクレチン受容体作動薬)の血糖降下作用は既存の経口糖尿病治療薬を上回り、SU薬、グリニド薬やインスリンと併用しない限りは重篤な低血糖を起こさない、という作用機序であることから糖尿病を専門としない医師からの処方も増やすことになった。 GLP-1受容体作動薬セマグルチドは2型糖尿病治療(オゼンピック)のみならず、肥満症の治療薬(ウゴービ)としても承認された。そして2型糖尿病や肥満症において大血管症や腎疾患、肝疾患に対する効果に関するエビデンスも出つつある 1~9)。 ここでは日本で多く使用されているGLP-1受容体作動薬セマグルチド、デュラグルチドと、GIP/GLP-1受容体作動薬チルゼパチド(表1)を中心に最新エビデンスを交えながら解説する。 表1 主なインクレチン受容体作動薬
2025年01月15日 -
特集
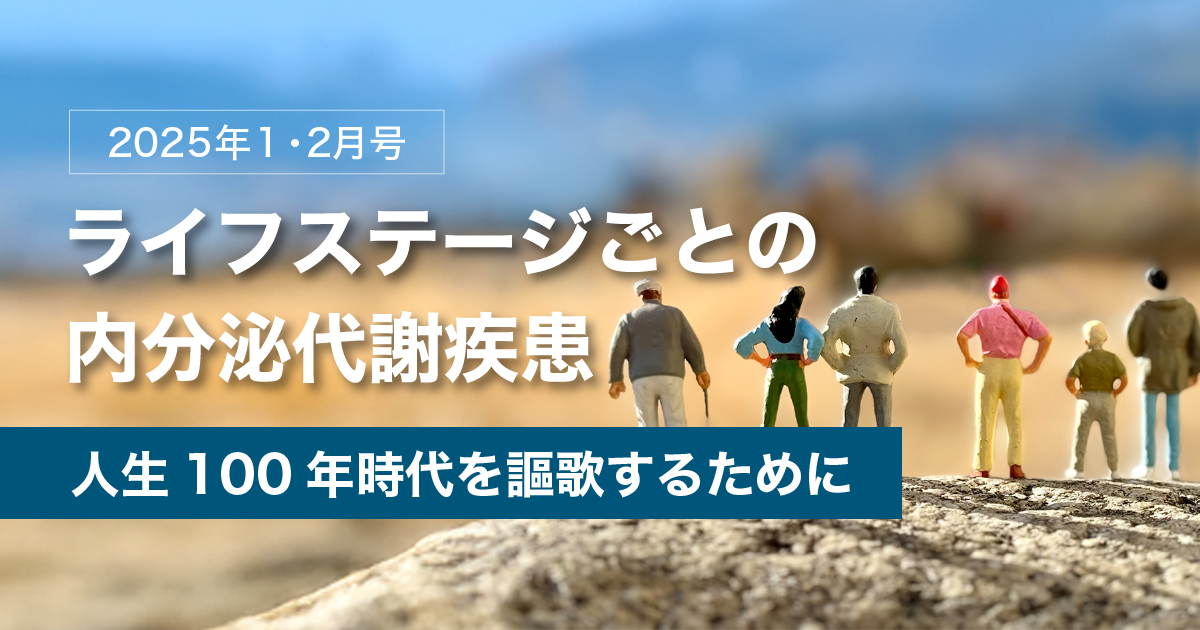
1.成人期を見据えた小児期発症1型糖尿病の診療
はじめに 小児期発症1型糖尿病の医療的ケアはライフステージ(乳幼児期、学童期、思春期)により異なる。それは子どもの成長段階におけるセルフケア能力が異なり、かつ病気の理解力、考える能力も異なるからである。多くの場合、初期治療は入院で行われ、その後、外来で子どもの血糖管理状況を把握し、より良くしていくための診療が行われる。その際に、時々長期的な視点で子どもの発達状況に応じ、少し先を見据えて、病気に関するセルフケアを増やしていき、親のケアが自然に少なくなるように導くことができれば理想的である。本稿では、ライフステージごとの診療上の留意点を解説しながら、どのように先を見据えて診療していけばいいのかについて考察した。 1.小児のライフステージ別の医療的ケア 小児慢性特定疾患事業へ2007~2008年に新規登録された1型糖尿病患者1,082人の発症年齢分布によると、小児期全般に発症が見られ、思春期に入り(10~14歳にピーク)その発症が多くなる 1)。具体的な医療的ケアについて乳幼児期、学童期、思春期それぞれのステージ別に述べる。 1)乳幼児期 育児にとても手がかかり、親子関係が密接な乳幼児期に発症した子どもを持つ親にとって病気のケアを行うことは、とても大変であることは容易に想像される。発症当時、親はケアに対する自信はなく、不安を抱くばかりであるため、具体的なケアの方法を繰り返し説明し、失敗しても次に生かせばいいことをアドバイスする。祖父母などの協力を提案したり、患者家族会に参加してピアサポートを促したり、同じくらいに発症したケースの数年先の様子などを話したりすると気持ちが和らぐことがある。 インスリン投与は自分で注射ができないことが多く、インスリンポンプを用いた持続皮下インスリン注入療法(CSII)が多く選択される。小児インスリン治療研究会第5コホート研究によると半数以上がCSIIで加療されている(図1) 2)。血糖自己測定(SMBG)は上手に教えれば4~5歳頃から自分でできるようになる。最近は持続血糖モニター(CGM)を発症早期から使用するケースが増え、センサの穿刺・交換はこの時期に自分ですることは困難である。体が小さいため穿刺する部位が臀部に集中し、ローテーションも不十分となりやすい。成長とともに穿刺する部位を大腿や腰部などに拡大していきながら、ローテーション指導を継続することが重要である。就学前頃には自分でインスリン注射やSMBGができ、さらにセンサ値の確認、ポンプに糖質量やセンサ値などの入力ができるように準備していく。 図1 ステージ別インスリン投与方法(菊池透: わが国の小児期・思春期1型糖尿病治療の現状. 小児看護. 2021; 44(10): 1234-1239より一部改変)
2025年01月10日 -
特集
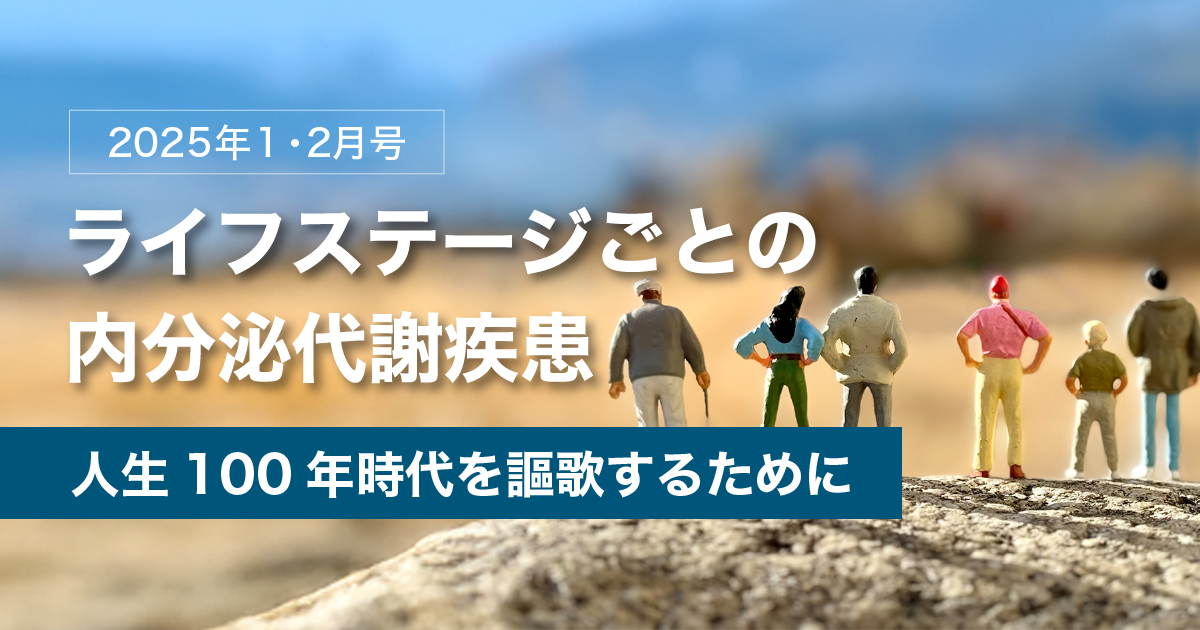
(扉)特集にあたって
「令和6年版高齢社会白書」によると、2023年10月1日現在の日本の高齢化率は29.1%である。65歳以上の人口は1950年(昭和25年)には総人口の5%に満たなかったが、1995年には14%を超え、2005年には20.2%となり、以降も上昇を続けている。さらに2050年には37.1%に達すると推定されている。平均寿命は男性81.09年、女性87.14年と、わが国は世界に誇る長寿国である(厚生労働省「令和5年簡易生命表」)。 一方で、健康寿命は平均寿命より約10年短く、個人の生活の質(QOL)の低下を防ぎ、社会的負担を軽減する上で、健康寿命の延伸が今後の大きな課題となっている。ベストセラーとなったリンダ・グラットン氏の著書『LIFE SHIFT-100年時代の人生戦略-』で提唱された「人生100年時代」。この長い道のりを健やかに、自分らしく生き抜くために、医療従事者が果たす役割の重要性はますます増している。 本特集では、ライフステージ特有の問題を有し、医療ケアが大きく異なる内分泌学的疾患を取り上げ、各分野のエキスパートに執筆をお願いした。小児期発症1型糖尿病について、子どもの成長段階に応じた医療ケアや成人期への移行を見据えたセルフケア能力の習得について、神野和彦先生に執筆いただいた。また、中村伸枝先生には、看護師の立場から、小児・思春期1型糖尿病患者とその家族への指導・支援における心のケアや社会との関わりの重要性について執筆いただいた。さらに、依藤亨先生には、小児がんサバイバーが小児期以降も抱え続ける内分泌後遺症について、ライフステージごとの診療ポイントと成人期医療へのスムーズな移行のための対応について執筆いただいた。そして、人生100年時代の中盤〜後期にかけて、QOLに大きな影響を与え得る女性更年期障害とLOH症候群について、それぞれ北島百合子先生、小川純人先生にその病態と診断・治療の詳細を執筆いただいた。 エキスパートの詳細かつ実践的で読み応えのある本特集の論文が、ライフステージごとのさまざまな臨床現場で活用いただけることを願っている。 著者のCOI (conflicts of interest)開示:菊池 透;講演料(ノボ ノルディスク ファーマ)、原稿料(エムティーアイ) 本論文のPDFをダウンロードいただけます
2025年01月10日 -
特集
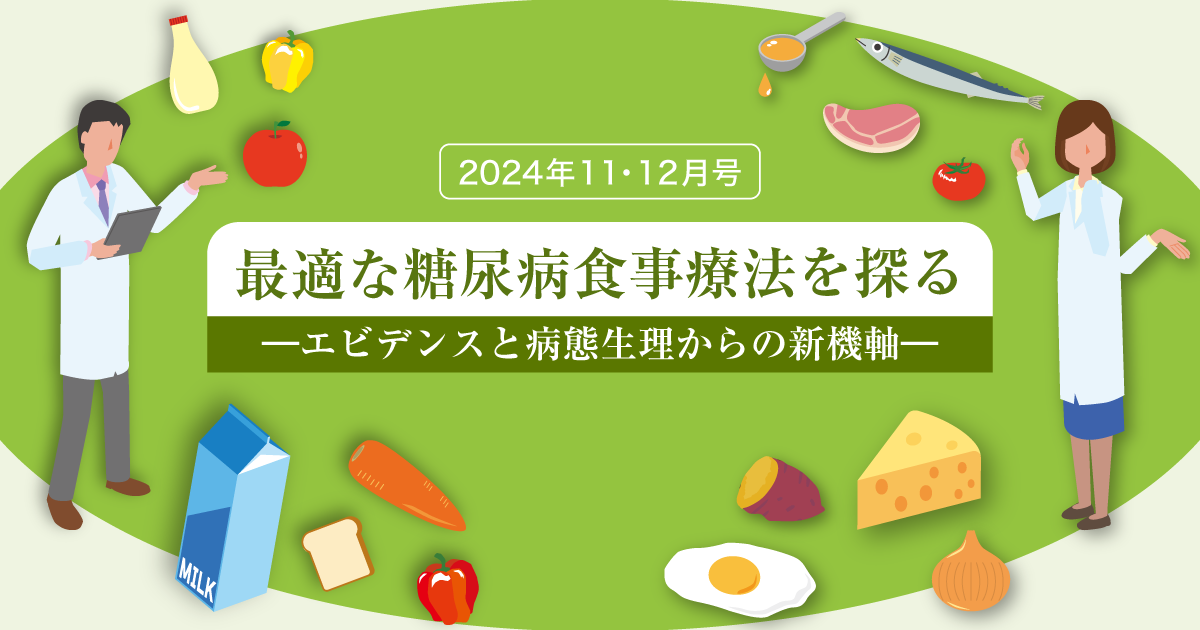
5.高齢者の食事療法
はじめに 高齢化するわが国の糖尿病患者について、エネルギー管理を主とする過剰栄養対策とサルコペニア・フレイルなどの低栄養対策のどちらを主とするのかについてフォーカスし、栄養食事管理に関わるエビデンスを基に解説する。 1.高齢者の低栄養の要因 高齢者では徐々に体組成に変化を生じ、身長、体重の減少、脂肪組成の割合が増加し、筋肉・骨格などの除脂肪(lean body mass:LBM)が減少する。さらに、インスリン分泌低下、身体活動量の低下に伴いインスリン抵抗性を増大させている 1, 2)。 また、複数の疾患と病態を合併している多くのケースは、生活機能障害が高頻度に発生し、その病像を複雑にしている。そこに生活の質(QOL)が低下し、さらに栄養状態の低下が加わることで、看護・介護を必要にしている。糖尿病では糖尿病でない患者と比較してMNA®評価による低栄養が多い 3)。 たんぱく質、エネルギーの過不足状態の持続は体重を減少し、次いでLBMの減少に強く影響する。筋肉・骨格の減少による関節・骨疾患の発症は日常の生活活動を低下させ、栄養摂取量を低下させる4)。 消化器官では、唾液・胃液・胆汁・膵液などの分泌量が減少し、咀嚼機能・嚥下反射・食道および蠕動運動の低下が起こり、消化・吸収機能は全体的に低下する。口腔内では、口腔の乾燥、舌乳頭や味蕾数の減少、味細胞機能の減退などにより味覚の低下が起こり、舌や口腔粘膜の温度覚、触圧覚の減退により嗜好の変化が認められる。また、うつ症状、認知機能障害、意欲低下などの精神障害、孤独感、不安感、疎外感に起因した摂食量の低下も見られ、栄養摂取量の低下は医学的、身体的、心理的、社会的要因を重複し引き起こされる(表1)。 葛谷は、過栄養が健康障害へ関与しているとし、一方では一般に75歳を超えると徐々に体重が減少し、フレイルやサルコペニアを介して、要介護状態に至るプロセスの存在を明示している(図1) 5)。 高齢者糖尿病の入院患者(平均年齢78歳)の調査では、39.1%が低栄養の高リスク状態にあり、21.2%はMNA®スコア低値の低栄養だった。また低栄養素では基本的ADL低下、握力低下、下肢の身体能力低下(椅子から立ち上がり試験)、QOL低下、在院日数の延長、在宅復帰率の減少、死亡率の増加との関連を示していた 6, 7)。 これらは、高齢糖尿病の治療目標となるサロゲートに筋肉・骨格の減少の阻止、関節・骨疾患の発症予防への栄養状態保持を説明づけるものである。 表1 高齢者の代表的な低栄養の要因
2024年12月26日 -
連載

第75回 診療報酬改定2024 ―糖尿病・内分泌疾患に係るDPC/PDPSについて―
はじめに DPC(Diagnosis Procedure Combination)/PDPS(Per-Diem Payment System)は、2003年4月より82の特定機能病院を対象に導入された、急性期入院医療を対象とする診断群分類に基づく1日当たり包括払い制度である。そして2024年6月1日時点で1,786病院・約48万床が対象となり、「急性期一般入院基本料等」に該当する病床の約85% 1)を占める。 今回は、このように普及したDPC/PDPSについて、糖尿病・内分泌疾患を対象に、2024年診療報酬改定に基づいた内容を概説する。 1.DPC/PDPSの基本事項(図1, 表1, 図2)1~3) 包括評価の基本原則として評価の対象は、バラつきが比較的少なく、臨床的にも同質性・類似性・代替性のある診療行為または患者群としている。そして、平均的な医療資源投入量を包括的に評価した定額報酬(点数)を設定し、包括評価(定額点数)の水準は出来高報酬の点数算定データに基づいて算出している。 DPC(診断群分類)は、 ①「診断(Diagnosis)(医療資源を最も投入した傷病名)」 ②「診療行為(Procedure)(手術、処置等)等」の「組合せ(Combination)」 これらの順に14桁の英数字で構成され、DPC/PDPSは診断群分類に基づく1日当たり定額報酬算定制度を意味する。DPCの14桁の英数字のうち、図1のように上6桁の1層目は傷病名の層で、表1に示すMDC(Major Diagnostic Category:主要診断群)コード18種類と傷病名の細分類は疾患コードで、医療資源病名がどの6桁分類に属するかを示す。9・10桁目の2層目は手術の層で、実施した手術がどの手術分類に属するかを示す。11~14桁目の3層目は処置、副傷病名、重傷度の層で、手術・処置1、2、副傷病の有無、重症度などを示す。なお、「手術」、「手術・処置等1、2」で示されるKコードは、医科診療報酬点数表で定めている手術のコードである。「定義副傷病名」で示されるICDコードは、「疾病および関連保健問題の国際統計分類:International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems」であり、世界保健機関が作成した分類である。 画像をクリックすると拡大します 図1 DPCの構成(項目の詳細)(文献2より) 図1 DPCの構成(項目の詳細)(文献2より) $(".vol6_r11_z1").modaal();
2024年12月23日 -
TRENDS

スポーツ栄養学 ―スポーツ現場におけるビタミンD栄養を考える―
脂溶性ビタミンの一種であるビタミンDは、食事からの摂取のほか、紫外線の作用により皮膚でかなりの量が産生されるユニークな栄養素である。ビタミンDの最も基本的作用は、腸管におけるカルシウム・リンの吸収促進であることから、ビタミンD不足は骨の脆弱化を招き、骨折リスクを高める。フィンランドの若年男性を対象とした研究では、ビタミンD栄養状態の指標である血中25ヒドロキシビタミンD(25OHD)濃度の低値において、疲労骨折の発生率が増加したことを示しており 1)、スポーツ現場における骨障害予防の観点からもビタミンDの栄養状態を良好に保つことは重要なテーマといえる。さらに近年、ビタミンDと免疫、骨格筋、脂質代謝、心血管疾患などとの関連があるなど、アスリートのコンディショニングや競技パフォーマンスを向上させる可能性のあるエルゴジェニック特性がある栄養素としても注目されている 2)。 ビタミンD不足は世界的な問題となっているが、日本人を対象とした疫学研究においても、ビタミンD欠乏の指標となる20ng/mL付近またはそれを下回る低い結果が報告されている。『日本人の食事摂取基準(2020年版)』3)では、日照によって皮膚で産生されるビタミンDの量を差し引き、食事からの摂取目安量を8.5μ/日としているが、国民健康・栄養調査の結果でも、日本人のビタミンD摂取状況は6.2μg/日と十分な摂取に至っていない 4)。その原因は、表1に示すようにビタミンD供給源となる主な食品が一部の魚類ときのこ類などに限られていることにある。ビタミンD含有量の多い鮭であれば1切(100g)で約32μgのビタミンDを含むため、週3~4回程度、習慣的に摂取すれば約15μg/日程度のビタミンD摂取が可能となる。まずは習慣的な魚の喫食の見直しや、ビタミンDが強化された乳製品などを積極的に活用したい。
2024年12月19日 -
特集
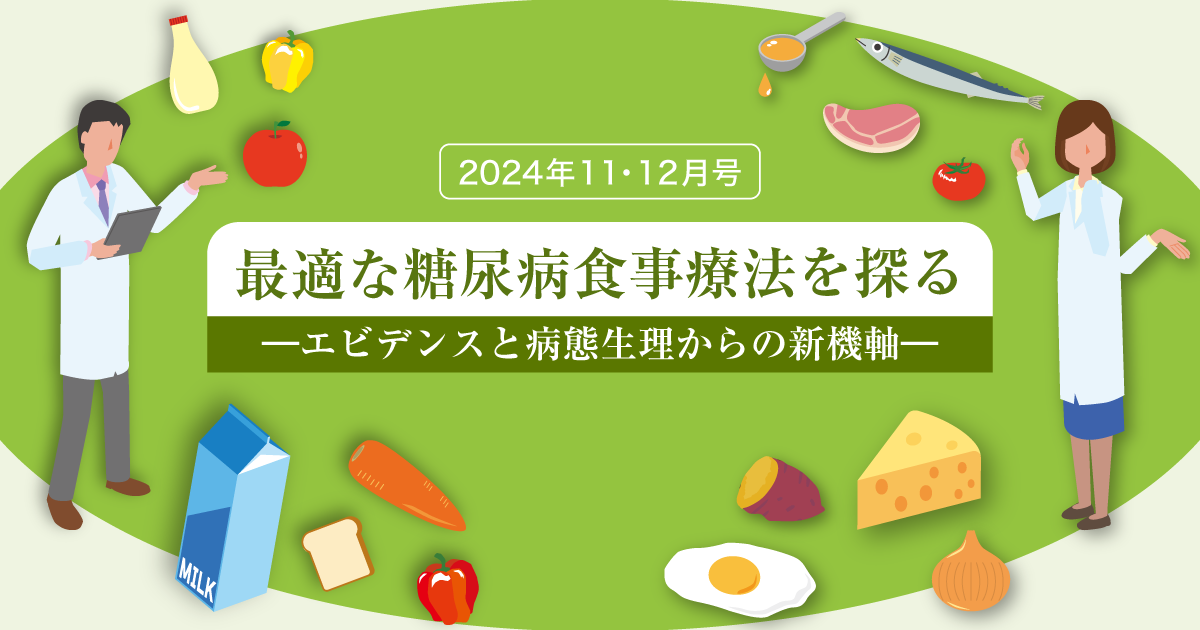
4.糖尿病性腎症の食事療法
はじめに 糖尿病を有する患者も高齢化が進んでおり、高齢者糖尿病は腎症を含む最小血管症や動脈硬化性疾患のほか、認知症、サルコペニアなどの併存疾患をきたしやすい 1)。 糖尿病性腎症の食事療養基準として、「CKDステージによる食事療法基準」(表1)を参照するが、CKDは病期の進展とともに、たんぱく質やリン、カリウム、食塩の制限が必要になる。そして、これらは摂取エネルギー不足となり、Protein Energy Wasting(PEW)をはじめとする低栄養状態を招くことが多い。その上、糖尿病や腎臓病は病態そのものからくる炎症性代謝亢進も加わるため、さらに注意が必要である。 これらのことを踏まえ、サルコペニアを有する高齢者糖尿病性腎症の食事療法について概説する。 表1 CKDステージによる食事療法基準(日本腎臓学会: 慢性腎臓病に対する食事療法基準2014年版. 東京医学社, 東京, 2014, p.2より改変) 『慢性腎臓病に対する食事療法基準2014年版』で示されている「CKDステージによる食事療法基準」をベースに、食塩については『エビデンスに基づくCKD診療ガイドライン2023』の内容を考慮し、下限値を外した。※別表については本出典元を参照のこと 1.サルコペニアを有する高齢者糖尿病性腎症の食事療法 1)エネルギー (1)CKDステージによる食事療法基準 エネルギー(表1)は、CKDステージ1~5まで同様で、25~35kcal/kgBW/日と幅がある。CKDはステージが進展すると、たんぱく質をはじめとする各種の栄養素制限が必要になり、それによりエネルギー不足になる患者も多い。そのため、病態、現体重と目標体重の差、身体活動レベルなどを考慮した個別のエネルギー適正量の設定のための幅であると考えられる。 (2)エネルギー不足の傾向と対策 2型糖尿病を有する高齢患者を対象とした研究で、サルコペニアを有する患者は、サルコペニアを有さない患者に比較して、たんぱく質ではなく、エネルギーと脂質の摂取量が少なかったとの報告がある 2)。サルコペニア対策となると、たんぱく質に注目しがちだが、必要エネルギー量が摂れているのかを確認し、糖質や少量高エネルギー源の脂質の上手な摂取方法を指導すべきである。 高齢になるとあっさりしたものや口当たりのよい食べ物を好む傾向にあり、脂質の摂取比率が減り、炭水化物では水分が多く、口当たりがよい果物が増え、エネルギーと植物性たんぱく質の大切な供給源の穀類が減る 3)。『日本食品標準成分表2020年版(八訂)』で確認すると、100g当たりの「米飯」は156kcal、「果物 生」94品の平均は52kcalとなっている。 当院では入院食で、中鎖脂肪酸油と低リン・低カリウムのプロテインパウダーを使用した少量・高エネルギー・高たんぱく・低リン・低カリウムの粥、味噌汁、スープ、ゼリーなどを栄養サポートチーム(NST)介入とともに提供している。外来患者には中鎖脂肪酸油は高額で、町のスーパーでは容易に入手できないため、ごま油を勧めている。醤油との相性もよく、香ばしいため食欲をそそり、昔からなじみの深い食品である。おすすめレシピは軟らかめのご飯にサケフレークを混ぜ入れ、ごま油と醤油で混ぜた「鮭のやわらかご飯」である。筆者自身、父の介護時に活用し、食欲がなく食べてくれない時でも、このメニューは口を開けてくれた。美味かつ時短のおすすめのメニューである。
2024年12月13日 -
連載
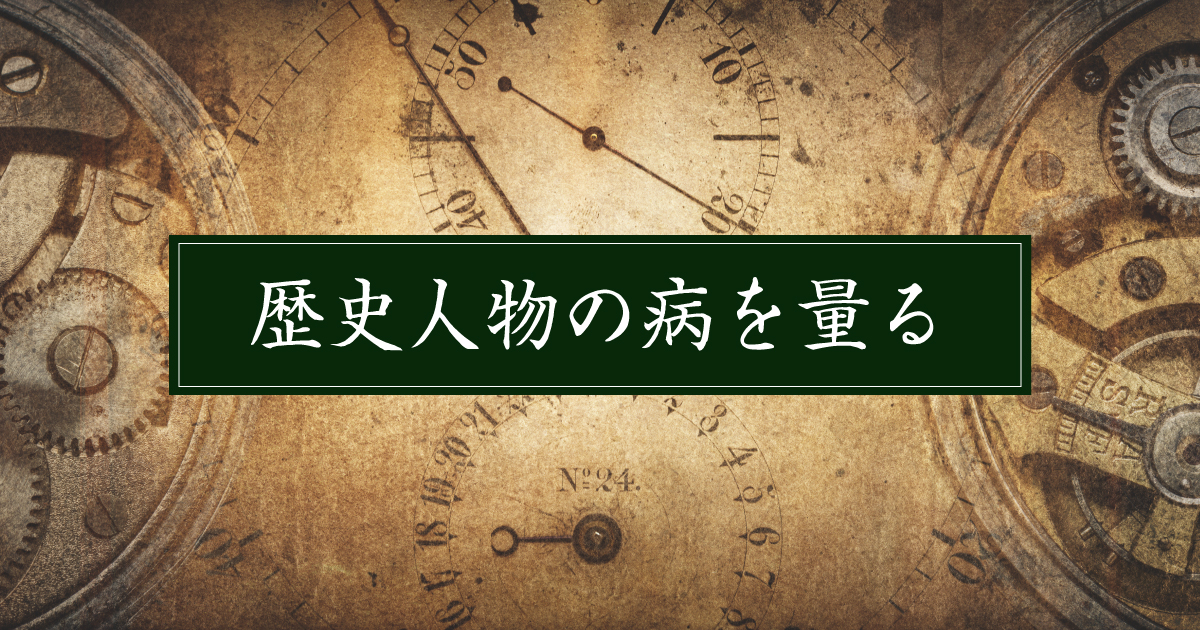
第6回 北原白秋と糖尿病の合併症
北原白秋、本名隆吉が生まれたのは1885年(明治18年)1月25日(戸籍上は2月25日)であった。実家は江戸時代から柳川藩の御用達であった豪商一族で、長男が死去していたため、事実上長男として育った。2歳で腸チフスに罹患し、同時期にかかった乳母は死去した。1897年(明治30年)2年の飛び級で福岡県立の尋常中学伝習館に進むも、いくばくの成績が足りず2年生に落第、この留年が心の傷となり5年生の後半にノイローゼで休学、結局は退学し、私立である早稲田大学英文科予科に入学した。白秋は中学3年生の頃から表現活動を始め、同時期に島崎藤村の『若菜集』に没頭した。実はこの時期に白秋の生家が大火にて類焼し酒倉が焼け落ち、以降没落していった 1, 2)。早稲田入学時には潤沢な仕送りがあったが、1909年(明治42年)、白秋が24歳の処女詩集『邪宗門』が刊行される年には破産に至った。その2年後、詩集『思ひ出』を上梓、人妻とのスキャンダルもあったが、歌集や童謡集などさまざまな分野で作品を発表し文壇での地位を確立した。 図 北原白秋(不明Unknown author, Public domain, ウィキメディア・コモンズ経由で)
2024年12月11日