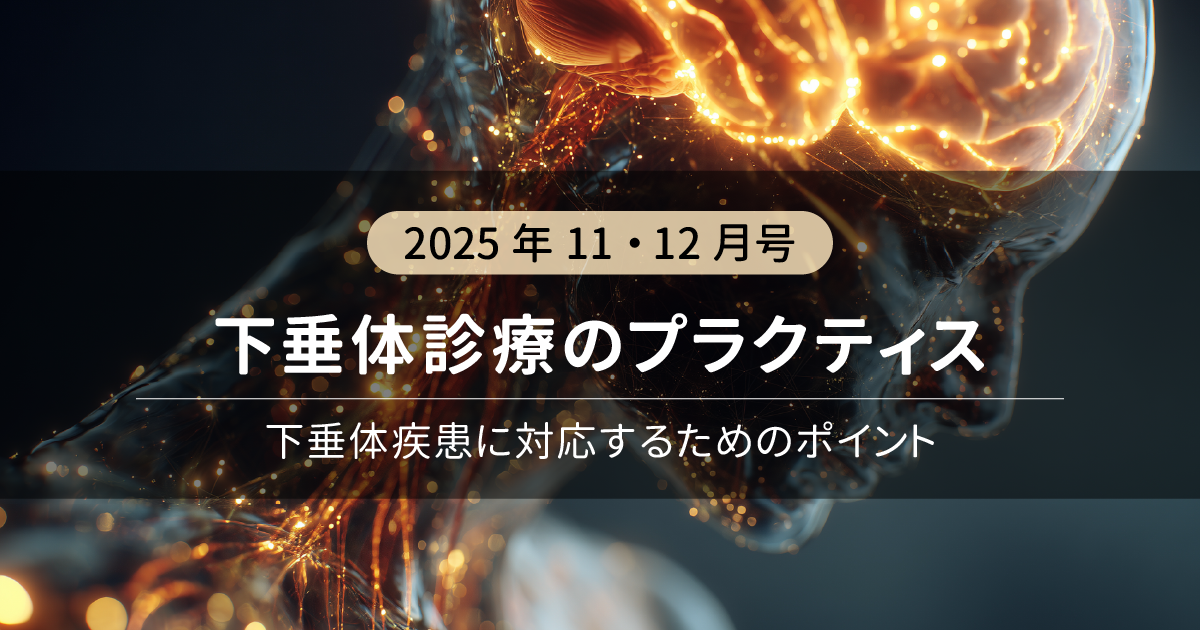- トップページ
- 新着論文一覧
新着論文一覧
-
特集
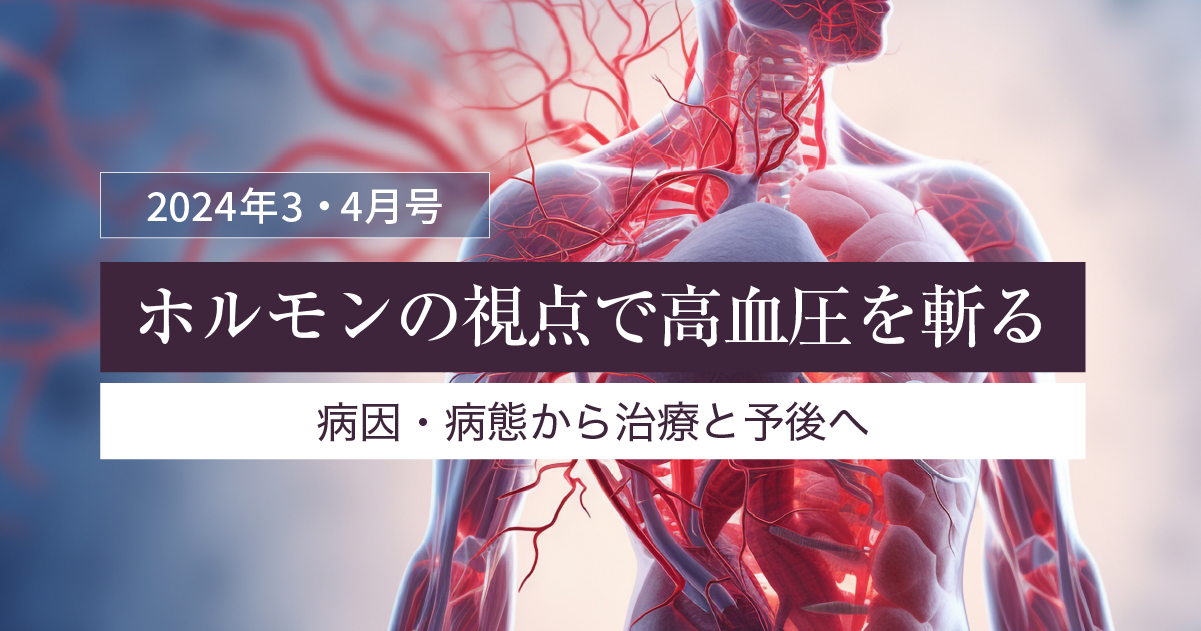
5.糖尿病合併高血圧のマネージメント
はじめに 糖尿病治療の目的は、「糖尿病のない人と変わらない寿命とQOLの実現を目指すこと」とされており、糖尿病に関連する合併症を防ぐことである。英国で行われたUKPDS(United Kingdom Prospective Diabetes Study)において血糖以上に血圧コントロールがより有効に、効率的に合併症を防げることが明らかとなり、糖尿病合併高血圧患者の降圧治療は必須である。 糖尿病合併高血圧患者は脳血管障害・冠動脈疾患のハイリスク集団であり、厳格な血圧管理が求められている。高血圧の治療目標が、脳心血管病の抑制であることを考えれば脳心血管イベントの予防を目指した厳格な降圧療法は極めて重要である。これまで高血圧症への治療介入については、従来から豊富なエビデンスの蓄積があるレニン・アンジオテンシン(RA)系阻害薬が中心的な役割を担ってきたが、近年開発された新規ミネラルコルチコイド受容体(MR)拮抗薬や経口血糖降下薬であるSGLT2(sodium glucose co-transporter 2)阻害薬が糖尿病関連腎臓病(DKD)進行抑制効果や降圧作用も併せ持つことが報告されている。 本稿では、DKDの進展抑制において極めて重要な要素である糖尿病合併高血圧症の疫学、病態、治療について、「高血圧治療ガイドライン(JSH)2019」および「糖尿病診療ガイドライン2019」を踏まえながら概説する。さらに、前述したMR拮抗薬やSGLT2阻害薬に加えて、高血圧治療薬として承認されているアンジオテンシン受容体ネプリライシン阻害薬(ARNI)についても最新の知見を述べる。 1.糖尿病合併高血圧症の疫学 国内外の疫学研究によると糖尿病患者では、非糖尿病患者に比べて高血圧の頻度が高く、高血圧患者においても糖尿病の頻度は非高血圧に比べて高いことが報告されている 1)。また、1型糖尿病および2型糖尿病で高血圧を合併すると、大血管疾患発症および死亡のリスクが上昇する。アジア・太平洋地域の前向きコホート研究の個人データに基づくメタ解析(APCSC)によると、糖尿病患者では、収縮期血圧が10mmHg上昇するに従い大血管疾患死亡は18%増加することが示されている 2)。また、2型糖尿病における高血圧症例を非厳格降圧療法群と厳格降圧療法群に割り付け、平均10.5年間追跡した介入研究(UKPDS36)によると、大血管疾患の発生率は、追跡完了までの平均収縮期血圧の上昇とともに増加することが示されている 3)。そのため、糖尿病診療ガイドライン2019のステートメントとして、糖尿病と高血圧はいずれも動脈硬化による大血管疾患の確立したリスク因子であり、糖尿病に高血圧が合併すると大血管疾患の発症頻度が増加し、予後が悪化すると明記されている 4)。 さらに、高血圧症が糖尿病性腎症、糖尿病網膜症、糖尿病性神経障害などの細小血管症のリスク因子となることが1型糖尿病、2型糖尿病ともに報告されている。一般的に、1型糖尿病患者における高血圧症は、微量アルブミン尿または明白な腎症を有する患者に認められる。デンマークの横断研究によると、蛋白尿陰性の1型糖尿病患者で、高血圧症の頻度は一般人口4.4%に対して3.9%であったと報告されている 5)。一方で、2型糖尿病患者における高血圧症は、一般的に腎臓病に先がけて存在する。新規に診断された蛋白尿陰性の2型糖尿病の58% 6)もしくは70%以上 7)に高血圧症の合併が認められると報告されている。すなわち、高血圧発症は腎機能低下には関連するが、糖尿病罹病期間には関連しないことが示唆されている。 このように、アルブミン尿は2型糖尿病よりも1型糖尿病で高血圧に先行するが、両病型とも腎機能の増悪はさらなる血圧上昇に関連する。糖尿病性腎症における高血圧の罹患率は、慢性腎臓病(CKD)の各stageで増加し、末期腎不全患者では90%に近い 8)。腎疾患や高血圧症に対する個々の感受性は、多くの糖尿病患者に共通する代謝性障害と血行動態変化の組み合わせ、さらには各患者の脆弱性をさらに左右する遺伝的決定要因を含む可能性がある。
2024年04月12日 -
セミナー

持続可能な糖尿病運動療法
Q&A編はこちら はじめに ―運動療法に行動経済学を取り入れる 皆さんは、目の前の患者に対して、「なぜ、この方は運動しようとしないのか?」「なぜ、この方も運動療法が続かないのだろう?」と感じたことはないだろうか? そう、「ヒトは不合理な行動をとる生き物」 1)である。運動が体にいいことは100人中100人は分かっている。行動経済学とは、人間が必ずしも合理的な行動をとらないことに注目し、人間の心理的、感情的側面の現実に即した分析を行う学問である。「ヒトは不合理な行動をとる生き物」と考えるのである。 1.ヒトは現在バイアスの中で生きている ―「先延ばし」の心理 2) 例えば、ダイエットをしようとしても今日は食欲を優先し、来週からダイエットをしようと思いがちである。糖尿病の重症化リスクが将来生じるものであるため、その影響を大きく割り引いて考えてしまう。現在症状がないことは過大評価されており、治療開始が先延ばしになる。このように、後々苦労をすると分かっていても目の前のことを先延ばしにしてしまう行動は「現在バイアス」によるといわれている 2)。 バイアスとは、合理的なものから系統的にずれるヒトの意思決定をいう 3)。系統的に逸脱する傾向、先入観ともいえる。糖尿病治療の現場においても、このバイアスを前提に患者への説明が必要になる。その中で、現在バイアス 3)とは、人間が効用の大きさを感じる時、現在に近いほど大きく感じ、先のことになればなるほど小さく感じることを指す。例えば、「今すぐもらえる1万円と1年後にもらえる2万円のどちらを選ぶか?」を考えた場合、後者を選ぶのが合理的だが、実際に多くの人は前者を選ぶ。現在バイアスが働き、ヒトはいますぐ手に入る効用に大きな価値を見出してしまう。あるいは、現状維持バイアス 3)「まだ大丈夫」というバイアスが働く。これは現状を変更するほうがより望ましい場合でも、今までの生活や習慣を失うことを損失と考えてしまって、現状維持を好む傾向を指す。計画はできても、それを実行する時になると現在の楽しみを優先し、計画を先延ばしにしてしまう特性である。このように、重大な意思決定を先延ばしにしてしまう。将来の健康的な状態の価値を大きく割り引いて評価するため、現在時点で発生する費用の方を大きく感じてしまい、積極的な医療健康行動を取らない傾向にある。 患者は糖尿病の重症化リスクについて理解していないわけではなく、それが将来生じるものであるため、その影響を大きく割り引いて考えてしまう。現在症状がないことは過大評価されており、その結果、治療開始が先延ばしになる。 手前にある小さな木と奥にある大きな木を見るとき、遠くから見ると奥の木のほうが大きく見えるが、近くから見ると小さな木のほうが大きく見える(図1)。運動もこれと同じで、今すぐという状態では、将来的な健康が小さく見え、現在の休憩が重要なものに見えてしまうのである 3)。 遠くにあるものの価値が割り引かれるという特性である「時間割引」 3)があり、その結果現在バイアスが生じる。この時間割引が高いものほど、喫煙、肥満が多く、予防接種に参加しない、食事制限、運動療法をしないともいわれているようである。
2024年04月10日 -
連載

第71回 糖尿病と医療計画
はじめに 医療計画 1)は、都道府県が国の定める基本方針に即し、地域の実情に応じて都道府県における医療提供体制の確保を図るために策定するものである。1985年に医療計画制度が導入され、2006年の第五次医療法改正においては、糖尿病を含む4疾病と5事業の具体的な医療連携体制が位置付けされた。そして2024年度からの第8次医療計画では、対象が「5疾病・6事業および在宅医療」となり、都道府県別に6年間の医療計画が策定されて推進される。5疾病は、「がん」、「脳卒中」、「心筋梗塞などの心血管疾患」、「糖尿病」、「精神疾患」、6事業は、「救急医療」、「災害時における医療」、「新興感染症発生・まん延時における医療」、「へき地の医療」、「周産期医療」、「小児医療(小児救急を含む)」であり、これらに「在宅医療」が加わる。今回は、この医療計画と、その中核に含まれる糖尿病について概説する。 1.医療計画の歴史 2)(表1) わが国の衛生法規の根幹をなす医療法は1948年に制定され、第一条に掲げる「医療を受ける者の利益の保護及び良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を図り、もって国民の健康の保持に寄与すること」を目的とする。そして1985年に、医療施設の量的整備が全国的にほぼ達成されたことに伴い、医療資源の地域偏在の是正と医療施設の連携の推進を目指して医療計画制度が導入された。そして都道府県の二次医療圏ごとの病床数の設定、病院の整備目標、医療従事者の確保などを記載し、2006年の第五次医療法改正により、4疾病・5事業の具体的な「医療連携体制」について記載されることとなり、2014年には「地域医療構想」が追加された。そして2017年には5疾病・5事業および在宅医療に係る指標の見直しにより「政策循環の仕組み」が強化され、2019年の通知では「外来医療計画」および「医師確保計画」が位置付けられることとなった。 表1 医療計画の歴史(文献2より) 画像をクリックすると拡大します 表1 医療計画の歴史(文献2より) $(".vol2_r14_h1").modaal();
2024年04月05日 -
特集
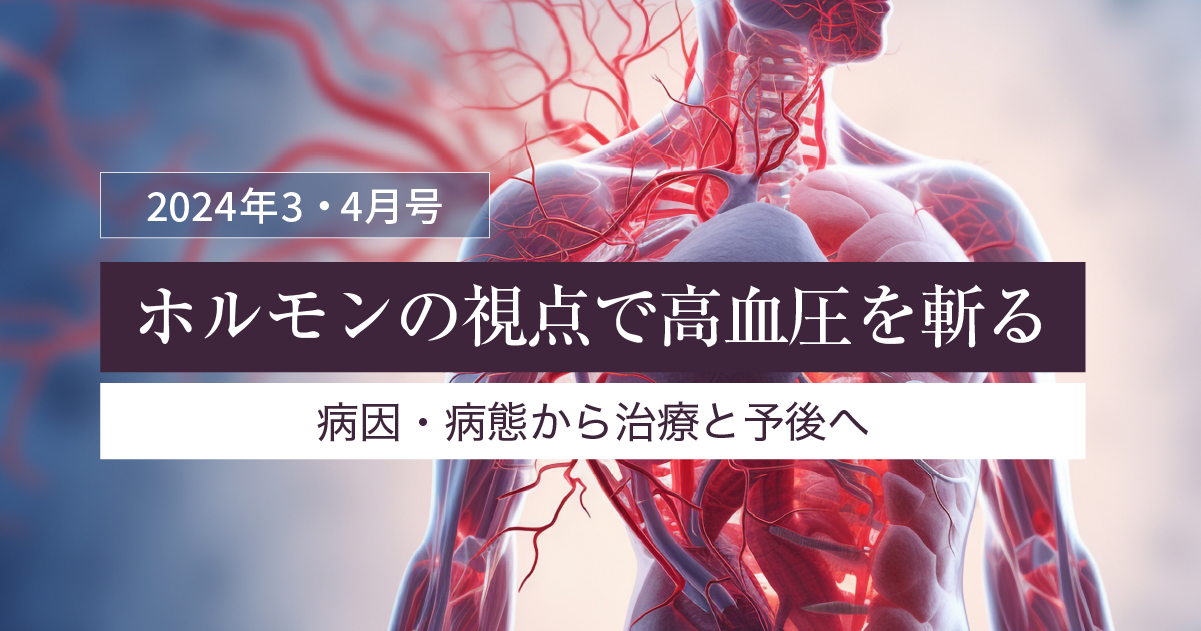
4.内分泌性二次性高血圧アップデート
はじめに 二次性高血圧は、ある特定の原因による高血圧であり、一般に難治性である。しかし原因を正しく診断し治療が行われれば、その後血圧の改善の見込みもある疾患であり、適切な診断、治療が求められる。今回、二次性高血圧の中でも内分泌異常が原因となる原発性アルドステロン症、クッシング症候群、褐色細胞腫・パラガングリオーマについて述べる。 1.原発性アルドステロン症(primary aldosteronism:PA) 1)疾患の概要 PAは高血圧全体の3~12%程度 1)を占める非常に多い疾患である。PAは副腎からのアルドステロン過剰産生により、腎尿細管でナトリウムの再吸収が促進され高血圧をきたし、同時にカリウム排泄を促進させ低カリウム血症をきたす。PAによる高血圧は難治性であり、脳血管疾患、虚血性心疾患、心房細動などの合併症が本態性高血圧の3~5倍多いとされている。近年本邦で行われたPA患者に対する他施設共同の後ろ向き研究(JPAS)において、PAは心血管疾患9.4%、脳卒中7.4%、不整脈4.0%と高率に合併症を発症していることが確認された 2)。PAは、一側性の腺腫によるアルドステロン産生腺腫(aldosterone-producing adenoma:APA)と両側性の過形成を呈する特発性アルドステロン症(idiopathic hyperaldosteronism:IHA)の2つのサブタイプに分類される。 2)診断方法 PAの診断は、①スクリーニング、②機能確認検査、③局在診断(サブタイプ診断)の順番で行われる。診断アルゴリズムを図1に示す。
2024年04月02日 -
特集
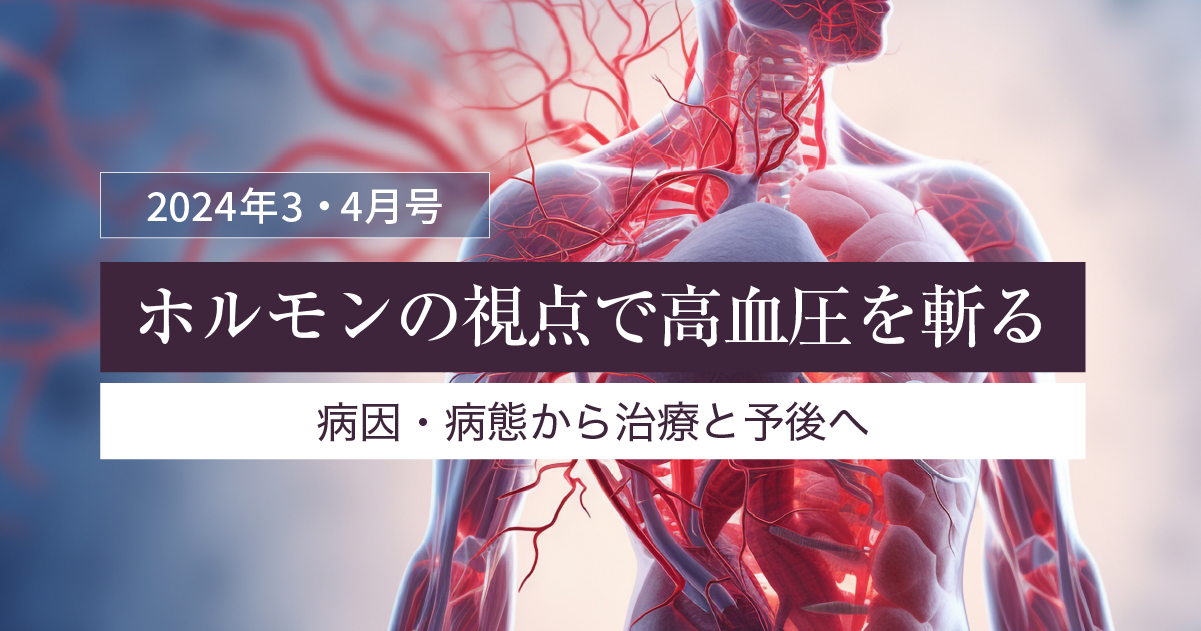
3.本態性高血圧の成因・診断・治療法―ナトリウム調節異常と本態性高血圧
はじめに 本態性高血圧の成因については複数の因子が互いに関連しながら関与しているという、いわゆるモザイク説が約80年前にPageにより提唱された 1, 2)。その中でも食塩、本稿で述べるところのナトリウム(Na)調節異常は中心的因子といえる。Guytonらは血圧上昇とともに尿中食塩排泄が増えることを発見し、血圧と腎におけるNaと水排泄との関係、すなわち圧利尿(Na利尿)曲線を明らかにし、この曲線が右側にリセットされることにより高血圧が持続するとした。これは高食塩下において腎でのNa排泄が不十分であることが細胞外液増加につながり、心拍出量の増加と末梢血管抵抗が上昇することで血圧が上がるとする理論である 3)。本稿では、高食塩下でのNa(ここでは食塩と同義)調節異常と本態性高血圧について述べる。 1.Na調節異常の成り立ち、どこで起きているのか? 本態性高血圧の原因としてのNa調節異常を説明する上で欠かせない圧利尿(Na利尿)とそのリセットには、腎臓内間質圧の上昇や近位尿細管のsodium hydrogen exchanger 3(NHE3)やsodium-phosphate cotransporter isoform 2といったNaトランスポーターの変化など複数の因子が関与している 4)。このことから、Na調節異常は腎臓で起こっているといえる。実際に本態性高血圧患者が正常血圧のドナーの腎臓を移植すると高血圧が改善したとの報告がある。この報告では、さらに平均4.5年のフォロー中、降圧薬投与なしで正常血圧を維持できたとされる 5)。この結果から、本態性高血圧には腎臓でのNa調整異常が主に関与していることがうかがえる。また、Na調節異常と関連がある食塩感受性についても腎臓なしには語れない。epithelial sodium channel(ENaC)は遠位ネフロンにおいてNaの再吸収に関わっているトランスポーターの一つであり、食塩感受性の始まりや維持に関与している 6)。これらはいわゆる腎障害説と呼ばれるものである。一方で、食塩感受性高血圧患者と食塩非感受性正常血圧患者とで食塩負荷後のNaバランスに差がみられなかったとする報告もあり 7)、Schmidlinらは食塩感受性のある患者と非感受性の対照群とで食塩負荷によるNaバランスや血行動態の変化を比較した結果、食塩負荷による心拍出量増加は両者で同等に起こるも、対照群では全身の血管抵抗の低下が起こるが食塩感受性あり群では血管抵抗低下が弱く血圧が上昇する経過を示した 8)。これらの結果より、食塩感受性が腎臓でのNa排泄異常だけで説明がつく現象ではないこともうかがえる。これらは血管機能障害説と呼ばれ、血管内皮細胞での一酸化酸素(NO)産生障害 9)や血管平滑筋細胞でのsoluble guanylate cyclase signalingの異常 10)などによる高食塩下の腎内や末梢血管の拡張障害が原因とするものである。 さらに、最近の報告では高食塩摂取期間にNaが皮膚やその他の組織の間質に蓄積し、プロテオグリカンと複合体を形成し高い浸透圧性をもって貯留することで、血管内容量ひいては血圧を干渉する役割を担うとされている 11)。組織でのNa蓄積は高食塩摂取や加齢により増加し、高血圧や心血管病リスクと関連するとの報告もある 12)。組織におけるNaの上昇はT細胞を刺激しサイトカインである IL-17Aが産生され 13)、これが血管のリモデリング、内皮機能障害や腎でのNa排泄障害を促進する。また、組織のNaはアミロライド感受性Naチャネルを介し樹状細胞活性化を促進し 14)、単球をIL-6、TNFαやIL-1βを産生する樹状細胞様フェノタイプへと変化させる 15)。その上、Naは骨髄細胞内に入るとCaによるNADPHオキシダーゼの活性化が起こり、活性酸素種(ROS)産生へとつながる。このように、組織に貯留したNaにより免疫細胞が活性化され、高血圧発症や維持につながる。 加えて、高血圧患者やマウスにおいて腸内細菌叢の多様性が減っている状態、すなわちdysbiosisが指摘されている 16)。また、マウスやヒトへの高食塩摂取によりLactobacillus murinusが減り、これによりインドール産生が低下する。このインドールはCD4+細胞からTH17細胞への分化に影響を与えることが示されており、逆にLactobacillus murinusを高食塩摂取下のマウスに投与すると食塩感受性高血圧や自己免疫性脳脊髄炎が改善したとの報告もある 17)。このように腸内においてもNa調節や高血圧との関連が示唆される知見もある。 以上のまとめとして、図1に高Na(食塩)摂取時の血圧上昇のメカニズムを示す。
2024年03月27日 -
セミナー

ステロイド薬の使い分けとステロイドカバー
Q&A編はこちら はじめに 糖質コルチコイド(以下ステロイド)はどの分野においても診療の中で使用することの多い薬剤である。しかし、ステロイドには血中半減期・生物活性半減期・力価の異なるさまざまな製剤が存在することや、各疾患によって投与量や投与方法、減量速度などが異なること、副作用に注意しなければならないことなどから、煩雑だと感じる医師も少なくない。本稿では各種ステロイドの特徴とその使い分けについての基本事項と、内分泌領域での使用例、ステロイドカバーについて述べ、実際の症例を紹介する。 1.各種ステロイドの特徴 ステロイドには力価の異なる多くの製剤が存在する。以下の換算表(表1)を参考に投与量を考える。各ステロイド製剤1錠が大体ヒドロコルチゾン(コートリル®20mg)に相当し、健康成人の1日のコルチゾール分泌量とほぼ同等であると考えると覚えやすい 1)。コートリル®は半減期が短いため視床下部-下垂体-副腎皮質系(HPA axis)への機能抑制が起こりにくく、即効性があるため主に副腎皮質機能低下症のホルモン補充療法に使用される。プレドニゾロン(プレドニン®)は作用時間が比較的短く、電解質代謝への影響が弱いため、薬理作用を狙った各疾患のステロイド治療において第一選択薬としてよく用いられる。デキサメタゾン(デカドロン®)は鉱質コルチコイド作用がなく電解質代謝への影響は少ないが、半減期が長いためHPA axisへの機能抑制が強く、短期的に使用される場面が多い。 ステロイドには経口だけでなく、経静脈投与や、外用(塗布、点眼、点鼻など)、吸入、関節内投与など局所的にも使用される。経口ステロイドは吸収率が非常に高いが、注射製剤は水に難溶性でありリン酸やコハク酸でエステル化した製剤となっており、生体内で活性型となり効力を発揮するため、経口投与よりも生体内利用率が劣る可能性がある。そのため、経口投与から経静脈投与への切り替えの際は、最初は同量で開始し、その後反応性をみて増減する。また、連日投与する際も生体内利用率の低下を考慮し、臨床経過をみて投与量を調整する。 表1 ステロイド換算表(筆者作成) 画像をクリックすると拡大します 表1 ステロイド換算表(筆者作成) $(".vol2_k12_h1").modaal();
2024年03月22日 -
特集
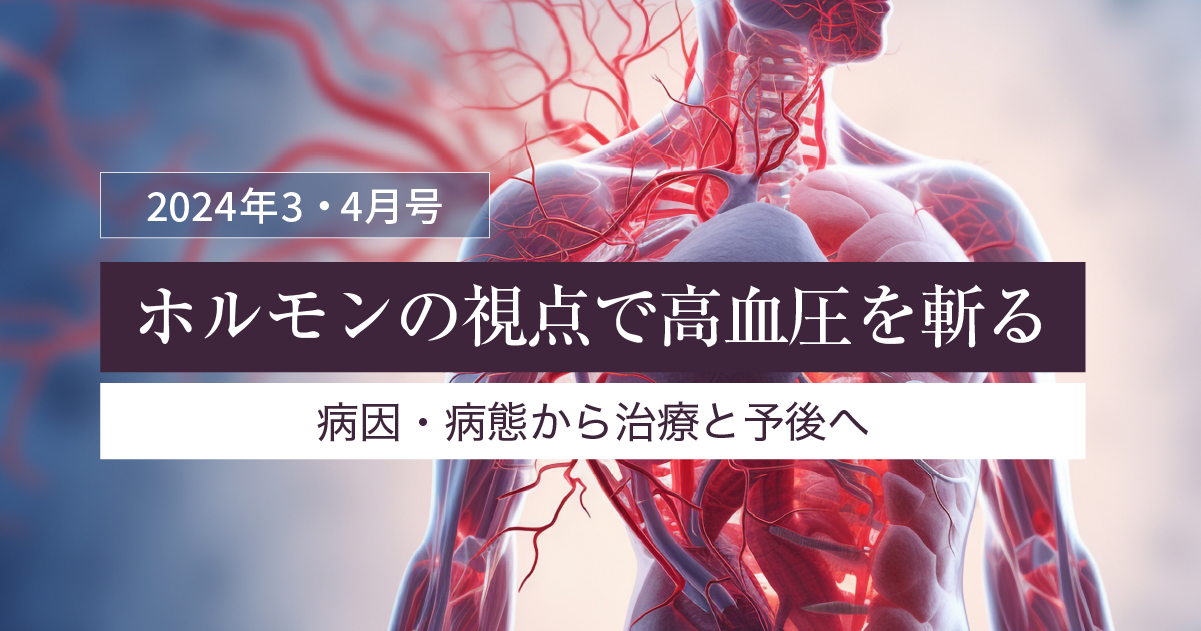
2.本態性高血圧の成因・診断・治療法―血管調節異常と本態性高血圧
はじめに 血管調節は血管平滑筋と血管内皮による収縮と弛緩の均衡維持により担われている。本態性高血圧の病態では交感神経系やレニン・アンジオテンシン(RA)系の活性化、酸化ストレス、血行動態の変化、機械的伸展力や物理的刺激の増大によりこの均衡が崩れ、血管収縮の亢進、動脈リモデリング、血管内皮機能障害が生じて、血管緊張(トーヌス)異常をきたし、動脈壁が硬くなり伸展性を失った動脈スティフネスの進行とともに慢性的な高血圧が形成されていく 1, 2)(図1)。本稿では高血圧における血管調節異常の機序を解説し、診断や治療について触れていく。 図1 高血圧における血管調節異常(筆者作成) RA系:レニン・アンジオテンシン系 1.血圧形成における血管の役割 動脈系は大血管、中~小動脈、細動脈、毛細血管からなる。動脈壁は解剖学的に3つの層、単層の「内皮細胞」、弾性繊維と血管平滑筋細胞の多層からなる「血管中膜」、線維芽細胞や結合組織、細胞外マトリックスを含む「外膜」から構成される。血管の中膜は自律神経系に支配されており、その収縮はホルモンや血管作動性ペプチド、活性酸素種によって調節されている。動脈は、中膜の弾性繊維の含有量や機能の違いから、大動脈や心臓に近く太い弾性動脈、末梢にある中型の筋性動脈、その先の細動脈(抵抗血管)、毛細血管に分類される。弾性動脈は平滑筋より弾性線維を豊富に含有するため、血管の伸展や収縮を介して血圧調節に寄与している。一方、筋性動脈は平滑筋を多く含有し、平滑筋の収縮と弛緩により血流分布を調節する。細動脈は抵抗血管と呼ばれ、平滑筋が豊富で、神経性あるいはホルモンなどの液性因子により血管平滑筋の収縮が調節される。例えば、交感神経興奮時はノルアドレナリンが平滑筋に作用して血管を収縮させ、血管抵抗が増大し、血圧が上昇する。大動脈から次第に中小の動脈に枝分かれしていく課程で、血管の総断面積、流速、血圧はそれほど大きく変動しないが、細動脈レベルで血管抵抗が急に増大する。 心臓からの血液拍出は断続的であるが、動脈の血流が連続的で末梢組織まで血液を送ることができるのは、心収縮力以外に、弾性血管と抵抗血管が心収縮期に拡張し、心拡張期には元に戻ろうとする駆動圧を生じて血圧を維持しているからである(Windkessel効果)。また、こうした血管の作用は心駆出エネルギーが直接動脈壁に及ぼす壁応力を減弱させて血管保護的に働き、末梢へのエネルギー伝搬を減衰させて末梢臓器の微小血管保護に働く(クッション効果)。こうした機能を担う中膜の血管平滑筋は一過的な収縮に関わるだけでなく、普段より持続的な筋トーヌスを維持しており、これが血流抵抗を形成する本体となっている。血管抵抗は血管半径(内腔径r)の4乗(r4)に反比例するため、血管径が4分の1になると、血管抵抗は256倍増大し、内腔径のわずかな変化が血管抵抗に大きな影響を与える 3)。高血圧形成においては血管抵抗の増大が中心的な役割を果たしている。
2024年03月19日 -
特集
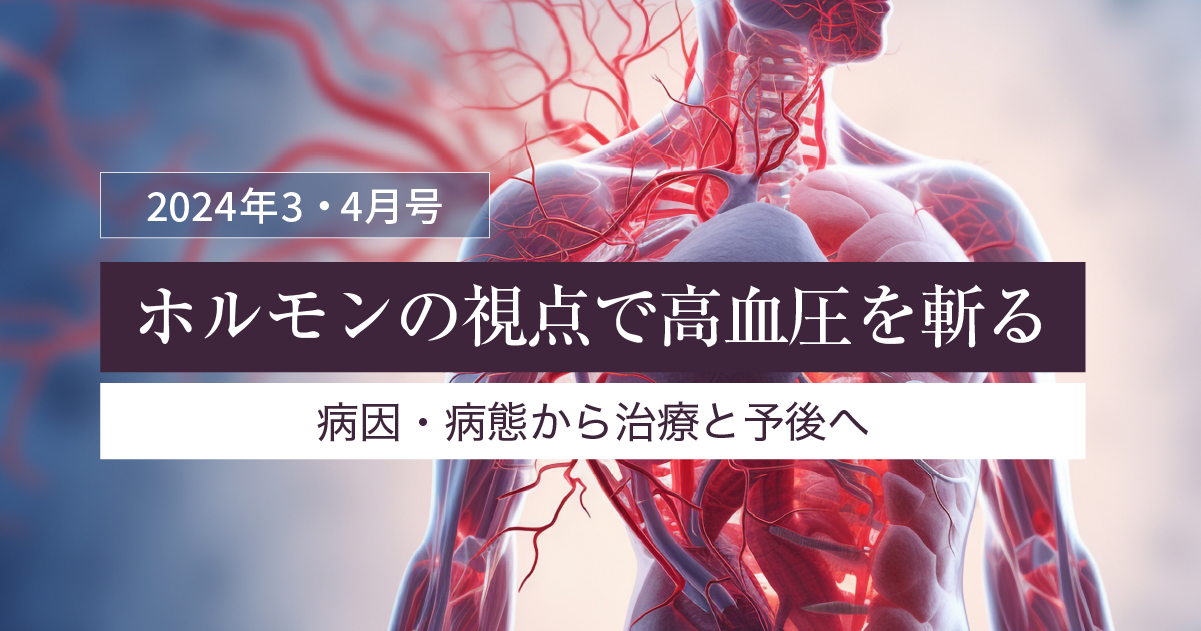
1.本態性高血圧の成因・診断・治療法―神経調節異常と本態性高血圧
はじめに 高血圧の発症や進展、高血圧性臓器障害において、交感神経活性化を主体とした神経調節異常が重要な役割を果たしている。交感神経系は、血圧調節に関与する心臓、腎臓、血管などの末梢臓器に強力に作用し、血圧上昇の方向に働く。また、脳は末梢からさまざまな入力を受け、それらを統合・調節し交感神経出力を制御している。本稿では、心・腎・血管の各臓器に対する交感神経系の働きについて概説し、さらに、高血圧における中枢性循環調節機構と、交感神経系亢進の診断と関連する治療について、最新の知見も含めて述べる。 1.心・腎・血管に対する交感神経系の働きと高血圧の発症・進展 交感神経系は心臓、腎臓、血管に対して、以下のような生理的作用を持つ。交感神経系の亢進により、心臓に対しては心収縮力・心拍数の増加、それに伴う心拍出量の増加をもたらす。腎臓に対しては、レニン分泌の増加(レニン・アンジオテンシン〔RA〕系の亢進)、Na再吸収の増加を起こし、血管に対しては血管収縮を引き起こす。交感神経系の持続的な亢進により、これらの慢性的な作用が生じ高血圧を発症し進展する。さらに、各臓器は高血圧性臓器障害を起こすが、持続する高血圧による二次性変化だけでなく、交感神経活性化により血圧非依存的にも臓器障害が進展することが知られている。 脳すなわち中枢神経系は末梢からのさまざまな入力を受け、それらを統合・調節して最終的に全身への交感神経出力を規定している(図1)。交感神経出力の中枢性調節機構はオーバーラップする部分もあるが、末梢からの入力により異なる中枢性機構が存在する。主な中枢性交感神経調節機構を、末梢からの入力により分類して次項より解説する。 図1 脳を介した交感神経系調節・臓器連関
2024年03月13日 -
特集
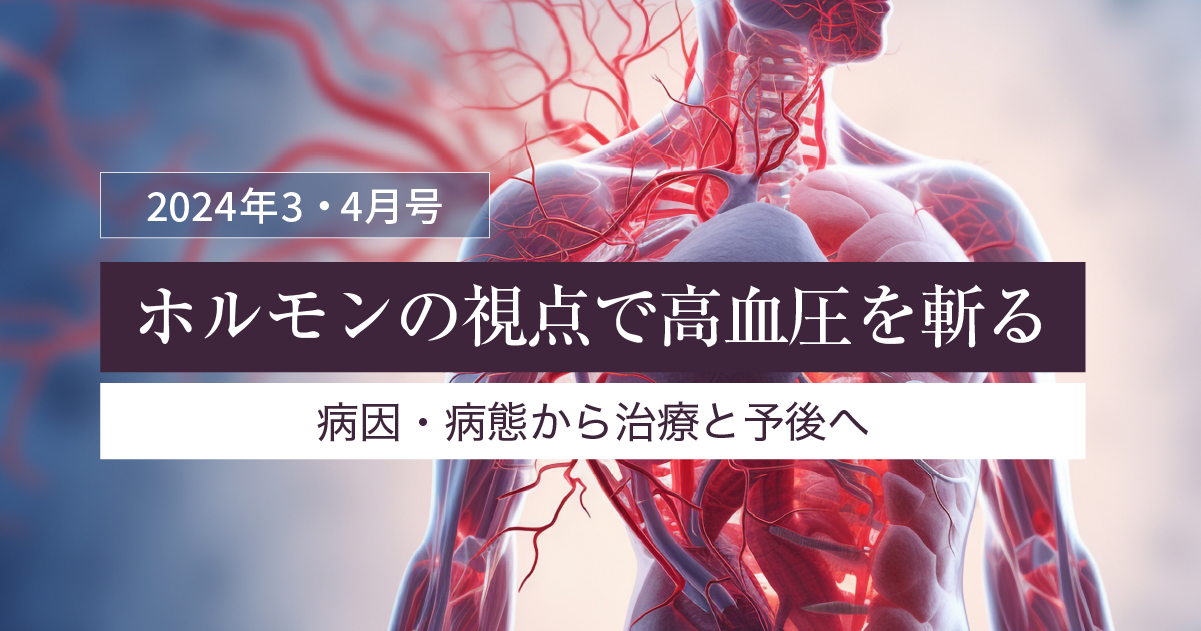
(扉)特集にあたって
2022年の国民生活基礎調査によると、男女とも「高血圧症」での傷病別通院者率(男性146.7人/人口1,000人、女性135.7人/人口1,000人)が最も高く、その数は年々増加している。高血圧の大半は本態性であるが、近年では検査・治療の進展に伴い二次性高血圧の診断が増えてきている。そこで、この「国民病」に対する造詣をあらためて深め、診療の質の向上を図る企画として本特集を組んだ。 高血圧の最適な診療には、成因・診断・治療エビデンスを適確に理解することが不可欠である。また、高血圧に合併する頻度が高い糖尿病やCKDの病態も同時に把握することが適確な治療薬選択につながる。同時に、近年続々と登場している高血圧およびその関連疾患についての診療ガイドラインの活用も有用である。 本特集では、病因・病態の解説から始まり治療と予後の説明へとシステマティックに展開する読みやすい形式で、この分野のエキスパートドクターにそれぞれ詳説を執筆していただいた。本態性高血圧の成因・診断・治療法に関して、篠原啓介先生には神経調節異常、河原崎和歌子先生には血管調節異常、荒川仁香先生にはナトリウム調節異常の解説をしていただいた。吉田雄一先生・柴田洋孝先生には、主な内分泌性二次性高血圧疾患である原発性アルドステロン症、クッシング症候群、褐色細胞腫・パラガングリオーマを中心とした最新情報を解説していただいた。さらに、角谷裕之先生・杉本 研先生には、本誌の読者にとって非常に関心があるポイントだと思われる糖尿病と高血圧を合併したケースでのマネージメントをご執筆いただいた。また、昨年上梓された「エビデンスに基づくCKD診療ガイドライン2023」を踏まえ、長浜正彦先生には生活習慣修正、亀井啓太先生・今田恒夫先生には降圧薬治療を中心に、 CKD合併高血圧のマネージメントを詳細していただいた。 本特集は、基礎医学的側面と実臨床的側面の両方向からのアプローチによる充実したものとなっていると自負している。読者の方々に、本特集を明日からの日常診療や研究に積極的に活かしていただければ、特集の企画者として至上の喜びである。 著者のCOI (conflicts of interest)開示:下澤達雄;報酬(積水メディカル、EPメディエイト)、講演料(ノバルティス ファーマ、第一三共、サノフィ、大塚製薬)、研究費・助成金(日本ベーリンガーインゲルハイム)、能登 洋;講演料(住友ファーマ、日本イーライリリー、ノボ ノルディスク ファーマ)、研究費・助成金(マルホ) 本論文のPDFをダウンロードいただけます
2024年03月13日 -
セミナー
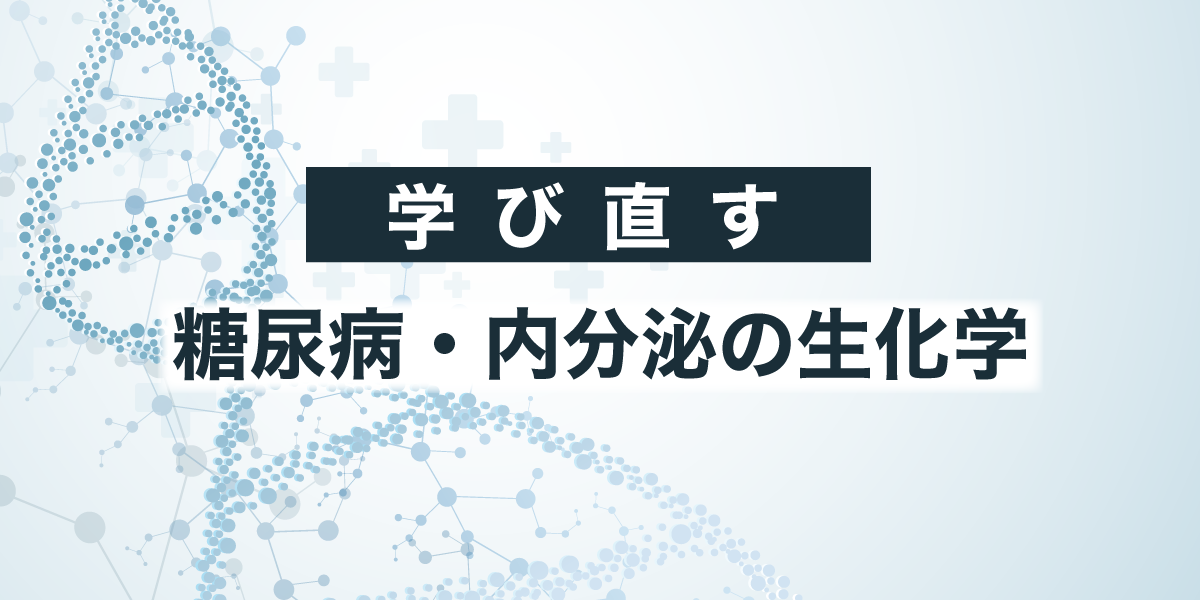
脂質の代謝
はじめに 生体膜の主要な構成成分やエネルギー貯蔵体として重要な役割をもつ脂質の代謝異常はさまざまな疾患の原因となる。肝臓や脂肪細胞での異常は脂肪肝、肥満などのcommonな疾患やまれな脂質蓄積病を引き起こす。また、血中の脂質の大部分を占めるリポタンパクの代謝異常は脂質異常症と動脈硬化症の原因となる。本稿では、これらの臨床的に重要な病態と関連する脂質の代謝異常に関して生化学的観点から概説する。 1.脂質とは 脂質の主な特徴と機能、およびその分類を表1に示す。脂肪酸に代表される炭化水素鎖に富む脂質は高度なエネルギー貯蔵体(トリグリセリド)となり、また、極めて疎水性が高い一方で、一部にリン酸基や水酸基による極性(親水性)を合わせもつ両親媒性のため脂質二重膜を形成し、生体膜の基本成分となる(リン脂質、コレステロール)。また、炭素数20(C=20)のアラキドン酸から派生するエイコサノイド(プロスタグランジン、ロイコトリエン、トロンボキサン)は多様な生理活性を発揮し、アスピリンなどの非ステロイド抗炎症剤(NSAID)の作用はプロスタグランジンH2合成酵素阻害によるエイコサノイドの産生抑制による 1)。その他、コレステロールに由来するステロイドや胆汁酸、ビタミンD、およびその他の脂溶性ビタミン(ビタミンA、E、K)も重要な脂質である(表1)。 表1 脂質の機能と分類
2024年03月08日 -
セミナー

苦労しています、服薬指導 ―短時間で患者の心を掴み、リスク回避!
Q&A編はこちら はじめに 特定薬剤管理指導加算は、適正使用ができていないことで患者に大きな健康被害を及ぼす可能性のあるハイリスク薬に関する服薬指導について、薬剤師の専門的能力を活かし、適正かつ安全な使用ができるよう2010年度調剤報酬改定で新設された。 薬学的知見を最大限活かすことが求められる点数であり、薬剤師の対人業務の中核の一つと言える。 日本薬剤師会が「薬局におけるハイリスク薬の薬学的管理指導に関する業務ガイドライン」 1)を策定したことなどを背景とし、ハイリスク薬に関する服薬指導について診療報酬だけでなく、調剤報酬においても処方箋受付1回につき特定薬剤管理指導加算として10点を算定できるようになった。糖尿病薬関連では、「糖尿病用剤」および「膵臓ホルモン剤」が該当する。 つまり、医師のみならず、薬剤師が患者または患者家族に対して、正確に必要な薬剤の情報を伝えることが法的に認められたことを意味し、多くの保険薬局で糖尿病薬を交付する際に責任をもって対応している。しかし、一方で保険薬局での服薬指導にかかる平均時間は3~4分であり 2)、法的に求められる情報提供量を短時間に正確に伝えることは大変難しい。 今回は、糖尿病治療薬の特定薬剤管理指導加算および関連加算の算定条件と、これまでに筆者らがさまざまな背景の患者に対して行ってきた服薬指導について紹介する。 1.薬剤師による服薬指導 薬剤師が医薬品を処方箋により調剤し、薬剤師が患者または患者家族に対して行う服薬指導の項目は多岐に及ぶ。薬学部における実務実習では、ハイリスク薬に指定されていない医薬品においても服薬指導時に確認・説明する主な項目として下記が挙げられている。 薬の説明(効果・効能、用法・用量、併用薬、剤型、臭い・味) ジェネリック医薬品についての説明(薬効、薬価、選び方、先発医薬品との相違点など) 費用に関する説明(調剤報酬、保険など) 副作用の説明 生活上の注意点(飲食、睡眠、入浴など) 使用上の注意点(服用間隔、保管方法など) 乳幼児、小児、高齢者、妊婦に対する使用上の注意点 検査値の確認 お薬手帳についての説明 患者教育、患者情報の確認 疾患の予防などについての説明(QOL向上、予防接種推奨など) 患者が罹患している疾患についての説明 患者との処方確認(処方薬と疾患の関連性の確認) 薬剤師業務の必要性の説明(処方監査、服薬指導など) 保険薬局への問い合わせ方法(夜間の電話対応など) かかりつけ薬局、かかりつけ薬剤師の必要性 保険薬局におけるハイリスク薬(特定薬剤)には下記内容の調剤報酬の算定が可能である。
2024年02月28日 -
特集
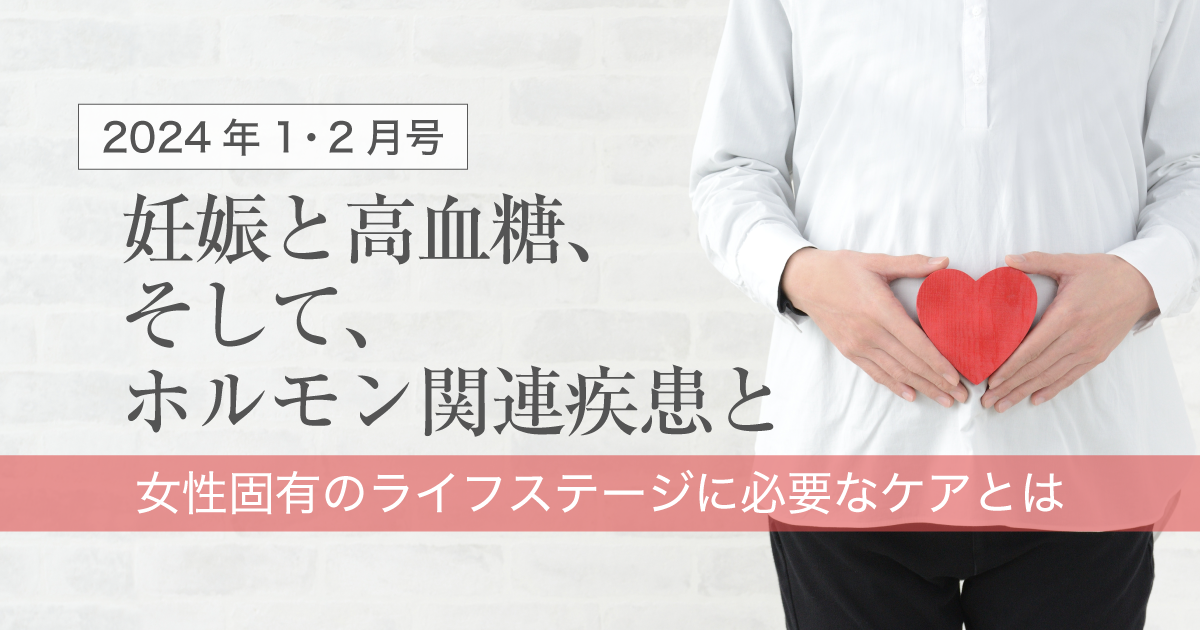
≪6.妊娠と内分泌疾患 ―特論―≫ 6-2.鞍上部に進展するプロラクチン産生PitNET患者の妊娠中の管理
はじめに プロラクチン産生PitNET(プロラクチノーマ)は下垂体前葉から発生するプロラクチン(PRL)を自律分泌する腫瘍である。治療の第一選択はドパミンアゴニスト(DA)、特にカベルゴリンによる薬物療法であり、血清PRLの低下と腫瘍縮小が得られる。プロラクチノーマの多くは女性に発生し、ほとんどはミクロプロラクチノーマ(<10mm)であり、マクロプロラクチノーマ(>10mm)、特に鞍上部進展を伴うものは少ない。高プロラクチン血症は中枢性に性腺機能を抑制し、女性では月経不順や無月経で診断されることが多く、不妊の原因となる 1)。 1.プロラクチノーマと妊娠 プロラクチノーマでは、一般にカベルゴリンが奏効すると半年以内にPRLが正常化することが多い 1)。PRLが低下することで抑制されていた性腺機能は回復し、妊娠が可能となる。腫瘍はPRLの正常化に遅れて緩徐に縮小するが、その場合もPRLが正常化していれば妊娠は可能となる。また、なかには血清PRLが正常化しても腫瘍縮小が得られない症例も存在する。 妊娠した場合にはDAは胎盤を通過するため、中止することが推奨されている 1, 2)。ただし、妊娠6週までのDA曝露は母体および胎児のリスクを増加しないことが分かっている 2, 3)。 2.妊娠中の腫瘍増大 妊娠中は胎盤からエストロゲンが大量に分泌され、その刺激により正常下垂体においてもPRL分泌が亢進する。妊娠後期~出産直後までに下垂体高位は最大12mmまで増加し、出産後6カ月以内には通常の大きさまで戻る 3)。プロラクチノーマもエストロゲン刺激により増大するリスクがあり、PitNETの中で妊娠中の増大はプロラクチノーマが最も頻度が高い 4)。妊娠中のプロラクチノーマが大幅に増大するリスクは、ミクロプロラクチノーマでは3%と低いが、マクロプロラクチノーマでは20~30%と高くなる。マクロプロラクチノーマでも妊娠前に十分に腫瘍が縮小した場合や、手術または放射線療法を受けた場合は5%以下に腫瘍増大リスクが下がる 2, 3)。そのため、鞍上部進展を伴うようなマクロプロラクチノーマでは妊娠中の増大により視機能障害を呈するリスクがあることから、十分に腫瘍の縮小が確認できるまで適切な避妊を指導することが望ましい 5)。DAが有効な腫瘍では経口避妊薬の併用は安全である 5)。また、DAによる腫瘍縮小効果がない場合や妊娠を急ぐ状況では妊娠前の手術も選択肢となる 1, 3)。
2024年02月26日 -
特集
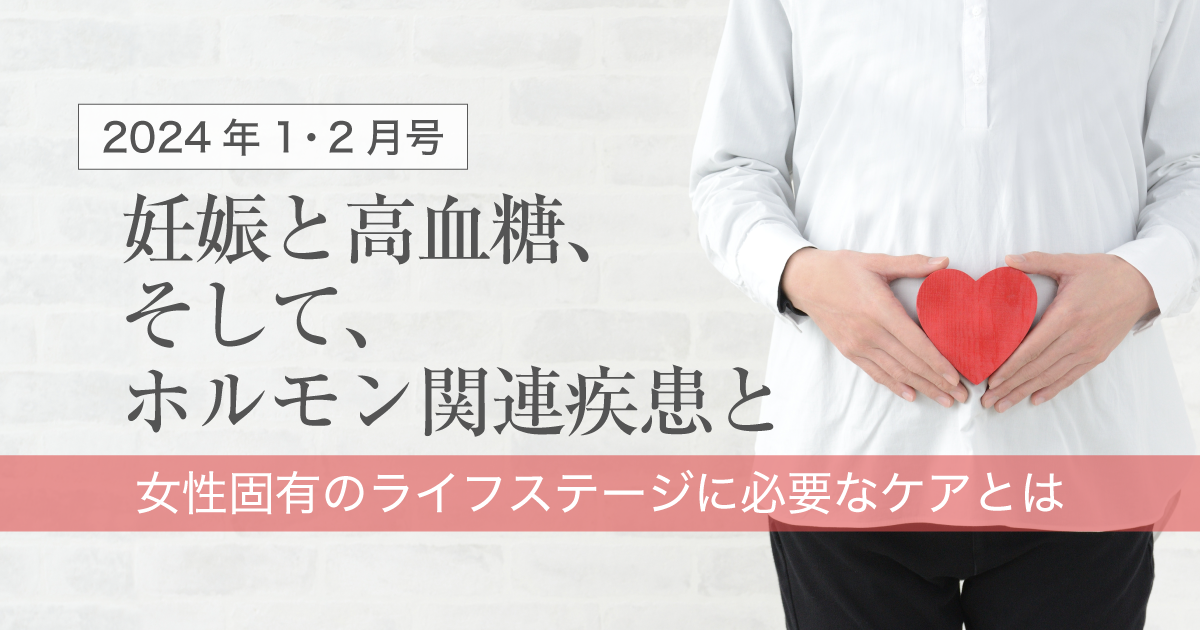
≪6.妊娠と内分泌疾患―特論―≫ 6-1.妊娠中に診断された原発性副甲状腺機能亢進症の治療
はじめに 原発性副甲状腺機能亢進症(primary hyperparathyroidism:PHPT)は比較的頻度の高い内分泌疾患であり、40歳以上での発症が多く、男女比は約1:3と女性に多い 1)。そのため、妊娠可能年齢の女性や妊娠中に診断されるケースもある。高カルシウム(Ca)血症をきたしたPHPT合併妊娠では、母体および児にさまざまな合併症をきたし得る。本稿では、妊娠合併PHPTの診断・治療や母体・児への影響について解説する。 1.原発性副甲状腺機能亢進症の診断 高Ca血症があり、副甲状腺ホルモン(PTH)上昇を認めれば比較的容易にPHPTと診断できる。ただし、PTH、Caの一方が、もしくは両者が基準範囲内高値にとどまることもある。一般的な合併症として尿路結石症や骨粗鬆症などがみられるが、高Ca血症のみから診断に至る無症候性PHPTが多い。産婦人科診療ガイドラインの妊娠初期のスクリーニング検査には、血清Caは含まれていない 2)。そのため、妊娠中の軽症PHPTは見過ごされている可能性もある。 1)妊娠中のCa代謝 妊娠中のCa代謝の評価にあたっては母体特有の変化を理解しておくことも重要である。妊娠中は循環血漿量の増加による体液希釈や糸球体濾過率の増加に伴い、高Ca尿症、低Alb血症を呈する。通常、細胞外Caの約半分はAlbと結合して存在し、その他はイオン化Caとして存在する。したがって、低Alb血症がある場合には以下の補正式を用いてCa濃度を評価する。 補正Ca濃度(mg/dL)=血清Ca濃度(mg/dL)+(4−血清Alb濃度〔g/dL〕) 妊娠中は生理的な低Alb血症により見かけ上の総Ca値は低下する。軽度の高Ca血症は、Alb補正を行わないと見逃してしまう可能性がある。 また、妊婦の血清1,25(OH)2D値は胎盤での1,25(OH)2D産生により非妊娠時の2~3倍に増加している。母体の腸管Ca吸収の一部はビタミンD非依存性に増加する。その結果、母体のPTH濃度は基準値内下限~基準値未満に抑制される。また、胎盤や乳腺由来のPTHrP(PTH-related protein)は母体骨からのCa動員および胎盤を介したCa輸送を促し、胎児へのCa供給に貢献している(図1) 3)。
2024年02月20日 -
セミナー

肥満の外科治療 ―減量・代謝改善手術の最新エビデンス―
ポイント 肥満症患者に外科治療(肥満手術)は有用であり、主に3つの術式が行われているが、本邦で保険適用となっているのは、腹腔鏡下スリーブ状胃切除術(LSG)のみである。 2型糖尿病などの肥満関連合併症の改善を目的としたメタボリックサージェリー(代謝改善手術)も近年注目され、先進医療として、腹腔鏡下スリーブバイパス術(LSG-DJB)も行われている。 本邦における手術適応年齢は、現在は18~65歳であるが、世界の動向を鑑みると66歳以上の高齢者や18歳未満の小児・思春期への減量・代謝改善手術も今後行われるようになる可能性が高い。 1.総論 1)肥満症に対する外科治療・内視鏡治療の歴史 肥満症に対する外科治療は、1950年代に米国ミネソタ大学で空腸・結腸バイパス手術が行われ、1960年代に米国アイオワ大学で胃バイパス術が行われた。後者はその後改良が加えられ、Roux-en-Y胃バイパス術(Roux-en-Y gastric bypass:RYGB)として現在でも広く普及される術式となった。1986年には、調節性胃バンディング術(adjustable gastric banding:AGB)が報告された。その後、これらの手術は腹腔鏡下に行われるようになり、腹腔鏡下RYGB(LRYGB)、腹腔鏡下AGB(LAGB)として普及した。近年増加している腹腔鏡下スリーブ状胃切除術(laparoscopic sleeve gastrectomy:LSG)は、元々、二期的手術(十二指腸変換を伴う胆膵路バイパス)の初回手術として開発されたが、単独でも一定の治療効果が得られることから、その後広く普及した。近年では、LSGに空腸バイパスを付加した腹腔鏡下スリーブバイパス術(laparoscopic sleeve gastrectomy with duodenojejunal bypass:LSG-DJB)も行われている 1)。 これに対して、肥満に対する内視鏡的治療は1980年代に開発された胃内バルーン留置術である。米国ガイドラインでは、最も歴史のあるOrbera Systemを含む5種類のバルーンが記載されている(Orbera、Obalon、Spatz、Ellipse、ReShape) 2)。また、Apollo Endosurgery社の OverStitch というデバイスを用いた内視鏡的スリーブ状胃形成が報告されており、手術と比較すると体重減少率は劣るものの、入院期間は短く、合併症は少ないとされている 3)。
2024年02月16日 -
特集
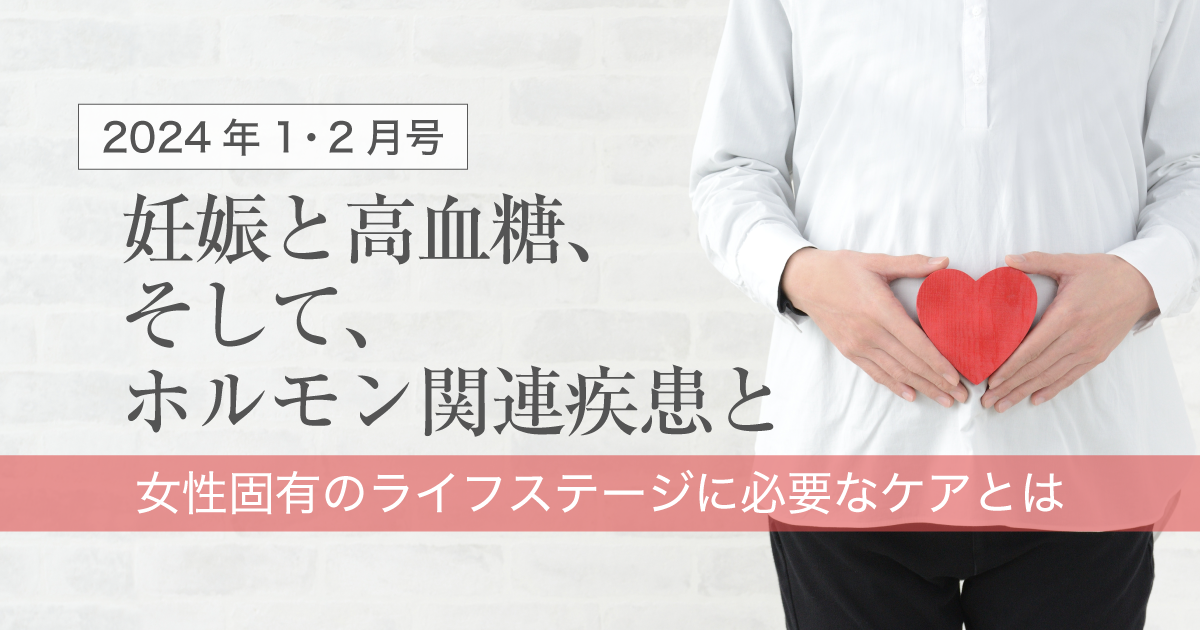
5.妊娠中の内分泌性高血圧症の治療
はじめに 高血圧を合併する妊婦は6~8%であるが、その大部分(88%)は本態性高血圧症で、内分泌性高血圧症は1%未満と非常にまれである 1)。本稿では、妊娠中の内分泌高血圧症として原発性アルドステロン症(primary aldosteronism:PA)、褐色細胞腫・パラガングリオーマ(pheochromocytoma/paraganglioma:PPGL)の診断・治療について述べる。 1.原発性アルドステロン症(PA) 1)疫学 一般の高血圧患者におけるPAの有病率を約10%とすると、全妊婦の0.6~0.8%でPAと診断されると推定される 2)。しかし実際は、英国のコホート研究では約300万件の妊娠でPAと診断された症例は3例のみであること 3)、また妊婦のPA症例の報告は数十例と少ないことから、診断されていない症例が極めて多いと考えられる。 2)病態 正常妊婦において、レニン-アンジオテンシン-アルドステロン系は亢進している。胎盤より産生されるエストロゲンによりアンジオテンシノーゲン産生が増加し、血中レニン活性が上昇する。レニン活性の上昇はアンジオテンシンⅡを上昇させ、糸球体でのアルドステロン産生を促進する。しかしプロゲステロンが遠位尿細管でのアルドステロン作用を減弱させるため、正常妊婦において通常は血圧上昇をきたさない。 PA合併により高血圧の増悪が予想されるが、妊婦における経過は多様で、血圧コントロール不良により胎児や母体の重篤の合併症を引き起こす例から、妊娠中に血圧が改善する例などさまざまである。PA合併妊婦において正常妊婦と比較して、妊娠関連合併症の発症率が高いとされる。特に妊娠高血圧腎症はPAを有する妊婦の3分の1に見られると報告されている 4)。
2024年02月14日 -
連載

第70回 糖尿病と社会保障
はじめに 糖尿病とその合併症に関連した障害に対し、一定の条件を満たす場合には社会保障を受けることが可能であり、その主な社会保障には表1に示すような制度がある。また高額療養費制度、難病医療費助成制度、小児慢性特定疾病医療費助成制度は、費やされた医療費を助成し、障害年金、身体障害者手帳、特別児童扶養手当、心身障害者(等)福祉手当は、生活面を支援する制度である。そして今回は、これらの公的支援制度について、糖尿病に係る内容を概説する。 表1 糖尿病と社会保障(糖尿病の方が受けられる公的支援) 1.介護保険制度(表2) 介護保険制度導入の背景としては、高齢化の進展に伴い、要介護高齢者の増加、介護期間の長期化などにより、介護ニーズはますます増大したが、核家族化の進行、介護する家族の高齢化など、要介護高齢者を支えてきた家族をめぐる状況も変化し、従来の老人福祉・老人医療制度による対応では限界となった。そして、高齢者の介護を社会全体で支え合う仕組みとして介護保険が創設された。 介護保険制度 1)の被保険者(加入者)は、表2に示すように二つに分けられ、以下のようになっている。 ① 第1号被保険者は65歳以上の者 ② 第2号被保険者は40~64歳の医療保険加入者 また介護保険サービスの受給要件は、以下の二つの場合に受けることができる。 65歳以上の者は原因を問わず要支援・要介護状態 40~64歳の者は「1.がん」や「2.関節リウマチ」、「12.糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症」など、表2に示す16の特定疾病 2)が原因で要支援・要介護状態 要介護状態区分は要支援1、2と要介護1~5までの7段階であり、区分に応じて1カ月あたりの保険給付の支給限度額が定められている。一般に介護サービスの費用のうち介護費用の1割、一定以上の所得がある場合は介護費用の2割が自己負担となる。 実際にサービスを受ける手順は、はじめに居住地の市区町村の窓口で要介護・要支援認定を申請する。申請後は市区町村担当者の訪問を受け、認定調査が行われる。また、市区町村からの依頼により、かかりつけの医師が主治医意見書を作成する。その後、認定調査結果や主治医意見書に基づくコンピュータによる一次判定、および一次判定結果や主治医意見書に基づく介護認定審査会による二次判定を経て、市区町村が要介護度を決定する。
2024年02月08日 -
特集
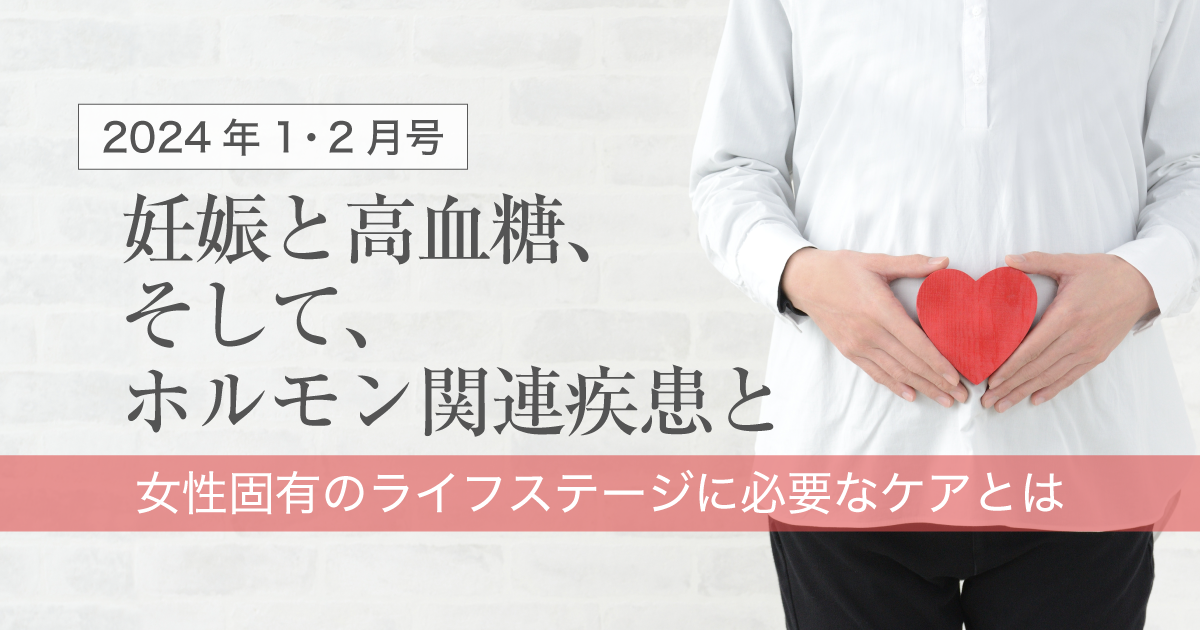
4.下垂体機能低下症患者における妊娠・分娩・授乳に関する内科的課題
はじめに 下垂体機能低下症患者では障害されたホルモンに応じて継続的な補充が必要である(表1)。一方で、ホルモンの需要はライフステージやライフイベントにより大きく異なるため、都度調整の必要がある。本稿では妊娠中・出産時・授乳期の女性における課題とホルモン補充について概説する。 表1 下垂体機能低下症女性に対する補充療法の例 ACTH:adrenocorticotropic hormone、TSH:thyroid stimulating hormone、LH:luteinizing hormone、FSH:follicle stimulating hormone、GH:growth hormone、PRL:prolactin、AVP:arginine vasopressin 1.妊娠に関連した課題と管理 ゴナドトロピン分泌低下症の女性が妊娠するためには、子宮などが萎縮しないよう婦人科でエストロゲン・プロゲスチンの周期的投与などのホルモン補充を行った上で、排卵誘発などの生殖医療を受けることが必要である。下垂体機能低下症の女性であっても、ゴナドトロピン分泌が正常であれば妊娠は通常と同様に成立するが、下垂体機能が正常である女性に比べ妊娠率は低く流産率が高い 1)。近年では、産婦人科・内分泌代謝科・小児科が協同してサポートすることで出産に至る汎下垂体機能低下症の患者が増加している 2)が、本稿で述べるような内科的管理の観点から計画的な妊娠が望ましい。
2024年01月31日 -
セミナー

糖尿病関連デジタルデバイスのエビデンスと使い方
Q&A編はこちら はじめに 慢性疾患を有する外来患者へのパーソナルヘルスレコード(personal health record: PHR)をはじめとしたデジタル技術の応用が、治療アドヒアランス、自己管理または自己効力感改善に有効であることが報告されてきている 1)。糖尿病治療においてもデジタル化の波が進んできており、間歇スキャン式持続グルコースモニタリング(intermittently scanned continuous glucose monitoring:isCGM)、コネクテッドインスリンデバイス、PHRを中心とした臨床応用が広がっている。 これら糖尿病関連デジタルデバイスを有効に用いることで、糖尿病治療に関連するさまざまな情報を統合し、治療にフィードバックすることが可能となる。本稿では糖尿病関連デジタルデバイスに関するキーデバイスとその実臨床での応用法、および現在までに得られているエビデンスを含め概説する。 1.間歇スキャン式持続グルコースモニタリング(isCGM) isCGMであるFreeStyleリブレは、従来の持続グルコースモニタリングと異なり、指先採血による自己血糖測定(self-monitoring of blood glucose:SMBG)でのキャリブレーション作業が不要となっている。使用法が簡便なこと、令和4年度診療報酬改定に伴い、インスリン療法を行っているすべての糖尿病患者に適用となったことにより、その使用が広く拡大している。 FreeStyleリブレは上腕背側に500円玉大のセンサーを装着することにより、14日間、連続的に間質液中のグルコース値を毎分測定し、15分ごとに保存することで連続的に血糖をモニタリングすることを可能としている。FreeStyleリブレは間質液中のグルコース濃度を測定しているため、急速な血糖変動時には血糖値と5~10分程度のタイムラグが発生する可能性に注意を要する。グルコース値の確認はFreeStyleリブレReader、もしくはスマートフォンアプリのFreeStyleリブレLinkからでき、FreeStyleリブレLinkでは自動で測定結果がクラウド上にアップロードされ、医療機関とのデータ共有も可能となる(図1)。また、記録されたグルコース値を集約し、その傾向を視覚的に把握しやすくしてくれる解析方法である ambulatory glucose profile(AGP;図2)により、低血糖や高血糖となる可能性の高い時間帯や、血糖変動が大きい時間帯を容易に把握することを可能としている。近年、HbA1cとともに臨床で用いられる血糖コントロール指標としてtime in range(TIR)が用いられてきている 2)。治療域血糖値を70~180mg/dLとし、この血糖範囲を維持できた時間割合をTIR(%)と定義し、このTIR が70%以上の場合、HbA1c 7.0%未満を達成できる可能性が高いとされている。良好なTIRを維持することは糖尿病網膜症や糖尿病性腎症の進行抑制につながり 3)、逆にTIRの低下は、総死亡、心血管死リスクの増加につながることが報告されている 4)。isCGMの導入は従来のSMBGと比べ、1、2型糖尿病を問わず、インスリン加療中患者の低血糖発現時間を抑制し 5, 6)、非インスリン加療中の2型糖尿病患者においても、良好な血糖域維持時間(TIR)を増加させHbA1cも改善することが報告されている 7)。
2024年01月25日